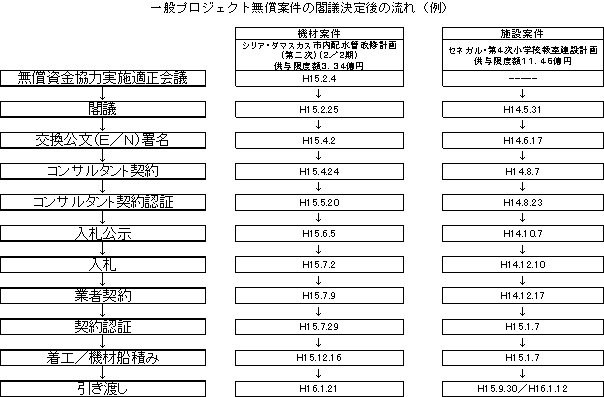| (イ) |
5月閣議では、4月閣議同様、分野は教育(15件)、水(9件)、保健衛生(8件)、人材育成(2件)、植林(2件)、電力(2件)、道路・橋梁(3件)等、多岐にわたっている。
|
| (ロ) |
これまで既に多く実施している学校建設案件については、先方政府の要望も踏まえつつ、様々なやり方を用いている。例えば通常の一般プロジェクト無償以外にも草の根・人間の安全保障無償によりNGO等を活用して学校建設を行う場合もあれば、一般プロジェクト無償においても、我が国支援により施工管理のコンサルタントを派遣するとともに建築のための資機材提供を行い建設自体は現地の父兄会等の関係者が行うというケースもある。こうしたやり方であれば、額に比して多数の教室を建設することが可能となる。
|
| (ハ) |
今回の閣議では、中国に対する無償資金協力案件が含まれている。対中援助については厳しい見方があり、オリンピックの開催予定や有人宇宙衛星の打ち上げの成功、中国の第三国援助といった事情がこうした見方に拍車をかけているところがあるようにも見受けられる。しかしながら、例えば円借款については、ピーク時では毎年約2千億円に達していたが、現在では1千億円を切っており、さらに今後は新規供与額より返済額が多くなる見込みである。また、インフラの整備が進む沿海部に比べて引き続き深刻な貧困状態にある内陸部に力点をおいて援助を行っている。
|
| (ニ) |
パレスチナについては世銀管理の信託基金に対して1千万ドルの拠出を実施する。財政支援については、日本の無償資金協力においてはかなりハードルの高い支援形態であるが、今回の基金への拠出については、パレスチナの財政状況の悪化に対処するための国際社会全体の取り組みの一環として実施するものである。
|