無償資金協力実施適正会議(平成16年度第1回会合)議事録
4月6日、無償資金協力実施適正会議が開催されたところ、概要以下の通り(出席者別添1、議題別添2)。
1.無償資金協力課からの説明と質疑応
2.コンサルタント契約状況、入札実施状況(JICA)
JICAより、閣議請議案件のE/N後進捗状況、コンサルタント選定状況について説明があった。
3.一般プロジェクト無償実施予定案件の説明/無償資金協力の予算執行の制度(外務省)
最後に、第12回会合は5月25日(火)に外務省(霞ヶ関)にて行うこととし、会合は終了した。
出席者
1.無償資金協力課からの説明と質疑応
| (1) | イラクに対する支援について(最新状況) 無償資金協力課より、3月26日付の記事資料をもとに、対イラク支援の最新状況について以下のとおり説明を行った。
|
||||||||||||||
| (2) | アフガニスタンに対する支援について 続いて、3月末に開催されたベルリンでの会合等、我が国の対アフガニスタン支援の現状について説明がなされた。
|
||||||||||||||
| (3) | 質疑応答 以上のやり取りを踏まえて、以下のとおり質疑応答が行われた。
|
JICAより、閣議請議案件のE/N後進捗状況、コンサルタント選定状況について説明があった。
3.一般プロジェクト無償実施予定案件の説明/無償資金協力の予算執行の制度(外務省)
| (1) | まず無償資金協力課より、4月閣議請議予定の案件につき以下のとおり説明した。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 続いて、無償資金協力課より、無償資金協力の予算執行の制度について、別添3の配付資料をもとに以下のとおり説明した。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 続いて、以下のとおり質疑応答が行われた。
|
別添1
出席者
- I.無償資金協力実施適正会議委員(50音順)
-
1.大野 泉 政策研究大学院大学教授
2.小川 英治 一橋大学大学院商学研究科教授
3.敷田 稔 アジア刑政財団理事長・元名古屋高検検事長
4.西川 和行 財団法人 公会計研究会会長・元会計検査院事務総長
5.星野 昌子 日本NPOセンター代表理事
- II.外務省
-
6.古田 肇 経済協力局長
7.山田 彰 経済協力局無償資金協力課長
8.松井 正人 経済協力局無償資金協力課地域第一班長
9.田村 良作 経済協力局無償資金協力課業務班長
- III.国際協力機構
-
10.中川 和夫 無償資金協力部長
11.上垣 素行 無償資金協力部 管理調達グループ 管理チーム長
別添2
無償資金協力実施適正会議(4月6日16:30~18:30)議題(案)
場所:霞ヶ関(南庁舎)2階289号室
- 報告事項(外務省)
(1)イラクに対する支援について(最新状況)
(2)アフガニスタンに対する支援について(ベルリンでの会合)
- コンサルタント契約状況、入札実施状況(JICA)
- 一般プロジェクト無償実施予定案件の説明及び質疑応答(外務省)
- 無償資金協力の予算執行の制度について(外務省)
別添3
無償資金協力(予算執行)
- 予算執行の現状
(1)閣議(年7回実施)
<参考>・4月閣議 ・・新規国債案件、継続国債案件 ・5月閣議 ・・新規期分け案件、継続期分け案件、単債(単年度債務)案件 → 年間で最も実行協議案件が多い。工期が長い施設案件。(明許繰越) ・7月閣議 ・・単債案件 → 施設案件 (明許繰越) ・10月閣議 ・・単債案件 → 工期が短い施設案件。工期の長い機材案件。翌債(翌年度にわたる債務負担行為)開始 (明許繰越) ・12月閣議 ・・単債案件 → 機材案件のみ。国債の詳細設計案件。翌債。 ・2月閣議 ・・単債案件 → 工期の短い機材案件のみ。翌債。 ・3月閣議 ・・単債案件 → 工期の極めて短い機材案件のみ。翌債。 ・ 翌債(翌年度にわたる債務負担行為)→E/N署名前の時点で、当該会計年度内に全額支払いを完了しないことが明らかなものについては、予め財務省の承認を得ることにより供与期限が一年後の一日前まで供与期限が延長できる。
例:16年度2月閣議 E/N17年3月10日→18年3月9日・ 明許繰越→当該年度内に全額支払いを完了する予定で供与期限を会計の年度末日の3月31日としてE/Nを締結したが,止むを得ぬ事由により年度内に支払いを完了することが出来ず、翌年度に繰り越して支払う。
例:16年度5月閣議E/N6月10日、供与期限17年3月31日→18年3月31日・ 事故繰り越し→ 明許繰越、翌債をもって翌年度に予算を繰り越し、翌年度内に支払いを完了する予定であったが、その過程において避けがたい事故のために翌年度内の支払いを完了しない状況に立ち至った場合に財務大臣の承認を得て翌々年度に予算を繰り越して使用する。事故繰越が認められる条件は厳しく、こうした事態が起きないように努力している。
例:16年度5月閣議 E/N6月10日、明許繰越後供与期限18年3月31日→事故繰越後供与期限 19年3月31日
- 予算執行における問題点
(1)年間7回の閣議(2)単年度主義と国外での援助プロジェクト
(3)明許繰越が多いことについて
(4)国債案件の数
(参考)閣議から案件実施に至るまでの流れ(概略)
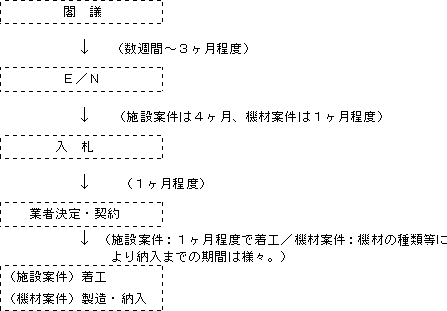
以上

