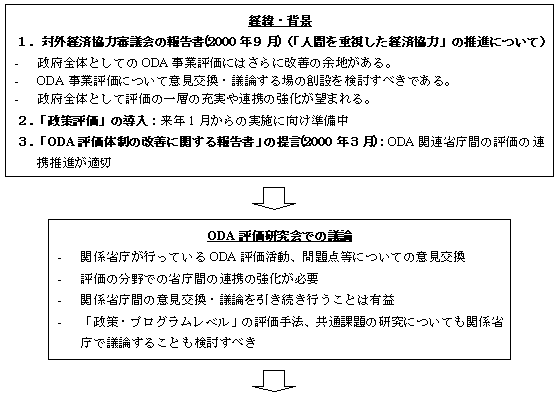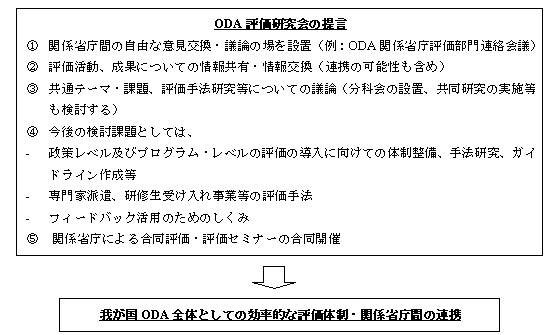ODA評価研究会では、(a)政策レベルの評価の導入とプログラム・レベルの評価の拡充、(b)評価のフィードバック体制の強化、(a)評価の人材育成と有効活用、(c)評価の一貫性の確保(事前から中間・事後に至る一貫した評価システムの確立)、(d)ODA関係省庁間の連携推進、の5つの主要課題について議論・検討を行った。
討議の主要ポイント及び指摘された今後の課題を、課題別に取りまとめると以下のとおりである。
|
2.1 政策レベルの評価の導入及びプログラム・レベルの評価の拡充
|
|
我が国のODAは、個別プロジェクト支援を中心とする援助形態から、特定地域、或いは分野の開発に向けて包括的な支援を提供し、援助効果を高める方向へ転換しつつある。こうした中で、評価についても、従来のプロジェクト・レベル中心の評価にとどまらず、政策やプログラム全体を対象とした総合的な視点からの評価を拡充する必要性が高まっている。そのため、プロジェクト・レベルの評価より上位にある「政策・プログラムレベルの評価」を早期に導入、確立することが望ましいが、具体的にどのような評価手法・体制を取り入れるべきかという問題意識を踏まえて議論を行った。
討議の主要ポイントと今後の課題
本課題については、委員の報告、外務省で実施中の委託調査「政策レベル及びプログラム・レベルの評価に関する手法研究調査」調査団報告等を受けて議論・検討を行った。その中で「政策レベル」或いは「プログラム・レベル」の評価等、プロジェクト・レベルより上位のレベルの評価を早期に導入、拡充することが必要とした上で、導入、拡充に当たってはこれら上位レベル評価の目的・意義を明らかにして、評価手法を確立するべきであることが確認された。
討議の主たるポイントと今後の課題をまとめると、以下のとおりである。
-
1)早期導入・拡充と評価手法の確立:「政策・プログラムレベルの評価」の時期については、早期導入・拡充の必要性が強調された。政策・プログラムレベルの評価については、国際的にもその必要性が認められ、一部の海外援助機関においては導入が試みられているが、未だ統一された具体的手法は確立していない。このため、今回の外務省による委託調査の結果、これまで行われてきたプログラム評価の実践等も踏まえて、他の海外援助機関の動向等を勘案しながら、日本のODAに適した評価手法と実施体制を確立させていく必要性があることについても共通の認識が得られた。
2)計画の体系図と評価指標の明確化:政策・プログラムレベルの評価を実施するに当たって、援助政策、国別援助計画、プログラム、プロジェクト等の体系図を用いる手法が紹介された。政策決定・計画作成段階において、この手法を用いることの有効性について意見が交わされ、さらに具体化する方向で意見の一致をみた。また、評価指標の選定やデータの収集方法、そしてモニタリング方法等について、事前段階において明確に設定することの必要性も確認された。
3)標準的なガイドライン、マニュアル、雛型等の作成:定量的評価のみならず定性的評価の重要性が確認された。それぞれの評価に一貫性を持たせるために、政策・プログラムレベルの評価について、手法・手順に関する標準的なガイドライン、マニュアル、雛型等を作成することが有益であるとの指摘があった。
4)他ドナー・国際機関との協力:政策・プログラムレベルの評価では、特定国や特定テーマを対象とすることが多く、他のドナー・国際機関の援助の動向を考慮して評価することは望ましいため、他ドナー・国際機関の協力を得た評価実施を念頭に置く必要がある。また、他のドナー・国際機関との合同評価の現状と、今後の改善策についても検討された。
5) 評価能力の向上:政策・プログラムレベルの評価を効果的に行うために、援助国側・被援助国側双方における評価能力の向上及び協力の必要性について認識が一致した。また、そのための研修の開催や被援助国を中心とした評価に関するワークショップを開催することの有益性が確認された。
6)十分な準備と予算的配慮:政策・プログラムレベルの評価の導入については、事前段階において目的、評価指標や目標の設定、モニタリングの方法及びフィードバック体制等、多くの分析作業が含まれることから、効果的な評価を行うためには十分な準備と予算的手当が必要であることについて意見の一致をみた。
なお、研究会会合では、「政策」及び「プログラム」という用語の定義、さらにそれぞれのレベルでの評価の役割等について活発な議論が行われた。
本研究会における議論では、政策決定レベルへのフィードバックを主目的として行う評価が「政策レベルの評価」であり、個別プロジェクト群を包括して上位計画への貢献度等を評価し、援助機関の援助方針・計画作成レベルへのフィードバックを主目的とする評価を「プログラム・レベルの評価」と考え、討議を進めた。
ちなみに評価研究作業委員会の「『ODA評価体制』の改善に関する報告書」では、これらの評価の定義について、次のように説明している。
|
【参考資料】:「ODA評価体制」の改善に関する報告書より抜粋
評価の3段階分類について
[政策レベル」、「プログラム・レベル」、「プロジェクト・レベル」の評価
ODA評価の分野では、かかる3段階の分類を便宜的に行っている。国際的な流れとしては、ODA評価は個々のプロジェクトやプログラムの評価に限らず、政策レベルの評価も行うべきとの方向に向かいつつある。
現在、多くのドナー国・国際機関は援助実施に際して、個々の具体的なプロジェクトの実施だけでなく、関連する複数のプロジェクトを有機的に組み合わせて実施するプログラム・アプローチを取り入れるようになってきている。
これに呼応して、ODA評価もプロジェクト・レベル評価(英語のProject Evaluationに対応)に加えて、プログラム・レベル評価(英語のProgram Evaluationに対応)を導入するようになってきている。
また、最近特に、政策レベルの評価(英語のPolicy Evaluationに対応するもの)の重要性が、国際機関等が主催する会議等で指摘されている。ここでいう政策レベルの評価には、援助機関全体として目指すべき方向性や戦略(例:DfIDの「貧困削減」)や国別の援助政策等が含まれる。
ただし、現在のところ明確な政策レベルの評価の定義が存在するわけではなく、プロジェクト、プログラムのレベルよりも一段上のレベルの評価を念頭に置いたものである。政策レベル評価のための手法も確立しているわけではなく、他ドナー国・国際機関も今まさに試行錯誤を重ねて政策レベルの評価を行おうとしているところである。
|
|
|
2.2 評価のフィードバック体制の強化
|
|
ODA評価を拡充することにより、我が国ODAの質的向上及び透明性確保を実現するためには、評価によって得られた教訓・提言等のフィードバックが適切に行われ、今後の援助政策の企画・立案やプロジェクト形成の場面に活用されること、及び評価結果の情報開示を行うことが必要不可欠である。適切なフィードバックが行われなければ、評価活動を行ったとしても、ODAの質的改善は期待できない。
また、2000年9月末に開催されたOECD・DAC東京ワークショップでは、「評価のフィードバック体制」が主要テーマであった。こうした問題意識と東京ワークショップの結果を踏まえて、今後のフィードバック体制の強化について議論・検討が行われた。
討議の主要ポイントと今後の課題
本課題については、委員の報告、DAC東京ワークショップの報告を受け、評価のフィードバックが果たす重要性について援助関係者の共通認識が確認された。
討議の主たるポイントと今後の課題をまとめると、援助機関内部におけるフィードバックの効率化に関連する議論と、評価の結果を広く公開して透明性の確保につなげることに関連する議論の2つに大別される。
援助機関内部のフィードバック体制効率化に関する議論は、以下のとおりである。
-
1)効果的なフィードバック体制の確立:評価結果をプログラムの改善、企画・立案に効果的に活かすことの重要性、及び評価部門と事業担当部門との協力によるフィードバックを図ることの重要性が確認された。さらに評価結果を効果的にフィードバックするための具体的なメカニズムとして、例えば、援助機関内部に、意思決定者(組織の長又は同委任を受けた者、以下同じ)を長として、企画部門、事業部門及び評価部門のメンバーから構成される常設の「評価フィードバック委員会」(仮称)等、適切なフィードバックができるしくみの整備の有効性も議論された。
2)援助関係者の更なる意識改革:フィードバック体制強化に向けて、評価部門だけでなく、意思決定者や企画部門及び事業部門における更なる意識改革と、組織全体として評価の重要性を認識すること、さらには評価結果を最大限に活用することが大切である。特に、評価によって得られた教訓・提言等に基づいて、政策や事業計画の改善につなげていくという評価の役割を再認識することが重要課題である。これらの意識改革を進める具体策として関係者のためにワークショップを開催することが有益であるとの提案がなされた。
3)早期段階のフィードバック:事後評価のフィードバックだけではなく、事業の様々な段階においてフィードバックを活用し、適切に計画に反映させていくことが効果的な事業実施につながる。このことは、DAC東京ワークショップでも指摘されている。特に、事業開始から早期の段階でのフィードバックを適切に活用できる体制を確立していくことは、ODA事業の効率化にとって重要であることが確認された。
4)評価結果に係る情報の一元管理:外務省とJICA、JBIC、及びODA関係省庁の連携体制の下、評価結果に係る情報を一元管理し、必要な情報をタイムリーに引き出せるデータベースの構築や教訓集の作成等、より活用しやすい情報管理システムを整備することについて意見の一致が見られた。その第一歩として、援助機関の間で、既存データベースの相互活用を推進していくことが有効と考えられる。
5)相互活用に向けてのしくみづくり:援助機関内部だけでなく、他の援助機関の評価結果をより効果的に相互活用するためのしくみ作りについて、その必要性が確認された。上記の情報の一元管理により、各機関の計画作成・審査・実施等の場面において、評価によって得られた教訓・提言等をタイムリーに引き出すことを可能とし、さらにそれぞれの政策策定、事業計画作成等の場面に適用できる体制を確立することともに、外務省とJICA、JBIC及びODA関係省庁の参加による連絡会議を設置することが提案された。
-
上記の1)から5)は主に援助機関内部における評価のフィードバック体制強化に係る内容である。研究会会合では、評価のフィードバックは、広義において国民や被援助国をも対象に行われるべきであるという認識のもとに議論・検討が行われた。我が国国民や被援助国に対するフィードバックを強化して、透明性の確保につなげるという議論は以下のとおりである。
-
6)評価結果の公開と透明性確保:評価結果の透明性を確保するため、評価活動の内容及び評価結果を公表することの大切さが確認された。インターネット等を活用して、評価報告書、評価結果等を広く、解りやすく、かつ迅速に国民に公表し、透明性の確保に貢献することが必要である。
7)被援助国側へのフィードバック:評価結果について、被援助国側に対して確実にフィードバックすることの重要性が強調された。評価報告書の英文化や評価結果に関しての現地セミナー開催、ホームページ(英文)、本邦における評価に関する研修等による被援助国窓口機関、援助機関へのフィードバック、またこれら機関を通じての被援助国国民に対する我が国ODAの広報及び透明性確保を一層促進する必要がある。
8)被援助国側の参加促進:評価の質を向上し、より良いフィードバックを得るためには、被援助国側の視点・意見等を取り入れた評価を行うこと、或いは政策提言レベルから受益者レベルでの活動等幅広く開発活動に携わっているNGO等を積極的に活用して、相手国側のニーズを反映することが有益である。被援助国側関係者や対象受益者らの評価活動への参加を促進することによって参加型評価を積極的に実施するとともに、被援助国側の評価実施能力を強化していくためのエンパワーメント評価を推進し、援助事業全体の改善に結びつけていくような環境づくりが大切であるとの認識が示された。
9)我が国民間関係者の参加促進:また、我が国の民間(有識者、シンクタンク、NGO、企業等)関係者が有する専門知識・知見を活用することにより、評価並びにフィードバックの質をレベルアップし、透明性確保へつなげていくことの重要性も指摘された。
|
|
2.3 評価人材の育成と有効活用
|
|
ODA評価体制を拡充するためには、組織・制度の強化のみならず、評価活動に携わる人材「評価人材」の育成が必要不可欠である。評価人材には評価手法に堪能なだけでなく、専門分野への造詣、評価のしくみの熟知、援助や評価分野の深い経験等が求められる。評価全体のレベルアップを図り、また評価の透明性をより高めていくためには、内部要員の評価能力を向上させて、援助機関自体の評価実施体制を改善すると同時に、外部要員の育成も図り、評価のアウトソーシング体制を強化することが必須である。こうした問題意識を踏まえて、具体的な議論が行われた。
討議の主要ポイントと今後の課題
本課題については、委員の報告及び外務省により実施中の委託調査「評価人材の育成及び有効活用に関する調査研究」の報告を受けて、議論・検討が行われた。
討議の主たるポイントと今後の課題をまとめると、以下のとおりである。
-
1)評価実施体制の拡充:援助機関において、評価人材の育成を通じて評価実施体制をさらに拡充していくことの重要性が強調された。
2)評価人材の育成:大学院・研究教育機関等において評価に関する研修プログラムを強化・拡充するとともに、先進的な評価手法・事例等を学ぶために、世界銀行(WB)、アジア開発銀行(ADB)、国連開発計画(UNDP)等の国際機関及び他国援助機関との評価人材の派遣交流を推進し、海外大学院との連携等を強化することが必要かつ有効である。
3)日本評価学会等の活用:2000年9月に設立された日本評価学会等の専門学術機関を通じて、評価に関する知識・技術の向上を行うことが必要である。さらに、同学会が中心となって、評価の手法・手順、人材育成方法等についての研究・開発を進めたり、大学院生等を実際の評価業務に参画させることが有益である。また、各専門分野の知識を有する人材の確保・活用・育成することも必要である。
4)評価予算の拡充と市場(参加機会)の拡大:人材が育成されないことの大きな要因として、現在の評価の資質・能力を潜在的に有する人材が評価に関わる機会がそもそも少ないことが挙げられた。また、援助機関等が評価の重要性を認識し、予算を含む評価関連施策を拡充することで評価市場(参加機会)の拡大を図ることが重要である。
5)外部人的資源の積極的活用:援助機関の評価部門が必要に応じて外部専門家を短期雇用したり、評価業務自体を委託する等、評価の効率化を図るために、外部の人的資源を積極的に活用してアウトソーシングを推進することが大切である。同時に、適切な外部人的資源を活用することで透明性の確保も期待される。
6)評価人材のデータベース:現在、評価人材のデータベースが十分に整備されておらず、またその活用方法も検討されていない。そのため、評価人材のデータベースを開発し、外務省、JICA、JBIC、ODA関係省庁、コンサルタント、研修機関、国内公共事業実施機関がこれを有効活用することが必要である。
7) 評価人材の有効活用:国家公務員や一般企業に所属する評価人材をより有効に活用するために、国立大学教授や国家公務員を派遣した場合の代用者雇用に関する人件費負担等の措置や規定の柔軟化といったインセンティブの拡大が必要であることが確認された。
|
2.4 評価の一貫性の確保
(事前から中間・事後に至る一貫した評価システムの確立)
|
|
「政策レベル」、「プログラム・レベル」、「プロジェクト・レベル」の各段階において、適切な評価を行い、それぞれから効果的なフィードバックを得るためには、事前の審査段階から、事業実施、評価段階に至るまで、各段階において評価の重要性が理解され、かつ目標・指標設定、或いは評価の視点・対象等について、一貫性が確保されていることが重要である。一方、外務省、JICA、JBIC、及びODA関係省庁等の援助機関の間においても、評価の一貫性が横断的に確保されなければならない。
特に、目標や効果測定の指標を事前の段階からはっきりと設定してベースライン調査を行い、事業実施段階或いは事後のモニタリング・評価活動を通じて、事業によってどのような効果が現れたかを定量的・定性的に明らかにできる体制を整備することは、説明責任(アカウンタビリティ)の確保やフィードバック活用体制を向上させるに当たって必要不可欠である。
討議の主要ポイントと今後の課題
本研究会では、事前から中間、事後に至る評価システムの確立に向けて鋭意準備を進めているJICA、JBICからの報告を受け、本テーマに関する議論・検討が行われた。
討議の主たるポイントと今後の課題をまとめると、以下のとおりである。
-
1)「事前評価表」の作成:外務省及びJICA、JBICが中心となり、事前、中間、事後に至る評価の一貫性確保のための活動を推進し、指標設定方法、評価のタイミング、フィードバックの方法、標準的なガイドラインの作成等について、相互連携・調整を図ることは有意義である。その上で、個別プロジェクトの計画段階において、目的、指標、達成目標、評価計画、フィードバックのあり方を網羅した「事前評価表」を作成・活用することが有効である。
2)評価の一貫性に係る共通認識を確立するためのツール整備:JICA、JBICで行われている試みの問題点・課題等をレビューし、それを踏まえた具体的かつ標準的なガイドラインを作成することの意義が確認された。また、評価の一貫性に係る関係者の認識・理解をより確実なものとするために「費用効果分析に関するガイドライン」や「ODA評価用語集」等を作成することが有効であり、また「公平性」や「公益性」という評価指標も必要であるとの指摘もあった。
3)定量的・定性的な評価のバランス:JICA、JBIC両機関とも一貫性の確保に当たって、評価指標の設定に力点を置いていることが確認された。さらに、定量的分析に加え、定性的分析の重要性について意見が交わされ、評価においては定量的・定性的な手法の相互補完とバランスが重要であるとの指摘がなされた。
4)評価の一貫性確保に係る更なる研究:政策、プログラム、プロジェクトの各階層間における一貫性確保のあり方、及び外務省、JICA、JBIC、ODA関係省庁間の異なる組織間における一貫性確保の必要性が確認された。なお、評価の一貫性を確保する方策については、今後とも関係者の参加による更なる研究が必要であるということで意見一致をみた。
5) 評価の質の担保:指標の設定については、国・案件等で個別事情を配慮する必要があるとした上で、可能な限り統一的な尺度(指標)の設定、計画策定段階における包括的な検討等を通じて、評価活動のクォリティ・コントロールを行うことが重要である。
|
|
2.5 ODA関係省庁間の連携推進
|
|
我が国ODAは、現在、外務省、JICA、JBICのみならず、複数の関係省庁によって実施されており、それぞれのODA事業に対する評価もそれらの事業の担当省庁及び機関が独自に行っている。従って、外務省、JICA、JBICと関係省庁間では、一部情報の共有はあるものの、一般的にODA事業活動或いは評価活動に関する情報・意見交換は十分に行われてこなかったのが現状である。
また、2000年9月に対外経済協力審議会より発表された報告書「『人間を重視した経済協力』の推進について」では、政府全体としてのODA評価の一層の充実や連携の強化、ODA評価について意見交換・議論する場の創設等が提言されている。更には2001年1月からの「政策評価」の導入に向けて、政府関係省庁では準備が進められている。
このような背景を受けて、我が国ODAを効率的・効果的に実施していくためには、援助機関がそれぞれの分野で有している経験・ノウハウ、評価から得られた教訓、或いは個別の研究活動の成果等を共有し、現状を改善していくための連携体制を確立することが必要不可欠である。
討議の経緯と主要ポイント(ODA関係省庁の現状把握及び懸案事項の確認)
本研究会では、オブザーバーである17のODA関係省庁と会計検査院から、それぞれが行っているODA事業内容、評価活動、問題点に関する質問票調査を行うとともに、各オブザーバーからその内容に関する報告を受けた。
これらを受け、以下の点が明らかとなった。なお、各関係省庁のODA活動を取りまとめたものは、別表のとおりである。
-
a)各関係省庁のODA活動は、各省独自の事業展開がなされており、多種多様である。これに応じ、その評価活動も各省庁独自に行ってきており、部分的に進んでいる点もあるが、改善の余地も多い。
b)一方で、関係省庁の大部分がJICA・JBIC事業への協力等を行っているなど共通点も存在する。従って、こうした共通点を援助機関間の連携が可能かつ必要な部分として認識し、より効率的なODA評価体制を構築するために協力を推進していくことが今後ますます重要となる。
c)技術協力、専門家派遣等は、ほとんどの関係省庁で行われており、これに対する評価は今後の共通課題である。
これをもとに各関係省庁の行っているODA事業及びその評価活動の内容と、評価に係る関係省庁間の連携について、研究会で討議・検討を行ったところ、議論の主なポイントは、次のとおりである。
-
1)関係省庁間の意見交換・議論の有益性
本研究会に引き続き、関係省庁間の意見交換・議論の場を設置し、定期的に会合を開催していくこと、またこのような連携を進めることにより、援助機関における評価実施能力の向上を図っていくことが大切であるとの認識が深まった。
2)関係省庁間の連携強化の必要性
上記1)と同様、具体的かつ実践的な話し合いのできる場を創設し、また報告書等公開できるものは、他省庁に配布・交換する等、連携強化に向けて早期に実現が可能なことから着手していくことが肝要であるとの指摘が多くなされた。
3)「政策・プログラムレベル」の評価手法、共通課題の研究
「政策・プログラムレベル」の評価手法、共通課題の研究についても、今後関係省庁間の協力のもとに取組む必要があることが確認された。
連携強化に向けての具体的な議論
以上の議論とODA関連省庁の評価の実施状況、現在の連携体制を踏まえ、事務局より研究会としてのODA関係省庁間の連携強化へのステップに関する提言案(図1)を取りまとめ、議論を行った。研究会として概ね合意された内容は、次のとおりである。
-
i) 関係省庁間の意見交換の場の設置
今後の連携強化に当たっては、本研究会を引き継ぐものとして、2001年からODA関係省庁間の意見交換・議論の場を設置し(例:ODA関係省庁評価部門連絡会議)、定期的に会合を開催していくことが重要である。
ii) 評価活動及び成果についての情報共有・情報交換
ODA関係省庁間で、評価活動、成果についての情報共有・情報交換の体制を構築することが望ましい。
iii) 関係省庁による合同評価・評価セミナーの合同開催
関係省庁による合同評価の実施、評価セミナーの合同開催等について具体的検討を行うことが必要である。
|
図1 ODA関係省庁間のODA評価における連携の方向性 ※
-連携強化へのステップ-
-
iv) 評価に関する標準的なガイドライン、マニュアル、雛型の作成
各省がそれぞれのニーズに合わせて活用できる標準的なガイドラインやマニュアル、雛型の作成も有益なものとして、今後これらの作成について検討すべきである。
v) 共通テーマ、重要課題、評価手法研究等についての議論
共通テーマ、重要課題の抽出、絞込み、対応策の検討を行う。
検討課題例としては、以下の項目が挙げられる。
- 政策レベル及びプログラム・レベルの評価の導入に向けての体制整備、手法研究、標準的なガイドライン、マニュアル、雛型等の作成
- 援助国側の国益等、援助方針・計画等の目的に必ずしも盛り込まれない事項に対する評価方法、評価の観点等についての検討
- 専門家派遣、研修生受け入れ事業等の評価手法の検討
- フィードバック活用のためのしくみ
今後の課題
外務省、JICA、JIBC及びODA関係省庁間の連携の推進は、重要な課題であり、本件については関係省庁間の協力なくして推進し得ないものである。従って、引き続き来年以降もODA関係省庁が参加する連絡会議を外務省が中心となり設置することを検討すべきである。いずれにしても、我が国ODA全体としての効果的な評価体制を確立し、関係省庁間の連携を推進することが極めて重要である。
なお、このような援助機関の連絡会議の場に、有識者、シンクタンク、NGO等の民間からの関係者を含めることは、評価能力の一層の向上や、情報開示、透明性の確保の観点からも有益と考えられる。
|