パレスチナに“希望に満ちた壁画”誕生
不幸な歴史を背負って紛争が絶えなかったイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)の間で、「パレスチナ暫定自治合意(ガザ、ジェリコ合意)が調印されたのは1994年。これにより、ガザとヨルダン川西岸のジェリコにおけるイスラエル軍の撤退と、パレスチナ側への権限委譲が実施され、中東和平プロセスにとって、歴史的な一歩を踏み出した。
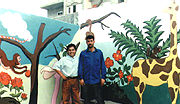 ”希望に満ちた壁”と神谷氏(パレスチナにて) 写真提供(UNDP) |
残念なのは、昨年(95年)のラビン首相の暗殺事件や、今年に入ってからの連続バス爆破事件(イスラム過激派の仕業とされている)など、ここにきて悲しい出来事が続いていることだが、各国が協力して和平路線を維持していくことが重要である。
日本政府は1993年9月、積極的な対パレスチナ援助を表明し、以来、国際機関を通じた援助や、直接援助に精力的に取り組んでいる。
日本政府は1993年9月、積極的な対パレスチナ援助を表明し、以来、国際機関を通じた援助や、直接援助に精力的に取り組んでいる。
壁に残された傷跡
中東和平のカギを握るそのガザ地区に、国連ボランティア計画(UNV)のスタッフとして、94年から派遣されている日本人がいる。神谷哲郎さんだ。その神谷さんが推進しているプロジェクトの1つに「壁画制作プロジェクト」がある。
「占領時代の名残りで、当時、壁という壁が、イスラエルへの抗議、政治的プロパガンダとして使われていた」と、神谷さん。
1967年以降、イスラエル占領下にあったガザ・ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人は、イスラエルに政治・経済などあらゆる面で支配され、厳しい軍事圧力の中で生きてきた。そうしたパレスチナ住民の怒りは、87年以降、インティファーダ(民衆蜂起)となって爆発。イスラエル治安部隊との衝突が繰り返され、女性や子供たちまでが石を投げ、抵抗運動に加わった。ガザの街では、いまもそのインティファーダ時代の傷跡が残っていて、路地の塀、家の壁、いたるところにイスラエルに抗議する殴り書きが見られる。
「壁画制作プロジェクト」は、この怒りや憎しみが塗り込められた壁の殴り書きを“未来の希望に満ちた壁画”に書き替えようというものだ。
「占領時代の名残りで、当時、壁という壁が、イスラエルへの抗議、政治的プロパガンダとして使われていた」と、神谷さん。
1967年以降、イスラエル占領下にあったガザ・ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人は、イスラエルに政治・経済などあらゆる面で支配され、厳しい軍事圧力の中で生きてきた。そうしたパレスチナ住民の怒りは、87年以降、インティファーダ(民衆蜂起)となって爆発。イスラエル治安部隊との衝突が繰り返され、女性や子供たちまでが石を投げ、抵抗運動に加わった。ガザの街では、いまもそのインティファーダ時代の傷跡が残っていて、路地の塀、家の壁、いたるところにイスラエルに抗議する殴り書きが見られる。
「壁画制作プロジェクト」は、この怒りや憎しみが塗り込められた壁の殴り書きを“未来の希望に満ちた壁画”に書き替えようというものだ。
石を絵筆に持ち替えて
15人のスタッフはみな20歳前後。インティファーダの頃、投石し、抵抗運動の英雄の顔やプロパガンダをスプレー書きしていた若者たちが、いまは絵筆を持って壁画制作に取り組んでいる。そのうちのひとりは「当時、投石はガザ市民としての義務だったが、こうして平和のもとで壁画を描けるなんて、とてもハッピーです」
イスラエル兵が撤退してから約2年。かつて石を投げていた子供たちの目から、恐怖や憎悪の影を窺い知ることはできない。
「いまは自由だ。イスラエル兵に怯えることもなく、好きな時に好きなだけ外出できる」と、ある青年は素直に喜ぶ。それは大人たちも同じだ。
平和の到来とともに壁画は日一日と増えてゆく。このガザ地区が、未来の希望に満ちた壁画で埋めつくされるのも、そう遠い話ではないだろう。
実は、この「壁画制作プロジェクト」で働く若者には1日10ドルの日当が支払われる。イスラエルによる封じ込めで経済の悪化が深刻さを増し、いま、ガザ地区の失業率は70%を超えていると言われるから、この「壁画制作プロジェクト」は、雇用創出という副産物も生み出していることになる。
石を絵筆に持ち替えた若いスタッフたちには、絵の腕を磨き、近い将来、会社組織にするという計画がある。そうした夢のある計画の牽引車としてここまで引っぱってきた神谷さんは、「顔の見える援助」が高く評価され、UNV・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。
イスラエル兵が撤退してから約2年。かつて石を投げていた子供たちの目から、恐怖や憎悪の影を窺い知ることはできない。
「いまは自由だ。イスラエル兵に怯えることもなく、好きな時に好きなだけ外出できる」と、ある青年は素直に喜ぶ。それは大人たちも同じだ。
平和の到来とともに壁画は日一日と増えてゆく。このガザ地区が、未来の希望に満ちた壁画で埋めつくされるのも、そう遠い話ではないだろう。
実は、この「壁画制作プロジェクト」で働く若者には1日10ドルの日当が支払われる。イスラエルによる封じ込めで経済の悪化が深刻さを増し、いま、ガザ地区の失業率は70%を超えていると言われるから、この「壁画制作プロジェクト」は、雇用創出という副産物も生み出していることになる。
石を絵筆に持ち替えた若いスタッフたちには、絵の腕を磨き、近い将来、会社組織にするという計画がある。そうした夢のある計画の牽引車としてここまで引っぱってきた神谷さんは、「顔の見える援助」が高く評価され、UNV・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。

