4 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の実施状況
ハーグ条約は、国際結婚が破綻した場合等の子の監護権(親権)に関する手続は、子が元々居住していた国で行うことが望ましいとの考えの下、国境を越えて不法に連れ去られた子を、原則として元の居住国に返還するための協力について定めた条約である。また、国境を越えた親子間の面会交流の機会を確保するために、各締約国が援助を行う義務についても定めている。
ハーグ条約は、2014年4月1日に日本について発効し、同日、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する法律が施行された。2016年12月末時点で、日本を含め95か国がこの条約に加盟している。
ハーグ条約は、各締約国において「中央当局」として指定された機関が相互に協力することにより実施されている。日本では外務省が中央当局として、様々な分野の専門家の知見を得ながら、条約の適切な実施のため、外国中央当局との連絡・協力、子の所在特定、問題の友好的解決に向けた協議のあっせんなどの当事者に対する支援を行っている。
ハーグ条約発効後2016年12月末までの2年9か月間に、外務大臣は、子の返還を求める申請を118件、子との面会交流を求める申請を111件、計229件の申請を受け付けた。そのうち、外国から日本への子の返還が14件、日本から外国への子の返還が19件実現したほか、面会交流が実現した例が多数あるなど、日本として着実に条約を実施している。
| 返還援助申請 | 面会交流援助申請 | |
|---|---|---|
| 日本に所在する子に関する申請 | 67 | 86 |
| 外国に所在する子に関する申請 | 51 | 25 |
2016年2月には、ドイツでハーグ条約の運用の改善に取り組んできたドイツの元裁判官を日本に招へいし、その知見を日本の関係者と共有した。また、6月には、ハーグ国際私法会議(HCCH)事務局及び早稲田大学との共催で、「ハーグ条約に係るアジア太平洋シンポジウム」を開催し、ハーグ条約実施に携わる関係者の知見を深め、実施体制の強化を図るとともに、アジア太平洋地域におけるハーグ条約非締約国に締約国の知見を共有する機会を設けた。同シンポジウムでは、アジア太平洋を中心に21の国と地域から64人が参加し、活発な議論が行われた(コラム「『ハーグ条約に係るアジア太平洋シンポジウム』に参加して」258ページ参照)。
このほかにも外務省は、在外公館又は国内の地方自治体、関係機関等でのセミナー実施、多言語でのリーフレット配布などの広報活動に力を入れている。
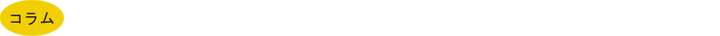
弁護士 磯谷文明
2016年6月29日、30日の2日間にわたり、外務省と早稲田大学、ハーグ国際私法会議事務局の共催で、早稲田大学において「ハーグ条約に係るアジア太平洋シンポジウム」が開催されました。私は、アジア諸国から代表者を招き、ハーグ条約に関するさまざまな論点を議論する非公開のセッションにおいて、共同司会を務めました。

非公開のセッションでは参加者は4つのグループに分けられ、いずれのグループも、①常居所地国/監護の権利、②条約13条1項bの重大な危険、③強制執行、④タイムフレームという4つのテーマを、各90分ずつ検討しました。各グループはそれぞれの教室にとどまり、各テーマを担当する司会が巡回する形式で行われました。ちなみに、私は、オーストラリア家庭裁判所のビクトリア・ベネット判事と共に第1のテーマを担当しました。
「共同司会」とは言うものの、実際にはベネット判事が上手に仕切られ、豊富なご経験を踏まえてわかりやすく解説されましたので、私は隣で勉強させていただいたというのが実態でした。議論の題材は事務局が用意した架空の事例でしたが、これがとても適切で、いずれのグループでも活発な意見交換を誘っていました。非締約国からの代表者のなかには、条約にあまりなじんでおられない方も少なくありませんでしたが、セッションを通して条約の主要論点を効率よく把握できたのではないかと思います。
セッションは2日目の午前まで続き、午後は日本の弁護士や調停委員によるハーグ模擬調停が披露されました。後に聞いたところ、弁護士や調停委員が自分たちの経験を踏まえ、苦労して作り上げたシナリオだったとか。終了後は出演者が会場からの質問を受けましたが、外国からの参加者から、日本では調停に裁判官が直接関わっていることに少し驚いたという感想も聞かれました。善し悪(あ)しはともかく、日本の調停のユニークな点を世界に発信できたのではないかと思いました。
2014年4月の条約発効から、日本は少しずつではありますが実務を積み重ねてきました。もちろん全てがうまくいっているわけではなく、実務に関わる中で課題を感じることもあります。しかし、そういった経験を世界、とりわけ非締約国の多いアジア地域に発信し、共有していくことは、締約国を広げる観点から大変重要なことだと思われます。
今回のシンポジウムに参加して下さった代表者の方々が母国に戻り、条約の輪を広げる礎となって下さることを期待しています。
