日本の安全保障政策
小田原外務大臣政務官の第53回ミュンヘン安全保障会議出席(結果)
平成29年2月21日


1 会議概要
(1)2月18日(土曜日),小田原潔外務大臣政務官は,独・ミュンヘンにおいて開催された第53回ミュンヘン安全保障会議(注:会議日程は2月17日~19日)に出席しました。
(2)今回の会議には,独(メルケル首相、ガブリエル外相、フォン・デア・ライエン国防相),米(ペンス副大統領、マティス国防長官),英(ジョンソン外相、ファロン国防相),仏(エロー外相、ル・ドリアン国防相),露(ラヴロフ外相),EU(モゲリーニ上級代表),NATO(ストルテンベルグ事務総長)をはじめとする各国首脳・閣僚計500名以上が参加。「ポスト真実,ポスト西側諸国,ポスト秩序(Post-Truth, Post-West, Post-Order?)」との全体テーマの下,欧州安全保障や米欧関係、テロ,難民問題,アジア情勢、中東・アフリカ情勢を始めとするグローバルな安全保障問題について幅広い議論が行われました。
(2)今回の会議には,独(メルケル首相、ガブリエル外相、フォン・デア・ライエン国防相),米(ペンス副大統領、マティス国防長官),英(ジョンソン外相、ファロン国防相),仏(エロー外相、ル・ドリアン国防相),露(ラヴロフ外相),EU(モゲリーニ上級代表),NATO(ストルテンベルグ事務総長)をはじめとする各国首脳・閣僚計500名以上が参加。「ポスト真実,ポスト西側諸国,ポスト秩序(Post-Truth, Post-West, Post-Order?)」との全体テーマの下,欧州安全保障や米欧関係、テロ,難民問題,アジア情勢、中東・アフリカ情勢を始めとするグローバルな安全保障問題について幅広い議論が行われました。
2 セッション「太平洋は泰平?東アジアの安全保障と朝鮮半島」概要
(1)小田原政務官は,18日(土曜日)午後5時(現地時間、以下同)より約120分にわたり行われた「太平洋は泰平?東アジアの安全保障と朝鮮半島(Pacific No More? Security in East Asia and the Korean Peninsula)」と題するセッションに出席しました。このセッションでは,尹炳世外相(韓)、ウン・エンヘン国防相(星)、ダン・サリバン上院議員(米)、ラッシーナ・ゼルボCTBTO事務局長、傅瑩(Fu Ying)全人代外事委員会主任委員(中)がパネリストとして登壇し、現下の北朝鮮情勢への対応や米中関係を中心に,率直な議論が行われました。
(2)小田原政務官は、各パネリストが発言した後、フロアから、議論がなされた事項に係る日本の基本的な立場について発言を行いました。その概要は次のとおりです。
(2)小田原政務官は、各パネリストが発言した後、フロアから、議論がなされた事項に係る日本の基本的な立場について発言を行いました。その概要は次のとおりです。
- 昨(17)日、ドイツ・ボンにおける日米韓、日韓、日中の各外相会談でも議論された北朝鮮問題について、今月12日の弾道ミサイルの発射の強行や、昨年2度にわたって行った核実験,様々な種類のミサイルの立て続けの発射は,まさに新たな段階の脅威である。日本としては,米国,韓国等と緊密に連携しつつ,また,中国の協力も得つつ,北朝鮮に対し,挑発行動の自制や,関連する安保理決議等の遵守を求めていく。特に日本と韓国は地理的にも隣接し,戦略的利益を共有するパートナーである。今こそ力を合わせ,北朝鮮の無謀な挑発の抑止のため協力すべき。さらに,拉致問題は,主権及び国民の生命と安全に関わる問題である点を指摘した。こうした厳しい安全保障環境にあって,日本としては,この地域の平和と安定に向けて一層積極的な役割を果たしていく。
- 日米は多くのものを共有するが,その一つは太平洋である。アジア太平洋地域の安全保障を維持する上で,米国の関与は必要不可欠。揺らぐことのない日米同盟はアジア太平洋地域における平和,繁栄及び自由の基礎。この点,先週の日米首脳会談では,日米同盟の絆を一層強固にするとともに,アジア太平洋地域と世界の平和と繁栄のために日米両国で主導的役割を果たしていくことを確認した。更に,日米同盟を基軸として,日米韓や日米豪,日米印など,地域のパートナーとの協力強化が重要。さらに中・露との間でも信頼関係の増進に取り組んでいきたい。
- 地域の安全保障を議論する上で,よりグローバルな視点を持つことが重要。国際社会の安定と繁栄の鍵を握るのは,「2つの大陸」と「2つの大洋」の交わりによって生まれるダイナミズムである。「2つの大陸」とはアジアとアフリカを,「2つの大洋」とは,太平洋とインド洋を指す。地域の平和と安定の確保のためには,今後の世界の成長の源とも言える「インド太平洋」の連結性を高め,自由で開かれたものとしていく必要がある。
- この観点から,海洋安全保障は重要な課題。この点、海における法の支配は重要。日本は,海における法の支配の貫徹のため,途上国に対する能力構築等の取組を引き続き実施していく。
3 二国間会談の実施
小田原政務官は,この機会に,アリ・バングラデシュ外相、フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官及びタバン・デン南スーダン共和国第一副大統領と個別に二国間会談を行ったところ,各会談の概要は以下のとおりです。
(1)アリ・バングラデシュ外相(18日(土曜日)14:00~14:30)
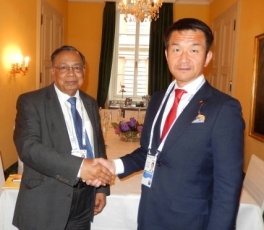
小田原外務大臣政務官から,ダッカ襲撃テロ事件後のバングラデシュ政府による安全対策措置に謝意を表明するとともに,在住日本人の安全確保に対する一層の取組を要請しました。また、我が国としても「包括的パートナーシップ」の下,両国友好関係の更なる強化に向け,可能な協力を引き続き行っていくことを伝えました。
これに対し,アリ外務大臣から,バングラデシュ政府による治安対策を説明しつつ,国際協力事業関係者を含む邦人の安全確保の徹底に全力を尽くす旨述べるとともに、日本の国際協力事業の円滑な実施を確保し,日本と緊密に協力してテロとの戦いに取り組んでいきたい旨を述べました。また,双方は,地域協力,国際場裡での協力等についても連携していくことを確認しました。
これに対し,アリ外務大臣から,バングラデシュ政府による治安対策を説明しつつ,国際協力事業関係者を含む邦人の安全確保の徹底に全力を尽くす旨述べるとともに、日本の国際協力事業の円滑な実施を確保し,日本と緊密に協力してテロとの戦いに取り組んでいきたい旨を述べました。また,双方は,地域協力,国際場裡での協力等についても連携していくことを確認しました。
(2)フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官(18日(土曜日)14:30~15:00)

小田原政務官から,難民問題は国際社会全体の課題である,人道支援とともに,難民発生の根本原因の解決に資する開発協力を連携して実施するという方針に変わりはない旨述べました。また,小田原政務官は,日本は,昨年のG7伊勢志摩サミットで発表した総額約60億ドルの支援と,国連総会で表明した総額28億ドル規模の貢献策に沿って,難民及び受入れ国・コミュニティ支援を着実に実施する旨述べました。さらに小田原政務官は,日本は「人間の安全保障」に基づき,引き続き,グランディ国連難民高等弁務官と協力して難民支援に取り組んでいくとして,中東やアフリカ等における難民支援のためにUNHCRに約8,800万ドルを拠出する旨述べました。
グランディ高等弁務官から,シリアの内戦など大きな危機状況に対して解決策は見いだせないものの,難民への支援は続けていく必要があると説明がなされるとともに,日本からの支援に感謝する,日本とは引き続き協力して取り組んでいきたい旨が述べました。その他両者は,日本のNGOとの関係強化や邦人職員の増強等について意見交換を行いました。
グランディ高等弁務官から,シリアの内戦など大きな危機状況に対して解決策は見いだせないものの,難民への支援は続けていく必要があると説明がなされるとともに,日本からの支援に感謝する,日本とは引き続き協力して取り組んでいきたい旨が述べました。その他両者は,日本のNGOとの関係強化や邦人職員の増強等について意見交換を行いました。
(3)タバン・デン南スーダン共和国第一副大統領(18日(土曜日)16:00~16:40)

冒頭,小田原政務官から,日本として,南スーダンの平和と安定及び国造りに貢献していく考えを表明し,国際機関を通じた2,200万ドルの人道・復興支援の実施を決定した旨伝えました。また、小田原政務官からは,衝突事案や市民に対する殺傷行為が報告されていることを深く憂慮している旨述べました。
その上で,南スーダン政府を含む全ての当事者が全ての敵対行為の停止を始めとする衝突解決合意を着実に履行すること、包摂的な国民対話の実施に真剣に取り組むこと,並びに,国連南スーダン派遣団ミッション(UNMISS)の地域保護部隊が早期に展開することを強く期待する旨述べ,南スーダン政府の対応を求めました。
これに対し,タバン・デン第一副大統領は,南スーダンにおいて戦争やジェノサイドは起きていないことを説明するとともに,引き続き、衝突解決合意の履行を通じて平和を実現していきたい旨述べました。また,タバン・デン第一副大統領からは,これまでの日本による南スーダンに対する支援への謝意が表明され,日本との協力を続けたい旨述べました。
その上で,南スーダン政府を含む全ての当事者が全ての敵対行為の停止を始めとする衝突解決合意を着実に履行すること、包摂的な国民対話の実施に真剣に取り組むこと,並びに,国連南スーダン派遣団ミッション(UNMISS)の地域保護部隊が早期に展開することを強く期待する旨述べ,南スーダン政府の対応を求めました。
これに対し,タバン・デン第一副大統領は,南スーダンにおいて戦争やジェノサイドは起きていないことを説明するとともに,引き続き、衝突解決合意の履行を通じて平和を実現していきたい旨述べました。また,タバン・デン第一副大統領からは,これまでの日本による南スーダンに対する支援への謝意が表明され,日本との協力を続けたい旨述べました。

