ODAと地球規模の課題
外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ「若手外国人とともに歩む~次世代に向けた挑戦~」(概要と評価)
平成26年2月25日
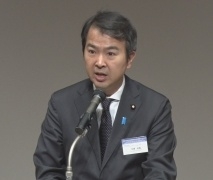
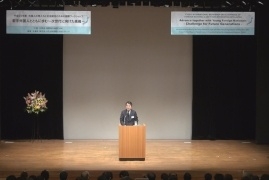
2月21日,外務省は,国際移住機関(IOM)との共催により,目黒区及び財団法人自治体国際化協会(クレア)の後援の下,めぐろパーシモンホールにおいて,標記ワークショップを開催した(内外の有識者,在京外交団や一般市民を含め約200名が参加)。本ワークショップでは,冒頭,石原宏高外務大臣政務官が開会の挨拶を行い,スウィングIOM事務局長が基調講演を行ったほか,アンツィンガー・エラスムス大学(オランダ)教授による欧州の経験に基づく社会統合のための提言,韓国及びブラジル出身の若手外国人による体験に基づいたプレゼンテーションに続き,パネルディスカッションでは活発な議論が展開されたところ,概要と評価は以下のとおり。
1.ワークショップの概要と評価
(1)今回のワークショップでは,欧州の多文化共生の第一人者から欧州の有益な事例紹介があったのに続き,10代で来日し,日本語修得や進学,就職,病気など様々な問題を克服し,自分の夢を実現した2名の若手外国人(韓国籍の看護師及びブラジル国籍の中学教師)から体験談が述べられ,参加者から大きな感動と評価を得た。その後,(ア)教育の問題,(イ)多様性の受け止め方,(ウ)次世代の外国人の課題の3点を中心に,報道,教育,在日外国人,企業といった各界のパネリストによる議論が行われた。
(2)グローバル化,少子高齢化が進む日本の成長を促すためには,外国人の力を活用することが必要不可欠となっている。そのためには,当事者である外国人側の努力のみならず,日本人側も多様な価値観を持った外国人をどのように受け入れ,それを如何に日本の成長につなげていくかが鍵となる。本ワークショップではそのような問題を初めて取り上げ,若手外国人との共生に向けて様々な課題に関する認識を共有し,同問題の重要性とともに多様な意見を発信できたことは,外国人材の活用が議論されている時だけに時宜にかなったものであり,有意義であった。
2.パネルディスカッションにおけるパネリスト意見及び議長総括(議長:山田伸二・日本放送協会(NHK)解説委員)
(1)日本語教育の現場においてボランティア任せになっている現状を変える必要がある。日本語能力に関係なく学年齢に合わせた児童・生徒の扱いや外国人児童・生徒に対する就学義務を課す等の法的制度の確立が必要である。
(2)外国人を通して,日本人は新しい豊かな意識や物の考え方を新たに高められる格好の機会を与えられた。教育の意識改革を通じて社会統合に貢献したい。
(3)在日の若手フィリピン人は,コミュニティが組織化されていないため,教育や言語の面で問題がある。そのため,在日若手フィリピン人に対して個別カウンセリングを行っている。
(4)人の移動には高度人材,建設労働者,日系人等様々な層の移動がある。そのような外国人が日本社会にとどまり,日本の適切なリソースとなったときに初めて社会統合が達成されると考える。日本のリソースとして如何に外国人を活用するかが鍵である。
(5)「多様性」を重視し外国人留学生を多く採用したところ,企業の環境改革に大きく貢献した。外国人社員が組織の意思決定に参加できる管理職に登用されることによって,長時間労働,古い風習,女性の活躍の場など日本企業において長年解決できなかったことが,一瞬にして解決される可能性を秘めている。
(6)こうした議論を踏まえ,議長より次のとおり総括があった。(1)日本社会が多様性を認めることは,マイノリティー(女性,高齢者,障がい者)の存在を認めることであり,これは外国人にとっても住みやすい社会を作るということにつながる,(2)在日の2世,3世の若手外国人が頑張って成功すれば,日本社会のパワーも倍増する,(3)欧州ではかつて移民排斥運動が起こった。これは他人事ではない。日本人も過去の歴史を勉強する必要がある。

