タイ王国
タイ王国(Kingdom of Thailand)
基礎データ

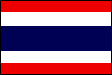
一般事情
1 面積
約51万平方キロメートル
2 人口
6,605万人(2025年)
3 首都
バンコク
4 民族
大多数がタイ族。その他 華人、マレー族等
5 言語
タイ語
6 宗教
仏教 94%、イスラム教 5%
7 略史
タイ王国の基礎は13世紀のスコータイ王朝より築かれ、その後アユタヤ王朝(14~18世紀)、トンブリー王朝(1767~1782)を経て、現在のチャックリー王朝(1782~)に至る。1932年立憲革命。
政治体制・内政
1 政体
立憲君主制
2 元首
マハ-・ワチラロンコン・プラワチラクラーオチャオユーフア国王陛下(ラーマ10世王)
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, The Kingdom of Thailand
(2016年10月即位)
3 議会
- 下院500議席(公選)
- 上院200議席(小選挙区比例代表並立制)
4 政府
- (1)首相名 アヌティン・チャーンウィーラクン(Mr. Anutin Charnvirakul)
- (2)外相名 シーハサック・プアンゲートゲーオ(Mr. Sihasak Phuangketkeow)
5 内政・社会状況
(1)タイの政治変遷
1932年の立憲革命から近年に至るタイの政治体制の変遷については、世界大戦や共産主義勢力の東南アジア地域での拡大といった国際情勢を反映して軍部中心の権威主義体制が長く続いた後、1980年代から1990年代にかけて民主化が進展し、冷戦終結による軍部の影響力が相対化する中で「1997年憲法」の下で急速に勢力を拡大したタクシン党首率いるタイ愛国党やその後継政党と、これに反発する勢力の政治的対立が深刻化してきた。
(2)最近の内政動向
2023年5月14日に下院総選挙を実施し、第二党の「貢献党」(旧野党、タクシン元首相派)と第三党の「名誉党」(旧与党、保守派)等が、大躍進し第一党となった「前進党」(旧野党、改革派)を排除する形で連立を組み、旧与野党11党による大連立政権が樹立。貢献党のセター氏が首相に就任したものの、2024年8月の憲法裁判所判決により失職し、同月、タクシン元首相次女のペートンターン首相が首相に就任した。2025年8月、ペートンターン首相とカンボジアのフン・セン上院議長との電話でのやり取りをめぐり、憲法裁判所はペートンターン首相失職の判決を下した。
同年9月、アヌティン名誉党党首が首相に就任し、少数与党政権を発足。12月、同首相は憲法改正を巡る与野党の対立を理由に下院解散を決定。2026年2月に総選挙の実施が予定されている。
外交
タイは、伝統的に全方位外交を基本としつつ主要国との距離を内外の事情に応じて変更する柔軟な外交を展開している。その基本的な姿勢は最近も変わっていない。その上でASEAN諸国との連携と、日本、米国、中国といった主要国との協調を外交の基本方針としている。
近年は、積極的な経済外交を展開し、中東やEU諸国との関係強化の動きが見られる。国際的に関心の高い問題に対して声明を発表する等、国外の情勢や地球規模課題等について立場表明を行う傾向がある。また地政学的にメコン地域の中核を成すことから地域情勢にも積極的に関与する傾向が見られる。
国防
1 軍事予算
2,000億バーツ(2025年版ミリタリーバランス)
2 兵役
徴兵2年、予備役20万人
3 兵力
正規36万850人(陸軍245,000人、海軍69,850人、空軍46,000人)(2025年版ミリタリーバランス)
経済
1 主要産業
製造業が主要産業となっており、タイGDPの約30%を稼いでいる。一方、農業については、就業者数ではタイ就業者数全体の約30%を占める産業となっているが、GDPのシェアでは10%未満にとどまる。また、タイ経済の柱は観光であり、例えば、新型コロナウィルス感染症拡大前の2019年には海外からの観光収入が605億ドル(世界第4位)となった。
2 GDP
5,246億ドル(名目、2024年、IMF)
3 一人当たりGDP
7,492ドル(2024年、IMF)
4 経済成長率
2.5%(2024年、タイ国家経済社会開発委員会)
5 消費者物価指数(総合)
-0.1%(2025年)、0.4%(2024年)(タイ商務省)
6 失業率
1.0.%(2024年、IMF)
7 総貿易額
- (1)輸出3,007億ドル(2024年、タイ商務省)
- (2)輸入3,055億ドル(2024年、タイ商務省)
8 主要貿易品目
- (1)輸出 自動車・同部品、自動データ処理装置・同部品、貴石・宝石類(2024年、タイ商務省)
- (2)輸入 原油、電子集積回路、機械・同部品、電機機器・同部品(2024年、タイ商務省)
9 主要貿易相手国・地域(2024年、タイ商務省)
- (1)輸出 1.米国(18.3%)2.中国(11.7%)3.日本(7.7%)
- (2)輸入 1.中国(26.4%)2.日本(9.4%)3.台湾(6.8%)
10 通貨
バーツ(Baht)
11 為替レート
1ドル=31.1バーツ(2025年12月、タイ中央銀行(月中平均))
12 経済概況
(1)概観
2014年はタイでクーデターが発生するなど政情混乱等により、1.0%の緩やかな成長率となった。その後、外需を中心に回復し、経済成長率は概ね3~4%台で推移した。しかしながら、2019年には米中貿易摩擦の影響もあり2.2%の成長率にとどまった。2020年には、世界的な新型コロナウィルス感染症の蔓延の影響により、-6.1%と2009年以来のマイナス成長となったが、世界経済の回復による輸出の回復、海外観光客数の回復もあり改善し、2024年の成長率は2.5%となった。2025年は、米国の関税政策発動前の駆け込み需要もあり輸出が大きく増加した一方、GDP比約90%まで上昇した家計債務問題や製造業の低迷等から成長率は2.0%程度にとどまる見込み。
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長率 | 2.7 | 1.0 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | -6.1 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 2.5 |
| インフレ率 | 2.2 | 1.9 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 6.1 | 1.2 | 0.4 |
(2)対外経済関係等
ア タイの二国間のFTA/EPA
- <締結済みの主な協定>
- 日本(JTEPA、2007年11月発効)
- 豪州(TAFTA、2005年1月発効)
- ニュージーランド(TNZFTA、2005年7月発効)
- チリ(2015年11月発効)
- <アーリーハーベストを開始済みの主な協定>
- インド(2004年9月発効、2012年1月に追加第2議定書へ署名):家電製品、自動車部品など、82品目の関税を先行して引き下げ開始
- ペルー(追加第3議定書署名、2011年12月発効)
- <交渉中の主な協定>
- EU(2013年5月に交渉開始、2014年4月には第4回交渉実施、2014年のクーデターにより交渉停止、2023年1月に交渉再開で合意)
- パキスタン(2015年8月に交渉再開)
- トルコ(2017年7月に交渉開始)
- スリランカ(2018年7月に交渉開始)
イ ASEAN加盟国としてのFTA/EPA(締結済みの協定)
- 日本(AJCEP、2009年6月発効)
- インド(AIFTA、2010年1月発効)
- 韓国(AKFTA、2010年1月発効)
- 豪州・NZ(AANZFTA、2010年3月発効)
- 中国(ACFTA、2010年1月発効)
ウ 地域的な包括的経済連携協(RCEP)
2022年1月1日より、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ラオスの10か国で発効(韓国は22年2月1日に発効)。
経済協力
日本の援助実績
| 年度 | 円借款 | 無償資金協力 | 技術協力 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94.34 | 0.14 | 28.27 |
| 2020 | – | 1.74 | 16.74 |
| 2021 | – | 2.11 | 25.03 |
| 2022 | 500.00 | 6.76 | 27.93 |
| 2023 | – | 6.78 | 25.49 |
| 累計(億円) | 24,289.02 | 1,742.55 | 2,469.14 |
- (注)
- 1 年度の区分及び金額は、円借款及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は予算年度の経費実績ベースによる。
2 累計金額は、円借款は借款契約ベース、無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は予算年度の経費実績ベースによる。
二国間関係
1 総論
日タイ両国は600年にわたる交流の歴史を持ち、伝統的に友好関係を維持している。長年の両国の皇室・王室間の親密な関係を基礎に、政治、経済、文化等幅広い面で緊密且つ重層的な関係を築いており、人的交流は極めて活発である。2022年は日タイ修好135周年を迎えた。
(1)人の交流
タイにおける在留邦人は70,421人(2024年)に上る。また、タイへの日本人渡航者は新型コロナウィルス感染症の世界的蔓延の影響により、年間約9,500人(2021年)に激減したが、2024年は約115万人まで回復した。
日本における在留タイ人は65,398人(2024)、また日本へのタイ人渡航者は新型コロナウィルス感染症の世界的蔓延の影響により、2021年は年間約3,000人に激減したが、2024年は約105万人まで回復した。
(2)ハイレベル交流
2025年5月には岩屋外務大臣が訪日したマーリット外相と会談を実施し、経済・安全保障分野の協力強化を確認したほか、カンボジアとの武力衝突発生後は日・タイ外相電話会談等を通じて緊張緩和を働きかけた。
アヌティン政権発足後は、同年12月にシーハサック外相が訪日し、茂木外務大臣とワーキングランチを実施した。
2 経済関係
1980年代後半以降、日本企業は円高を背景に積極的にタイに進出し、タイの経済成長に貢献。現在、タイ進出日系企業数は、6,083社(2024年、JETRO調査)を数える。また、タイはメコン地域開発を進める上での日本の重要なパートナーである。
(1)日本からタイへの輸出入(日本財務省)
ア 貿易額 (財務省貿易統計、単位:億円)
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出(タイへ) | 35,072 | 33,198 | 33,870 | 29,744 | 33,004 | 35,625 | 32,906 | 27,226 | 36,246 | 42,674 | 41,170 | 40,219 |
| 輸入(タイから) | 21,503 | 22,995 | 24,711 | 21,896 | 25,502 | 27,707 | 27,651 | 25,401 | 28,931 | 35,000 | 36,107 | 37,383 |
イ 主要品目(タイ商務省)
タイから日本への輸出:電気機器、機械、自動車・同部品、加工鶏肉等
タイの日本からの輸入:鉄及び鉄鋼、機械・同部品、自動車関連の部品電気機器・同部品
(2)日本からタイへの直接投資(タイ投資委員会、認可ベース)
| 年 | 件数 | 金額(バーツ) |
|---|---|---|
| 2014 | 417 | 1,819億3,200万 |
| 2015 | 451 | 1,489億6,400万 |
| 2016 | 296 | 808億1,100万 |
| 2017 | 270 | 918億100万 |
| 2018 | 315 | 936億7,500万 |
| 2019 | 217 | 880億6,700万 |
| 2020 | 210 | 643億5,709万 |
| 2021 | 189 | 735億300万 |
| 2022 | 216 | 499億6,000万 |
| 2023 | 275 | 654億7,200万 |
| 2024 | 295 | 623億400万 |
(累積外国直接投資額において、日本はタイにとっての最大の投資元)
(3)インフラ
タイにおけるインフラ海外展開として、日本は鉄道整備をはじめとする各種案件について官民を挙げて売り込みを実施している。このうち、首都バンコクにおける都市鉄道については、都市鉄道新線パープルラインの車両及び信号システム並びにメンテナンス保守請負業務や、レッドラインの車両及び信号システム等を日本企業連合が受注している。とりわけパープルラインについては、我が国鉄道事業者が海外の鉄道事業の保守請負業務を受注した初めての案件となっている。
(4)観光
観光客誘致・人的交流については、2013年7月、日ASEAN友好協力40周年を契機として、我が国は、タイ国民の短期滞在者に対して、ビザ免除措置を開始した影響もあり、訪日タイ人数は増加傾向にある。2019年は約132万人(同約16%増)で、過去最高を記録したが、新型コロナウィルス感染症の影響で2020年は約22万人、2021年は年間約3,000人に激減したが、2022年は約20万人まで回復した。なお、新型コロナウイルス拡大前の2019年時点で、訪日外国人の国・地域別ではタイは6番目に訪日者数が多い国・地域となっている。
| 年 | タイ人渡航者数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2013 | 約45万人 | 約74%増 |
| 2014 | 約65万人 | 約45%増 |
| 2015 | 約80万人 | 約21%増 |
| 2016 | 約90万人 | 約12%増 |
| 2017 | 約100万人 | 約11%増 |
| 2018 | 約114万人 | 約14%増 |
| 2019 | 約132万人 | 約16%増 |
| 2020 | 約22万人 | 約83%減 |
| 2021 | 約3,000人 | 約99%減 |
| 2022 | 約20万人 | 約7,083%増 |
| 2023 | 約100万人 | 約402%増 |
| 2024 | 約115万人 | 約15%増 |
他方、タイへの日本人渡航者数については、2013年に約153万人を記録し2014年に政治情勢の影響を受け、一時、約127万人まで減少した。その後、2019年には約180万人に達し、過去最高を記録したが、新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延の影響により、2020年には約35万人、2021年には約9,500人に止まっていたが、水際措置の緩和を受けて、2022年には約29万人まで回復した。
| 年 | 訪タイ日本人渡航者数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2013 | 約153万人 | – |
| 2014 | 約127万人 | 約17%減 |
| 2015 | 約138万人 | 約8%増 |
| 2016 | 約143万人 | 約3.6%増 |
| 2017 | 約154万人 | 約7.6%増 |
| 2018 | 約164万人 | 約7.1%増 |
| 2019 | 約180万人 | 約9.7%増 |
| 2020 | 約35万人 | 約81%減 |
| 2021 | 約9,500人 | 約97%減 |
| 2022 | 約29万人 | 約2966%増 |
| 2023 | 約81万人 | 約180%増 |
| 2024 | 約105万人 | 約23%増 |
(5)地方自治体の動き
近年では、我が国の地方自治体によるタイとの関係を構築しようとする動きが見られる。この背景には、東南アジア諸国の経済成長に伴うマーケットの拡大と共に、中国への進出を巡る環境の変化に伴う売り込み先の多角化の他、2013年7月に実施された短期査証免除措置による訪日タイ人観光客の増加、地方からも引き続き中小企業を中心とする企業のタイ進出が続いていることなどが上げられる。新型コロナウィルスの影響により、地方自治体関係者のタイ訪問は一時的に停滞したが、水際措置の緩和により、2022年以降、再び活発化している。
3 文化関係
(1)総論
昭和の時代から、「おしん」をはじめとする日本のドラマや「ドラえもん」、「一休さん」をはじめとするアニメが放映され、現代においてもアニメが多数放映されていることから、幅広い世代に日本のポップ・カルチャーが浸透しており、その人気度は非常に高い。また、日本語学習者を中心にいけ花、茶道、かるた、剣道などのサークル・団体が活動しており、日本の伝統文化に対する関心も総じて高い。日タイ修好135周年の2022年、両国の新型コロナウィルスに関する水際措置が緩和されたこともあり、バンコク国立博物館における日タイ陶磁器の展示会など、年間を通じ、様々な交流事業が実施された。日本ASEAN友好協力50周年を迎えた2023年には、三味線コンサートを始め、年間を通じて、記念文化交流行事が実施された。また、民間企業主催による総合的な日本文化イベントも年に数回開催されており、中には数十万人規模の来場者を誇るイベントも開催されている。
(2)日本語教育
日本語学習者は約18万4千人(2018年度より約1,000人減)、日本語教育機関は676機関(同比17機関増)となっている(2021年度「海外日本語教育機関調査」(国際交流基金))。日本語は、中等教育機関における第二外国語の一つとして位置付けられており、中等教育段階の学習者が多い。2014年度から、中等教育機関における日本語教育を支援するため、「日本語パートナーズ派遣事業」が開始され、日本語教育の質的量的向上が期待されている。
(3)青少年交流
青少年交流事業「JENESYS」「東南アジア青年の船」「アジア高校生架け橋プロジェクト」等による交流のほか、スポーツ交流、子供親善大使等により日本とタイの青少年の交流が行われている。
4 在留邦人数
70,421人(2024年)
5 在留当該国人数(短期滞在除く)
65,398人(2024年:外国人登録者数)
6 要人往来(2005年以降)
| 年月 | 要人名 |
|---|---|
| 2005年1月 | 町村外務大臣 |
| 2005年8月 | 秋篠宮殿下 |
| 2006年6月 | 天皇皇后両陛下(タイ国王即位60周年記念式典) |
| 2007年3月 | 秋篠宮殿下 |
| 2009年1月 | 中曽根外務大臣 |
| 2009年4月 | 麻生総理大臣、中曽根外務大臣(ASEAN関連首脳会議:中止) |
| 2009年7月 | 中曽根外務大臣 |
| 2009年10月 | 鳩山総理大臣(ASEAN関連首脳会議) |
| 2010年8月 | 岡田外務大臣 |
| 2011年3月 | 秋篠宮殿下 |
| 2012年6月 | 皇太子殿下 |
| 2012年11月 | 秋篠宮殿下 |
| 2013年1月 | 安倍総理大臣 |
| 2016年5月 | 岸田外務大臣 |
| 2017年3月 | 天皇皇后両陛下(前国王プミポン陛下御弔問) |
| 2017年10月 | 秋篠宮同妃両殿下(前国王プミポン陛下御火葬式御参列) |
| 2018年6月 | 河野外務大臣 |
| 2018年12月 | 秋篠宮同妃両殿下 |
| 2019年8月 | 河野外務大臣(ASEAN関連外相会議) |
| 2019年11月 | 安倍総理大臣(ASEAN関連首脳会議) |
| 2020年1月 | 茂木外務大臣 |
| 2022年5月 | 岸田総理大臣 |
| 2022年11月 | 岸田総理大臣(APEC首脳会議)、林外務大臣(APEC閣僚会議) |
| 2023年10月 | 上川外務大臣 |
| 年月 | 要人名 |
|---|---|
| 2005年5月 | カンタティー外相(ASEM外相会合) |
| 2005年8月 | タクシン首相 |
| 2006年4月 | タクシン首相(非公式訪問) |
| 2006年5月 | カンタティー外相(タイ・フェスティバル) |
| 2006年8月 | シリントーン王女殿下 |
| 2006年10月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2007年2月 | ニット外相(日タイ修好120周年開幕式典) |
| 2007年4月 | スラユット首相 |
| 2007年10月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2007年11月 | ニット外相(日タイ経済連携協定(第1回合同委員会)) |
| 2008年1月 | ニット外相(日メコン外相会議) |
| 2008年5月 | ノパドン外相(タイ・フェスティバル) |
| 2008年9月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2009年1月 | ソムサワリー王女殿下 |
| 2009年2月 | アピシット首相 |
| 2009年11月 | アピシット首相、カシット外相(日メコン首脳会議) |
| 2010年1月 | カシット外相(アジア中南米協力フォーラム) |
| 2010年10月 | シリントーン王女殿下 |
| 2010年11月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2012年3月 | インラック首相、スラポン外相 |
| 2012年4月 | インラック首相、スラポン外相(日メコン首脳会議) |
| 2013年5月 | インラック首相、スラポン副首相兼外相 |
| 2013年11月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2013年12月 | ニワットタムロン副首相兼商務相 |
| 2014年11月 | プラウィット副首相兼国防相 |
| 2015年2月 | プラユット首相、タナサック副首相兼外相 |
| 2015年3月 | プラユット首相(第3回国連防災世界会議)、タナサック副首相兼外相 |
| 2015年4月 | シリントーン王女殿下 |
| 2015年7月 | プラユット首相(第7回日本・メコン地域諸国首脳会議)、タナサック副首相兼外相 |
| 2015年11月 | ソムキット副首相 |
| 2016年5月 | ドーン外相(タイ・フェスティバル) |
| 2016年5月 | ソムキット副首相 |
| 2016年12月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2017年5月 | タナサック副首相(タイ・フェスティバル) |
| 2017年6月 | ソムキット副首相(第3回日タイハイレベル合同委員会) |
| 2017年9月 | ドーン外相(日タイ修好130周年) |
| 2017年12月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2018年7月 | ソムキット副首相(第4回日タイハイレベル合同委員会) |
| 2018年10月 | プラユット首相(第10回日本・メコン地域諸国首脳会議) |
| 2019年5月 | ドーン外相(タイ・フェスティバル) |
| 2019年6月 | シリントーン王女殿下 |
| 2019年6月 | プラユット首相、ドーン外相(G20大阪サミット) |
| 2019年10月 | プラユット首相(即位の礼) |
| 2019年11月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2020年2月 | ソムキット副首相 |
| 2022年5月 | プラユット首相(国際交流会議「日経アジアの未来」) |
| 2022年9月 | ドーン副首相兼外相(安倍元総理国葬儀) |
| 2022年12月 | チュラポーン王女殿下 |
| 2023年5月 | ドーン副首相兼外相(国際交流会議「日経アジアの未来」) |
| 2023年12月 | セター首相兼財務相、パーンプリー副首相兼外相(日ASEAN友好協力50周年特別首脳会議) |
| 2024年5月 | プームタム副首相兼商務大臣(タイ・フェスティバル) |
| 2024年5月 | セター首相、マーリット外相(国際交流会議「日経アジアの未来」) |
| 2025年5月 | マーリット外相(タイ・フェスティバル) |
| 2025年5月 | マーリット外相(国際交流会議「日経アジアの未来」) |
| 2025年8月 | スリヤ副首相兼運輸大臣(大阪・関西万博) |
| 2025年12月 | シーハサック外相 |
7 二国間条約・取極
- 修好宣言(1887年)
- 航空協定(1953年)、文化協定(1955年)、貿易取極(1958年)、技術協力協定(1981年)、青年海外協力派遣取極(1981年)、租税条約(1990年)、経済連携協定(2007年)、受刑者移送条約(2010年)、防衛装備品・技術移転協定(2022年)

