欧州
EU関連用語集
平成30年11月13日
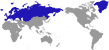
あ
か
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| か | 加盟交渉 | EUへの加盟に向けて加盟候補国として認定された国とがEUとの間で協議すること。 |
| 加盟候補国 (Candidate States) |
EUから加盟することを前提とするとの承認を経て加盟の為の交渉を開始するに至った国。 | |
| 関税同盟 | 加盟国間の貿易に対する関税・数量制限を撤廃し、域外に対する共通関税率と共通通商政策を適用したもの。 | |
| き | 議長国 | 半年の輪番制で加盟国が務めるもの。 |
| 規則 | EU法令の一つ。加盟国に対し、国内法への適用を待たずに直接拘束力を有する。 | |
| 強化された協力手続 (enhanced cooperation) |
「緊密な協力手続(closer cooperation)」がニース条約により改正されたもの。EUが排他的管轄権を有する分野及び共通外交・安全保障政策を除き、リスボン条約に規定される分野で、統合を更に進める意見のある加盟国同士が互いに協力する制度。加盟国の増加に関わらず、9カ国の賛成で手続きを開始できる。参加しない加盟国は拒否権を有しない。 | |
| 共通安全保障防衛政策 (Common Security and Defense Policy: CSDP) |
共通外交安全保障政策(CFSP: Common Foreign and Security Policy)の一翼を担うもの。90年代後半のボスニア紛争、コソボ空爆等紛争の経験などにより、外交政策を軍事力によって裏付ける必要性が認識されたことから、実際の軍事協力と必要な軍事能力の整備を推進するため、欧州安全保障・防衛政策(ESDP)が発展した。2009年12月のリスボン条約発効を機にESDPはCSDPに名称が変更された。主な任務は人道・救援活動、平和維持活動、平和構築のための戦闘任務、危機管理関連業務。 | |
| 共通外交安全保障政策 (Common Foreign and Security Policy: CFSP) |
各加盟国の権限に属する外交、安全保障についても可能な限りEUとしての共通政策をとることにより、国際場裏においてEUとして統一的に行動することを目指すもの。決定は原則として全会一致で行われる。 | |
| 共通農業政策 (Common Agricultural Policy: CAP) |
農家への直接支払いを柱とした、農業収入、食品の安全と質、環境的に持続可能な生産を保障する政策。 現在、2014年から2020年までの改革案が審議されている。 |
|
| 共同決定手続 | リスボン条約の発効に伴い、欧州議会の強化された権限のうちの一つ。EU理事会と欧州議会が対等に権限を有し、議会における二度の検討を経て欧州委員会の提案を審査するもの。通常の立法手続(Ordinary Legislative Procedure)とも呼ばれる。 | |
| 銀行同盟 (Banking Union) |
単一監督メカニズム(Single Supervisory Mechanism :SSM)、単一破綻処理メカニズム(Single Resolution Mechanism)、単一預金保険制度(Deposit Guarantee)の3つの構成要素からなる。欧州債務危機の進展に伴い、銀行とソブリン(国債など)の悪循環を断ち、金融セクターの安定のために銀行同盟の創設が必要との議論が活発化。ECBが一元的に銀行監督を行うSSMは2014年3月またはSSM法案施行日の12か月後のどちらか遅い日より導入予定。単一破綻処理メカニズムと単一預金保険制度については現在議論中。 | |
| け | 経済通貨同盟 (Economic and Monetary Union: EMU) |
加盟国間の外国為替相場の変動率を一定の幅に押さえるため1979年より実施されていた欧州通貨制度(EMS)を更に一歩進め、各国通貨間の相場の固定と単一通貨の導入を行ったもの。欧州連合条約に盛り込まれた手続に従い、1994年に欧州通貨機構(EMI)(現在の欧州中央銀行(ECB))を設立、各国の経済・財政政策の収斂を図り、物価の変動率や財政赤字の対GDP比率等に関する基準を満たした11か国が1999年1月1日より単一通貨ユーロを導入した。 2002年1月1日よりユーロ貨幣の流通が開始された。現在のユーロ参加国は19か国。 |
| 結束基金 (Cohesion Fund) |
構造政策の実施スキームの一つで、GNI(国民総所得)がEU加盟国平均の90%を下回る国の交通・環境インフラ、エネルギー効率、再生可能エネルギーに焦点をあて支援するための基金。 | |
| 決定 | EU法令の一つ。決定は拘束力を持ち、決定において特定された対象にのみ適用され、一般には適用されない。 | |
| こ | 構造基金 (Structural Fund) |
構造政策の実施スキームの一つで、主に地域を単位として、プロジェクトを自治体、中央政府、欧州委員会等で協議をしながら設定し、実施していくもの。 |
| 構造政策 (Structural Policy) |
EUの地域政策。域内の地域間格差を是正し、結束と連帯を確保するための政策。構造基金、結束基金等が主要な手段。 | |
| 公用語 | 24の公用語(アイルランド語、イタリア語、英語、エストニア語、オランダ語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ハンガリー語、フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ポーランド語、ポルトガル語、マルタ語、ラトビア語、リトアニア語及びルーマニア語)。 | |
| コレペール (常駐代表委員会 Comite des Representants Permanents:COREPER) |
各種EU理事会の準備・補佐機関で、各加盟国から派遣されているEUへの常駐代表による会議。通常週一回開催されている。コレペールは理事会の指示に従って下部委員会や作業部会を設置し、特定事項の準備・調査を進める。 | |
| コペンハーゲン基準 | 中・東欧等諸国の加盟交渉に当たり加盟条件とされる一連の基準(クライテリア)。政治的基準(民主主義、人権、法の支配等)、経済的基準(市場経済等)などがある。 |
さ
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| さ | 財政協定条約 | 正式には「経済通貨同盟における安定・協調・ガバナンスに関する条約」。一般政府予算は「均衡又は黒字」(構造的赤字が対GDP比0.5%以内、但し例外あり)とし、財政均衡ルール及び自動是正メカニズムを本条約施行1年以内に憲法等の国内規定に導入することや、債務残高対GDP比60%超の締約国は、年平均1/20ずつ減少させること等を規定。2012年3月に英とチェコを除く25カ国で署名され、2013年1月より発効。 |
| し | シェンゲン協定 | 1985年にルクセンブルクのシェンゲンで署名された、共通国境管理の漸進的撤廃に関する協定(85年シェンゲン協定)及び90年に署名されたシェンゲン実施協定からなる。85年に協定に署名した国はフランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクの5か国のみであったが、現在はEU加盟28か国のうち22か国がシェンゲン領域に参加している(注)。また、EU非加盟のノルウェー、アイスランド、スイス及びリヒテンシュタインがシェンゲン領域に参加している。 なお、99年に発効したアムステルダム条約により、シェンゲン協定はEU条約に統合された。 (注)キプロス、ブルガリア及びルーマニアは、シェンゲン領域に部分的に参加(国境管理撤廃未実施)。また、英国及びアイルランドは、シェンゲン領域には参加していないが、警察協力等は実施。 |
| 市民発案 (Citizen's initiative) |
一定数のEU市民が欧州委員会に対して、その権限の範囲内で特定の内容の提案を行うよう求めることができる制度。 | |
| シューマン・デー | 1950年5月9日、当時フランス外相であったロベール・シューマンがパリで行ったシューマン宣言により、石炭・鉄鋼の共同管理のための超国家的な機構の創設を提唱し、後の欧州共同体、そして、EUの基礎となった。以後、5月9日はシューマン・デー(ヨーロッパ・デー)として記念日にされている。 | |
| 自由・安全・司法の空間 (Area of Freedom, Security and Justice) |
基本的人権の保障、シェンゲン共通査証政策、共通移民政策、民事・司法協力、警察間協力を通じて実現を目指すもの。リスボン条約の発効により、それまで決定手続きの異なっていた難民、移民、民事司法の分野と警察、刑事司法協力の分野について、原則として「自由・安全・司法の空間」の全ての領域に共同決定手続を適用することになった。 | |
| 指令 | EU法令の一つ。加盟国を拘束するが、その具体的な形式及び手法は加盟国に委ねられる。適用にあたっては、加盟国内での実施手続(担保法の制定等)が必要。 | |
| せ | 先行判決(先決的判決) | 加盟国の裁判所に係属する事件について、基本条約の解釈又はEUの機関・部局等の行為の有効性及び解釈に関する問題点が生じた場合に加盟国の裁判所が審判の前提として当該問題点についての判断が必要と認めるときは、欧州司法裁判所に対し、当該問題点について意見(=先行判決)を求めることができる。 |
た
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| ち | 駐日欧州連合代表部 (Delegation of the European Union to Japan) |
EUとしての外交使節団で、駐日代表は1990年以来天皇陛下に信任状を奉呈し、大使の地位を認められている。 1974年設立。 |
| つ | 通常立法手続 (Ordinary Legislative Procedure) |
共同決定手続の項を参照。 |
| と | 東方パートナーシップ | アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、モルドバ、ウクライナ及びベラルーシの6か国が対象国。地域的協力を強化し、EUとの価値の共有を進めつつ、地域の安定化を進めることを目的とする。 |
| 特定多数決制 | 外交・安全保障政策以外の分野についてとられる意思決定制度。各加盟国の人口の数に応じて票を割り当てる。現行の特定多数決制では、加盟国の過半数、EUの加盟国人口の62%が意思決定に必要となる。 リスボン条約の発効に伴い、2014年11月以降は加盟国数の55%、EU加盟国人口の65%に変更となることが規定されている。 |
な
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| に | ニース条約 | EUの基本条約(欧州連合条約、欧州共同体条約、欧州原子力共同体条約)を改正するもので、2001年2月署名、2003年2月発効。EU拡大を見据え、EUの意思決定手続の効率化及び機構改革を目指すもの(2009年12月にはニース条約を改正するリスボン条約が発効している)。 |
は
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| は | バルセロナ・プロセス | 地中海諸国との間で、1995年11月バルセロナ会議において政治・経済・文化面での協力を謳った「地中海宣言」を採択。2010年までの欧州・地中海自由貿易地域設立を目標に国別の連合協定を締結・交渉。 |
や
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| ゆ | ユーロ | EU加盟国の内、19か国が参加する単一通貨の単位。補助単位はユーロセント。 1999年1月1日導入、2002年1月1日流通開始。 圏内では、現金、小切手、トラベラーズチェック、クレジット・カード、銀行間振替などの全ての支払い手段がユーロで行われている。 7種類の紙幣:5,10,20,50,100,200,500ユーロ 8種類の硬貨:1,2,5,10,20,50ユーロセント、1,2ユーロ |
| ユーロ圏 | ユーロ参加国=ユーロ圏は19か国(ベルギー、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、スロベニア、フィンランド、マルタ、キプロス、スロバキア、エストニア、ラトビア、リトニア)。ユーロ参加国の首脳で構成されるユーロ圏首脳会合(ユーロサミット)が少なくとも年2回開催されることが財政協定条約で規定されており、欧州理事会と同時に開催されることが通例となっている。 |
ら
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| り | リスボン戦略(プロセス) | 2000年3月のリスボン欧州理事会(首脳協議)において、10年間の期間を念頭においた経済・社会政策についての包括的な方向性が示され、以降「リスボン戦略」と呼ばれている。 「より多い雇用とより強い社会的連帯を確保しつつ、持続的な経済発展を達成し得る、世界で最も競争力があり、かつ力強い知識経済となること」を目標とする。 |
| リスボン条約 | 2009年12月1日発効。正式名称は、「欧州連合条約及び欧州連合の運営に関する条約」。拡大したEUが新たな課題に対応する能力を強化することを目的とし、常任の欧州理事会議長の任命、議長国制度の改革、意思決定手続の改善、外交実施体制の強化等を主な内容とする。 | |
| 離脱交渉 | 欧州連合条約第50条に基づき、EU離脱を通告したEU加盟国が、EUとの間で当該加盟国とEUとの将来的な関係の枠組みを考慮しつつ、当該加盟国の離脱に関する協定を交渉すること。 |
わ
| 五十音 | 語句等 | 説明・意味 |
|---|---|---|
| わ | 枠組み決定 (対象分野:PJCC) |
加盟各国の法律や規則を集約することを目的とする。決定は、欧州委員会ないし加盟国が提案し、採択に当たっては全会一致を条件とする。これらの決定を実施する際の形式や手段は各国の主権に委ねられているが、その結果は各加盟国を拘束する。 |

