![]()
「等身大の日本を知ってもらうために--動き出すテレビ対外発信」
(「外交フォーラム」9月号より転載)
【要旨】
日本発の英語によるテレビ国際放送を世界に広めることは、日本外交にとって喫緊の課題である。CNNやBBCは世界に浸透し、国際世論に影響を与えるほどまで成長している。一方日本は、北朝鮮のミサイル発射に絡んだ日本の先制攻撃論を、欧米のマスコミに許してしまうほど、国際放送に関して出遅れている。年間運営費も、受け手にとって見やすい環境をつくる努力もまだまだ不十分である。
情報鎖国にいるような喪失感
外国に旅行して初めてのホテルに泊まると、部屋のテレビを前に一瞬祈るような気持ちになることが多い。途上国の地方都市ならいざ知らず、欧米の主要都市やアジアの大都市の一流ホテルなら地元のテレビ局に加えてCNNとBBC、さらに日本の「テレビ・ジャパン」が映っていてほしいという願いである。CNNとBBCは期待を裏切られることはめったにないが、「テレビ・ジャパン」は確率6割といったところだろうか。がっかりすることがいまだに多い。
私が外務報道官をしていた時、外務大臣の外国訪問に随行する機会が度々あったが、2002年8月、初めての大臣同行で泊まった南アフリカ、ヨハネスブルクではCNNとBBCはあっても日本のテレビは見えなかった。その翌年には、アメリカの首都ワシントンの一流ホテルで同じ経験をし、フロントに問い合わせたところ「新築間もないので……」という、わかったようでわからない説明を受けた。そうした残念な経験をする度に、私はいつも2つの思いにとらわれた。1つは、日本の外務大臣が自ら外交活動を行うために外国を訪問しているのに、その場で、自分の活動が日本でどのように報道されているかを見ることができないとは、あまりにも大きなハンディキャップではないか。また、大臣が日本のテレビ放送で、日本国内の政治、経済、社会の関心事がどの辺にあるかを見ることができないとは、いかにも残念ではないかという気持ちであった。実はそのことは、外務大臣のスポークスマンとして随行している私自身にとっても重要な問題で、訪問先の記者団や有識者と会見や懇談をする際に、その時々の日本のメインニュースを承知しているかどうかは、私自身の発言内容に大きく影響することを何回も実感したものだ。
もう1つは、日本についての情報をCNNとBBCなどの外国メディアによって知らなければならないという無念さだ。CNNとBBCはなかなか日本についての情報を流さず、ましてや地元テレビ局のニュースに日本が登場することなどめったにない。したがって一生懸命チャンネルを回しても「テレビ・ジャパン」が見つからないとなると、まるで情報鎖国の中にいるような喪失感を味わうことになる。そのことは同時に、世界の中で、日本についての、あるいは日本が関心を寄せる問題についてのテレビ報道が、量的にも質的にもいかに少ないかを改めて実感するという、無力感に通じる気持ちでもあった。
テレビ・ジャパンは海外でどう観られているか
歴代の外務大臣はこうした状況を憂慮し、テレビを通じた日本からの情報発信の強化を折にふれて説いていた。2004年9月に就任した町村信孝外相はこの問題に積極的に取り組んだ1人で、就任直後から「テレビ国際放送。とりわけ英語による日本発世界向けのテレビ放送」の可能性を探るよう指示していた。その町村外相の指示が一段と強さを増したのは2005年4月。中国で反日デモが3週間にわたって荒れ、北京の日本大使館、日本大使公邸、上海の日本総領事館、各地の日本レストランや日本企業が大きな被害を受けた時だった。町村外相は自ら北京に乗り込んで、被害のあとも生々しい大使館や大使公邸を視察する一方、中国の李肇星外相らと会談し、謝罪と修復、責任者の処罰、再発防止を強く求めた。この旅の途中、町村外相は同行した私たちに対して、中国の反日デモがいかに理不尽なものであり、中国政府の責任がいかに大きいかを世界に向けて知らせていく必要があるという思いを語り続けた。そして、テレビが伝えた反日デモの様子、中でも警備にあたる公安警察が、笑いながらデモ隊の投石を黙認していたシーンやデモを終えた学生や労働者のために、何台ものバスが用意されていたことを示すシーンが各国で放映された結果、中国に厳しい国際世論が形成されたことは間違いないとして、テレビ広報の重要性、有効性を指摘していた。
テレビ国際放送は日本外交にとって喫緊の課題だという指示を受けた私たちがまず始めたのは、実際のところ世界各国は自国の外に向けたテレビ放送をどのように行なっているか、また、日本のNHKが1995年から行なっている海外向けテレビ放送「テレビ・ジャパン」がどのように観られているかという実態調査だった。このうち、各国のテレビ国際放送についての情報はNHK放送文化研究所が毎年発行している「NHKデータブック・世界の放送」に紹介されている。2006年版によると、同研究所が調べた世界80カ国と2地域の中でテレビ国際放送を行なっているところは、42カ国1地域。しかし、その大半は国外にいる同胞向けの自国語による放送で、文字通り世界中の人々に観てもらおうと英語で放送している局はCNNインターナショナル(米)、BBCワールド(英)、CCTV9(中)、アリラン(韓)の4局であった。フランス、ドイツ、カタールのアルジャジーラなどは、テレビ国際放送としての知名度は高いが、使用言語は自国語で、汎用性においてCNNとBBCに敵わない。NHKの「テレビ・ジャパン」は「NHKワールド」という名称で一部英語を主体とした番組を放送するほか、英語の字幕をつけたり、副音声に英語を流したりして英語化度を上げ世界各国の人々に観てもらおうと努力しているが、在留邦人と日本人旅行客向けの放送という受け止め方がもっぱらだ。
日本のステータスが低下する?
それでは、これらのテレビ国際放送は世界各国でどのように観られているのだろうか。中でも「NHKワールド」はどの程度観えるのだろうか。外務省広報文化交流部総合計画課は世界各地の日本大使館の協力を得て、2005年12月から3カ月にわたって各国のテレビ国際放送の視聴状況を調査し、114カ国について結果をまとめた。
それによると、地上波テレビ放送、ケーブルテレビ、衛星放送等、通常の手段で一般家庭が受信できるテレビ国際放送の種類を比べた場合CNNの普及率が最も高く、114カ国中113カ国で視聴可能であることがわかった。これに次いでBBCが111カ国、TV5(仏)が100カ国、CNBC(米)が94カ国、ドイチェベレ(独)が79カ国、CCTV9(中)が78カ国、アリラン(韓)63カ国の順となり、日本のNHKワールドは遙か下の12カ国という結果だった。
NHKの資料によるとNHKワールドは現在3つの衛星を使ってほぼ全世界に伝送され、180の国と地域で7200万世帯が視聴可能とされている。180カ国と12カ国……。あまりにも大きな開きだが、その原因は、一般家庭が受信しやすいかどうかという判断基準の違いである。NHKは「この放送は、本来は放送局間の伝送に使うCバンドという電波を使って世界中に流れているが、直径4・5メートル程の大型パラボラアンテナと受信機器があれば誰でも視聴できる」として、世界の総人口の99%が視聴可能と位置づけている。しかし、大人2人が両手を広げてもまだ足りない大型パラボラアンテナを、自宅に設置できる人が世界にどれほどいるだろうか。そこでNHKワールドがケーブルやCSテレビで正式に配信されているかどうかを基準に調べたところ、12カ国が受信可能という結果が出たわけだ。改めて、日本のテレビ国際放送が世界中の人々に見てもらう体制にはまだなっていないことを示す調査結果であった。
それでは旅行者にとって欠かせないホテルの受信状況はどうだろうか。114カ国に置かれた日本大使館が「よく利用する代表的なホテルの受信可能状況」として報告した結果はこうなった。調査対象となったホテルは220軒。このうちCNNが視聴可能なホテルは207。次いでBBCが186、TV5が156、CNBCが101、ドイチェベレが93と続き、6位にNHK(91)が入った。因みにCCTV9は7位、アルジャジーラは8位、アリランは9位であった。
私は数年前、中東の外交官から「外交交渉をする時、常にもう1人の相手と戦う気がする。CNNだ」という述懐を聞いたことがあるが、この調査結果を見るとCNNとBBCがいかに世界に浸透し、国際世論に影響を及ぼす地位を築いているかがわかるようだ。
外務省の調査では、このほか、各日本大使館に対して「他国が国際放送を強化していることで何か影響が出ているか」という質問をしてみた。大半のところは「特になし」と回答しているが、アジア、大洋州、アフリカの25公館は「日本のステータスが低下している」とか「このままでは低下は避けられない」という回答を寄せた。これらの地域は、中国のCCTVの浸透が著しいところであり、何かと中国を意識することが多い外交現場の感触がそのまま表れた結果と言えるのではないだろうか。
図表1:チャンネル毎の視聴可能国数
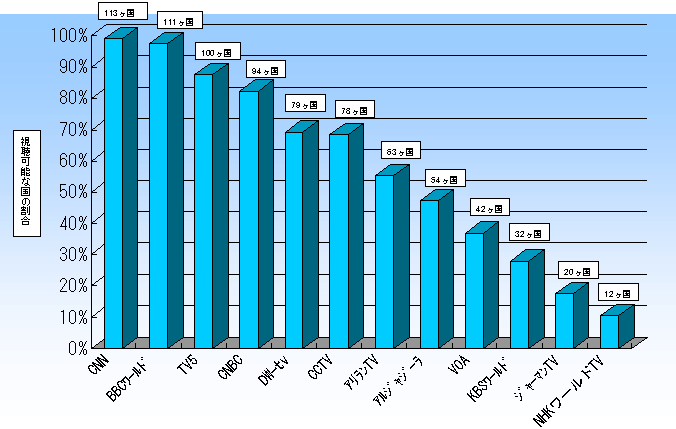
- 在外公館を通じた114ヶ国の調査結果。100%=114ヶ国。
- NHKワールドTVのみは、上記114ヶ国のうち、正規契約による再送信を実施している国の数を示す。
図表2:チャンネル毎の視聴可能ホテル件数
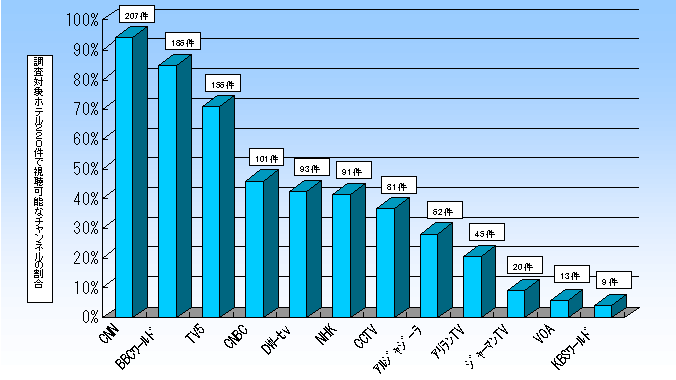
- 在外公館を通じた220件のホテルの調査結果。100%=220件
新しいテレビ海外発信の実現へ
日本発のテレビ国際放送を強化しようという動きは今に始まったことではない。1996年には当時の郵政省の音頭でNHKや民放も参加した連絡会が開かれ、翌97年になると自由民主党外交調査会がこの問題を検討。それを受けて自民党内に「映像国際放送懇談会」がつくられ、後の町村外相、谷垣禎一財務相も幹事役として参加していた。2年後に関係省庁が一堂に会した「映像国際放送のあり方に関する勉強会」が開かれたが、その後数年間は停滞していた。ところが最近になって一気に事が動き始めた。去年7月「文化外交の推進に関する懇談会」が、小泉総理に対して「国際社会に対するわが国の発信力を高めるべきだ」という提言を提出し、小泉総理は今年2月10日の閣僚懇談会で、海外向け放送の強化を竹中平蔵総務相に指示。これを受けて、放送と通信のあり方を話し合う竹中総務相の私的懇談会がテレビ国際放送の問題を取り上げることになった。一方、自民党内では、町村前外相を会長とする「対外発信強化を考える議員の会」が発足して、日本にCNN、BBC並みの世界的な放送機関を設立しようという声をあげた。自民党電気通信調査会の通信・放送産業高度化小委員会も片山虎之助委員長を先頭に、海外向けテレビ放送強化の議論を推進し始めた。
外務省では2005年10月末に就任した麻生太郎外相(前総務相)がこの問題を担当する広報文化交流部に「総務省と話し合って新しいテレビ海外発信を実現するように」と指示し、これからのテレビ国際放送にはCMが入ることが望ましいなど具体的な考えを示した。また、外務大臣の諮問機関である海外交流審議会も「外国人をターゲットに日本関連情報を提供する英語による専門チャンネルの設置が望ましく、政府は応分の負担をすべきだ」という見解を表明した。
こうした流れを受けて政府と与党は今年6月20日、安倍晋三官房長官、竹中総務相、中川秀直自民党政調会長、井上義久公明党政調会長ら8人の連名で「通信・放送の在り方に関する合意」をまとめ、その中のNHK関連事項の1つにテレビ国際放送を取り上げて次のように規定した。
「新たに外国人向けの映像による国際放送を早期に開始する。その際、新たに子会社を設立し、民間の出資等を積極的に受け入れるとともに、必要な国費を投入する」
この合意は7月7日に閣議決定された経済財政運営の基本方針「骨太の方針」に盛り込まれ、その結果、テレビ国際放送を、NHKの子会社方式により、民間資金と国費を投入して速やかに始めることが国の方針として正式に決まった。テレビによる世界への情報発信という長年の懸案が具体的に動き始める歴史的な出来事であった。
年間運営費は十分なのか
しかし、この方針を実際にスタートさせるには、難しい問題が山積している。真っ先に浮かぶ疑問は、そのような放送を、誰に対して、どのように行なっていくかということだ。5月に発表された海外交流審議会の見解は「外国人を対象に、ニュース・報道主体に、良質の教養・エンターテインメントを加味し、日本を中心にアジアの動きが広く把握でき、また、わが国文化・社会・経済・政治に対する関心に広く応える魅力ある番組内容とする。柔軟な編成でオピニオン・リーダーから一般大衆までを広く対象とするチャンネルとすることは可能だ」としている。しかし、今のNHKが英語でこうした放送を作ることは可能だろうか。日本国内向けの既存の放送に英語の字幕をつけて、さあ観てくださいと言っても外国の視聴者がついてこないことはNHKワールドで実験済みだ。はじめから対外向けを意識して番組を企画し、制作することが不可欠であり、そのためには要員を含めた制作体制や予算の抜本的な作り直しが必要になる。問題はそのための経費だ。放送法にはNHKがテレビ・ラジオの国際放送をする中で政府の命令に基づく放送を行なう場合、その費用は交付金の形で国が負担するという規定があり、短波によるラジオ国際放送には毎年20億円余が交付されている。この制度のテレビ国際放送への援用についてNHKは、編集権独立の観点から問題があるとして拒み続け、議論の行方はいまだに不透明な状態にある。一方、今のNHKのテレビ国際放送の番組制作等の予算は年間29億円だが、これまでとは全く違う、真に世界に向けた発信のためのテレビ放送を作ろうというにはどう考えても足りそうにない。各国のテレビ国際放送の年間運営費を調べてみると、BBCが95億円、ドイチェベレが352億円(ラジオとドイツ語専門の別チャンネルを含む)、アリランが45億円で、近く放送が始まる予定のフランスのCFIIは87億円を予定しているという。満足な結果を得ようとするなら必要な経費をまかなうための外部資金の導入、とりわけ国費の導入について真剣な検討がなされるべきであろう。
編集権の問題について海外交流審議会は「日本発のテレビ国際放送の信頼性を確保するためには、編集権の独立が確保される事が必須」としている。もっともな考え方であり、今後行なわれる国費投入についての議論の中では、国とNHKの双方が「いかに魅力的な放送にするか」という基本的な考え方に立った上で、交付金と編集権の問題について柔軟な姿勢で検討を行なうよう期待したい。
もう1つの問題は、どうすればより多くの外国の人々に放送を観てもらえるかである。番組の質がよいことは当然だが、今のように直径4・5メートルものアンテナが必要というのでは話にならない。CNNやBBCがそうであるように、ここぞという主要な地域では、日本のテレビ国際放送が地元のケーブルテレビか普通のCS、BSテレビのチャンネルの中に収まっている必要がある。最近は放送のデジタル化の進展でチャンネル数が増え、ケーブル等に入り込むチャンスが随分大きくなってはいるが、それでも状況は厳しい。中国、韓国のテレビ国際放送がそうであるように、当面はチャンネル使用料を払って参入せざるを得ないケースが多くなると予想される。この使用料を誰が負担すべきかの検討はすでにNHKと政府の間で始まっているが、受信環境が良くなければ誰も観てくれないという放送の特性から考えて、この点についても関係者、とりわけ国側の前向きの取り組みが期待される。
地道に取り組む姿勢の必要性
テレビ国際放送については「どんなに一生懸命やっても、どうせ観てもらえない。ケーブルやCSチャンネルに使用料を払うなど大金をドブに捨てるようなものだ」という批判が放送に詳しい人々の間からも聞こえてくる。確かに、これだけさまざまな放送がひしめき合っている中で、日本発のテレビがすぐさまCNN、BBS並みの存在になることは不可能だろう。しかし、ジャーナリズム精神に満ちた、質の高いニュース・情報を常に出し続け、その合間に「クール」な日本をさまざまな形で紹介するチャンネルがあれば、話題になり、注目を集め、次第に人気を博すことは確実だろう。あのCNNも最初の5年余りはほとんど無視され、「ケーブル・ニュース・ネットワーク」でありながらCNNのないケーブルが全米の至る所にあったと聞く。息の長い、志に満ちた取り組みが必要である。
もう1つ。このテレビ国際放送を日本国内に流すことができれば、日本に住む外国人や日本を訪れる外国人旅行者にとってこの上ない朗報となるだろう。CSでもBSでもどこでもよい。チャンネルさえ決まっていれば、いざという時に、あわてずにテレビのスイッチを入れ、英語で(たぶん、中国語、ハングルあるいはポルトガル語の字幕も付いて)大地震の避難勧告や被災地での救援情報を簡単に入手することができるだろう。またこのチャンネルは、日本にいる外国の人々にとって、日本についての情報を知るためのもっとも身近な窓口になるわけで、これこそ国際化時代を迎えた日本に欠かすことのできないサービスと言うことができるだろう。
最後に一言。この原稿をまとめている時に、欧米のマスコミで、北朝鮮のミサイル発射に絡んだ日本の先制攻撃論がしきりに取り沙汰されていることがたいへん気になった。あたかも日本が明日にも攻撃を始めるかのような乱暴な書きぶりが多い。そうした記事を読みながら「ワシントン・ポスト」のウェブサイトに目をやると週末のテレビ・トークショーの欄が出てきた。アメリカ政府の閣僚や議会の指導者をゲストに迎え、著名なリポーターやコラムニストが3人程のグループになってじっくりと話を聞く、日曜昼時の定番番組だ。
「もし今、日本発の英語によるテレビ国際放送があって、きちんとした聞き手を相手に、日本のしかるべき人物が北朝鮮のミサイル危機や日本の防衛政策について理を分けた話をすれば、そしてその番組が欧米とアジアで繰り返し放送されていれば、あのような先制攻撃論がいかに現実離れしたものかわかってもらえるだろうに」と口惜しく思ったものだ。 「日本が何を考えているかを知ってもらう。等身大の日本を見てもらい、日本を理解してもらう」。今ほどその努力が必要とされている時はないように思う。

【略歴】
![]()
たかしま はつひさ
1963年NHK入局。ワシントン特派員、ロンドン支局長、「ニュース21」アンカーマン、報道局局長、解説委員長などを歴任。2000年9月国際連合広報センター所長に就任。2002年8月外務省に入り、外務報道官。2005年7月に退任し、同年8月より外務省参与。
