「大学生国際問題討論会 フォーラム2009」
開催の概要報告
平成21年10月
1.はじめに
外務省は、次代を担う大学生が、我が国の外交政策や国際情勢に対する理解を深めるとともに、ディベート能力を高めることにより、国際社会で活躍する人材を育成することを目的として、9月13日(日曜日)、明治大学リバティーホールで「大学生国際問題討論会 フォーラム2009」を開催しました。本年度の論題は「日本政府は、全世界の核兵器を削減し、安全保障における核兵器の役割を減らすための取組を強化すべきである。」でした。全国各地から34チームの参加登録があり、そのうちの26チームから提出された立論書の事前選考を経て、本選出場権を得た4チームによって白熱した議論が展開されました。当日は80名を超える多くの傍聴者が参加し、極めてレベルの高い論戦が戦わされた結果、「霞山学生会」チームが優勝しました。表彰式において3名の審査委員からそれぞれ講評をいただいた後、審査委員、出場者、傍聴者が出席した懇親会が行われ、終始和やかな雰囲気の中で有意義な意見交換も行われました。
今回、本事業の広報活動にご協力頂きました各大学、大学院等の教育機関の教職員の皆様、弁論サークルや関連団体の皆様には厚く御礼申し上げます。
2.討論風景

3.受賞チーム(お名前は順不同です。)
外務大臣賞:霞山学生会チーム

村野 将さん 拓殖大学国際開発学部4年
角田和広さん 明治大学大学院博士後期課程1年
木越寿人さん 東京大学公共政策大学院1年
優秀賞:慶應義塾大学神保謙研究会チーム
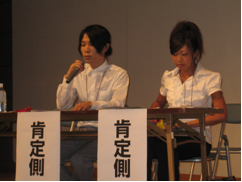
伊藤 岳さん 慶應義塾大学総合政策学部4年
田中香名さん 慶應義塾大学総合政策学部4年
奨励賞:聖心女子大学チーム

染木 彩さん 聖心女子大学文学部3年
高木里英さん 聖心女子大学文学部3年
飯田ひろ美さん 聖心女子大学文学部3年
奨励賞:防衛大学校チーム

大塚邦博さん 防衛大学校国際関係学部3年
大門 航さん 防衛大学校国際関係学部3年
山下琢磨さん 防衛大学校国際関係学部3年
4.表彰式の後、全員で記念撮影

5.審査委員による講評
(1)川上高司 拓殖大学海外事情研究所教授

討論会に参加された皆様、今日はご苦労様でした。また、入賞されたチームは本当におめでとうございます。非常に白熱した論議で、しかも非常に資料を読みこまれ、審査委員もどちらのチームに投票したらいいか、はなはだ迷うところが多かったわけであります。
今の状況というのは、皆さんが述べられたように、オバマ大統領がプラハ演説を行い、キッシンジャーやシュルツなどの4賢人が核軍縮・不拡散の提案を行い、まさに安全保障上メガトン級の爆弾が落とされたような状況であります。かつて、ジョージ・ケナンがX論文で封じ込め政策を説きましたけれども、彼はその後のデ・タントの情勢を見て、「危険な雲」の中で、「もはや封じ込め政策は終わった」と述べています。今後は新しい状況に入るということで、リアリストからリベラリストに一見変更して、今までの状況を風刺したような状況でありましたが、しかしながら、彼は決して現実を忘れることはなかった。つまり、この教訓に、歴史の教訓に鑑みますならば、今回の審査基準というのは、うまく玉を投げたチームにおそらく票が入ったのではないかと思います。つまり核のある世界、核の無い世界、この2つの世界があって、そこに向かう時に両方バランスの取れた論議、つまり、核の無い世界に向かって歩む際には、決して核のある世界を忘れてはいけない。つまり、抑止力を維持しながらも、かつ、軍縮、それから不拡散は追及していかなくてはいけない。この3つのバランスが取れた論議をしたチームに軍配が上がったのではないかという気が致しました。
論議を見ておりまして、かなり勉強しているチーム、もうちょっと資料を読み込んで欲しかったチーム、もう少し軍縮、不拡散について論議をしていただきたかった点、そういう点も多々ありますが、みなさんは非常によく勉強され準備されて本日の討論会にのぞまれた様子が理解できました。これから社会に出て、ぜひこの経験、この日のために準備したことを役に立てて、日本の国のために貢献されることを願いまして、私の講評を終わります。
(2)阿部信泰 日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長

白熱した議論が展開されました。核軍縮、核不拡散をどの様に進めていくべきかについて、興味深い議論を聞かせて頂きました。
この討論会は、賛成と反対の立場に分かれて議論を戦わせ、どちらがよりよい議論を展開したかを競うディベート・コンテストです。論題を良く読んで下さい。「全世界の核兵器を削減し」とあり、「核廃絶」とは言っていません。理想としての核廃絶はあるかもしれませんが、そして核廃絶の方が単純で力強い議論となるかもしれませんが、論題の問いかけているのは、核廃絶の過程としての核削減を推進すべきか、推進すべきとしてどの様な手法をとるか、なのです。
大切なのは、どうやって聴衆の支持を獲得するかです。削減をするのかしないのか、不拡散はするのかしないのか、不拡散の後に削減をするべきなのか、それとも削減も不拡散も同時にすることが可能か、相手の主張と自らの主張の共通点を明らかにしつつ、異なる論点についての自らの主張の優位性を明らかにすることにより聴衆を取り込む、このmiddle ground(中間地帯)をどちらが取るかというのが、ディベートの手法として非常に重要です。
加えて、ディベートの手法として大事なのは、相手の議論に切り込んでいくことです。直前に立場が決まり、相手の議論を聞きつつ自らの議論を組み立てる、ストレスのかかるなかで、自己矛盾をきたさずに、相手側を攻撃していく巧みさが求められます。
一部は議論がかみ合っているところもありましたが、事前準備が足りなかったところもありました。
討論会の中で、大変興味深い論点もありました。例を挙げれば、核を無くした世界が本当に平和か?という我々が真剣に考えなければならない問題。その他には、日米同盟を可視化していく努力、核の先制不使用宣言を核兵器の役割を減らす文脈にどう位置づけていくか等が印象に残りました。
(3)黒澤 満 大阪女学院大学大学院教授(審査委員長)

お二人の審査委員が非常に細かく講評されましたので、それにお二人の意見とほとんど同じなので、それは繰り返しません。私自身、非常に勉強させていただいたし、久しぶりにものすごくノートを取ったわけでありまして、これだけ勉強したのは久しぶりという感じです。これは日々われわれが議論している問題であり、そして、アメリカがオバマ政権に代わり、日本の政府も代わる非常に重要な時です。そして、安全保障政策、核軍縮政策も、多分大きく変わる可能性があるわけです。そういう時期にこれを議論されたということは非常に有意義だったと思います。参加された方は当然だと思いますが、われわれも非常に良い勉強になりました。
一つ別の話をしますと、8月15日にNHKで放送した核問題に関する討論番組で、7時半から11時頃までの議論を見た方がおられるか分かりませんが、32人の一般の方と5人の識者がおられました。後半から、みんなエキサイトしだしまして、司会者が当てなくてもしゃべりだし、そして、人がしゃべっていてもしゃべる、2人同時にしゃべる、司会者が止めないという、非常に混乱状態に陥りまして、私は非常に不満で帰ったわけです。ですから、今日のディベートを見て、彼らにディベートのベースをきちんと理解して欲しかったと思いました。時間内にきちんと自分の意見を論理的にしゃべるという訓練を今日の方は受けておられるけれども、一般市民は受けていなくて、そのルールに反してもしゃべったら勝ちということは、民放だったらともかく、NHKがやったことに非常に失望してクレームをしました。こういう形で毎年外務省で主催され、そして、勉強されて、ディベートの技術も覚えられてということで、これは非常に良いと思っております。
講評の最後になりますが、色々な意見が出まして、結果はこうなりましたけれども、これは中身だけではなくて、やり方とか、駆け引きとか、全て入って採点しているわけであり、その主張に賛成だからではなく、反対の側もそれが論理的であればきちんと採点しました。公平であったかどうかは、皆様に判断してもらうしかありませんが、われわれも全力を尽くして採点しました。今日はどうもありがとうございました。
6.懇親会
討論会の終了後、リバティータワー9階の教室にて懇親会を行いました。審査委員や出場者、傍聴者の多くの方々が出席し、引き続き討論内容について議論したり、出場チーム同士で歓談したり、審査委員長にサインを求める光景も見られ、終始和やかに有意義な懇談の一時を過ごすことができました。
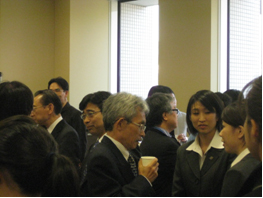

7.参考(フォーラム2009募集案内時の開催要領)
1.日時及び開催場所
| 日時 | 場所 |
|---|---|
| 平成21年9月13日(日曜日)13時00分~ | 明治大学リバティーホール ※ |
※東京都千代田区神田駿河台1-1 明治大学リバティータワー1階
JR中央線・総武線/東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅から徒歩3分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅から徒歩5分
都営地下鉄三田線・新宿線/東京メトロ半蔵門線 神保町駅から徒歩5分
2.討論会概要
(1)論題:「日本政府は、全世界の核兵器を削減し、安全保障における核兵器の役割を減らすための取組を強化すべきである。」
(2)論題解説:核兵器を巡っては、核兵器不拡散条約(NPT)を中心とした不拡散体制の強化が図られていますが、本論題は、現在高まりつつある世界的な核軍縮の流れを活かして、核兵器の「不拡散」に止まらず、「削減」にも取り組むことによって、核兵器の安全保障上の役割を減らすことの是非を問うものです。北朝鮮による核・ミサイル開発や中国の急速な軍事力の近代化など、厳しさを増している東アジア情勢、そうした中で、我が国が日米安全保障体制の下での核抑止力を重要な柱として自国の安全を確保しているという現実、国際社会における核テロリズムの危険性増大などの視点も採り入れて論点を構成してください。
(3)チーム構成:1チーム原則2名、3名でも可とします。
※チームの構成は、全員が同じ大学・大学院在籍者でなくとも可とします。
※各対抗戦において、チーム構成員のそれぞれが最低1回発言することを条件とします。
(4)出場チーム
肯定側立論書の書類選考による事前審査を行い、上位4チームが討論会(準決勝2試合及び決勝戦)への出場権を獲得します。選考結果は8月末日頃、応募されたチームの代表者へメールにて通知します。
※出場者の交通費を支給します。(但し、通常の居住地から会場までの外務省規定額となりますのでご了承ください)。
(5)討論形式
- 肯定側第一立論 (5分)
- 否定側質疑応答 (2分)
- 否定側第一立論 (5分)
- 肯定側質疑応答 (2分)
- 肯定側第二立論 (5分)
- 否定側質疑応答 (2分)
- 否定側第二立論 (5分)
- 肯定側質疑応答 (2分)
- 作戦タイム (1分)
- 否定側第一反駁 (4分)
- 肯定側第一反論 (4分)
- 否定側第二反駁 (4分)
- 肯定側第二反論 (4分) (最大45分)
(注意事項)
- 本討論会では、論題分析、論理構成、論拠・証拠資料、話し方・マナーの観点から総合的に審査を行いますが、特に説得力、表現力、交渉力等については重視しております。
- 討論においては、日本の国益及び日本国民の利益を増進するとの観点を踏まえつつ、国際社会における課題をいかに解決すべきかとの問題意識から、具体的かつ客観的、論理的な立証を心掛けるものとします。
- 反駁、反論では、それまでの立論で示された議論を踏まえて論を深めるものとし、全く関係のない新しい論点は提示できません。
- 試合中、チーム・メンバー以外の者から助言を受けることを禁止します。
- 発言の速度や発声方法のために発言が聞き取りにくい場合、審査員が注意することがあります。
- 討論は口頭のみで行うものとし、パワーポイントやパネル等の使用を含む資料の提示は行わないものとします。なお、資料を引用する際には、その出典を口頭で明らかにしてください。
3.開催日スケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 12時30分~ | 開場、受付開始 |
| 13時00分~13時15分 | 開会式 |
| 13時15分~14時00分 | 準決勝第1試合 |
| 14時00分~14時45分 | 準決勝第2試合 |
| 14時45分~15時00分 | 休憩 |
| 15時00分~15時05分 | 決勝戦進出チーム発表 |
| 15時05分~15時50分 | 決勝戦 |
| 15時50分~16時05分 | 休憩および最終審査 |
| 16時05分~16時25分 | 講評、表彰 |
| 16時30分~17時00分 | 懇親会 |
※報道関係者による取材が行われる場合があります。また、外務省が広報目的で、大会当日の様子を撮影したビデオ、写真等を利用することがあります。予めご了承ください。
4.賞
『外務大臣賞』1チーム:賞状、トロフィー
『優秀賞』1チーム:賞状、トロフィー
『奨励賞』2チーム:賞状
5.傍聴者
傍聴者の参加を歓迎します。会場の座席の都合上、事前の申込者を優先します。
1.応募資格
大学生、大学院生(国籍は問いません。使用言語は日本語とします。)
2.応募方法
(1)参加登録:応募フォームに必要事項を記入し、7月25日(土曜日)までに下記(4)の宛先まで送付して下さい。チーム名は、簡潔かつ適切な表現で、必ず記入のこと。
→応募フォームリンク(WORD/PDF![]() )
)
(2)立論書の提出:参加登録チームは、立論書フォームに肯定側立論書(※1)を記入し、8月10日(月曜日)24時00分必着で下記(4)の宛先までメールで送付して下さい。(※2)
→立論書フォームリンク(WORD/PDF![]() )
)
※1:肯定側立論書は、論題及び論題解説で使用されている主要な言葉を必要に応じて「定義」した上で、現状を分析し、如何なる取組を強化すべきかについての「プラン」を提示し、その結果として「メリット」が発生する過程とその重要性を論証する5分間のスピーチ原稿(A4用紙40字X40行で2枚に収まる程度)にまとめてください。この立論書を実際に本選で使用するか否かは問いません。
なお、スピーチ原稿ですので、図、表、グラフは添付しないで下さい。
※2:立論書の受領を確認する意味で、事務局から代表者へ受領通知を返信します。
(3)傍聴者登録:傍聴のみを希望される方は、氏名・所属・連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)を明記し、「傍聴希望」とお書きの上、9月10日(木曜日)までに下記(4)の宛先までお申し込み下さい。当日の受付も可能ですが、お席の確約はできませんので、できる限り事前に登録をしてください。
(4)宛先:「大学生国際問題討論会 フォーラム2009」事務局
メールアドレス:kokusaimondai@mpc-inc.co.jp
ファックス:03-5468-0557
※送付の方法はメールが望ましいですが、不可能な場合はFAXでも可とします。なお、郵送は不可とします。
※記載頂いた個人情報は適切に管理し、本事業を遂行するための連絡先情報として利用させて頂きます。御本人の同意なしに目的以外に使用することはありません。
3.問い合わせ先
外務省 国内広報課 03-3580-3311(内線3993)
![]() Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
