グローカル外交ネット
令和5年度 地方連携フォーラム
地方連携推進室
令和6年1月11日、「令和5年度地方連携フォーラム」をウェビナー形式で開催しました。本フォーラムは、地方自治体の国際的取組を支援する目的で、地域レベルの国際交流活動に関する外交政策等や最近の国際情勢等に関する説明を地方自治体の実務担当者等を対象に行うものであり、平成20年度から実施しています。今回は第1部「経済外交と官民連携」、第2部「自治体の中古消防車・救急車等を通じた国際貢献・地方交流」、第3部「コロナ禍後のインバウンド観光の最新動向と地方における取組」の三部構成で、それぞれ地方自治体の関心が高いテーマについて、講師による講演を行いました。
第1部 外交政策等説明会
『経済外交と官民連携』
講師:柴田隆 外務省経済局政策課首席事務官
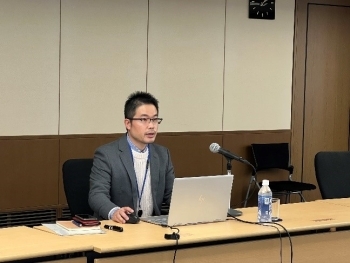 外務省経済局政策課による講演の様子
外務省経済局政策課による講演の様子
第1部では、外務省経済局政策課首席事務官として、G7広島サミット・APEC首脳会談等の経済外交及び官民連携に携わってきた柴田隆氏が講演を行いました。
柴田首席事務官からは、経済外交の3つの側面として、(1)自由で開かれた国際経済システムを強化するためのルール作り、(2)官民連携による日本企業の海外展開支援、(3)資源外交とインバウンドの促進があることを説明。G7広島サミットでの広島AIプロセスの立ち上げや、G7広島サミットの成果をグローバルサウスもメンバーに含まれるG20ニュー・デリーサミットにつなげて一貫性を持たせたことなどを紹介しました。
官民連携については、日本企業の海外展開やインフラシステム輸出のための総理大臣・外務大臣等によるトップセールスの例、日本産品輸出促進として、東京電力福島第一原発事故に起因する風評被害を防ぐための各国・地域への働きかけや、日本の安全確保の措置等の情報発信を行っていることを紹介しました。在外公館の日本企業支援の事例や在外公館における地方自治体のPR事業について説明し、地方自治体と連携し日本産品を効果的に発信していくことが重要であることを紹介しました。
第2部 日本外交協会による説明会
『自治体の中古消防車・救急車等を通じた国際貢献・地方交流』
講師:渡邊信裕 一般社団法人日本外交協会事務局長
 一般社団法人 日本外交協会による講演
一般社団法人 日本外交協会による講演
第2部では、地方連携推進室長、在ホーチミン総領事等を歴任し、現在は一般社団法人日本外交協会事務局長として地方自治体等と連携して中古消防車・救急車等の途上国への寄贈といった国際協力事業にも携わる渡邊信裕氏が講演を行いました。
渡邊氏からは、冒頭、協会の設立経緯・目的、協会の事業として、リサイクル援助事業、外交政策の広報・講演会の実施、外交支援事業として在外公館施設保守等のエンジニア派遣を実施していることを紹介しました。
リサイクル援助事業について、全国289の消防本部等の協力の下、これまでに約1,300台(2022年度まで)の車両が寄贈されていること、事業フロー(車両の整備や輸送、更には寄贈車両の使用等に係る現地研修など)の説明を行いました。また、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンをきっかけとして、千葉県松戸市とドミニカ共和国、福岡県みやま市とバヌアツ共和国など、更なる国際交流に繋がった事例も紹介しました。また、支援のトレンドとして、最近では消防車・救急車以外に塵芥収集車・給水車などにもニーズがあり、自治体で寄贈の候補となる機材等があれば是非協会に連絡や相談をいただきたいとの話もありました。
講演後の意見交換では、ベトナムと交流希望のある自治体から交流の可能性について質問があり、ベトナムは日本との自治体交流に積極的で、ハノイ、ホーチミンといった大都市だけでなく、地方都市とも交流の可能性があること、こうした交流の実施について相談先として地方連携担当官が大使館、総領事館に配属されていることを紹介しました。
第3部 観光庁による説明会
『コロナ禍後のインバウンド観光の最新動向と地方における取組』
講師:遠藤翼 観光庁観光地域振興部観光資源課文化・歴史資源活用推進室長
 観光庁による講演
観光庁による講演
第3部では、観光庁観光地域振興部観光資源課文化・歴史資源活用推進室の遠藤室長から、文化や食、歴史等の多岐にわたる分野を対象とした観光施策、インバウンド旅行者の本格的な回復を図るため、全国津々浦々で観光回復の起爆剤となる特別な体験の創出や誘客促進に向けた受入環境整備支援等について、『コロナ禍後のインバウンド観光の最新動向と地方における取組』をテーマに講演を行い、講演後には参加者との意見交換を実施しました。
冒頭、観光の持つ多面的な意義、日本が持つ「観光先進国」への可能性、観光交流人口増大による経済効果について説明を行いました。現在オーバーツーリズムが話題になる中、経済効果だけでなく、「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを行っていることも紹介しました。
続いて、旅行消費におけるコロナの影響と直近の状況として、2023年7~9月期の訪日外国人消費額は2019年同期比17.7%増であること、「持続可能な観光」への関心が高まっていること等について説明しました。
その上で、観光政策の方向性として、観光立国推進基本計画(第4次)で2025年(大阪・関西万博開催)に向け、「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」をキーワードとしていること、2023年の主な施策と来年度の事業等について説明しました。
講演後の意見交換では、「富裕層を継続的に誘致するにはどのような取り組みが効果的か」、「これから海外観光客誘致に取り組む中で、どこまでのレベルに引き上げれば観光庁の事業に採択されるか」、「DMOなど観光には多くのプレーヤーがいる中、自治体に求められる役割はなにか」といった質問があり、遠藤室長から、「富裕層とのパイプ役を誘致し、IT企業が提供するサービスを最大限活用しPRすること」、「今その地域にある魅力を活用し、走りながらレベルアップすること」、「自治体が管理している施設を公開するなども含めて自治体にしかできないことに取り組むこと」の重要性等についてアドバイスを行いました。
実施後、参加者からは、「これから活用できる事業の紹介もあり、今後の施策の検討材料となった。」、「他の地域の具体的な事例や承知していなかった事業を知る貴重な機会となった。」、「インバウンドを進めていくという方針があるものの自治体としての役割に悩んでいたが、今回の講義内容・質疑の内容で方向性を把握でき、非常に有益であった。」という感想が寄せられました。

