グローカル外交ネット
令和4年度 地方連携フォーラム
地方連携推進室
令和5年1月27日、「令和4年度地方連携フォーラム」をウェビナー形式で開催しました。本フォーラムは、地方自治体の国際的取組を支援する目的で、地域レベルの国際交流活動に関する外交政策等や最近の国際情勢等に関する説明を地方自治体の実務担当者等を対象に行うものであり、平成20年度から実施しています。今回は第1部「外交政策等説明会」、第2部「外部有識者による説明会」の二部構成で、それぞれ地方自治体の関心が高いテーマについて、講師による講演が行われました。
第1部 外交政策等説明会
『コロナ禍を乗り越えて、地方の魅力をいかにして世界へ発信するか?』
講師:兒玉和夫 公益財団法人フォーリン・プレスセンター理事長
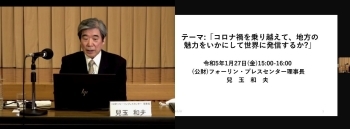 兒玉和夫フォーリン・プレスセンター理事長の講演の様子
兒玉和夫フォーリン・プレスセンター理事長の講演の様子
第1部では、外務報道官や欧州連合日本政府代表部特命全権大使等を歴任し、長年にわたり外交やメディア発信の業務に携わっておられる兒玉和夫理事長を講師にお迎えし、講演を行っていただきました。
兒玉理事長からは、海外に向けた効果的な情報の発信方法について、国内外の各種調査結果等に関する紹介・分析も交えながら、世論調査やメディアの背後にいる海外の人々が日本をどのように評価しているか、日本のどのようなコンテンツに関心があるかを把握して広報戦略を策定し、それを踏まえて、科学技術や歴史・文化、生活様式等といったありのままの姿の日本や、少子高齢化や気候変動等の世界共通の課題に対する地方の取組といったコンテンツを効果的に発信していくことが重要であるといった点が紹介されました。
参加者から事前に寄せられた質問に対する説明も行われました。「分野による効果的な発信方法に違いはあるか。」との質問に対し、兒玉理事長からは、「分野による発信方法に大きな違いはないが、少子高齢化、ゼロエミッション等、メディアの関心の高い世界共通の課題への取組と併せて発信すると効果的である。」との回答があり、また、「コロナの影響で変化した発信方法はあるか。」との質問には、「最近はコロナ禍前のようにメディアが対面での取材を求める声が多く聞かれる。自治体から積極的にかつタイミング良く取材機会を周知することや、プロのジャーナリストが発信するリアルと、誰もが発信できるバーチャルを戦略的に使い分けることが重要である。」との説明がありました。
実施後、参加者からは、「海外への戦略的情報発信を課題と感じていたため、非常に参考になった」といった声や、「自治体が苦手とする海外への広報について、数値分析に基づく有効な手段などを知ることができた」、「地方にも、海外に発信する上で強みになるネタがあるのだと自信が持てた」といった感想が寄せられました。
第2部 外部有識者による説明会
『地方自治体におけるSDGs推進 持続可能なまちを考える』
講師:伊藤夢人 山形県米沢市元参与
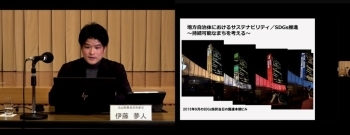 伊藤夢人・山形県米沢市元参与の講演の様子
伊藤夢人・山形県米沢市元参与の講演の様子
第2部では、かつて外務省職員として開発協力や日本企業の海外展開等に従事し、現在は「世界のまちづくりネットワーク形成」と「日本のまちづくりの世界発信」をテーマに活動する、伊藤夢人氏をお迎えし、講演を行っていただきました。
伊藤氏からは、地方におけるサステナビリティについて、2030年までの目標としてSDGsがあるが、その先にあるサステナビリティも見据えて、『経済・社会・環境の三側面』のバランスを考えて行動することが重要である、特に、地域やコミュテニィの次元でサステナビリティを広めるには、『人にやさしい場所・空間』がカギとなるとの説明がありました。また、自身が参与を務めた米沢市の事例を含む、国内外の魅力的なまちの取組やその共通点が紹介されました。さらに、地方の企業がサステナビリティを推進するための取り組み方についても示唆がありました。
講演後の意見交換では、神奈川県横浜市、岐阜県高山市及び福岡県北九州市から、それぞれの地方自治体のSDGsへの取組が紹介され、意見交換が行われました。横浜市による「地元企業に向けてSDGsへの取組を啓発していくにはどうするのがよいか。」という質問に対し、伊藤氏からは、「企業がインセンティブを感じられるような形でその取組を可視化することが有効である。また、行政と地元の異業種が混ざり合う仕組みができるとよい。」との説明が行われました。また、高山市による「海外の先進的な事例を教えてほしい。」との質問に対しては、「欧州等では、自然観光と子どもの教育を結びつけたサステナブルツアー等をやっている事業者を支援するといった例も多く、自然が豊かな日本の自治体にも参考になるであろう。」というアドバイスがありました。さらに、北九州市による「SDGsは目標が高く当初より達成が難しいと言われる中、新型コロナやウクライナ情勢、原材料費高騰等の影響で達成がより困難になってきている状況をどのように受け止めるか。」という質問に対して、「SDGsの先も見据えて、経済・社会・環境という普遍的な要素のバランスがとれたかたちで、各自治体の課題や強みを生かした攻めの部分を発信すること、2030年以降も通用するような施策や意識啓発を行うことが重要である。」との回答がありました。
実施後、参加者からは、「地方自治体の施策に反映できる有益な情報が多くあった」といった声や、「SDGsについて疑問に思っていた点を講師に直接訊くことができた」、「SDGsの知識を深め、さらに各自治体の取り組みなども知ることができた」という感想が寄せられました。

