|
1.テーマ:NGO支援
|
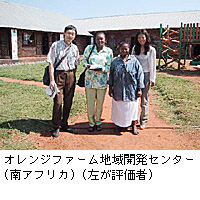 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:南アフリカ、ケニア
|
|
3.評価者:今里 義和 東京新聞論説委員
|
|
4.現地調査実施期間:2001年2月12日~22日
|
5.視察対象プロジェクト:
(1)オレンジファーム地域開発センター施設拡充計画(南ア)
(2)プリンセス・ダイアナ・モハウ児童ケア・センター施設整備(南ア)
(3)ガイゼ小学校施設整備(ケニア)
(4)エンブ子供診療所拡張(ケニア)
(5)セーブ・ザ・チルドレン・センター職業訓練校建設(ケニア)
|
6.評価結果:
| (1) |
日本経済が長期の不況に苦しむ昨今、納税者たちは、直接利益に結びつかない途上国支援に対し、せちがらくなりがちである。半面、途上国の人々は日本の状況が問題にならないほど厳しい貧困に苦しんでいるのであって、そこに救いの手をさしのべるのは国際社会の一員としての義務でもある。
この相反する要請の一つの調和点は、特に日本のNGO、または日本人が参加しているNGOに対する「草の根無償」協力の分野だろう。 |
| (2) |
(イ) |
「オレンジファーム地域開発センター」では、低所得層地域の女性の自立を図るため、小規模の資金で託児所、職業訓練施設としての裁縫教室などを整備していて、協力にあたっている日本のNGOが「日本の顔」にもなっている。 |
| (ロ) |
「プリンセス・ダイアナ・モハウ児童ケア・センター」は、HIVに感染した児童らを保護、収容する施設であり、日本のNGOの姿はなかったが、玄関入り口の目立つ場所に日本の貢献を顕彰するプレートが飾られていて、少なくとも日本の足跡がしるされていた。 |
| (ハ) |
「ガイゼ小学校」及び「エンブ子供診療所」は、首都ナイロビから車で2時間以上かかる郊外に定着した日本人夫婦が、学校建設に協力、あるいは医療や職業訓練の施設を直接運営している事業で、同夫婦の、子供を失った苦難や強盗の恐怖を乗り越えながらの活動は特筆に値する。 |
| (ニ) |
「セーブ・ザ・チルドレン・センター職業訓練校」は、ナイロビ近郊で孤児、ストリートチルドレンらを保護して織物、陶器、農業などの職業訓練を行うのが目的で、日本人主宰のNGOが運営に奮闘している。
|
|
7.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等)
| (1) |
「草の根無償」は、性格上、1,000万円未満の比較的小規模な支援が中心である一方、申請が大量に寄せられる大使館も多い。アフリカ各国にある大使館には、経済協力担当者は2-4人程度しかいないのが通例のようであり、申し込み受付、審査、供与、事後検査といった事務の処理をこなしていくのは相当に煩雑な仕事になる。
しかし、どの案件が最も支援を必要としているのか、あるいはどの案件に支援すれば最も協力の効率が高いのかは、現地を訪れてみなければ実際にはわかりにくい。たとえば、同じケニア国内の小規模無償資金協力であっても、井戸さえないガイゼ小学校と、給水施設を完備したセーブ・ザ・チルドレン・センター職業訓練校とでは、「ありがたみ」に大きな開きがある。 |
| (2) |
「草の根無償」をさらに展開していくには、こうした差を事前に情報収集して支援金額に反映させる努力が必要である。それには大使館の要員の確保、予算手当がまず不可欠であるという印象を強く受けた。
とりわけ、南アはこの地域ではいわば経済大国であり、基本的には国内における「富の再配分」の自助努力を優先させることとし、日本の人道上の経済協力は、できるだけ、より貧しい国に振り向けるべきである。南アにおいては、単純な人道支援よりも「周辺国を含む地域の安定に果たす役割への支援」といった戦略的支援に重点を置くべきであり、「草の根無償」は、日本のNGOまたは日本人参加のNGOを最大限優先すべきではないか。 |
| (3) |
また、各事業の支援金額と整備された施設を見比べると、効率性にもかなりの開きがあるように見える。プロジェクトのモニタリングや評価は、外部委託してでも厳密に実行すべきだ。
さらに、最も基本的な問題は、日本のNGOがもっとこの制度を活用できるよう、プロの人材と組織を育成することだ。たとえば「専門化」、「提携・合併による大型化」といった目標を立てつつ、日本国内の教育訓練体制を急いで整備、強化していく必要がある。 |
|
8.外務省からの一言:
| (1) |
草の根無償は、少額であるが木目細かな手当を行うことが可能であり、かつ末端の一般庶民に日本の「顔が見える援助」として受け止められる制度であり、今後とも一層活用したい。 |
| (2) |
また、提言にも指摘されているとおり、制度導入後10年が経ち、予算、件数が飛躍的に伸びていることから実施体制の強化が急務である。案件の適正な実施及び在外公館の対応能力の強化のために、専門家、青年海外協力隊員との連携を一層強化するとともに、外部調査委託制度を更に活用していきたい。 |
| (3) |
長年の白人支配体制の結果、南アフリカの所得格差は世界で最悪である。南ア政府は格差の是正に取り組んでいるが、急激な富の再配分はむしろ経済・政治上の混乱を来すとの立場であり、日本を含む国際社会も同意見である。従って、我が国は草の根無償を含む南ア貧困層への支援は引き続き必要であると認識している。また、中央・地方政府の政策を実施するための能力が十分育っていないことから、現在コミュニティやNGOがその代替媒体として社会開発(教育、基礎医療、職業訓練等)事業を実施せざるを得ない状況であり、これらの分野では草の根無償を継続する意義は高い。 |
|
