1-3 調査の方法(評価のフレームワーク)
本NGO事業補助金制度の評価調査は、A.目的、B.プロセス、C.効果の3つの視点で行った。
| A. | 目的(NGO事業補助金制度の目的が妥当であったか?):
NGO事業補助金制度の目的((1)「被援助国に対して国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」、(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」)の妥当性について検証した。 |
| B. | プロセス(NGO事業補助金制度のプロセスの適切性・効率性はどうか?):
NGO事業補助金制度の(1)申請手続き、(2)書類審査と採択の通知、(3)完了報告書、補助金の支払い、という一連のプロセスについて、適切性、効率性を検証した。 |
| C. | 効果(NGO補助金制度の目的が達成されたか?):
補助金制度で行われたプロジェクトにおいて、NGO事業補助金制度の目的((1)「被援助国に対して国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」、(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」)が達成されたか、分析した。ただし、ケーススタディーとして扱ったのは、フィリピンの保健セクターでは9団体が活動しているのみであって、4団体のみ検証できた。 |
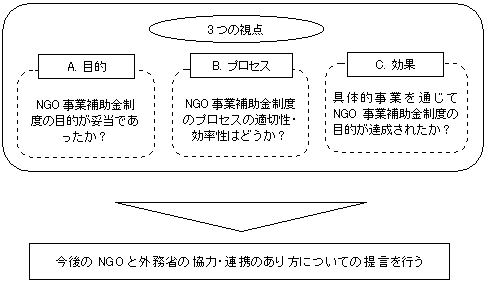
本調査では以下のように、「目的」「プロセス」「効果」という3つの評価視点に基づいて、調査内容と評価基準を設け、国内調査および現地調査により調査を実施した。なお、調査にあたり、参考事例として、JICAフィリピン事務所、他ドナー(USAID, AusAID, CIDA)、JICAプロジェクト1の現地カウンターパートにおいても情報収集を行った。その結果については、参考情報として、第3章及び第4章にそれぞれ、「参考:NGO事業補助金の特徴」「参考:NGO事業の特徴」として、章末に附すこととした。
| 評価の視点 | 調査内容と評価基準 | 調査方法 | 情報収集 相手先 |
| A-1 目的(1)の妥当性
a. 上位概念との整合性 b. 相手国のニーズとの整合性 |
A-1
a. ODA大綱、ODA中期政策、対フィリピン国別援助計画 b.国家保健計画、地方自治法 |
- 文献
- 文献 - フィリピン保健省 |
|
| A-2 目的(2)の妥当性
a. 上位概念との整合性 |
A-2
a. ODA大綱、ODA中期政策 |
-文献 | |
| B-1 適切性
a. 各手続きと本制度の目的との整合性 b. 各手続きと我が国の上位概念および法・規則との整合性 |
B-1
a. 本制度の目的 b. ODA大綱、ODA中期政策、我が国の法・規則 |
- 外務省民間援助支援室
- 在比日本大使館 |
|
| B-2 効率性
a. 時間的、コスト的な効率性 |
B-2
a. NGOへのアンケート調査(質問票2) |
- NGO事業補助金交付先9団体3) | |
| C-1目的(1)の達成度
a. 草の根レベルの成果がでているか? b. 地域住民のニーズにかなった事業であったか? c. 地域住民の参加が得られ、自立発展性があったか? d. 女性の裨益効果があったか? |
C-1
・NGO 4団体2) へのアンケート調査(質問票1)、インタビュー調査(現地) |
- NGO事業補助金交付先4団体及び現地カウンターパート | |
| C-2目的(2)の達成度
a. プロジェクト運営力・スタッフの育成・経験蓄積 b. 資金調達力・社会的PR力 c. 草の根レベルのネットワーク作り d. 提言活動の改善 |
C-2
・NGO 4団体2) へのアンケート調査(質問票1, 2)インタビュー調査(現地) ・上記NGO 4団体以外の5団体へのアンケート調査(質問票2) |
- NGO事業補助金交付先9団体3) |
| (注1) | NGO事業補助金の申請から補助金支払いまでの手続きのこと。 |
| (注2) | NGO 4団体:(社)銀鈴会、(特非)金光教平和活動センター、(特非)地球ボランティア協会、(特非)日本フィリピンボランティア協会 |
| (注3) | NGO 9団体:上記4団体に加えて以下の5団体。(特非)国際ボランティアセンター山形、(特非)ICA文化事業協会、(特非)AMDA(アジア医師連絡協議会)、神奈川海外ボランティア歯科医療団、太平洋に歯科医療を育てる会。 |
A. NGO事業補助金制度の目的の評価
NGO事業補助金制度は、「外務省とNGOの連携及び支援」という上位目標の下、2つの目的、すなわち、目的(1)「被援助国に対して国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」と、目的(2)「本邦NGOの組織能力を強化する」を有していた。ここでは、目的の妥当性を、ODA大綱、中期政策、我が国の国別援助計画の上位概念との整合性、また相手国のニーズとの整合性の視点から検証した。
B. NGO事業補助金制度のプロセスについての評価
補助金の一連のプロセス((1)申請手続き、(2)書類審査と採択の通知、(3)完了報告書、補助金の支払い)について、NGO事業補助金制度の目的、及び、我が国の法・規則との整合性の視点から、適切性を検討した。また、制度運用の実態を調査し、時間とコストの観点からプロセスの効率性の評価を行った。
C. NGO事業補助金制度の効果
NGO事業補助金の交付先事業2を事例に、NGO事業補助金制度の目的((1) 「被援助国に対して国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする」、(2)「NGOの組織能力を強化する」。)が達成されたかについて検討した。
目的(1)「被援助国に対して国家レベルの協力では対応が難しい、きめこまかな援助を可能にする」の達成度については、審査の基本的考え方にある4点、すなわち、「(1)政府レベルでは対応が困難な草の根レベルの事業であり、途上国住民に対する人道的配慮及び環境保全の観点から配慮がなされており、かつ経済・社会・地域開発、民生の安定につながること、(2)地域社会のニーズが十分把握されていること、(3)地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること(4)援助効果が対象地域の女性にも裨益するように配慮されていること」の達成度につき、質問票1による調査3と現地調査により、検討を行った。
目的(2)「NGOの組織能力の強化」の達成度については、調査対象NGO 9団体に日本国内で質問票2による調査4を行い、また、現地事業に日本のNGOの組織能力の向上が現れているか調査することにより、検証した。
1 対象プロジェクトは、JICAプロ技「家族計画・母子保健プロジェクト(フェーズI及びII)」、及びJICA研修員受入れ事業「ミンダナオ平和開発特別地域参加型包括的保健行政推進」事業の2事業であった。対象プロジェクトの選択基準は、「フィリピン保健医療分野において、NGO事業補助金事業と対象分野が類似しており、かつ事業評価終了済みの案件」とした。
2 本調査対象のNGOの選定基準は、「フィリピンにおける1997年以降のNGO事業補助金交付先案件でかつ保健医療事業であること」であり、9団体が候補に上がった。まず9団体全てに質問票1(添付9参照)を送付し、現地調査の依頼を行った。その中で、今回現地調査受入れ可能な団体は4団体であった(別添6参照)。現地調査では、日本側NGO、又はカウンターパートNGOを訪問することとした。
3 別添9参照。
4 別添10参照。

