1-4. 評価方法
評価とは、評価される当事者に、彼らが遂行する事業に対する建設的な視点を与え、その事業をよりよいものにするための示唆を得させるものでなければならない。すなわち、評価とは、本来は評価を行う側が評価される側に評価されるのだという、気骨の折れる行為なのである。村人のコメントを極力聞くことが肝要である。さらに、今回の評価行為は、それぞれが数年以上を経過している2つの事業を、たかだか数日で全般的に評価しようという、とりようによっては、誠に傲慢ともいえる行為である。従って、プロジェクトが設定した目標の達成や個々の活動の妥当性など、通常の評価で把握すべき項目は今回は問わなかった。短期間の外部者による評価として何が出来るか、という観点に立ち、以下の視点からの評価を行うこととした。
□ 評価の概念的枠組み
今回の評価においては、以上の点を考慮に入れつつ、評価のための以下のような概念的枠組み1を設定してみた。まず、今回の評価のテーマを「持続可能な開発」とし、それを、1)経済面での開発(Economic Development)、2)環境面での開発(Ecological Development)、3)地域社会、生活共同体の開発(Community Development)の3つの構成要素が調和のとれた状態であると定義した。
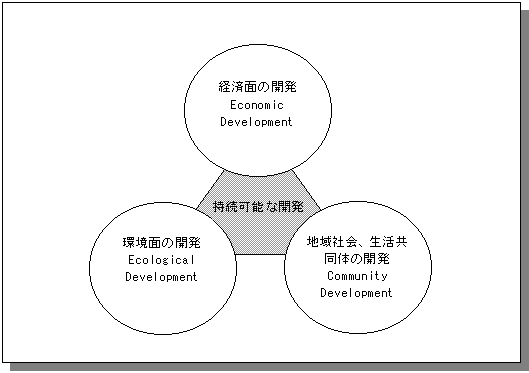
この概念的枠組みを、実際の評価においては、以下のように展開した。すなわち、事業(案件)全体並びに事業の個々の活動を、この3つの構成要素面から把握した。時間軸においては、以下の図1-2に示す事業遂行の各段階において、この3つの構成要素がいかに考慮されているを検討した。
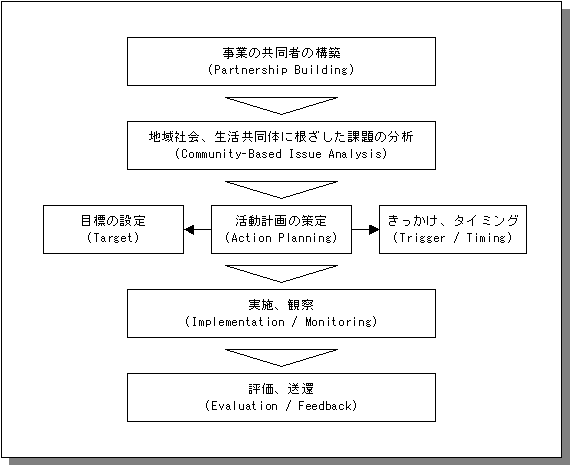
□ 方法論(アプローチ)に関する評価の枠組み
また、持続可能な開発を実現するための方法論の概念としては、
- ■ 分権(Decentralization)
- ■ 参加(Participation)
□ 持続可能な開発達成確認のための視点
また、事業が3つの構成要素間の調和のとれたものであり、なおかつ、上記のような方法論的要請を満たしているかどうかを確かめるための視点として、以下の点に留意した。
- ■(当該事業は)住民が維持できるか
- ■(当該事業は)環境的に維持できるか
- ■ 住民による再生産が可能である
- ■ 他の村の住民により、模倣が可能である
また、後者に関しては、事業が事業の遂行中のみ成らず、終了後の将来にわたっても環境への負担に留意しているかどうか、環境への負担を予測する当該社会の変動に対する適切な分析がなされているかどうかが問われる。
□ 当事者の概念
今回の評価の対象となる2事業には、厳密に言えば、事業の執行者と受け手の区別はない。すなわち、ODA、NGOの事業とに係わらず、事業の基本的目標、性格からいって、
- ■ 外部機関
- ■ 外部機関の現地のカウンターパート
- ■ 住民
- ■ 外部機関の現地のカウンターパート
同時に、我々が見逃してはならないのは、いわば隠れた当事者である。それは、事業を直接間接に左右する影響力を持つ以下の要素である。
- ■ 当該国の国家政策、戦略(特に今回の場合は、ラオスの農業戦略など)
- ■ 外部機関の政策、戦略(今回の場合、日本のODA戦略など)
- ■ グローバライゼーション
- ■ 外部機関の政策、戦略(今回の場合、日本のODA戦略など)
1 この枠組みは "The Agenda 21 Planning Guide - An Introduction of Sustainable Development Planning -", ICLEI, 1996にヒントを得て展開したものである。

