第2章 GIIの7年間の活動実績に関する分析
2.1 GIIの活動実績
2.1.1 GIIの特徴1
(1)他のドナーとの積極的な連携を推進
地球環境の保全をはじめ、人口問題、エイズ、食料、対人地雷を含む地域紛争、子供の健康、さらには薬物の蔓延など深刻な問題が地球を襲いかかり、国際社会においてこれらの問題に対する早急な対策が声高に叫ばれるようになった1990年代、その世界的な状況を受け、1993年に日米両首脳間で「地球的展望に立った協力のための共通課題」(日米コモン・アジェンダ)が合意されて以来、日本政府は世界二大ドナー国間の日米協力を含め、主要援助国や国連の諸機関との協調の中でこれらの問題に積極的に取り組んできた(第4章参照)。経済摩擦ではない新たな日米関係を作ろうという発想の元、日本政府の提案にアメリカが合意し1993年に発足した日米コモン・アジェンダであったが、続いて1994年にスタートしたGIIもその流れを大きく受け、日米をはじめとする他のドナーとの連携を積極的に推進し様々な成果を収めてきたイニシアティブであった(第5章参照)。
GII発足以前には、人口・エイズ問題、および家族計画の分野にはほとんど日本政府としての実績は多国間援助(UNFPAやIPPF以外)はなく、二国間援助の形では低調であった。日米コモン・アジェンダには数十にわたる分野があった中で、なぜGIIとして人口・エイズという保健分野に特化させたかについては、当時の政策担当官は以下のように語っている(2001年11月15日インタビュー)。
1994年の国際人口・開発会議(1994年9月、カイロ)、同じく94年の横浜エイズ会議が開催され、その中で、
| 1) | 途上国における家族計画の問題の解決においては、日本国内での経験が十分に生かされる場であったこと、 |
| 2) | エイズに関しても、血友病患者が増えたことが大々的に報道されたことなどで、日本国内でも関心が高まった時期であったこと、 |
| 3) | 日本の援助がハード面からソフト面へ移行する時期であったこと、 |
日米コモン・アジェンダによってカバーされる分野としては、1994年2月にGIIがスタートした当初は人口・エイズ問題のみであったが、子供の健康が後に追加、1995年にはその子供の健康分野の中にポリオが加わり、さらに女性と開発、新興・再興感染症が新たな項目として組み込まれた。感染症対策の一環としては、水資源の保全プロジェクトがアフリカの9カ国において取り組まれた実績がある。
1995年中期には、リプロダクティブ・ヘルス(および地球規模食料供給)が日米コモン・アジェンダの項目に加わり、それが日本ではGIIに組み込まれた(後述)。これは、女性問題や基礎的な教育を充実させることによって人口増加率を下げることが期待された。特に、日本の経験を生かせるように採った対策が、「人口間接協力」という概念を盛り込むことにもつながった(後述)。ただしGII発足当初は、当時のスキームに当てはまらないものもあった。例えば、コンドーム一つをとっても「消耗品」というカテゴリーと捉えられていたため、日本政府は供給できない時代であった。その際には、GIIのプログラムとしてUNFPAとのマルチ・バイで対策を講じた経験がある。その後、様々な形で国際機関との連携が図られ推進されてきた。
また、日米の連携においては、徐々に外務省―USAIDの連携からJICA―USAIDの連携にシフトし、現場のプロジェクト実施レベルでの連携が可能になると同時に、技術専門員交換制度として、JICAの保健医療担当部局とUSAIDのグローバル局人口・保健・栄養センター(Center for Population, Health and Nutrition for Global Program (G/PHN))との間で人材交流をスタートさせた。USAIDの資金獲得の手法、USAIDとNGOとの連携のあり方などを短期間で研究するコースから始まり、やがてUSAIDの環境部門のスタッフをJICAに1年、またJICAのスタッフをG/PHNに2年送るインターンのプログラムを具現化した。
(2)包括的アプローチを採用
GIIは、人口・家族計画や母子保健といった直接的な協力だけでなく、女性と子供の健康にかかわる基礎保健医療、初等教育、女性の識字教育・職業訓練などのリプロダクティブ・ヘルス/ライツおよびジェンダー/エンパワーメントの視点を中心とする、間接的な協力を含めた「包括的なアプローチ」をとることを基本精神としており、この取り組み方は前述の国際人口・開発会議(1994年9月、カイロ)でも採用された(第2章参照)。また第4回世界女性会議(1995年9月、北京)において日本政府は「途上国の女性支援(Women in Development = WID)イニシアティブ」を発表。このイニシアティブは、1)教育、2)健康、3)経済・社会活動への参加、という3つの重点分野を中心に、他の援助国、国際機関、NGOとも協力しながら、WID分野での開発援助・協力の拡充に努力していこうというものであり、GIIの基本精神が活かされたものであった。ただ、当時のGIIは人口間接協力が過多になる傾向もあったため、人口直接協力とのバランス、またエイズ分野における協力、および人材育成の部門へ力を入れる動きが1995年半ばごろから出始めた。
一方アメリカは、包括的なアプローチではなく、個別のアプローチを重視しており、予算の100%が人口直接分野に投入されており、日本が人口間接分野として扱っている部分に関しては別の形で対応している。
(3)重点国の設定
さらに、GIIを推進していくに当たっては対象となる開発途上各国の問題の深刻さ、緊急性、政府等の受入れ体制、主要ドナー・国際機関(特にUNFPA、UNAIDS、UNICEFなど)の協力状況等より判断して、12の重点国をアジア、アフリカ、中南米地域より選定し、これら12の重点国すべてにおいてGII案件を発掘するために「人口・エイズ・プロジェクト形成調査団」を順次派遣、これら調査団の派遣により人口・エイズ関連のプロジェクトが新たに形成されてきた。GII発足当初に選定された12ヶ国とは別に、GIIの中間評価以降、新たにヴェトナム、ジンバブエ、ザンビア、カンボディアの4ヶ国が重点国として加わったほか、世界の主要ドナー国である日米の連携による地球規模問題への対策の必要性がそれまで以上に高まってきたことを受け、1998年にはザンビアへ、99年にはバングラデシュおよびカンボディアへ、また2001年にはタンザニアへ日米合同のプロジェクト形成調査団が出されている。
GII案件として、1994年に初のプロジェクト形成調査団がインドネシアおよびフィリピンに派遣された後、多くの日米協調によるプロジェクト案件が形成されていった。そのプロセスにおいて、アジアにおけるUSAIDの政策の見直しに日本の視点が多く取り入れられるようになるなど、日米間の相互理解が深まったことが、GII発足当時のUSAID東京事務所代表によって指摘されている。
(4)NGOとの連携
上記のように、GIIの枠組みではリプロダクティブ・ヘルス/ライツやジェンダーの視点を基本精神とした包括的なアプローチは主要ドナー国および国連機関との連携によって更に推進され、重点国各国にプロジェクト形成調査団が派遣された結果、既存のスキームとの組み合わせによってリソースの有効活用が図られ、プロジェクトが立案・実施されてきたことが特徴としてあげられる。
ここで忘れてはならないGIIにおけるもう一つの主な特徴は、NGOの役割の重要性が早くから着目されたこと、つまり、主要ドナー国および国際機関との協調と併せてNGOとの連携が基本方針の一つとして進められてきたことである。上記のGIIの特徴を実践に移し具体的な成果をあげるためにNGOが果たしてきた役割は大きかったと言われる。具体的には、プロジェクト形成調査の期間中に現地NGOとの対話を実現し、南の草の根レベルにおけるニーズを把握した他、日本国内における政府とNGOの対話を実現させたが、政府とNGOとの対話はNGOの数を拡大しながら定期懇談会へと発展していった。
またその流れを受け、2000年7月の九州・沖縄サミットの機会に他に先駆けて日本政府が新たに発表したIDIにおいても、NGOとの連携ははずせないアジェンダとして捉えられている。(第6章参照。)
2.1.2 実績額の推移
1994年から2000年までの7年間、我が国がGII関連分野(人口直接、人口間接、HIV/AIDS)で実施した協力実績額は5,431億円(約50億ドル)であった2。図2.1に、GII分野の協力実績額の経年推移を示す。実績額のピークである1998年度までの5年間で、GII分野の協力実績の総額は3,917億円(37億ドル)におよび、当初の目標額であった30億ドルを達成した。
図2.1 GII実績額推移(FY94-00)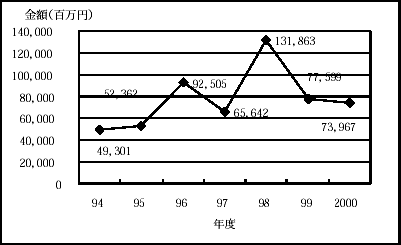 |
| 出所:外務省我が国GIIの7年間の実績(2000年度) |
2.1.3 外務省案件分野別分析
図2.2にGII開始後7年間の実績総額を人口直接、人口間接、HIV/AIDSの3分野別に示す。実績総額の82%(4,432億円)を人口間接が占めており、人口直接は16%(859億円)、HIV/AIDSは総額のわずか2%(135億円)であった。また、分野(人口直接、人口間接、HIV/AIDS)別に、実績額の経年推移をみると(図2.3)、人口直接分野とHIV/AIDS分野の実績額は、大きな変動はみられないものの漸増傾向に有り、2000年の年間実質額は1994年度に比較し、人口直接分野で約2倍、エイズ分野で約3倍に増加した。一方人口間接分野の協力実績額は、1996年度と1998年度に急増しており、その実績額は前年比の約2倍である。これは図2.1の実績額総額の推移と同じ動きであり、人口間接分野での実績額がその年の実績額総額に影響を及ぼしていることがわかる。
図2.2 GII実績額(FY94-00) 内訳(総額5,431億円)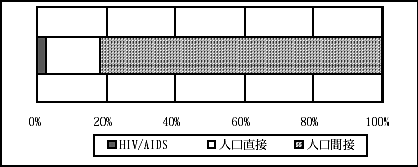 |
| 出所:外務省我が国GIIの7年間の実績(2000年度) |
図2.3 GII実績額 分野別推移(FY94-00)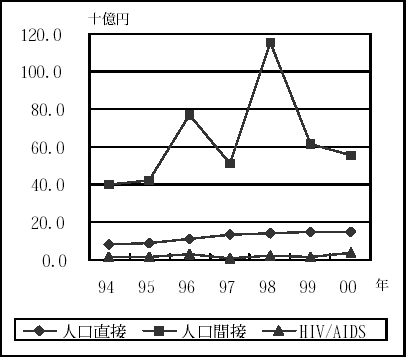 |
| 出所:外務省『我が国GIIの7年間の実績(2000年度)』 |
2.1.4 スキーム別実績額
図2.4に、(1)技術協力、(2)無償資金協力、(3)有償資金協力、(4)国際機関への拠出という、4つのスキーム別に協力実績額の推移を示す。有償資金協力は、1996年と1998年に、前年比約2倍に急増し、人口間接分野実績総額と同様の変動を示している。無償資金協力の実績額は、1998年以降、増加した。技術協力は、大きな変動はみられないが、継続して増加傾向を示している。
図2.4 スキーム別 実績額推移(FY94-00)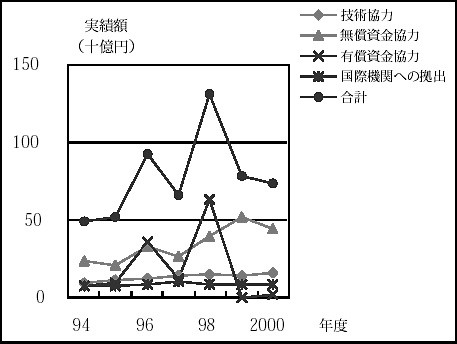 |
| 出所:外務省我が国GIIの7年間の実績(2000年度) |
これら4スキームによる協力を分野別に示したのが図2.5である。HIV/AIDS及び人口直接分野では、国際機関への拠出が、それぞれ約40%、約65%を占めている。人口間接分野では、無償資金及び有償資金協力が多く、これら2つのスキームを併せると人口間接分野の実績総額の約80%を占める。
図2.5 各分野スキーム内訳(FY94-00)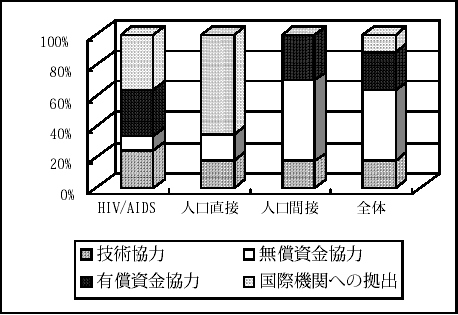 |
| 出所:外務省我が国GIIの7年間の実績(2000年) |
1 本稿2.1.1は、「GII/IDIの関するNGO懇談会」の代表者の執筆による。
2 外務省『我が国GIIの7年間の実績(2000年度)』。本項で分析の対象とした実績額には、以下12種のスキームによる協力が計上されている:(1)技術協力、(2)開発調査、(3)援助効率促進事業、(4)開発福祉支援事業、(5)開発パートナー事業、(6)無償資金協力、(7)草の根無償資金協力、(8)有償資金協力(円借款)、(9)NGO事業補助金、(10)依託調査、(11)評価調査、(12)国際機関への拠出。

