地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第6章 今後の地球温暖化対策関連ODAへ向けた提言
(1) 日本としての地球温暖化対策に基づくODA戦略の必要性
京都イニシアティブは、「ODAに関する中期政策」の中の7つの重点課題のひとつである「地球規模問題への取組」の中で位置付けられており、従来からのODA政策の中での地球温暖化への取組を構想化したものといえる。しかしながら、地球温暖化問題では、先進国の「共通だが差異のある責任」を京都議定書によって「削減目標」として明確にしており、国内でのGHG排出削減戦略との連携が今後重要になっていくと思われる。
特に、2002年3月に改正された地球温暖化対策推進大綱においては、「我が国は、優れた技術力と環境保全の蓄積された経験を背景に、国際協力を通じて世界の取組の先導的役割を果たしていく」とし、さらに排出削減目標達成に向けてCDMを含めた京都メカニズムの活用が位置付けられており、今後は大綱とODAとの連携も必要になってくる。
例えば、アメリカはUNFCCC締約国会議(COP)において継続的に途上国での排出削減の必要性を主張しているが、2002年2月に発表された「気候変動戦略」では、削減分野および吸収源分野を主な対象としており、モニタリング・システム以外の適応事業は対象として特記していない。また、京都議定書における削減目標達成のためにCDMの活用を予定するオランダ、ドイツ、カナダなどの国は、積極的にCDM有望国である中国(カナダ)やインドネシア(オランダ、ドイツ)で、CDM事業の実施を見越したホスト国側の能力開発(組織整備、案件発掘・審査、民間企業とのコンタクトなどに必要な能力)への支援を実施している。さらにオランダは、排出削減クレジットを「調達する」という考え方にたったCERUPTプログラムによってCDM事業への積極的投資を既に実行に移している(但し、ODAとは別の環境省予算を財源としている。なお、オランダでは、削減目標の6%の半分をCDMを含む京都メカニズムで確保する削減戦略を策定している。)
以上のような考え方から、日本の温暖化対策ODAは被援助国の持続可能な開発に貢献するのはもちろんのこと、京都議定書下での日本の排出削減目標達成に向けた戦略とも密接に連携し、貢献するものであることが望ましい。
<京都議定書批准・発効後の温暖化対策ODA戦略>
・ 地球温暖化対策推進大綱および京都議定書目標達成計画との連携
・ CDM具体化のための途上国のキャパシティ強化支援
・ 適応事業の強化
・ 京都議定書批准・発効後の京都イニシアティブの見直し
・ 新たな支出を伴わない温暖化援助スキームの検討(例えば、日本版「炭素基金」や温暖化対策ODAにおける債務・削減クレジット・スワップ) など
(2) ODA上流における地球温暖化対策関連ODAに係る政策支援、案件発掘・形成の強化の推進
<地球温暖化対策分野における案件発掘・形成の強化>
日本の外務省ODAが、要請主義を前提としている以上、案件発掘は、被援助国の責任において行われるのが本来のあり方である。しかし、一般的には多くの場合において、被援助国側は地球温暖化対策についての認識が相対的に低く、また具体的な対策分野であるクリーンエネルギー分野や炭素固定に資する森林管理および植林分野のノウハウも不足しているのが実情であるため、被援助国側が、自力で温暖化対策ODAの要請を作成することは、ほぼ不可能である。今回の現地調査の結果においても、この点が裏付けられた。
一般的に、これまでの案件発掘および形成促進は、「(1)日本の民間企業等が、自社負担にて非公式に実施してきたもの」、「(2)政府が実施機関等を通じて実施してきたもの」、「(3)社団法人等が、政府と協力しつつ実施してきたもの」に分類される。
これらのうちの(1)については、発掘した案件を自社で受注する可能性が必ずしも高くなく、民間事業としての採算性が低く留まることから、企業は案件発掘に従事するインセンティブが見出せず、案件発掘から撤退する企業が現れるなど、停滞状況にある。但し、(経済産業省所管であるため今回調査の対象外ではあるが)エネルギー分野の案件発掘に関しては、経済産業省のF/S支援制度である「地球環境・プラント活性化事業等調査委託費等(2002年度約16億円)」が、有効な制度として多いに活用されている。
(2)については、"援助効率促進費"によるプロジェクト形成調査の実施や企画調査員等の派遣、円借款に係る案件形成促進調査(SAPROF)等により、案件の発掘ないし形成促進を進めてきたが、これらが全体の案件発掘ないし形成促進に占める割合は、大きくはない。
(3)については、一般的に国際建設技術協会、海外建設協会、国際厚生事業団等の社団法人により実施されてきたが、地球温暖化対策に係る分野で見た場合、交通分野に限定できる。
これらの現況を踏まえ、今後、さらに、地球温暖化対策分野の案件発掘を充実させていくためには、「案件発掘を行う民間企業に何らかのインセンティブを与える仕組みを作るか、もしくは支援補助金を拡充する」、「公的な案件発掘体制を強化していく」の、主に2つの方法が考えられる。
現時点では、後者に力点を置く形で改良が進められつつある。すなわち、2002年度開発調査事業費の費目組替えによる「政策・プログラム支援協力」の創設、「民間提案型プロジェクト形成調査」の開始、円借款に係る「提案型・発掘型案件形成調査」の開始など、一部で政策提案型ODAを展開するための体制が強化されつつある。
この政策提案型ODAの展開の動きに協調する形で、その政策提案をする際の視点の中に、「地球温暖化対策」が盛り込まれるような仕組み作りを行うことが望ましい。その際、注意が必要なのは、現行の政策提案型ODAが、「国別」を基本として展開されている点である。「国別援助計画」の中に、「分野別、課題別援助方針」をどのように取り入れていくかは、議論されて久しいテーマであるが、温暖化対策ODAにおいては、地球規模の視点で戦略を作ることが非常に重要であるため、特に、この点に留意する必要がある。
以上を踏まえ、具体的な対応策として、以下を提案したい。
1) 途上国全体を対象とし、地球温暖化対策に係るポテンシャルやニーズ把握のための詳細なデータ収集調査を実施する。
2) 複数国を選定し、地球温暖化対策に係るプロジェクト形成調査を実施する。
3) 第二次ODA改革懇談会の最終報告で設置が提言された「ODA戦略総合会議」の中の分会として「地球温暖化対策関連ODA戦略部会」を設置し、有識者等の意見を踏まえた温暖化対策ODA戦略を作成する。
<電力セクターマスタープランに係る技術協力の重点的な推進>
3.2でも述べた通り、特に途上国においては、「電力が絶対的に不足している状況にあること」、「初期投資の大きい新エネルギーは成立し難いこと」等の理由により、新たな電力供給を行う際に大規模火力といったような従来型の伝統的な電源が選択されがちである。地球規模の視野で考えた場合、この中に「いかに"地球温暖化対策の視点"を適正な度合いで反映させていくか」、すなわち「GHGの排出量の少ない新エネルギー等の電源の選択を促進していくか」が、重要なポイントとなる。
従って、今後電力セクターマスタープランに係る開発調査もしくは政策アドバイザー専門家の派遣を積極的に実施し、被援助国の電源開発計画の中で「地球温暖化対策の視点」を適正に踏まえた電源選択が行われるよう支援すべきであろう。
(3) 「地球温暖化対策への貢献度」の適正な考慮の推進
地球温暖化対策に貢献する案件であっても、その事を示すような情報を意図的に記述するようにしなければ、「地球温暖化対策ODA」であることは、その実施に従事する関係者や一般国民・国際社会に認識されることはない。
今回、評価の対象とした案件のほとんどは、その案件の背景、目的、効果の説明の中で、地球温暖化対策への貢献に係る記述が不十分であった。
今後は、各被援助国の国別援助政策や被援助国自身の政策の中に「地球温暖化対策の視点」を適正に織り込み、メインストリーム化していくためにも、個々の案件の地球温暖化対策への貢献度につき、可能な限り記述するようにすべきと考える。
この際、米国USAIDの気候変動イニシアティブにおけるレポーティング・システムが参考になる。USAIDでは、気候変動イニシアティブ予算により実施したプロジェクト全てにつき、以下のような報告義務を課している。
- 下表に示すアウトラインのプロジェクト要約を、A4サイズ4頁以内の容量にて作成し、気候変動イニシアティブのホームページに掲載すること
- 「当該プロジェクト実施に伴う気候変動に係る指標の改善度合い」を示すデータを作成し、気候変動イニシアティブのホームページに掲載すること
|
||||||||||||
| 出所) "USAID Climate Change Initiative FY00 Reporting Guidance, USAID , Oct 2000"より野村総合研究所作成 |
日本の温暖化対策ODAの中で「地球温暖化対策の視点」をメインストリーム化していくためには、この米国の事例が参考になると考えられ、そのための具体的な手法として、以下を提案したい。
1) 地球温暖化対策プロジェクトとしての認証体制の確立
USAIDの事例と異なり、日本のODAにおいては、特に地球温暖化対策を主目的とする予算枠があるわけではない。従って、地球温暖化対策と見なせるプロジェクトについては、実施機関の環境分野を横断的に所管する部署(JBIC環境審査室、JICA企画部環境女性課)等が中心となり、案件選定の早い段階から、当該プロジェクトを「地球温暖化対策」として認証するのが好ましいと思われる。なお、ここでの"認証"手続は、必ずしも厳密な審査を前提とせず、比較的簡易な審査でも良いと考えられる。
また、認証手続を行うための前提として、要請書の背景・目的・効果の欄に、地球温暖化対策への貢献度に対する言及、記述等が記載されている必要があり、これを誘導するためには、日本政府が温暖化対策ODAに取り組むことを、途上国政府に積極的に伝えていくことが先決となる。
2) 地球温暖化対策プロジェクトとしての案件選定・モニタリング体制の確立
認証されたプロジェクトについては、USAIDの事例を参考に、温暖化対策への貢献度合いを示す情報の提出を義務付けるようにし、温暖化対策の観点からモニタリングするのが良いと思われる。
また、案件選定の段階においても地球温暖化対策の視点が考慮されるよう、案件検討時の評価項目の一つとして「地球温暖化対策への貢献度」を適切な比重にて採用すべきであろう。
3) レポーティング・ガイドラインの作成
上述の、認証、モニタリング・システムを創設する場合には、地球温暖化対策に係る知識が余りない担当者でも容易に報告書類の作成が出来るよう、また報告書類の品質や構成がある程度統一的になるよう、レポーティング・ガイドラインを作成することが必須となる。
USAIDで作成しているガイダンス等をベースにして、1)日本のODAスキームに合致するような内容とする、2)より使い易く、分かり易い形式とする、の主に2点に留意しつつ作成するのが好ましい。
4) 排出削減量が定量化可能な案件の経済分析における便益としての位置付けの推進
資金協力案件に係る基本設計時の事業評価もしくは開発調査(技術協力)中のフィージビリティ・スタディの際、内部収益率(IIR: Internal Rate of Return) を算出する過程において、「二酸化炭素の排出削減による便益」を計上することを、積極的に推進すべきである。
既に、円借款案件の一部において、「二酸化炭素の排出削減による便益」を社会便益として位置付け、経済内部収益率(EIRR)の算出に組み入れている事例がある。今後、京都議定書が発効すれば削減クレジットの価格の安定化も見込めることから、財務内部収益率(FIRR)の算出にも「二酸化炭素の排出削減による便益」を早期に組み入れていくことが考えられる。
(4) CDMへの取組の検討の必要性
マラケシュ合意において、CDM事業に公的資金を活用する場合、その資金はODAの流用であってはならないと明文化された。
カナダ等、先進国の中には、ODAとは別枠の基金を設け、途上国での温暖化対策プロジェクトをODAとは切り離して行っている国もある。現在、日本政府は京都メカニズムの活用財源に関する明確なスタンスを示しておらず、COPでの交渉においてはCDMにODA事業を活用できると主張してきた経緯もあり、その扱いが注目されている。
| "Emphasizing that public funding for clean development mechanism projects from Parties in Annex I is not to result in the diversion of official development assistance and is to be separate from and not counted towards the financial obligations of Parties included in Annex-I," --- マラケシュ合意 Decision 17/CP.7 |
仮に、日本国政府が温暖化対策プロジェクトにODAを利用したとしても、従来BHN分野へ利用されていたODA資金の減少への懸念、温暖化対策以外のODA案件の減少への懸念、温暖化対策に傾倒したアンバランスな開発の進行への懸念等を指摘する向きも国際社会や非援助国政府にはあり、当該プロジェクトが被援助国政府にCDMとして承認されない可能性も考えられる。このような日本のODAに対する国際社会の懸念を生じさせないためにも、まずは国としてODA資金を利用してCDMプロジェクトを実施するかどうか、実施するならばどのようなプロジェクトなのか(例えば技術協力のみ)等を整理し、国際社会に示す必要があるといえる。
例えば、ODAの「流用(Diversion)」ではないという前提の下に、日本の企業がCDM事業に積極的に参入できる布石となるような、インフラ整備を中心としたCDMプロジェクトのパイロット事業を展開することは、企業にとっては参入障壁が低減され、途上国にとっては資金流入の拡大へつながるため、受け入れやすいと考えられる。具体的には、地域の電力利用のための配電網整備、物流スムース化のための道路インフラの整備等の実施が挙げられる。
一方で、ODA大国である我が国としては、ODAによる温暖化対策事業による削減クレジット獲得可能性の検討も重要な課題といえる。ODAの流用でなく、かつ国の新たな資金の支出につながらないスキームとして、世銀PCFやオランダCERUPTなどを参考に、GHG削減に関心の高い企業等からの出資を集め、優良な温暖化対策ODA案件を発掘し、当該事業による削減・吸収量をクレジットとして獲得するような、日本版「炭素基金」(仮称)の検討も考えられる。
図表 日本版「炭素基金」〔仮称〕のイメージ
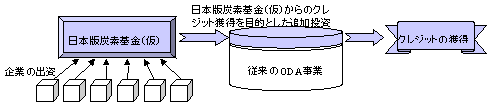 |
| 出所)野村総合研究所作成 |
また、直接CDM事業には当てはまらないものの、CDMホスト国のCDM事業受入能力の整備・向上を図り、民間による積極的なCDM事業への参入を促進するような能力開発事業の推進も望まれる。具体的には、CDM管轄機関の設立支援を含めた国内制度整備、CDMに関わる人材育成、CDMとしての可能性のある案件の発掘能力等、世銀NSSを通じてドイツ等が実施しているような事業(21ページ参照)などが考えられる。
このようなCDM事業およびCDM支援事業は、地球温暖化対策推進大綱においても「相手国政府の理解促進等に向けた取組の実施」として「主要相手国が京都メカニズムの参加資格を満たせるよう、モニタリング制度の構築等に係る能力育成支援を行う」としており、国内対策とも整合することから積極的に推進していくことが望まれる。
(5) 適応事業の検討
温暖化対策としては削減対策を第一義的に進めるべきではあるが、第1章でもみたように、IPCCの第3次評価報告書によれば、国際的な地球温暖化対策が計画通り実施されたとしても、地球温暖化は進行することが予想される。その場合、やはり一番の被害を受けるのは、気候変動への適応能力に劣る途上国である。特に小島嶼国をはじめとして、海面上昇などによって大きな被害が予想される国々では、先進国による削減活動はもちろん、地球温暖化への適応事業にもっと関心を払ってもらいたいとの意見がUNFCCC-COPなどを通じて高まっている。
ISDにも掲げられている、途上国の持続可能な開発そして人間の安全保障の確保からすれば、このような脆弱性の高い途上国の要望に応えて、適応支援事業を拡充することは、我が国の方針にも合致するものといえる。また、適応事業は、主にインフラ整備と人づくりが中心であることから、京都イニシアティブの方針とも合致する。
しかしながら、適応事業の多くは、今後数十年かけて起こるであろう気候変動に対して備えるためのものであり、その案件の形成等には十分な検討が必要である。また、UNFCCCマラケシュ合意に盛り込まれた3つの基金(特別気候変動基金、最貧国基金、京都議定書適応基金)との整合についても、十分取っていく必要がある。
UNEP(国連環境計画)によると、適応策には、「撤退」、「順応」、「防護」があり、下表のように様々な事業が存在する。実際の適応策の立案では、撤退策、順応策にかかわる計画的・政策的対応と技術的な対応を組み合わせることが重要とされている。
ODAを利用した適応策としては、現段階では「防護」のためのハード・ソフト技術の建設支援が中心となっているが、これからアジア地域においても「順応」の技術協力、最終的には事業途中に「撤退」を考慮する可能性も視野に入れることが求められる。
今後は、どの地域あるいは国で、どのような適応事業(撤退・順応・防護、あるいはハード整備・能力開発)が必要かを、被援助国と共同で調査・検討し、適応事業の戦略を検討することが望まれる。
- <今後実施すべき適応事業支援の具体例>
- ・ 詳細な国別脆弱性調査の実施
・ 適応戦略および行動計画の策定支援
・ 適応技術・事業の被援助国との共同開発
図表 UNEPによる適応策の定義および事業例
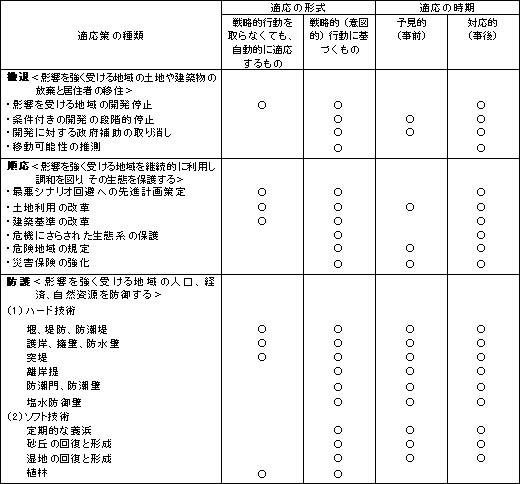 |
| (出所)海面上昇データブック, 国立環境研究所地球環境研究センター(2000)より野村総合研究所作成 |
(6) 地球温暖化対策に係る啓蒙・啓発活動の支援の強化
今回の現地調査では、一般市民のみならず、中央省庁の役人や政策決定者においても、地球温暖化に係る知識や危機意識が低いレベルに留まっているということが明らかになった。
身近な大気汚染や水質汚濁等の環境問題であれば、粉塵の吸引による呼吸器障害の発症や、汚染された水を認識すること等により、環境の悪化を実感することができる。これらと異なり、地球温暖化問題は、緩やかな時間進行の気候変動の結果として比較的遠い未来に生じる問題であるため、身をもって実感することも出来なければ、それによって引き起こされる被害が具体的に何なのかを理解することも容易でない。
これらを踏まえ、日本をはじめとする先進国諸国は、今後GHG排出量の急増が予想される途上国において、早い時期から地球温暖化に係る意識を高めることに取り組むべきであろう。
特に、我が国は、国内対策として「改訂:地球温暖化推進対策大綱、2002年3月」を策定し、この中で民生部門が取り組むべき事項について、事細かに示している(冷蔵庫の効率的使用や、洗面所の節水など)。また各自治体においては、住民の中から地球温暖化対策推進員を任命することにより、草の根の地球温暖化対策を推進するなど、地球温暖化に係る啓蒙/普及活動においても、一定程度の経験を積み上げてきている。このような経験は、ライフスタイルの相違に係る部分を除けば、途上国において応用可能なものである。
具体的には、次のような手法が考えられる。
1) 途上国の国家開発戦略、PRSP等に、温暖化対策が組み込まれるような働きかけ
2) 地球温暖化に係る啓蒙/普及活動分野へのシニアボランティアや青年海外協力隊員の派遣
3) 地球温暖化対策分野の派遣専門家の業務における啓蒙・普及活動項目の組み入れ・拡充
4) 地球温暖化対策研修コースプログラムにおける啓蒙・普及活動項目の組み入れ・拡充
5) e-ラーニング等の新たなツールを活用した地球温暖化に係る啓蒙・教育プログラムの提供

