2 戦略性の強化ときめ細やかな制度設計
(1)政策と実施の一貫性の強化
ア 開発協力政策の枠組み
政府の開発協力の理念や原則等を定める開発協力大綱の下、外務省は国別開発協力方針注15を定めると同時に、分野別開発政策を策定しています。
国別開発協力方針は、相手国の政治・経済・社会情勢を踏まえ、その国の開発計画、開発上の課題等を総合的に勘案して、日本の援助重点分野や方向性を示すものです。また、開発協力の予見可能性を高めることに役立つ資料として、実施決定から完了までの段階にあるODA案件を、その国の援助重点分野・開発課題・協力プログラムに分類して一覧にした事業展開計画を作成し、関係者間で共有しています。
持続可能な開発目標(SDGs)など、開発に関する国際的な取組を踏まえて、分野別開発政策注16も策定しています。
より効果的な開発協力のため、中期的な開発協力の重点分野や開発協力政策を相手国政府と共有するとともに、相手国政府との政策協議を強化し、相互の認識や理解を共有する取組も進めています。
イ 開発協力の実施体制
開発協力政策に則した開発協力の実施に際しては、政府と実施機関が一体となり、無償資金協力、技術協力、有償資金協力といったスキームの効果的な活用に努めています。二国間協力と国際機関やNGOを通じた多国間協力などを、共創を実現するための様々な主体との連帯を通じて、最適な組合せで実施し、開発効果を最大化することを目指しています。
具体的な案件の形成・選定・実施につなげていくための体制を強化するために、二国間関係、相手国の政治・経済・社会情勢を踏まえた開発ニーズや開発協力の実態を最も直接的に把握できる立場にある現地の大使館やJICA事務所などから構成される現地ODAタスクフォース解説を、原則全てのODA対象国に設置しています。ODAタスクフォースでは、開発協力ニーズの把握に加えて、国別開発協力方針や事業展開計画の策定への参画、協力候補案件の形成・選定、他ドナーや国際機関、現地で活躍する日本企業やNGOとの連携強化、開発協力手法の連携や見直しに関する提言を行っています。
個々の事業が長年にわたって相手国政府および国民に広く認知され、事業終了後も正しく評価されるためのフォローアップも行っています。
ウ ODAの管理改善と説明責任
開発協力の効果・効率性の向上に加え、国民への説明責任を果たす観点からも、適切に評価を行い、評価結果を政策や事業の改善につなげることは重要です。日本はこれまで、ODAの管理改善と説明責任を果たすために(ⅰ)PDCAサイクル(政策立案・案件形成(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Act))の強化、(ⅱ)プログラム・アプローチの強化、(ⅲ)「見える化」の徹底を進め、開発協力の政策立案、実施、評価、改善のサイクルにおける戦略的な一貫性の確保に努めてきています。
PDCAサイクルの強化について、日本は、(ⅰ)全ての被援助国についての国別開発協力方針の策定、(ⅱ)開発協力適正会議の開催、(ⅲ)個別案件ごとの指標の設定、(ⅳ)評価体制の強化といった取組を進めています。
より効果的・効率的なODAを行うためには、事業レベルだけではなく、政策レベルでPDCAサイクルを強化していくことが必要です。そのため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づいて経済協力に係る施策などについて政策評価を実施注17するとともに、客観性や公平性を確保するため第三者によるODA評価を実施し、評価の結果から得られた提言や教訓をODA政策にフィードバックすることで、ODAの管理改善を図っています注18。
第三者評価は、被援助国の開発に役立っているかという「開発の視点」に加え、日本の国益にとってどのような好ましい影響があるかという「外交の視点」から実施しています。
「開発の視点」では、ODA政策が日本の上位政策や国際的な優先課題、被援助国のニーズに整合しているか(政策の妥当性)、実際にどのような効果が現れているか(結果の有効性)、政策の妥当性や結果の有効性が確保されるようなプロセスが取られていたか(プロセスの適切性)の3つの評価基準に基づいて評価を実施します。「外交の視点」では、日本の国益にどのように貢献することが期待されるか(外交的な重要性)、日本の国益の実現にどのように貢献したか(外交的な波及効果)の2つの基準に基づいて評価を実施しています。
また、2022年度に実施した「過去のODA評価案件(2015~2021年度)のレビュー」で得られた提言も踏まえて、開発協力大綱の重点政策、アプローチおよび実施原則に照らしたODA評価を強化していきます。
評価結果は、外務省ホームページ注19で公表し、国民への説明責任を果たすとともに、ODAの透明性を高めてODAに対する国民の理解と支持を促進しています。
事業レベルでは、無償資金協力・有償資金協力および技術協力の各プロジェクトについての評価やテーマ別の評価を主にJICAが実施しています。JICAは、各プロジェクトの事前、実施中、事後まで一貫した評価を行うとともに、それぞれの援助手法に整合性のある評価の仕組みを確立しています。なお、一定金額以上の案件については、JICAは外部評価者による事後評価を実施しています。事業の効果を定量的に把握することも重要であり、インパクト評価注20の強化にも取り組んでいます。
外務省およびJICAが実施するODA評価は、主に経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会(DAC)の評価基準注21を踏まえて実施しています。
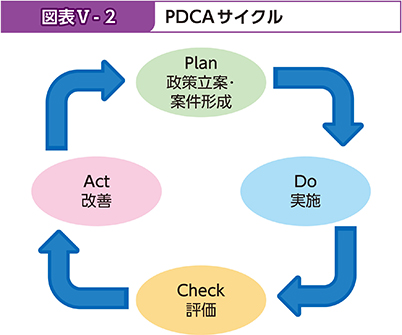
- 注15 : 各国の国別開発協力方針・事業展開計画 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html
- 注16 : 分野別開発政策 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunyabetsu/index.html
- 注17 : 施策レベル以外にも、交換公文(E/N)供与限度額150億円以上の有償資金協力プロジェクト、およびE/N供与限度額10億円以上の無償資金協力プロジェクトについて事前評価を実施している。また、「未着手・未了案件(未着手案件とは、政策決定後、5年を経過した時点で貸付契約が締結されていない、あるいは貸付実行が開始されていない等の案件。未了案件とは、政策決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である等の案件を指す。)」の事後評価を行っている。
- 注18 : 政策レベルのODA評価(第三者評価)に加え、2017年度からは外務省が実施する無償資金協力についても、交換公文(E/N)供与限度額10億円以上の案件については予算上実施可能な範囲で第三者評価を、2億円以上10億円未満の案件については内部評価を実施し、これらの事後評価結果が次のODAの案件形成にいかされるよう努めている。
- 注19 : ODA評価 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka.html
- 注20 : 開発事業の効果を、統計学や計量経済学の手法を用いて検証する評価方法のこと。
- 注21 : DAC評価基準:1991年から活用されてきた妥当性(Relevance)、有効性(Effectiveness)、効率性(Efficiency)、インパクト(Impact)、持続性(Sustainability)に、2019年12月に整合性(Coherence)が追加された。
