2017年度 ODA評価結果フォローアップ
外務省では、第三者評価から得られた提言について、その対応策を策定し、その実施状況の確認を行っています。2017年度の第三者評価から得られた主な提言に対する対応策の実施状況(2019年7月時点)をご紹介いたします。
インド国別評価
提言
生産性や付加価値の高い農業の支援に努めるとともに、森林資源管理分野においては、これまでの成果を総括して今後の戦略を明確化する。また、環境・防災教育の実施や大気汚染対策に関する協力の強化を検討する。
重点分野のうち「持続的で包摂的な成長への支援」は、大規模インフラ事業のように目立つ協力ではないため、広報を工夫する。現地NGO・民間企業等との連携や日系企業進出支援の促進のため、JICAインド事務所に必要な人員を配置する。また、次回の国別援助方針改定時には、インフラ分野の包摂性・持続可能性の観点に基づく留意事項を記載する。
対応策の実施状況
インド政府の要望及び国別援助方針を踏まえ、2018年度には持続的な森林管理や生計向上活動を支援する「トリプラ州持続的水源林管理計画」やコールドチェーン(低温流通体系)整備等を行う「酪農開発計画」といった円借款の実施を決定した。
森林分野における日本の支援に基づく教訓・経験や知見・技術をインド各州の関係者に紹介する「持続的森林管理及び生物多様性保全」という本邦研修を形成した。
大使館では報道発表に加え、大使館facebookや大使インタビューの機会等を積極的に活用して広報に努めている。JICAは国際デーに合わせた取組発信や、2019年にはfacebookを開設して更なる広報の充実に努めている。
JICA事務所の拡充については、中小企業・SDGsビジネス支援の強化に向け、人員の追加配置の可能性を検討している。また、現地NGOとの連携強化のため窓口設置を検討中である。
次回の国別援助方針の改定のタイミング、記載内容について総合的に検討している。

トリプラ州持続的水源林管理事業。
生計向上活動の様子(機織り)
写真提供:JICA

酪農開発事業。
集乳場の様子。毎日多くの農家が協同組合に生乳を売りに来る
写真提供:JICA
ウガンダ国別評価
提言
援助の個別事業の成果を普及・拡大するため、ウガンダ側の政策・制度面への働きかけを強化し、ウガンダ側関係者による主体性や自助努力の醸成に向けた取組を強化すべきである。また、長期にわたる援助事業、特に職業訓練事業における出口戦略を策定し、運営主体をウガンダ側に移行すべきである。
大使館やJICA事務所など現地における援助実施体制を強化し、政策アドバイザーを積極的に活用して開発援助政策分野において人材発掘と育成をすべきである。
知日・親日人材を育成して積極的に活用するとともに、日本とウガンダの多層的な交流拡大に向けた取組を強化すべきである。
対応策の実施状況
JICA職業訓練プログラムを活用し、ウガンダ政府の主体的な取組の下、2018年から職業訓練の全国展開を目指して地方での協力を開始するとともに、2019年4 月にJICA運営指導調査団を派遣し、ウガンダ側と協議を実施した。運営主体の移行については、要人往来の機会を捉えてハイレベルで働きかけを行っている。
大使館及びJICA事務所の人員体制強化の可能性は、引き続き検討している。政策アドバイザーを引き続き積極的に活用し、人材発掘と育成に努めていく。
邦人向け安全対策協議会で日本の対ウガンダ経済協力についての情報共有を開始したことに加え、希望者に大使館が作成するウガンダ月報のメール配信を開始した。
2018年8月、アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(ABEイニシアティブ)壮行会に帰国留学生を招待し、現地でのネットワーキング強化に努めた。カンパラでの日本の大学による留学フェアーにウガンダ国費留学生の会が参加し、留学経験を発表した。また、日本でも日本企業とABEイニシアティブ留学生とが交流するネットワーキングフェアの機会を設けている。

産業人材育成体制強化支援プロジェクト。
電子科実習室で職業訓練に励む訓練生
写真提供:JICA

ワキソ県カチリにあるSt. Mbaaga Collegeでのコンピュータの授業
写真提供:佐藤 浩治/JICA
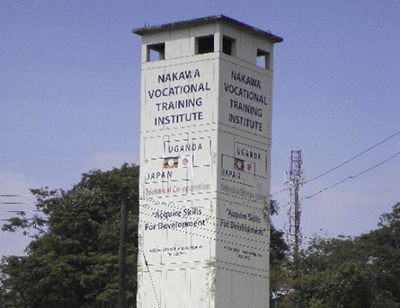
ナカワ職業訓練校
写真提供:JICA
カンボジア国別評価
提言
援助規模の相対的低下を踏まえ、「質の高いインフラ」の支援を継続し、意思決定、支援手続きの簡素化及び迅速化に取り組むべきである。
援助の質と量を確保するためには、政府機関と民間企業が幅広く連携することが必要であり、多額な拠出が可能な国際協力銀行やアジア開発銀行と協力・連携して支援することが適当である。
より強固な二国間関係を構築するために、日本への留学機会を拡充すべきであり、教育分野や水道分野など人材育成分野におけるODAの充実・拡大が期待される。
日本の支援と中国の支援の差別化が可能なガバナンス改善に対する支援を積極的に行うべきである。また、NGOをはじめとする市民社会や法曹人材の交流など幅広い国民各層の参加を得て協力を拡充していくことが有効である。
対応策の実施状況
日本の「質の高いインフラ」をアピールするため、2018年10月の日メコン首脳会議において農業用灌漑水路改修及び入出港管理電子情報処理システム導入に係る協力を表明した。
カンボジア政府との緊密な情報共有を行い、意思決定・支援手続きの簡素化・迅速化に取り組んでいる。
在カンボジア日本大使館と在カンボジア日本商工会会員企業が共同で、カンボジア政府の関連省庁に対して直接投資環境改善の提案を行う官民合同会議を年1〜2回開催しており、今後も引き続き協力・連携していく。2019年2月には、日本の国土交通省とカンボジア国土整備・都市化・建設省との間で、「日カンボジア都市開発・不動産開発プラットフォーム」の設立に関する覚書が締結され、多数の日本企業も参加して第1回会合が開催された。
カンボジア政府の要請を受け、2018年5月にカンボジアの若手行政官の日本への留学支援を目的とする「人材育成奨学計画」に関する国際約束を締結した。
また、ガバナンス支援の一環として、カンボジアの若手政治関係者・司法関係者・選挙関係者等の招聘を実施した。

トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業。
ルム・ハック地区既存幹線水路の様子(改修前)
写真提供:JICA

カンボジア若手政治関係者招聘(河野外務大臣表敬 平成30年12月3日)
JICAボランティア事業の評価
提言
「JICAボランティア事業」の名称・制度の変更など事業の設計・運営の見直しに取り組むべきである。
国別援助方針・事業展開計画において、より長期的な「JICAボランティア事業」の位置づけを明確化し、新たな職種や連携拡大などを検討すべきである。
「日系社会ボランティア事業」に関し、日系社会支援の理念に関する研修の強化、事業参加者募集要件の日系人への拡大、各種活動への参加促進を通じた派遣国における日系社会への支持拡大、日本国内における日系社会ボランティアの知名度向上等に努めるべきである。
JICA企画調査員やJICAボランティアの処遇・地位向上のための支援体制を充実させるべきである。
対応策の実施状況
「ボランティア」という言葉が「JICAボランティア事業」の本質を必ずしも代弁していないということで、事業の名称を「JICA海外協力隊事業」に変更した。また、年齢区分を廃止し、経験・技能の要否に基づいた区分へ変更した。「草の根外交官」として国と国との合意に基づき派遣されていることを自覚させ、必要な知識を定着させるために派遣前訓練カリキュラムの見直しを行った。
国別援助方針・事業展開計画との整合性を高めるため、国別派遣方針・計画の様式・記載内容を見直した。また、効果的な大学連携、自治体連携、民間連携による事業形成を促進するため連携方針を見直した。
「日系社会ボランティア事業」に関しては、日系社会に関する理解促進の機会を設け、同事業の認知度向上に向けた広報・発信を実施した。また、日本国籍を有する日系人への応募勧奨の一環として、NPO主催の日系社会向け行事に参加した。
企画調査員の募集・選考・派遣方法等の見直しを行った。また、企業や自治体に対する帰国隊員の報告会・交流会の拡充等を通して、隊員経験の価値の発信に努めた。隊員の帰国後の動向を把握するアンケート調査を実施し、適時に効果的なキャリア支援が行える体制・制度を整備した。

バレーボールで円陣を組む様子(ラオス)
写真提供:今村 健志朗/JICA

養護老人施設での活動の様子(ブラジル)
写真提供:渋谷 敦志/JICA
TICADプロセスを踏まえた最近10年間の日本の対アフリカ支援評価
提言
複数国にまたがる広域事業や、アフリカ諸国間で開発成果の共有・移転を図る南南協力の推進を一層強化することが望ましい。
他のドナーやアフリカ連合委員会(AUC)、国連開発計画(UNDP)等との連携の更なる強化に努める。更に、TICADの「冠事業」「冠施設」を広めて認知度を高める。
意思決定プロセスの一層の迅速化により、アフリカにおける日本のプレゼンス向上などが期待できるため、重点特定分野事業について、実施決定までの期間短縮のための措置を検討すべきである。
対応策の実施状況
対アフリカ支援政策において、広域協力・南南協力を引き続き実施しており、可能な範囲で盛り込むよう努めている。例えば、日本が策定を支援した西アフリカ「成長の環」広域開発マスタープランが2018年に完成し、関係諸国や他のドナーとも協力してマスタープランの実施に努めている。
連携強化については、世界銀行、UNDP、AU等とアフリカ支援・開発について連携しており、TICAD7に向け共催者会合を開催。今後の連携についても議論している。
TICADの「冠事業」「冠施設」の推進については、今後も適当な案件があれば検討していく。TICAD重点事業の実施迅速化については、引き続き円借款等の案件実施の迅速化に努めている。

ドンゴル村の井戸の様子(ギニア)
写真提供:坂本 達/JICA

ナイロビ国立公園から望む、ナイロビ中心部のビル群(ケニア)
写真提供:久野 真一/JICA

街中を走る乗り合い式タクシーのオート三輪車(エチオピア)
写真提供:久野 武志/JICA
南部回廊を中心としたメコン地域の連結性の評価
提言
外務省と他省庁との連携を強化し、日メコン地域協力に関する政策の一体化を図り、その目的・手法を明確にメコン地域各国に説明すべきである。
メコン地域各国の開発政策・ニーズに呼応した形で日本の開発政策の優先付けを検証し、国際競争力強化に繋がる開発協力を行う。
各国の特性を生かした支援や制度面の支援を継続することにより地域経済の活性化を目指す。
南部回廊の連結性強化に向けた取組を強化する。また、メコン地域支援における日本のイニシアティブを発揮する。
長期専門家の派遣により、政策策定や制度構築面の支援を継続し、各国の得意分野を生かした三角協力等を通じて地域協力を促進する。
対応策の実施状況
2018年の第10回日メコン首脳会議において採択された「東京戦略2018」の調整過程において、外務省と国内関係省庁との連携を強化した。また、メコン地域各国に対しては、首脳会談等を通して日本政府の協力の方向性や認識を丁寧に説明した。
「東京戦略2018」において、タイが主導するエーヤワディ・チャオプラヤ・メコン経済協力戦略会議(ACMECS)マスタープランの実施に貢献しうる100件以上の具体的なメコン支援案件を日本として特定した。これら案件の着実な実施を通じて、 メコン地域の持続可能な産業開発に貢献していく。
「東京戦略2018」は、(1)生きた連結性(2)人を中心とした社会(3)グリーンメコンの実現、の3本柱を掲げており、「生きた連結性」の実現のため、ハード連結性、ソフト連結性、産業連結性のそれぞれにおいて課題の特定と今後の対応を確認し、同戦略に沿った支援を実施している。
また、「東京戦略2018」においては、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想を共有し、地域の連結性強化を図っている。更に、各国首脳の指示に基づき、「2030 年に向けたSDGsのための日メコンイニシアティブ」策定に向けて作業中であり、日本がイニシアティブを発揮している。
法整備支援分野におけるJICAの技術協力を通じた長期専門家派遣及び課題別研修をはじめとする本邦研修を引き続き実施していく。また、JICAとタイ国際協力局(TICA)のパートナーシップ協定に基づくタイとの三角協力の実施等を通じたメコン地域の支援を強化している。

高層ビルからバンコク中心部を見下ろす(タイ)
写真提供:久野 真一/JICA

法・司法改革支援プロジェクト。
ハイフォン検察院でのセミナーの様子(ベトナム)
写真提供:JICA
無償資金協力個別事業の評価
1 2013年度ヨルダンに対する「シリア・アラブ共和国から流出した難民等に対する緊急無償資金協力」
提言
緊急人道支援と開発支援のそれぞれの目的に照らした事業対象範囲を明確化すべきである。また、事業計画時にその対象範囲の妥当性を確認する機能の強化を図るべきである。
事業の対象範囲の変更に伴う検討記録は保存されておくべきである。また、適切な広報を実施するとともに、相手国政府による供与機材の運用や維持管理について報告をさせることが望ましい。
対応策の実施状況
新規の事業を検討する際には、対象事業の緊急性をより明確にした上で実施するように努めている。また、現地大使館、各国際機関現地事務所、各国際機関駐日事務所等とよく連携した上で、重複なく、最も効果的な支援を形成・実施するよう努めている。
検討プロセスの記録については、適切に保存措置が執られており、今後も継続して記録の保存を徹底していく。
シリア難民支援等の広報について、他の支援も含め、外務省ホームページに加え、国際会議の場等を活用した広報を実施している。
供与後のモニタリング、管理及び日本の支援の適切な広報という観点も考慮しつつ、実施機関とより連携した仕組み作りを行えるよう留意する。
2 2014年度パレスチナ自治区に対する「ノンプロジェクト無償資金協力」
提言
事業完了報告書の適時の提出等をはかるため、外務省と在外公館との一層の連携が肝要である。また、見返り資金の活用事例を他の事業実施の参考となるように執務参考資料を整備していくことや積極的に国内及び現地での広報を実施することが重要である。
対応策の実施状況
パレスチナ側に頻繁に照会を行うことによって「事業完了報告書」または「進捗報告書」がほぼ遅滞なく提出されるようになった。報告書の提出が新規事業の承認にとって必要不可欠なプロセスであることがパレスチナ側担当者から理解が得られた。
新規に日本の外務省国際協力局に配属される職員を対象とした研修において、見返り資金の活用事例を経済協力におけるグッドプラクティス(優れた実施)の一例として紹介している。
広報については、在外公館ホームページへの適時の情報掲載など、引き続き積極的な広報に努めている。

