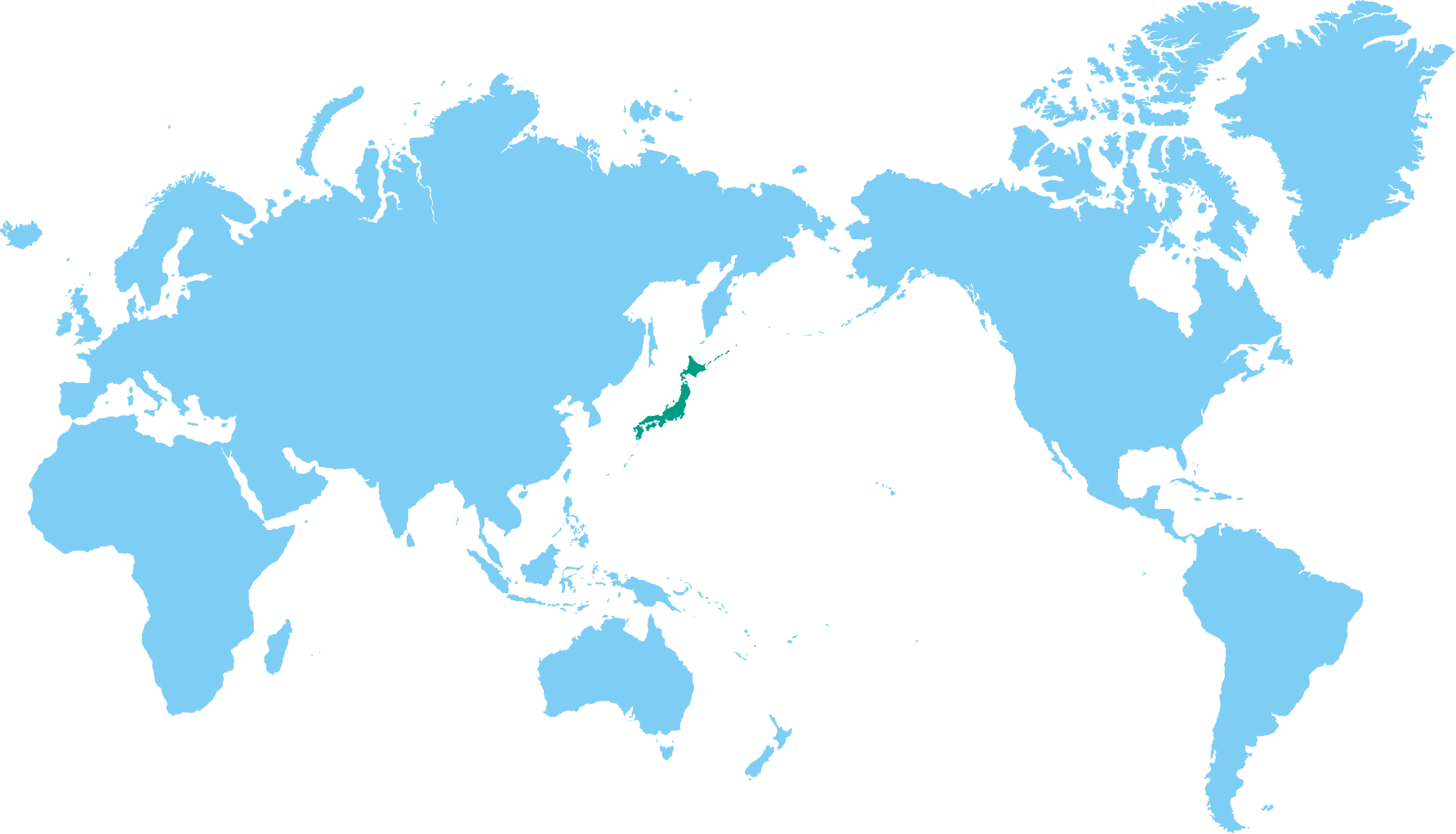コラム
ODAは日本にとってどのような外交的意義があるのか
内閣府が実施する「外交に関する世論調査」には、「開発協力を実施すべき観点」という項目があります。2018年10月の調査では、開発協力を実施すべき理由として、「エネルギー資源などの安定供与の確保に資する」、「国際社会での日本への信頼を高める必要がある」、「戦略的な外交政策を進める上での重要な手段」「「日本経済に役立つ」といった回答が上位を占めました。
過去のODA評価では、ODAが被援助国の開発にどの程度役立っているのかという「開発の視点」を中心に評価が行われてきました。しかし昨今、日本国内では様々な課題が山積し、財政事情も厳しい状況が続いています。そんな中、国民の皆様の関心も受け止め、なぜ諸外国に多額の公金を使う必要があるのか、日本にとってどのような意義があるのかについて、これまで以上に丁寧に説明する必要があります。
開発協力大綱(2015年)で「開発政策は外交を機動的に展開する上で最も重要な手段の一つ」と位置づけられて以降、全ての外務省ODA評価案件において、日本の国益への影響を測る「外交の視点」の評価を実施してきていますが、2017年度ODA評価では、外務省が評価チームと予め詳細な意見交換を行い、評価内容の充実化を図りました。
その結果、例えば「ウガンダ国別評価」では、「ウガンダは天然資源を有する近隣内陸国とケニアのモンバサ港を結ぶ要に位置し、南スーダン等に展開するPKOの拠点。地域統合を通じた自国経済発展に努めているため、対ウガンダODAは周辺地域の安定・発展にも貢献している」と同国に対するODAが持つ外交的な重要性が分かりやすく評価されました。また、ODAの実施によりもたらされた「外交的な波及効果」についても、民間連携事業を通じた自治体や企業による交流の深化、現地の報道件数増加による日本の認知度拡大、中小企業の同国での事業化・拡大展開の成功など、事実関係に基づき、具体的な効果が確認されました。
「外交の視点からの評価」は他国でも少しずつ試みが始まっていますが、国際社会においては評価手法がまだ確立されていません。相手国との関係もあるため非公開情報も多く、日本のODAに限定した「外交的な波及効果」を特定することも容易ではありません。試行錯誤が続きますが、国民の皆様からODAに対する理解が得られるよう、評価の一層の充実化を図っていきます。