責任ある農業投資に関するラウンドテーブル(概要)
平成22年4月27日
4月25日、ワシントンDCにおいて、日、米、アフリカ連合(AU)主催、世界銀行、国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)及び国連貿易開発会議(UNCTAD)共催により、「責任ある農業投資に関するラウンドテーブル」(Roundtable on Responsible Agricultural Investment)を開催したところ、概要以下のとおり(平松賢司経済局審議官、ホセ・フェルナンデス米国務次官補(経済・エネルギー・ビジネス担当)、エリザベス・タンクーAU貿易・産業委員が共同議長)。タンザニア、リベリア、バングラデシュの閣僚、ディウフFAO事務局長、アフリカ開発銀行副総裁をはじめ、各国より130名以上が出席した。
1.経緯
(1)世界的な食料価格高騰を契機として、途上国への大規模な国際農業投資が増加。これが「新植民地主義」あるいは「農地争奪」として国際社会の注目を集める中、我が国はG8ラクイラ・サミットの機会に「責任ある農業投資(RAI:Responsible Agricultural Investment)」の促進を提案し、昨年9月にニューヨークで高級実務者会合(以下、NY会合)を主催。本会合は、このフォローアップとして、世銀・IMF合同開発委員会のフリンジで開催されたもの。
(2)RAIとは、大規模な国際農業投資によって生じ得る負の影響を緩和しつつ、投資の増大によって投資受入国の農業開発を進め、受入国政府、現地の人々、投資家の3者の利益を調和し、最大化することを目指すアプローチ(別紙1(PDF)![]() )。
)。
2.主な出席国・機関
【政府】G8、中国、韓国、インドネシア、バングラデシュ、豪州、南アフリカ、エチオピア、タンザニア、スーダン、リベリア、モザンビーク、レソト、ガイアナ、メキシコ、ペルー、カタール、スイス、オランダ
【国際機関】共催4機関、WFP、EU、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行
【民間セクター】マーズ社、オラム社、プロビデント・グループ(投資銀行)
【市民社会】国際土地連合(
3.共同議長挨拶
(1)平松審議官より概要以下のとおり発言。
- NY会合の議長サマリーで、半年後に進捗状況をレビューすることを約束したが、これが今回このようなかたちで実現したことを喜ばしく思う。RAIの至上目的は途上国への農業投資の促進である。大規模な農地取得に伴う問題に適切に対処し、投資をより強力に促進していくにあたっての条件を整えることは喫緊の課題。
- 本件には、グローバルな共同対応が必要。幅広い関係者が参加する国際的枠組みがなければ意味のある対応はできず、平等な競争条件も確保されない。共催4機関が現地調査・分析に基づきRAI原則案や知識交換プラットフォームを共同で作り上げたことを評価。第一ステップとして原則を共有し、これを実地に移すために関係者が各々の立場から取り組むべき。本日の会合により更に広範な関係者が我々の共同取組に加わることを期待。
(2)このほか、フェルナンデス次官補より、透明性を確保しつつ農業投資を促進することの重要性を強調しつつ、本会合では特に途上国政府、市民社会、民間セクターとの詳細な意見交換を期待するとの発言があった。更に、タンクーAU貿易・産業委員、ブリマー米国務次官補(国際機関担当)、ディウフFAO事務局長より、RAIへの支持と本会合への期待が述べられた。
4.国際機関からの報告(第1セッション「NY会合以降の進展」)
(1)平松審議官の司会の下、共催の4国際機関より、NY会合以降の進展として、RAI原則案の策定と4機関による合意(参考1)、知識交換プラットフォームの構築(参考2![]() )、様々な関係者との協議の実施、20カ国における現地調査への着手等につき報告の上、今後の課題として以下の3点を指摘。
)、様々な関係者との協議の実施、20カ国における現地調査への着手等につき報告の上、今後の課題として以下の3点を指摘。
1)RAI原則につき、更に幅広い関係者と協議を行った上、これを確定
2)同原則の具体化に向けた取組への着手
3)投資受入判断等に関する途上国の能力開発
(2)その後の意見交換では、エル=ケシェン・アフリカ開発銀行副総裁、カズン米ローマ常駐代表、OECD代表等より、RAIへの賛同と協力の意思が表明された。
5.投資受入国の視点(第2セッション「国際農業投資に関する教訓」)
(1)ルビノス・タンザニア農業・食料安全保障大臣より、農業投資受入れを促進するためのタンザニア政府の取組について紹介の上、RAI原則を早急にまとめ、これを実地に移すことの重要性が強調された。
(1)ペルー投資公社代表より、RAI原則に対する支持を表明の上、ペルーの法的・制度的枠組み等について説明があった。
(3)ムヒス・バングラデシュ財務大臣、チェノウェス・リベリア農業大臣等より、土地問題の複雑さとそのガバナンスの重要性、途上国の能力開発の必要性等につき指摘。
6.投資国、市民社会、民間セクターの視点(第3セッション「農業投資を巡る対話の拡大」)
(1)カタール国家食料安保プログラム代表より、RAIの実現に向け最も重要なのは包括的で科学に基づく知識であるとしつつ、投資受入国側の交渉能力の強化の必要性を指摘。
(2)国際土地連合等の市民社会団体の代表より、RAI原則案が自発的なもので、法的拘束力がないことへの懸念を表明し、更に広範な対話と知識の共有の必要性を指摘しつつ、「農地争奪」に関する調査や協議の場の設置等の市民社会による活動の紹介があった。
(3)マーズ社やプロビデント・グループ等の民間企業代表より、途上国への農業投資は長年停滞していたが、現在多くの企業が関心を高めており、これを促進する良い機会であるとしつつ、RAIにつき投資受入国で具体的な取組を進めていくことの重要性を指摘。
(4)その後の意見交換では、韓国農業省局長、カナダ農業省次官補、アジア開発銀行代表より、RAIへの支持と今後の取組についての考えが表明された。
7.最後に3名の共同議長より、議論の概要につき取りまとめの発言があり、これを元に議長サマリーを発出することが承認された(事後、別紙2(英語)(PDF)![]() を発出)。平松審議官からは、今後APEC等の国際フォーラムを活用してRAIへの支持を拡大していく考えが示された。
を発出)。平松審議官からは、今後APEC等の国際フォーラムを活用してRAIへの支持を拡大していく考えが示された。
(1)土地及び資源に関する権利の尊重
既存の土地及び附随する天然資源に関する権利は認識・尊重されるべき。
(2)食料安全保障の確保
投資は食料安全保障を脅かすのではなく、強化するものであるべき。
(3)透明性、グッド・ガバナンス及び投資を促進する環境の確保
農業投資の実施過程は、適切なビジネス・法律・規制の枠組みの中で、透明で、監視され、説明責任が確保されたものであるべき。
(4)協議と参加
投資によって物理的に影響を被る人々とは協議を行い、合意事項は記録し実行されるべき。
(5)責任ある農業企業投資
投資事業は法律を尊重し、業界のベスト・プラクティスを反映し、経済的に実行可能で、永続的な共通の価値をもたらすものであるべき。
(6)社会的持続可能性
投資は望ましい社会的・分配的な影響を生むべきであり、脆弱性を増すものであってはならない。
(7)環境持続可能性
環境面の影響は計量化され、リスクや負の影響の最小化・緩和を図り、持続可能な資源利用を促進する方策が採られるべき。
【参考2】知識交換プラットフォーム
インターネット上(http://www.responsibleagroinvestment.org/![]() )に以下のようなオープン・アーキテクチャーを構築。
)に以下のようなオープン・アーキテクチャーを構築。
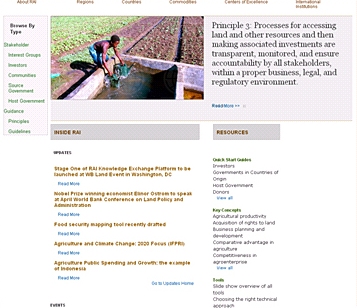
![]() Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
