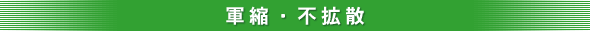
クラスター弾に関する条約第1回締約国会議
ビエンチャン行動計画
(仮訳)
I. 序文
- この行動計画は、国連、赤十字国際委員会、クラスター弾連合、その他のパートナーとの協議を経て、2010年11月9~12日、ラオス人民民主共和国のビエンチャンに於いて、クラスター弾に関する条約の締約国により 採択された。
- この行動計画の目的は第1回締約国会議の後の本条約の規定の効果的で時宜を得た実施を確保することである。本行動計画は、明確な期間内に完了されるべき、具体的で測定できる処置、行動及び目標を設定し、役割や責任を確定する。本行動計画の「行動」は法的要請ではなく、条約の具体的実施において締約国その他の関係者を支援するものであり、その意味について、条約の義務を全うしようとする締約国を支援するものである。締約国は、本行動計画の採択により、条約の迅速な実施へのコミットメントについての強いメッセージを発する。
- 本行動計画は、締約国や他の関係者の優先事項リストであり、実施プロセスを監視する手段である。いくつかの「行動」は、包括的で、集中的な資源が必要な業務の時宜を得た実施を確保するための標石となっており、他は、条約の下でのコミットメントへの対応を構成する上で、締約国を支援するものとなっている。
- 本行動計画は、条約が現場に直接の影響を与え、当面の実施上の問題に取組み、将来の開発に対処し、実施上の問題の変化を反映することの確保を目的としている。
本計画は、第2回締約国会議までの年に行われるべき行動や、第1回履行検討会議までに採られるべき行動を含む。具体的な措置は、例えば締約国が義務の遂行を成し遂げたり、他の国の条約への参加により新たな状況に直面する等、必要ある場合、将来の締約国会議で改訂・修正される。
- クラスター弾に関する条約の締約国は、クラスター弾により引き起こされた被害や犠牲を、恒常的に終わらせるという究極の目的を遂行するために、以下の措置について合意する。
II. パートナーシップ
- 全ての締約国は:
- 行動#1:影響を受けた国と受けていない国、クラスター弾連合、国連システム、赤十字国際委員会、各国の赤十字社及び赤新月社、国際赤十字・赤新月社連盟、ジュネーブ国際人道除去センター、国際・地域組織、クラスター弾の犠牲者・生存者、犠牲者・生存者の組織、他の市民社会組織との間の、条約を支える協力関係を認識し、更なる発展を継続する。
III. 普遍化
- 全ての締約国は、
- 行動#2:可能な限り早期に適当なフォーラムにおける条約支持促進の機会をとらえる。
- 行動#3:第2回締約国会議の前に締約国になるよう、非締約国を奨励・支援する。
- 行動#4:条約や条約の規範の普遍化を促進するため、他の締約国、国際組織や市民社会を含む他の適当なパートナーと協力する。
- 行動#5:条約の非締約国が直面する障壁や問題を認識し、これらの国による条約締結を助長する解決策の発見を支援する。これは、資源不足により条約規定の実施が困難な国への援助提供の検討を含む。
- 行動#6:クラスター弾のあらゆる使用、開発、製造、貯蔵、移譲をあらゆる可能な方法で思い止まらせる。
- 行動#7:クラスター弾により引き起こされる人道的な懸念を共有する条約非締約国の努力を、適当な場合、支援する。特に、条約の締約国になることを奨励するため、それらの国々が条約の公式・非公式会合への参加について支援する。
IV. 貯蔵の廃棄
- クラスター弾を貯蔵している締約国は、
- 行動#8:自国にとっての発効後1年以内に、貯蔵するクラスター弾の、期限や予算を含む廃棄計画を作成し、可能な限り早期に実際の廃棄を開始するよう努力する。
- 行動#9:貯蔵するクラスター弾を廃棄する義務を果たすために援助が必要な状況にある場合、廃棄計画に支障を来す問題を、締約国や適当組織に対し、遅滞なく公開することを確保する。
V. クラスター弾残存物の除去・廃棄と危険低減活動
- 自国の管理・管轄内のクラスター弾汚染地域につき報告を行った締約国は、
- 行動#10:国内・国際資源が配分されるに従い、第1回締約国会合において提示された計画・提案に則って、クラスター弾を 除去し危険低減活動を行う能力を2011年に高める。
- 行動#11:自国の管理・管轄内の地域がクラスター弾残存物により汚染されていることが判明し次第、クラスター弾汚染地域への市民の不慮の立ち入りを効果的に防止することにより、市民の更なる死傷を防ぐあらゆる実行可能な措置を採る。
- 行動#12:自国にとっての発効後の1年以内に、管理管轄内のクラスター弾汚染地域全ての、可能な限り正確な位置や規模を画定するよう努力し、割り出された影響のレベルに応じた除去及び危険低減教育の優先順位を決定し、かかる情報を第7条による報告と共に締約国会議へも報告する。
- 行動#13:自国にとって発効後の1年以内に、国家の除去計画を作成し、実施を開始するために汚染と優先順位の情報を体系的に使用するよう努力する。この除去計画は透明性のある、首尾一貫した除去の優先基準を含み,且つ危険低減教育を促進するものであり、適当な場合には、既存の体系、経験、関連する計画や手法に基づき作成される。この国家除去計画は、より広範な開発計画や適当な場合には地雷行動計画と関連づけられ、各国のオーナーシップやコミットメントが奨励される。
- 行動#14:影響を受けたコミュニティが、国家除去計画の作成、除去活動や土地貸借の計画化・優先順位決定について、通知され参加することを確保する。これは、意味のある、性別に配慮した方法でコミュニティが参加できるよう、コミュニティ連絡要員を使用して、あるいは類似の方法により行われる。
- 行動#15:第4条の完全で功利的な実施のため、非技術調査、技術調査や除去に関する、全ての利用可能で適当な手法を適用する。これは各国の基準、政策、手続きに盛り込まれ、他の締約国との間でベスト・プラクティスや得られた教訓が共有されなければならない。
- 行動#16:解放されたクラスター弾汚染地域の規模や位置についての正確で包括的な情報を毎年提供する。この情報は解放の方法毎に分類されなければならない。
- 行動#17:リスクを伴う行為を防止し、他の選択肢を提供するリスク低減教育プログラムを作成し、最も高いリスクに直面する人々に、提供する。リスク低減教育プログラムは、影響を受けたコミュニティのニーズに適合するよう作成され、性別に配慮し、年齢に適性で、各国や国際の標準に調和し、除去、調査、犠牲者支援活動に統合されなければならない。リスク低減教育活動は、適当な場合、学校及びコミュニティのプログラムや広報キャンペーンにも統合されなければならない。大規模な啓発活動は主に紛争直後の状況において行われなければならない。
- 全ての締約国は、
- 行動#18:クラスター弾残存物により影響を受けた締約国が可能な限り迅速に第4条1の義務を果たし、条約第4条5から8で決められた手続きにより延長を申請せざるを得ない締約国が可能な限り少なくなるよう努力する。
- 行動#19:第7条で決められた透明性についての措置、締約国会議、会期間活動や地域会合を、影響を受けた締約国が問題、計画、進展状況、支援の優先順位を提示する場として十分活用することにより、除去目標の達成、支援ニーズの確定を注視し積極的に促進する。
VI. 犠牲者支援
- 自国の管轄・管理下にある地域にクラスター弾による被害者が存在する締約国は、
- 行動#20:第1回締約国会議の場や会議後に提示された計画や提案に基づきクラスター弾による被害者を支援する能力を、自国や国際資源が利用可能になるに従って、2011年中に伸ばす。
- 行動#21:自国における条約発効後の6か月以内に、 第5条2に従い、犠牲者支援の政策や計画の進展、実施及び監視を調整する政府内の中央連絡先を指定し、中央連絡先がその業務を実施するための権限、専門知識、適当な資源を持つことを確保する。
- 行動#22:自国にとって発効後の1年以内に、必要なデータを収集し、性別、年齢別に分類し、クラスター弾による犠牲者のニーズや優先順位を評価する。収集されたデータは全ての適当な関係者が利用可能な状態にされ、各国の障害調査や他の適当なデータ収集システムのプログラム作成に使用され、これらに寄与する。
- 行動#23:本条約の犠牲者支援条項の実施を、他の条約や国連障害者の権利条約の下で作成された調整システム等、既存の調整メカニズムに統合する。そのようなシステムが存在しない場合、自国における条約発効後の1年以内に、クラスター弾による被害者や被害者を代表する団体、適当な保健、リハビリ、社会サービス、教育、雇用、性別、障害者権利専門家を積極的に包含する調整メカニズムを設立する。
- 行動#24:既存の被害者支援や障害者(支援)計画が条約の被害者支援の義務を遂行できるよう確保し、またそれらの計画を修正する。そのような計画をまだ作成していない締約国は、計画を作成し、包括的行動計画や予算がクラスター弾及びその他の爆発性の戦争残存物による被害者のニーズや人権に取り組むよう確保しなければならない。
- 行動#25:医療、リハビリテーション、心理的支援、経済的・社会的包容の分野におけるサービスの利用可能性、到達可能性及び質の高さを再調査し、クラスター弾による犠牲者によるこれらのサービスへのアクセスを妨げる障壁を画定する。画定された障害を取り除き、質の高いサービスの実施を保障するため、遠隔地や地方におけるサービスの利用可能性や到達可能性を増進すべく即刻行動する。
- 行動#26:自国にとっての条約発効後の1年以内に、クラスター弾による被害者のニーズを満たし人権を保護するとの観点から、国内法や政策を再吟味し、それらがクラスター弾による被害者に対して若しくはクラスター弾による被害者の間に又はクラスター弾による被害者と他の理由により傷害若しくは障害を被った者との間に差別を設けないことを確保する。必要に応じ新たに作成され、修正された関連する国内法や政策を、遅くとも第1回検討会議までに実施する。
- 行動#27:クラスター弾による被害者を含む障害を持つ人々の尊厳や人権の尊重を育成するため、クラスター弾による被害者、政府当局、サービス提供者、国民一般によるクラスター弾被害者の人権と利用可能なサービスに対する意識を向上する。
- 行動#28:医療、リハビリテーション、心理的支援並びに社会的・経済的包容の分野における既存の国際標準、ガイドライン、勧告を実施する。実施は,就中、障害を持つ人々への公共、民間セクターにおける教育、訓練、雇用促進プログラムを通じて、また,特に障害を持つ女性の弱さを認識しつつ、マイクロ・クレジットの可能性やベストプラクティスを通じて行われる。
- 行動#29:クラスター弾による被害者の目前の,及び長期的ニーズを考慮し、既存の金融資源や革新的な金融資源を通じて、適当な国内・国際資源を動員する。
- 第5条実施を支援し、全ての締約国は、
- 行動#30:クラスター弾による被害者や彼らを代表する団体を、性別及び年齢に配慮し、持続可能で意味のある、差別のない方法で、条約の業務に包含するよう、締約国を奨励し、その能力を向上する。
- 行動#31:クラスター弾の生存者や障害者団体の代表者を含む関係専門家を、全ての条約関連活動への代表団の一員とすることにより、含める。
- 行動#32:女性、男性、生存者の団体、犠牲者支援サービスを提供するその他の国内団体・組織の能力を促進・推進する。これは、各国のオーナーシップや持続可能性を強化するとの観点から、金融・技術資源、効果的リーダーシップや運営の訓練、交流プログラムを含む方途により行われる。
VII. 国際協力及び支援
- 貯蔵するクラスター弾を廃棄する義務、影響を受けた地域からクラスター弾を除去する義務、犠牲者を支援する義務を負う締約国は、
- 行動#33:自国にとって条約発効後の1年以内に、貯蔵弾廃棄、除去、犠牲者支援に関する全ての義務を果たす包括的国家計画を作成し、最新のものに改訂し、これらの義務を果たすための資源を確定し、国際協力・支援のニーズを確定する。
- 行動#34:これらのギャップに取り組むために、支援することが可能な関係する市民社会グループ、法人、国際組織及び他の締約国を見出し,共に取り組む。
- 行動#35:条約の実施についての他国の経験を得られるよう、可能な限り速やかに他の影響を受けた締約国を見出し、締約国会議や他の二国間や地域会合の機会を利用して情報や技術的専門知識を交換する。
- 行動#36:義務の遂行において得られた知識や専門知識を利用するため、他の影響を受けた締約国との間で、技術協力、グッド・プラクティスについての情報交換や他の形の相互支援を促進する。
- 実施可能な締約国は以下を行う。
- 行動#37:第1回締約国会議の場で、及び会議後に締約国により行われた除去、犠牲者支援、貯蔵弾廃棄を促進するための支援要請に応え、2011年以降、これらの活動の速度と効果が増進することを確保する。
- 行動#38:犠牲者支援、除去、危険低減教育、貯蔵弾廃棄義務の実施について支援を要請した締約国を迅速に支援し、これらの分野における当該国の優先順位に対応し、資源のコミットメントの継続、予見可能性、持続可能性を確保するよう努力する。
- 行動#39:市民社会活動家、国連、国際組織により行われているクラスター弾関連のプログラムを支援する。
- 行動#40:最貧国の具体的ニーズや状況に特に注意しつつ、当該国による運営やオーナーシップの下で、プログラムの長期計画作成を支援するための資金を提供することにより、クラスター弾プログラムを支援する。これにより、クラスター弾による結果に取り組む行動が、より広範な人道的、開発支援、軍縮・安全保障プログラムの中で、高い優先順位を占めるよう確保する。
- 行動#41:適当な場合、非国家主体が行う分野におけるクラスター弾汚染や犠牲者支援の取り組みを、人道団体へのアクセスを支援することを含め、支援する。
- 行動#42:影響を受けた締約国に対し、貯蔵弾廃棄、除去及び犠牲者支援を支援するために利用可能な資源、能力及びプログラムについて通知する。
- 全ての締約国は、
- 行動#43:ニーズを確定し、資源を動員し、更に他の締約国により得られた教訓やグッド・プラクティスを提示することを可能にするため、条約や条約下の非公式・公式実施メカニズムが、支援や国際協力の問題を議論する具体的で効果的な枠組みを包含・提供するよう確保する。
- 行動#44:国連、各国のNGO、国際NGO,その他の主体によるクラスター弾関連活動が、適当な場合、国家計画の枠組みに組み込まれ、各国の優先順位や国際的な責務と調和するよう努力する。
- 行動#45:条約の完全実施を確保するとの観点から、情報交換や技術的専門知識の交換などの支援・協力が可能な分野を確定するため、全ての締約国による協力を促進する。
- 行動#46:条約の完全実施を確保するため、経験、グッド・プラクティス、資源、技術、専門知識を共有するための、南南協力、三角協力を含む二国間・地域協力を開始・促進する。
- 行動#47:クラスター弾に関する条約の会合において、クラスター弾貯蔵弾の廃棄、クラスター弾残存物の除去、犠牲者への支援の提供における経験、特に他の締約国からの具体的支援要請への対応における経験を通じたグッド・プラクティスを共有する。
- 行動#48:国際協力・支援を伴う条約の様々な条項の具体的実施について、協力的で非公式な方法により、見解を交換し,経験を共有する。
- 行動#49:条約実施の活動を支援する新たな技術、有形・金融資源を確定、動員するため、影響を受けた締約国と影響を受けていない締約国との間、影響を受けた締約国同士の協力関係を強化する。
- 行動#50:クラスター弾による結果に取り組む支援が、適切な調査、ニーズ分析、費用対効果アプローチに基づくことを確保する。
VIII. 実施支援の行動
実施支援
- 全ての締約国は、
- 行動#51:適当な国際・地域組織や市民社会を、本条約の下の義務を遂行する努力の展開、実施、監視、報告に積極的に関与・参加させる。
- 行動#52:市民社会及び国際組織の広範な主体から組織的インプットを促進する方法で,条約の公式・非公式会合を運営し、例えば民間セクターとの新たな協力関係の出現を許容する。
- 行動#53:第2回締約国会議において検討される 定期作業計画及び会合スケジュール、締約国間のテーマ別リーダーシップ・システム及び調整メカニズムを作成する、議長の努力を支援する。
- 行動#54:第2回締約国会議において検討するため、実施支援ユニット(ISU)を含む実施を支援する最適の方法を作成し、また条約の公式・非公式会合を準備する議長の努力を支援し、議長と将来の調整メカニズムを支援し、締約国への助言サービスを提供し、支援プログラムを運営する。
- 行動#55:本条約と他の軍縮・国際人道法・人権法の条約との間の相乗効果を活用し促進する。
- 行動#56:他の枠組みで既に実施されている犠牲者支援、リスク低減教育、除去、その他の関連活動を十分活用し、計画、予算、協力、サービス提供、監視及び報告の分野での活動の効率性や効果を最大化するような方法で、より近い協力を補完し重複する義務を遂行する方法を模索する。
- 実施可能な締約国は、
- 行動#57:条約の会合への広い参加、特にクラスター弾により影響を受けた途上国による参加を補助し支援する。
透明性及び情報交換
- 全ての締約国は、
- 行動#58:第7条の透明性のための第1回報告を提出する義務を遅滞なく遂行し、適当な場合、その報告に第3条8に基づく情報を含める。
- 行動#59:第7条、適当な場合、第3条8に基づく透明性のための報告を毎年更新する。特に締約国が貯蔵するクラスター弾を廃棄し、クラスター弾残存物を除去し、犠牲者を支援し、又は第9条の法的、その他の措置を採らなければならない場合、実施を支援・協力するためのツールとしての報告の機能を最大化する。
- 行動#60:可能な範囲で、報告プロセスの柔軟性を十分活用し、特に要請されていないが、実施プロセスと資源動員を支援するかも知れない情報を提供する。
- 行動#61:条約の様々な条項の具体的な実施についての見解や経験を、協力的で非公式な方法で、交換・共有する。
- 行動#62:報告様式の作成や、適当な場合、他の軍縮・人道関連条約において存在する報告との相乗効果の推進に貢献する。
国内実施措置
- 国内実施措置を採っていない締約国は、
- 行動#63:緊急の問題として、条約の全ての義務を実施するため、第9条に従って、包括的な法的、行政的、適当な場合、その他の実施措置を作成適用する。
- 全ての締約国は、
- 行動#64:条約の公式・非公式会合や、第7条に従って作成される報告により、実施措置の内容や適用についての情報を共有する。実施措置を作成するために支援が必要な場合、締約国は他の締約国、赤十字国際委員会、その他の適当な団体に自国のニーズを通知する。
- 行動#65:条約の禁止・要請事項について、全ての関係機関に明確な命令を出す。
遵守
- 全ての締約国は、
- 行動#66:二国間会議、事務総長の斡旋、条約第8条1に従ったその他の方法で、非遵守の訴えにしっかりと対応する。
