 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アフリカにおける持続可能な開発のための環境とエネルギーに関する日本の国際協力
平成19年3月
1. 環境と開発の両立とエネルギー・アクセス確保は、アフリカにおける持続可能な開発のために、直接的かつ最も重要な課題です。
アフリカにおける環境と開発の両立及びエネルギー・アクセスの改善は、アフリカの人々にとって緊喫の問題であり、ドナー諸国のみならず、アフリカ諸国自身が幅広い対策を早急に行う必要があります。また、アフリカ諸国が環境及びエネルギー・アクセスに対応する能力を向上させることは、持続可能な開発、ミレニアム開発目標の達成にも貢献するものです。
2.わが国は、アフリカにおける環境とエネルギー分野に対し積極的に支援してきました。
わが国は、従来から、アフリカにおける環境・エネルギー分野を重視し、積極的支援を実施してきています。また、わが国は、これら取組においてもTICADプロセスで一貫して強調してきている「オーナーシップの構築」、「地域的協力の推進」、「パートナーシップの深化」という3つの視点が重要と考えます。
3.わが国は、アフリカの環境とエネルギー分野支援のために、今後も主導的役割を果たしていきます。
わが国は、環境と開発の両立をODA実施の原則に盛り込みつつ、引き続き持続可能な環境とエネルギー分野への支援を継続していきます。また、2008年のTICAD IVびG8サミットの開催を視野に入れ、アフリカ開発のために引き続き支援していきます。
I. 環境とエネルギー分野における日本のODA実績
わが国の、アフリカの「環境」と「エネルギー」分野における2001年から2005年の援助実績は、ドナー諸国の中でそれぞれ「第2位」、「第1位」となっています(OECD-DAC統計)。
1. 環境
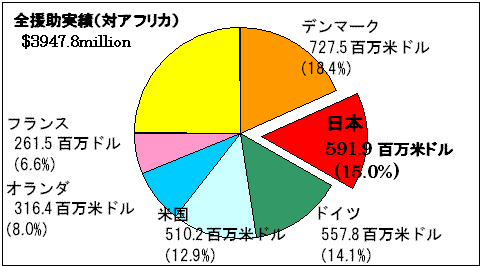
【ODA (set Environment as policy objective)of DAC countries(2001~2005年累積) [出典:OECD/DAC]】
2. エネルギー
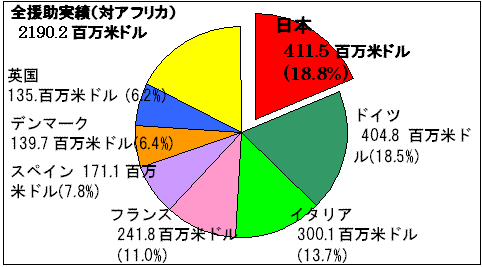
【ODA (set Environment as policy objective)of DAC countries(2001~2005年累積)[出典:OECD/DAC]】
II. 日本の具体的取組紹介
わが国は、環境とエネルギー関連のアフリカ開発を進めるにあたって、これまでTICADプロセスで一貫して強調してきている 1)各国政府の取り組みに代表されるオーナーシップの構築、 2)地域的協力の促進、 3)地方政府や民間、国際機関等のノウハウも最大限に利用したパートナーシップの深化、という三つの切り口が重要と考え、以下のような具体的取組を実施してきています。
1.オーナーシップ促進のための支援
- セグー地方南部住民主体の村落総合開発・砂漠化防止調査(マリ:開発調査)(2004年7月~2008年1月、5.5億円)
マリでは、500村を対象として、住民が主体となった生活の改善、自然資源の適正な管理を通じ、砂漠化防止のための村落開発計画を策定しています。また、各村落での事業成果を対象地域全域に面的に展開するために、当該地域を管轄する60名の村落指導員を活用し、村落指導員及び住民リーダーの育成を図っています。更に本案件においては、小規模金融事業の実施を通じて、住民のオーナーシップが発揮される各種事業が展開されています。 - 半乾燥地社会林業強化計画プロジェクト(ケニア:技術協力)(2004年3月~2009年3月、3.9億円)
我が国は、ケニアの半乾燥地であるキツイ県3郡を対象として、1985年以来17年間にわたって技術協力及び無償資金協力を実施し、育苗・造林技術の確率及び社会林業の促進を行ってきました。かかる経緯をふまえ、現在はケニア政府主導で同地域の個人農家や農民グループにより実施されるようになった社会林業活動を更に一層強化するために、我が国は、FAOとの連携もはかりつつ、様々な技術協力を行っています。 - 沿岸地方給水計画(ギニア:無償資金協力)(1999~2001年度、12.84億円)
我が国は、ギニアの農村の飲料水確保のため給水施設の建設に取り組んでおり、足踏みポンプ付井戸の建設等のほかに、太陽光発電を利用した小規模給水施設を建設しました。同施設により、女性や子供の水汲み労働が軽減され、安全な水が確保されることとなり、現在では、ギニア政府による適切なフォローアップシステムの導入により、同地域の貧困削減に大いに資するものとして高く評価されています。 - ザファラーナ風力発電計画(エジプト:有償資金協力)(2003年度、134.97億円)
エジプトは化石燃料への依存度を下げるために新・再生可能エネルギーの活用促進に取り組んでいます。我が国は、紅海沿岸ザファラーナ地区の120メガワットの風力発電所の新設を支援しました。風力発電所の稼働によって、同規模の火力発電所を稼働させた場合に比べ年間約25万トンのCO2排出削減の効果が期待され、日・エジプト両国はCDM案件として申請手続きを進めています。

(住民参加による穀物倉庫建設)

(定植苗・作物生育観察を行う農民)

(太陽光給水施設遠景)

(ザファラーナ風力発電所)
2.地域協力推進のための支援
- 地下水開発・水供給訓練計画フェーズ2(エチオピア:技術協力)(2005年1月~2008年1月、3.6億円)
我が国は、首都アディスアベバに水資源省訓練センターを設立し、1998年以来7年間にわたって水資源開発に関する人材育成の訓練コースの実施を支援しており、訓練生は延べ1,300名にわたります。また、2005年1月から開始されたフェーズ2では、従来のプロジェクトで培ったノウハウを活かし、第三国研修の形で他のアフリカ諸国15ヶ国に対しての協力も展開しています。 - AICAD(African Institute for Capacity Development)による技術協力プログラム(2000年8月~2007年7月)
AICADは、我が国が提唱した「アフリカ人造り構想」に基づき、ケニア、ウガンダ、タンザニア3ヶ国を構成員として、同地域の大学15校の参加を得て、貧困削減と開発に資するアフリカ人材育成を目的として設立された地域機関です。現在、同機関では、研究開発活動の中心的テーマとして、代替的バイオマス利用技術の開発、サトウキビバガス研究、水質モニタリング、環境保全、有機廃棄物処理技術に関する研究テーマが設置されています。 - サブサハラ地域地方部における貧困削減のためのエネルギー支援(ブルキナ・ファソ、ガーナ、ギニア、セネガル:対UNDP人間の安全保障基金)(2004年11月~2007年11月、231万米ドル)
我が国は、人間の安全保障基金を利用して、西アフリカの地方都市部において、生活の大半を水汲みや薪集めなどに費やしている地域住民の労働負担を軽減し、所得創出活動に従事できるようにする多目的ディーゼル発電機システムを導入しました。地方への電力供給が地域経済を振興させ貧困を改善することを国およびコミュニティに周知し、エネルギー供給能力の向上を図ります。更にコミュニティの能力強化を通じて、継続的なコミュニティ主導の電力供給の運用を目指しています。

(訓練センターを訪問する小泉前総理)

(AICAD本部)

3. パートナーシップ深化のための支援
- 地方電化マスタープラン開発調査(ザンビア:開発調査)(2006年5月~2007年12月、1.9億円)
ザンビアは、地方電化を貧困削減のための地域経済活性化策と位置づけ、地方電化基金を設立するなど、これまでも地方電化の推進を図っています。我が国は、同国政府自らが地方電化を体系的に進めるために必要な包括的マスタープランを策定できるよう、技術移転を行っています。今後は、ザンビア中央政府が、地方政府、民間投資家、開発融資機関との連携を深めながら、地方電化を強化していくことを目指します。 - アワサ市バイオガス開発環境衛生計画(エチオピア:草の根・人間の安全保障無償資金協力)(2004年実施、約848万円)
我が国は、従来より、NGOと連携を図ることにより、草の根・人間の安全保障無償資金協力のスキームを利用して小規模案件の実施支援を行ってきています。特に、環境・エネルギー分野では、2001~2006年の間、アフリカにおいて113件計約7億円の実績があります。中でも、エチオピアのローカルNGOである女性子供開発機構と連携して実施した同案件は、バイオガス開発によりアワサ市の環境衛生を改善した優良案件とされています。 - アジア・アフリカ戦略的パートナーシップ支援(対UNEP)(2007年3月、220万米ドル)
途上国における地球規模の環境問題への対処能力向上のため、我が国は、本年3月、アジア・アフリカ間の協力を通じ、環境法策定・実施等環境関連法制に関する能力を強化し、開発政策における環境の主流化促進を支援することを目的として、UNEPに対する資金協力を実施することを決定しました。
- UNDPパートナーシップ基金に対する追加拠出(対UNEP)(2007年3月、200万米ドル)
我が国は、本年3月、2008年に我が国で開催されるTICA IV及びG8サミットにむけて、特に環境・気候変動とエネルギー分野におけるUNEPの優良案件に対して追加的に拠出することを決定しました。

(小水力発電施設)

(アワサ市場)


