 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
ASEAN地域フォーラム(ARF)の概要
平成19年9月
1.目的・特色
- ASEAN地域フォーラム(ARF)は、1994年より開始されたアジア太平洋地域における政治・安全保障分野を対象とする全域的な対話のフォーラムであり、安全保障問題について議論するアジア太平洋地域における唯一の政府間フォーラム。ASEANを中核としていることが特徴である。現在参加しているのは26か国+EU。
- 政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じ、地域の安全保障環境を向上させることを目的とする。外交当局と国防・軍事当局の双方の代表が出席。
- 毎年夏に開催される閣僚会合(外相会合)を中心とする一連の会議の連続体であり事務局をもつ組織体ではない。
- コンセンサスを原則とし、自由な意見交換を重視する。
- 1)信頼醸成の促進、2)予防外交の進展、3)紛争へのアプローチの充実、という三段階のアプローチを設定して漸進的な進展を目指している。
2.活動の評価
- これまでの会合を通じて、率直な対話を行う機会は増しており、従来は「内政干渉」として忌避される傾向にあった参加国自身を当事者とする問題(朝鮮半島情勢、ミャンマー問題等)を含めて、率直な意見交換を行う慣習が生まれつつある。また、具体的な信頼醸成措置(年次安保概観ペーパーの提出、各種会合の開催等)が実施されており、参加国間の信頼関係の醸成に大きく貢献している。
2001年の第8回閣僚会合ではARFの活動の第二段階である予防外交への取り組みの基礎となる考え方として、「予防外交の概念と原則」他2つのペーパーが採択され、2002年の第9回閣僚会合では、ARFの将来に関する9つの提言が採択された。
さらに、2004年のARFユニット(事務局的な役割を行う)設置、2005年の「ARF基金設立のための付託事項」の採択、2006年の第1回専門家・賢人会合開催など具体的な取組が増えており、現在は第一段階から第二段階の過渡期にある。 - ARFはアジア太平洋地域における安全保障面での対話と協力の場として緩やかではあるが、着実に進展していると評価できる。
- 非伝統的な安全保障分野での協力が促進されており、特に、テロ対策に関する事務レベル会合が定期開催され、外交当局のみならず実務当局者も会合に参加するなど、テロ対策において信頼醸成のための対話を越えた「実務的」な協力が進められている。
3.参加国・機関
ASEAN10か国(ブルネイ、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、シンガポール、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)、日、米、加、豪、ニュージーランド、韓、北朝鮮、中、露、パプアニューギニア、インド、モンゴル、パキスタン、東ティモール、バングラデシュ、スリランカの26か国及びEU。
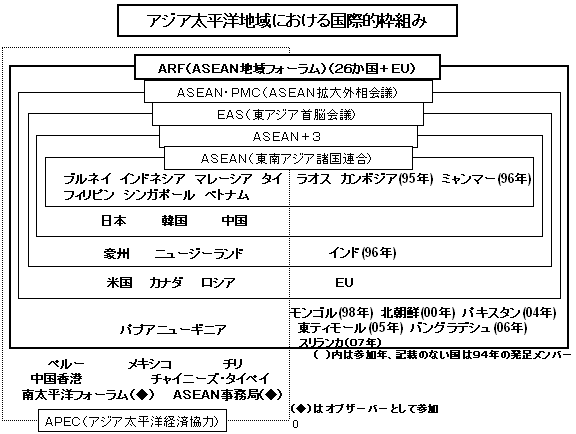
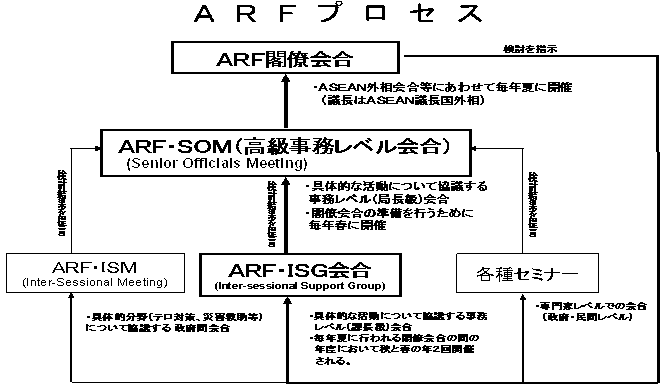
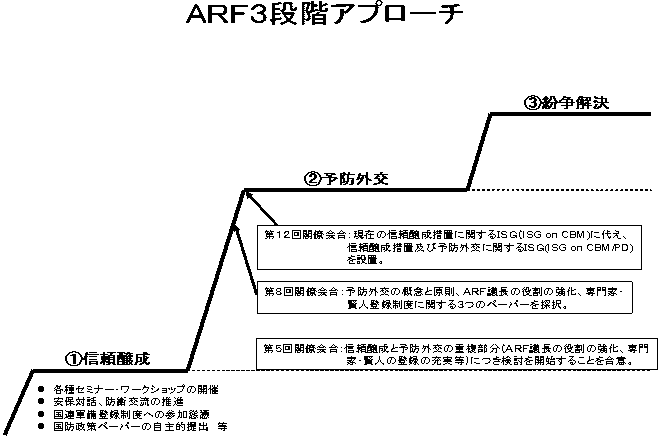
これまでの閣僚会合の成果
- 第1回閣僚会合(1994年7月、於バンコク)
- アジア太平洋地域の17か国及びEUの外相レベルが、地域の安全保障環境に関する意見交換を行うために初めて一同に会したという意味で歴史的な会合となった。
- 第2回閣僚会合(1995年8月、於バンダル・スリ・ブガワン)
- カンボジアが新たに参加。
- 中期的アプローチとして、1)信頼醸成の促進、2)予防外交の進展、3)紛争へのアプローチの充実という3段階に沿って漸進的に進めること、当面は信頼譲成措置を重視することに合意。
- 第3回閣僚会合(1996年7月、於ジャカルタ)
- 閣僚レベルにおける率直な意見交換が定着化。
- インド、ミャンマーが新たに参加。新規参加基準として、1)ARFの目的・活動に対する支持、2)アジア太平洋の安全保障との関わり、3)漸進的な拡大、4)コンセンサスによる決定、に合意。
- 第4回閣僚会合(1997年7月、於スバングジャヤ:マレーシア)
- ARFの第2段階とされている予防外交につき政府レベルでの検討開始を確認。
- 第5回閣僚会合(1998年7月、於マニラ)
- モンゴルの新規参加に合意。
- インド・パキスタンの核実験、ミャンマー・カンボジア情勢等のメンバー国自身にとって機微な問題についても、率直な意見交換を行うとの習慣が定着。
- 第6回閣僚会合(1999年7月、於シンガポール)
- 南シナ海をはじめとする東南アジア情勢、北朝鮮問題(ミサイル発射問題への懸念の表明を含む)、ARFにおける予防外交等につき率直かつ活発な論議。
- 第7回閣僚会合(2000年7月、於バンコク)
- 北朝鮮が新たに参加。
- 北朝鮮の参加を得た中で、朝鮮半島情勢についても率直に意見交換。
- 大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散、ミサイル防衛システムの影響についても議論。
- 第8回閣僚会合(2001年7月、於ハノイ)
- 朝鮮半島情勢、インドネシア・東ティモール情勢等、地域の安全保障情勢につき率直に意見交換。
- CTBTをはじめとする軍備管理・軍縮問題、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散等についても議論。
- 予防外交については、予防外交の概念と原則、ARF議長の役割の強化、専門家・賢人登録制度の3つのペーパーを採択し、ARFにおける取り組みの基本的考え方を提示。
- 第9回閣僚会合(2002年7月、於バンダル・スリ・ブガワン)
- テロ対策に継続して取組むことが確認されるとともに、テロ対策に関するISMの設置が承認。
- ARFの将来に関して、国防・軍事当局関係者の関与の強化や、ASEAN事務局を通じたARF議長の支援の強化を含む9つの提言が全会一致で採択。
- 閣僚会合に先立って、ARF国防・軍事当局者会合を初めて開催。
- 第10回閣僚会合(2003年6月、於プノンペン)
- 「海賊行為及び海上保安への脅威に対する協力に関する声明」及び「国境管理に関するテロ対策協力声明」を採択。
- ARFの将来に関して、議長の役割強化、国防当局者の関与の強化、有識者の活用など、ARFの活動を強化するための方途をめぐる議論が行われた。
- 第11回閣僚会合(2004年7月、於ジャカルタ)
- パキスタンが新たに参加。
- テロ、大量破壊兵器の拡散問題等に対して協力して取組むことの重要性が確認され、「国際テロに対する輸送の安全強化に関するARF声明」及びARFにおいて不拡散に焦点を当てた初の声明として「不拡散に関するARF声明」を採択。
- 中国が提案したハイレベルの軍及び政府関係者による「ARF安全保障政策会議(ASPC)」の第1回会合を2004年末までに中国で開催すること及び第2回以降は議長国においてSOMとバックツーバックで開催することが決定された。
- 第12回閣僚会合(2005年7月、於ビエンチャン)
- 東ティモールが新たに参加。
- ロンドン、シャルム・エル・シェイクでのテロ攻撃を非難し、犠牲者と家族に対し哀悼の意を表明。
- スマトラ沖地震及びインド洋津波により被害を受けた全ての人々に対し弔意、結束及び支援を表明するとともに、ARFにおいて災害救援に関する会期間会合の再開を決定。
- 朝鮮半島の情勢につき、六者会合の再開を歓迎し、朝鮮半島の非核化に向けて相互信頼と共通のアプローチを推進するための対話により、平和的解決を探求することの重要性を強調。
- ARFの将来に関して、「ARF基金設立のための付託事項」を採択。
- 第13回閣僚会合(2006年7月、於クアラルンプール)
- バングラデシュが新たに参加。
- 朝鮮半島の情勢につき、共同声明(05年9月)の遵守と実施の重要性について強調し、前提条件なく六者会合の再開を求めた。北朝鮮のミサイル発射実験に懸念を表明し、安保理決議1695の全会一致の採択に留意し、北朝鮮にミサイル実験に関するモラトリアムに復帰するように促した。
- イスラエル・レバノン情勢につき、中東における状況の悪化及び鎮静化しない暴力、特に、武力の行使に対して重大な懸念を表明。
- ミャンマーの国民和解プロセスの進捗の速度に懸念を表明。
- 国際テロリズムを予防、停止及び撲滅することに対するコミットメントを再確認。
- 第1回ARF専門家・賢人会合の開催を歓迎。
- 第14回閣僚会合(2007年8月、於マニラ)
- スリランカが新たに参加。
- 朝鮮半島の情勢につき、朝鮮半島の非核化が、アジア太平洋地域の平和と安定を維持のために極めて重要であることを強調し、六者会合に対する支持を改めて表明。
- ミャンマーの国民和解プロセスの進捗の速度に懸念を表明し、近い将来に民主主義への平和的移行につながる目に見える進展が見られることを強く促した。
- アフガニスタンの平和と発展のための継続的な支援を強調し、大韓民国国民に対する誘拐行為を非難し、すべての人質の即時、無条件及び安全な解放を求めた。
- あらゆる形態及び様態のテロリズムを引き続き強く非難することを強調し、テロリズムを特定の宗教や民族と関連づけるべきではないことに合意。
- ARF議長の役割を支援するために「議長フレンズ制度の付託事項」を採択。
