第一次外相時代
貿易の多角化を目指して
〔展示史料〕
11.高裁案「本邦ト「バルカン」黒海沿岸近東及埃及方面トノ貿易促進ノタメ外務省関係官会議開催方ニ関スル件」(1925年12月28日)
12.高裁案「対南洋印度貿易促進会議開催ニ関スル件」(1926年2月)
13.日本国トルコ国間通商航海条約(1930年10月11日)(批准書)
〔解説〕
幣原が外務大臣に就任した当時は第一次大戦後の世界的な不況に加えて、関東大震災(1923年)による甚大な被害の影響もあり、我が国の経済は深刻な状況に陥っていました。また、1925年度の外国貿易は約2億6千万円の入超であり、その善後策として新販路を開拓し貿易の伸長を図る必要に迫られました。
そこで幣原は、「打てば響く」関係にあったとされる佐分利貞男をはじめとする歴代の通商局長(斎藤良衛、武富敏彦)らとともに、通商局の拡充や商務書記官制度の新設など組織整備を行うとともに、従来それほど重視されていなかった地域との通商の拡大に努め、貿易の多角化を目指しました。こうした「経済外交」は、幣原外交の一側面でもありました。
【近東貿易会議の開催】
貿易販路拡大の対象地域として幣原は、早い段階から東部アフリカやエジプト(埃及)、トルコ、小アジアなどの近東地域に注目していました。幣原の意向を受けて1925年(大正14年)11月に着任した駐トルコ大使の小幡酉吉は、日本商品紹介の見本市を開催するなど、現地で活発な経済活動を行いました。こうした動きを背景に、外務省内では同地域における貿易促進を目的とした関係者会議の開催が検討され、同年12月末に高裁案が幣原の決裁を得ることとなりました【展示史料11】。
会議は、1926年(大正15年)4月26日から5月5日までトルコの首都コンスタンチノープルで開催され、小幡のほか、ルーマニアやギリシャの駐在公使など近隣の公館長が出席しました。会議では貿易振興策について活発な意見交換が行われ、直通航路の開設、在外公館の充実、商務書記官の派遣、見本市の開催などが議決されました。その後、日本郵船によって近東航路が開設されたことも、この会議の成果といえます。
【第一回貿易会議】
中近東地域における貿易振興に向けた動きと並行して、南洋方面の貿易促進のための会議開催も検討されました。1926年2月に起案された高裁案「対南洋印度貿易促進会議開催ニ関スル件」では、「対南洋印度貿易発展ハ我経済政策上極メテ重要」であり、同地域に対する貿易促進の策を講じて実行することが「寔ニ急務」として、販路の拡張、為替運輸保険の利便増進ならびに内外官民相互連絡方法の改善などにつき具体的協議の実施を求めています【展示史料12】。この高裁案はただちに幣原の決裁を得て、その後関係者による打ち合わせを重ねた後、同年9月13日から10日間、第一回貿易会議が東京で開催されました。会議には、外務省をはじめ大蔵、農林、商工、海軍、南洋などの関係省庁のほかに、民間の商業会議所、一般企業など広範な関係者が参加しました。
会議は、企業及び投資、輸入、輸出、通信運輸、調査情報、金融、法規の7部会に分かれて行われ、外国製品との競合や日本の輸出業者間での過当競争によりかえって粗悪品が横行していることなどが報告されており、政府による何らかの統制ないし保護を要望する発言がみられました。幣原は閉会に際しての挨拶の中で、「無限ノ満足」を表して本会議の成果を高く評価しています。
【通商条約の締結】
このように幣原外交期において積極的な通商の多角化がはかられたことは、幣原が外務大臣在職時に締結又は改訂された通商条約が十数カ国に上り、相手国の地域も様々であったことにあらわれています。幣原の外務大臣在職時の通商条約締結(改訂)相手国は、以下の通りです。
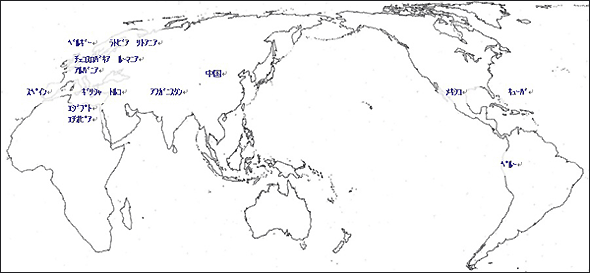
(ベルギー、ペルー、メキシコ、ギリシャ、スペイン、ギリシャ、チェコスロバキア、ラトビア、エジプト、キューバ、中国、リトアニア、アルバニア、トルコ、ルーマニア、エチオピア、アフガニスタン)
