外交史料 Q&A
その他
その他
戦前から外務省で使用していたバッジについて教えてください。
Answer

外務省の標章
1937年(昭和12年)、外務省では「外」の字をくずしたデザインの銀製バッジを作成して全省員に配布し、常に身に付けるよう励行しました。これは、同年7月の盧溝橋事件など時局が次第に戦争へと向かうなか、機密保持の観点から、省内への出入りを厳重にする必要が出てきたためといわれています。
バッジのデザインとなった「外」の字の紋章は、もともとは歴代外務大臣が使用していた硯箱の蓋に描かれていたもので、現在も外務省の標章として、外務省庁舎正門や外務省員の身分証明書などに使用されています。
大正期に外務省に雇用されていたフランス人レイに関する記録はありますか。
Answer
外務省記録「本邦雇傭外国人関係雑件 本省ノ部」に関係記録が所収されています。
1884年(明治17年)フランスに生まれ、パリ大学で法律を学んだレイ(Jean Joseph Ray)は、1916年(大正5年)9月、東京帝国大学に招聘されて訪日し、同大学の仏法科講師となりました。その後、1918年(大正7年)10月から1924年(大正13年)7月まで、外務省事務嘱託としてフランス語による外交文書類の校閲や諮問、調査を行いました。また、国際連盟をはじめヨーロッパにおける諸会議での交渉事務にも従事しました。ちなみに同時期の外務省雇外国人としては、英国人のベイティ(Thomas Baty)も有名です。
1930年(昭和5年)に帰国したレイは、その後、在仏日本大使館の事務を嘱託され、1943年(昭和18年)に亡くなるまで、日本関係の著述や講演を行うなど日仏親善に努めました。
戦前の外交官、石射猪太郎について教えてください。
Answer

石射 猪太郎
1887年(明治20年)、福島県に生まれた石射猪太郎(いしい・いたろう)は、日中両国の経済提携と善隣友好の促進を目的として上海に設置された東亜同文書院を1908年(明治41年)に卒業。その後、南満州鉄道株式会社(満鉄)などを経て、1915年(大正4年)に外務省に入省しました。
石射は、中国を中心に、米国、英国、シャム(現在のタイ)などの国で外交官として活躍したほか、通商局第三課長として移民問題の処理にもあたりました。また、満州事変時には、吉林総領事として不拡大方針を忠実に貫き、関東軍から強く非難されたこともありました。
1937年(昭和12年)4月、東亜局長に就任した石射は、その直後(同年7月)に勃発した日中戦争を拡大させないために主任局長として懸命の努力を続けました。1938年(昭和13年)6月には、新たに外務大臣に就任した宇垣一成に「今後ノ事変対策ニ付テノ考案」と題する長文の意見書を提出し、「国民政府ヲ対手トセス」とした、いわゆる近衛声明の撤回を求めるとともに、日中間の和平を要望しました。この意見書に記されている内容は自分の所見と同じであると考えた宇垣外相は、これを日中戦争への対策を検討するための五相会議(首相、外相、蔵相、陸相、海相)でも提起しましたが、各大臣からの賛同は得られませんでした。
石射は東亜局長の後、オランダ公使、ブラジル大使、ビルマ大使を務めたところで終戦を迎え、1946年(昭和21年)に外務省を退職し、1954年(昭和29年)に亡くなりました。
石射が宇垣外相に提出した意見書「今後ノ事変対策ニ付テノ考案」は、外務省記録「支那事変関係一件」に収められています。
戦前に、中国の呼称を「支那」から「中華民国」に変更した経緯を示す記録はありますか。
Answer
外務省記録「各国国名及地名称呼関係雑件」のなかに、1930年(昭和5年)10月に、浜口雄幸内閣が中国の呼称を常則として「中華民国」とするとの閣議決定を行った際の記録が残されています。
この閣議決定が行われるまで、日本政府は、条約や国書を除いて中国を「支那」と呼称するとの閣議決定(1913年6月)に基づき、中国の呼称として通例「支那」を使用していました。しかし、中国は侮蔑的なニュアンスの強い「支那」という呼称を好まず、「中華民国」を用いるよう求めていました。たとえば、中国国民政府文書局長であった楊煕績は、1930年5月に日本と中国との間で結ばれた関税協定において、日本が条文中に「支那」という字句を使用した事を批判し、「今後日本側カ重ネテ斯ノ如キ無礼ノ字句ヲ使用スルトキハ我方ハ之ヲ返附スルト共ニ厳シク詰責シ以テ国家ヲ辱シメサルコトヲ期スヘシ」と論じていました。
こうした中国官民の感情に配慮して、外務省は1930年10月27日に中国の呼称変更を閣議に請議し、同月30日に閣議決定となりました。
外務省の研修所が開所したのはいつですか。
Answer
外務省研修所は、1946年(昭和21年)1月に勅令第56号第19条にて開設が規定され、同年3月1日に東京都文京区の茗荷谷に開所しました。当初は「外務官吏研修所」と称していましたが、その後「外務省研修所」に改められました。
外務省研修所の設置に特に尽力したとされるのが当時の吉田茂外相です。占領期において外務省の機能と人員は大幅に縮小されましたが、吉田は研修所を設置することで、外交再開に備えて要員を温存するとともに、外務省員の訓練と若い職員の養成を目指したのです。この研修所開所の経緯については、外務省百年史編纂委員会編『外務省の百年』(下巻)に記されています。
茗荷谷の研修所の建物は、戦前から戦時中にかけて外務省文化事業部所管の対支文化事業で中心的役割を担った東方文化学院の東京研究所(終戦後、外務省所管となる)として、1933年(昭和8年)に建造されたもので、以来、1994年(平成6年)3月に神奈川県相模原市に新しい外務省研修所ができるまで、外務省の研修施設として利用されました。
なお、外交史料館では、外務省研修所に保管されていた「外務省茗荷谷研修所旧蔵記録」の閲覧が可能です。この史料群は、同研修所に未整理状態で保管されていたもので、主として対中国、満州経済活動に関する記録や対台湾、朝鮮といった植民地行政に関する記録が含まれています。
江戸時代に朝鮮通信使が持参した徳川将軍宛の国書を所蔵していますか。
Answer
外交史料館では、朝鮮国王純祖(李コウ、在位1800-1834)から第11代将軍徳川家斉に宛てた国書と別幅(将軍への贈答品目録)を所蔵しています。この国書は、1811年(文化8年)、朝鮮通信使より対馬にて奉呈されたもので、家斉の将軍職就任(1787年)を祝う内容です。
朝鮮通信使とは、朝鮮国王から日本の室町および江戸幕府の将軍のもとに派遣された外交使節です。江戸時代には、豊臣秀吉の朝鮮出兵により悪化した両国の関係を修復するために徳川家康が訪日を要請し、1607年(慶長3年)から1811年まで、12回にわたって派遣されました。将軍への慶賀や弔問、そのほか両国間の緊急な懸案事項を解決することが目的でした。
総勢300名から500名にのぼる通信使一行は、釜山を出発後、まず対馬に渡り、壱岐を経て下関に上陸、瀬戸内海沿岸の各所を経由して大坂に再上陸し、その後は陸路で江戸を目指すという旅程で日本を訪れ、日本での滞在費、交通費等はすべて日本側が負担しました。

朝鮮国王純祖(李コウ)より11代将軍徳川家斉あて国書
外務省の創設日はいつですか。
Answer
1869年8月15日(明治2年7月8日)です。この日、日本政府は「職員令(しきいんりょう)」を制定し官制を改革しました。その結果、太政官(だじょうかん)のもとに外務、大蔵など6省が設置されました。外務省の創設とその前後の事情は、外務省編『外務省の百年』に詳しく書かれています。なお、外務省では旧暦の7月8日をもって外務省記念日としています。
外務省敷地内に建てられている陸奥宗光像の建立の由来を教えてください。
Answer
日清戦争や条約改正といった難局に、外相として立ち向かった陸奥宗光の業績を讃え、各界の基金により1907年(明治40年)、外務省内に銅像が建立されました。しかし1943年(昭和18年)、戦時金属回収により供出されました。その後、同外相の没後70周年に当たる1966年(昭和41年)に再建されました。この経緯は外務省編『外務省の百年』下巻に記されています。
日本の「大使館」が最初に設置されたのは、いつ、どこの国ですか。
Answer
1905年(明治38年)12月2日に在イギリス公使館が昇格して大使館となったのが最初です。ちなみに、初代駐英大使に任命されたのは林董(はやし・ただす)です。
1890年代、日本政府内部では、各国に置いている公使館を大使館に昇格すべきだとの意見がしばしば示されました。このような意見は、日本の要望を列国が受け入れるかが不透明であり先送りされましたが、北清事変(1900年)、日露戦争(1904~1905年)を経て、日本の実力が徐々に各国に認められるようになり、日露講和会議の直後には、イギリスとアメリカの両国より、日本と大使交換をおこなう準備があるとの意向が伝えられました。日本政府はこの提案に応じて、まずイギリスとの間で大使交換が実現し、在英公使館が「大使館」に昇格しました。林董が駐英大使となった直後の1906年(明治39年)1月には、アメリカ、ドイツ、フランスでも公使館が大使館に昇格し、青木周蔵(アメリカ)、井上勝之助(ドイツ)、栗野慎一郎(フランス)がそれぞれ大使に任ぜられています。こうした大使館設置にいたる経緯については、外務省記録「欧米大国ト特命全権大使交換一件」に関連史料が残されています。また、外務省編『外務省の百年』にも、大使館設置について詳しく記されています。
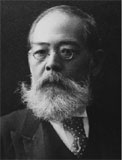
青木周蔵

林董

栗野慎一郎
戦前期にロシア(ソ連)にあった日本大(公)使館、総領事館の所在地を教えてください。
Answer
明治末期以降の所在地は、外務省編『外務省年鑑』で知ることができます。この『外務省年鑑』は外務省の制度・組織・人事を調べる上で大変便利な調書です。明治40年版が一番古く、戦前期は昭和17年版まで作成されています。ただし外交史料館にも全巻は揃っていません。
わが国の初代駐米外交官は誰ですか。
Answer
森有礼(もり ありのり、1847~89)です。明治政府が海外駐在外交官の制度を初めて制定したのは、1870年11月(明治3年閏10月)のことです。この時にイギリス、アメリカ、フランス、プロシア(現在のドイツ)に各1名の外交官が派遣されることとなりました。その1人として米国に派遣されたのが森有礼です。森は少弁務使(代理公使、charge d'affaires)に任命され、ワシントンに2年間在勤しました。その後森は、外務大輔(だゆう、現在の外務次官)や英国公使などの要職を歴任しましたが、文部大臣在任中に暗殺されました。
戦前の日本では、国号の英語標記を “Japan"から“Nippon"に変更しようとする動きがあったそうですが、このことに関する史料はありますか。
Answer
日本の国号標記に関しては、外務省条約局作成(昭和11年5月)の「我国国号問題二関スル資料」(外務省記録「条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件」所収)に、従来の経緯や諸学説、外国での実例などの調査結果が記されています。
1927年(昭和2年)、日本の国号について日本政府は、各国がどのように呼称するかは便宜上の問題であり、一般的に周知されている呼称を用いることが適当であるとして、各国が「ジャパン」という呼称を用いても構わないとの見解を明らかにしました。しかし、その後、1934年(昭和9年)に文部省の臨時国語調査会が国号の呼称を「ニッポン」に統一し、外国に発送する書類にも“Japan"ではなく“Nippon"を用いるべしとの案が政府に提出され、また翌1935年(昭和10年)には、衆議院に対して、「ジャパン」という呼称は「我ガ帝国ノ威信ヲ損スル」ものであり、世界各国に対して日本の国号の呼称を「大日本帝国」とするよう求める建議がなされるなど、国号標記の変更を求める動きが強まりました。こうした動きを受けて外務省は、1935年(昭和10年)7月、外務省所管である条約など外交文書の日本文(漢文もこれに準じる)について、それまで「日本国」「日本帝国」「大日本国」「大日本帝国」と様々な標記がされていた国号の標記を、「大日本帝国」とすると決定しました。しかし、英語標記については結局、統一的な見解が示されることはありませんでした。
戦前期に、日本の皇室とローマ法王との間で交わされた書簡はありますか。
Answer
外交史料館では、明治・大正期にローマ法王から届いた親書を数点所蔵しています。また、戦前期日本とローマ法王との関係を示す外務省記録としては、「各国特派使節来朝雑件」「羅馬法王就任関係雑件」などがあります。
(注)「羅馬」=ローマ

ローマ法王からの大使信任状
1923年(大正12年)
世界的な財閥として知られるロスチャイルド家と日本との関係を示す記録はありますか。
Answer
日露戦争後の外債募集にロンドンとパリのロスチャイルド家が協力した事を示す文書が、外務省記録「帝国内外公債雑件」の中にあります。
パナマ共和国と日本の関係について調べています。パナマに駐在した最初の日本領事、公使、大使の名前と着任年月日を教えて下さい。
Answer
初代領事としては今井忠直が1918年(大正7年)11月17日に領事代理に任ぜられ、翌年6月30日に正式に領事に就任しています。初代公使としては1938年(昭和13年)6月1日に越田佐一郎が、初代大使としては1962年(昭和37年)10月1日に公使館が大使館に昇格した際に、丸山佶(まるやま・ただし)公使が大使に就任しています。
大久保利通の息子が公使を務めたそうですが、何という人ですか。
Answer
大久保利通の次男で、遠縁の家督を継いだ牧野伸顕(まきの のぶあき、1861~1949)です。牧野は1897~99年(明治30~32年)に駐イタリア公使、1899~1906年にオーストリア公使を務めています。その後、文部大臣、農商務大臣を経て、1913~14年(大正2~3年)に外務大臣、1919年のパリ講和会議では日本全権を務めました。さらに1921~25年に宮内大臣、1925~35年(大正14~昭和10年)に内大臣を歴任しました。1936年の二・二六事件では反乱部隊に襲撃され、危うく難を逃れています。なお、娘雪子は政治家吉田茂の夫人です。
吉田茂元総理と辰巳栄一元陸軍中将の親交を裏付ける史料はありますか。
Answer
外交史料館には吉田元総理の遺品や関係資料が吉田茂記念事業財団(現、吉田茂国際基金)を通じて寄贈されています。この中に辰巳宛書簡や写真など親交を示すものがあります。
吉田茂元総理は「素淮」という号を使っていますが、この意味を教えてください。
Answer
「素淮」は「ソワイ」と読みます。吉田のイニシャル「S.Y」をもじったものだと言われています。
戦前期に長年外務省顧問を務めたベイティ博士に関する記録はありますか。
Answer
イギリスの法律学者であったトーマス・ベイティ博士は、1916年(大正5年)に日本外務省の依頼により来日し、外務省顧問に就任して、以後40年近くにわたり外務省の仕事に携わり、1954年(昭和29年)に日本で亡くなりました。外交史料館にはベイティ博士に関する記録が多数残っています。主な記録としては、ベイティの雇傭関係が外務省記録「本邦雇傭外国人関係雑件 本省ノ部」の中に、ベイティの叙勲関係記録が「外国人叙勲雑件 英国人ノ部」の中にあります。
ヘレン・ケラーに関する記録はありますか。
Answer
三重のハンデキャップを克服したことで世界的に著名な米国人女性ヘレン・ケラー(1880~1968)は、世界各地で講演活動を行いましたが、日本にも1937年(昭和12年)4月にやって来ました。この訪日に関する文書が、外務省記録「各国名士ノ本邦訪問関係雑件 米国人ノ部」にあります。また訪日時、彼女に秋田犬が贈られましたが、この犬は翌年事故で死んでしまいました。ヘレン・ケラーが愛犬の死に落胆していることを知った日本側は、死亡した犬の兄弟犬をあらためて贈りました。この関係文書が、外務省記録「邦人各国人間贈答関係雑件」にあります。なお、ヘレン・ケラーは戦後にも来日しており、1948年(昭和23年)9月に名古屋で講演会を開催したことが、外務省記録「連絡調整地方事務局執務報告書綴 東海北陸一」からわかります。
父が戦前に中国の山東省済南にあった済南銀行で働いていたのですが、済南銀行に関する記録は残っていますか。
Answer
済南銀行から外務省に提出された各種書類などが、明治大正期の記録は外務省記録「本邦銀行関係雑件 在支之部 上海銀行、済南銀行」に、昭和戦前期の記録は外務省記録「本邦銀行関係雑件 在満、支ノ部 済南銀行」の中にあります。
アメリカのことを亜米利加、フランスのことを仏蘭西と書くように、外国の地名を表す漢字の宛字が色々とありますが、アフリカのモロッコについての宛字もありますか。
Answer
モロッコについては、「摩洛哥」、「馬羅哥」、「莫羅哥」、「茂禄子」などの宛字があります。
明治時代の元外務大臣秘書官「中田敬義」について調べています。
Answer
中田敬義(なかた・たかのり、1858~1943)は、加賀国(石川県)金沢出身で、1876年(明治9年)に外務省に入省しました。北京、ロンドンなどでの在外勤務を経て、1891年(明治24年)7月から榎本武揚外務大臣の秘書官となり、外相が陸奥宗光に替わった後も引き続き大臣秘書官を務めました(1896年3月まで)。この間中田は、陸奥外相に同行して日清講和会議に出席するなど、日清戦争や三国干渉、条約改正問題など日本外交の難局にあたって両外相を支えました。特に陸奥外相の信任が厚かった中田は、病床にあった陸奥の『蹇蹇録』執筆を大いに助けたとされます。1895年(明治28年)10月からは政務局長を兼務し、1898年(明治31年)10月に依願免本官となるまでその任にありました。
中田に関する史料に関して外交史料館では、中田が旧蔵していた史料類を「中田敬義文書」として一般利用に供しています。同文書にはおもに、中田自身が関わった壬午事変や条約改正、日清戦争関係の書類のほか、調書類や旧蔵図書などが含まれています。同文書の概要については、「霞関会文庫「中田敬義文書」について」(『外交史料館報』第21号、2007年)に説明があります。また外交史料館所蔵「陸奥宗光書翰」には、陸奥が中田に宛てた書簡が16通含まれています。ほかにも外務省記録「諸修史関係雑件 外交資料蒐集関係」には、中田の口述記録「日清戦争ノ前後」(昭和13年)と「故陸奥伯ノ追憶」(昭和14年)が綴られており、外交史料館で閲覧することができます。
2011年(平成23年)は小村寿太郎元外務大臣の没後100年にあたります。
小村に関係する外交史料館の所蔵史料にはどのようなものがありますか。
Answer
小村寿太郎(こむら・じゅたろう、1855~1911)の日本外交史上における業績として、一度目の外相時代の1902年(明治35年)に日英同盟を推進したことや、1905年(明治38年)ポーツマス講和会議の日本側全権としてロシアと交渉し、日露講和条約を締結したことが特に知られています。また、二度目の外相時代の1911年(明治44年)には諸外国との条約改正交渉において税権(関税自主権)を回復し、最終的な条約改正を達成したこともよく知られているところです。外交史料館では、これらの事柄に関連する文書、条約書などの原本を多数所蔵しており、多くの文書が『日本外交文書』に採録されています。
そうした小村の外交的足跡を知る上で参考になるのが、外務省が編纂した小村の伝記である『小村外交史』(昭和28年刊行)です。この伝記は大正期から出版が計画されていたもので、外務省の委嘱を受けた国際法学者の信夫淳平博士が「侯爵小村寿太郎伝」として草稿を書き上げたものの、諸事情から刊行が遅れ、戦後に大幅に改訂されて世に出されました。外交史料館では、公刊された『小村外交史』及び、その改訂前の草稿である「侯爵小村寿太郎伝」をご覧いただけます。『小村外交史』は、外交史料館ホームページ内「日本外交文書デジタルアーカイブ」でもご覧いただけます。
なお、小村には1875年(明治8年)に第一回文部省留学生として米国に渡り、ハーバード大学で法学を学んだという経歴があります。外交史料館では、この時留学生に選抜された小村を含む11名の集合写真を所蔵しています。また、この留学時の旅券の写しが外務省記録「海外旅券勘合簿 本省之部」に収録されています。当時の旅券発給記録には申請者の身体的特徴が記述されており、それによれば19歳の小村は「鼻高き方/口小さき方/面長き方/色白き方」で、身長は「五尺一寸五分(約156センチメートル)」であったことがわかります。
(注)日本外交文書デジタルアーカイブ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/index.html

第一回文部省留学生の集合写真
(前列右端で足を組んでいるのが小村)
現在外交史料館がある場所は、戦前期はどのように利用されていたのですか。
Answer
外交史料館は1971年(昭和46年)、現在の所在地である港区麻布台一丁目に開設されましたが、戦前期、この場所には中華民国大使館がありました。
中華民国公使館(1935年(昭和10年)に公使館から大使館に昇格)はもともと、麹町区永田町二丁目(現在の千代田区永田町二丁目。国会議事堂付近)にありましたが、同地区付近に国会議事堂を建設し、議事堂周辺へ中央官庁を集中させることになったため、ベルギー、イタリア、ソ連大使館と同時期に移転することになりました。
1926年(大正15年)3月より移転交渉が開始され、麻布区飯倉町(現在の港区麻布台)の徳川頼貞(とくがわ・よりさだ)邸(紀州徳川家邸宅)が移転先の候補地となりました。途中、北京政府が蔣介石の北伐により消滅し、交渉は難航しましたが、1928年(昭和3年)10月末、交渉が成立し、11月1日、新敷地貸付契約が結ばれました。これにより、日本政府が徳川家から敷地を買い上げ、国有地として中華民国政府に貸し付け、敷地内の建物は、中華民国政府が買い取って、以後、公使館として利用しました。
戦前の中華民国公使館移転に関する記録は、外務省記録「在本邦外国公館敷地関係一件(建物転貸関係ヲ含ム) 中華民国ノ部」に残されています。
戦前期の外務大臣官邸について教えてください。
Answer
『外務省の百年』(外務省百年史編纂委員会編、原書房、1969年)によると、明治初期、外務卿は各自の自宅で執務を行っていました。しかし、庁舎と距離があるのは不便であり、且つ、外国の公使等との交際上不都合があるとの理由で、1875年(明治8年)、寺島宗則(てらしま・むねのり)外務卿が外務省構内に官舎を建築することを上申し、翌1876年(明治9年)、外務省構内に外務卿官舎(外務大臣官邸)が建築されました。
この外務大臣官邸が外国との交際の場として使用された記録としては、1922年(大正11年)4月にエドワード英国皇太子(後の国王エドワード8世)が来日した際の晩餐会の記録があります。外務省記録「外国貴賓ノ来朝関係雑件 英国之部 英国皇儲来朝ノ件」によると、内田康哉(うちだ・やすや)外務大臣は、同皇太子に寛いでもらおうと、晩餐会で帝劇女優による「娘道成寺」の上演を企画しました。同皇太子は非常に喜んで、女優、鳴物師に至る迄、握手を賜ったとの記録が残っています。
しかし、1923年(大正12年)の関東大震災により、初代大臣官邸は大きな被害を受けました。当時、外務省文書課により編纂・刊行された『外務省報』第47号によると、伊集院彦吉(いじゅういん・ひこきち)外務大臣は、震災直後、大破した大臣官邸の代わりに電信課長官舎を官邸として使用し、外交団の接見には同官舎の客間を充てていたようです。また、次官官舎の修理完了後には、そちらを一時的に大臣官舎とする予定であることも記されています。翌1924年(大正13年)発行の同誌第72号には、幣原喜重郎(しではら・きじゅうろう)外務大臣が同年10月31日に「裏霞ヶ関官邸」で天長節奉祝の晩餐会を開催したとの記事があり、震災の翌年には麹町区裏霞ヶ関(現在の千代田区霞ヶ関三丁目から永田町一丁目付近)に大臣官邸が置かれていたことがわかります。
その後、1932年(昭和7年)に大臣官邸は裏霞ヶ関から麹町区三年町(現在の千代田区永田町一丁目。内閣府付近)に移転します。外務省記録「本省庁舎及官舎関係雑件」には、裏霞ヶ関にあった外務大臣官邸を外務次官官舎とし、麹町区三年町にあった外務次官官舎を外務大臣官邸とする旨、在京の外国公館に通知した記録が残っています。『外務省の百年』によれば、麹町区三年町の建物は旧有栖川宮邸で、高松宮から譲り受けたようです。しかし、この官邸は1945年(昭和20年)5月の空襲により焼失しました。また、関東大震災時に被災した初代大臣官邸も、その後修理・増築され、外務省庁舎として使用されていましたが、この時、同時に焼失しました。
