外交史料 Q&A
昭和戦前期
1940年代(昭和15年~20年頃)
1940年(昭和15年)の「松岡・アンリ協定」について調べています。
Answer
日中戦争中に日仏間に締結された「松岡・アンリ協定」の文面は、外務省記録「支那事変関係一件 仏領印度支那進駐問題」に記されています。(なお、この記録はアジア歴史資料センターホームページでも御覧いただけます。)
日本は、「援蒋ルート」(蒋介石政府に対する英米の援助物資輸送路)の遮断のため、仏印(フランス領インドシナ)に対し中国との国境閉鎖等を要求していました。フランスは、本国政府がすでにドイツに降伏していたこともあって日本側の要求に屈し、1940年8月30日、松岡洋右外相とアンリ(Charles Arséne Henry)駐日大使との間に書簡形式の公文が交換されました。その内容は、フランスが極東の政治経済における日本の優越的利益を認め、日本に軍事上の便宜供与をはかるのに対し、日本はインドシナにおけるフランスの主権と、インドシナの領土保全を尊重するというものでした。この協定に基づき、仏印監視団長西原一策(にしはら・いっさく)少将はマルタン(Maurice-Pierre Auguste Martin)仏印軍最高司令官との間に細目協定を結び、北部仏印への平和的進駐が通達されました。しかしその後、南支那方面軍は国境を武力突破し、ハイフォン方面でも上陸した日本軍による爆弾投下事件が起こるなど、仏印側に為す術がないまま、日本の北部仏印進駐が完了しました。
1940年(昭和15年)に開催が予定されていた「東京万博」についての記録はありますか。
Answer
東京万博の開催決定から諸々の準備、そして延期決定に至るまでの経緯に関する記録が、外務省記録「本邦博覧会関係雑件 日本万国博覧会(一九四〇年)」に残されています。
東京商工会議所内におかれた博覧会倶楽部からの博覧会開催の建議を受けて、1930年(昭和5年)、日本政府は「皇紀二千六百年」(皇紀とは神武天皇が即位したとされる年を元年とする紀年法で、西暦1940年が皇紀2600年にあたる)記念祝典行事の一つ(ほかには「東京オリンピック」など)として、東京で万国博覧会を開くことを決定しました。その後、開催に向けて、くじ付の回数入場券や絵葉書が販売され、また、参加を勧誘するため世界各国に招請状の送付や使節団の派遣が行われるなど、開催に向けた準備が着々と進められていました。しかし、日中戦争が勃発(1937年7月)するなど、内外の情勢が緊迫すると、日本政府は1938年(昭和13年)7月に開催の延期を決定しました。
1940年(昭和15年)に東京でオリンピックを開催する予定があったと聞きましたが、本当ですか。
Answer

1940年「幻の」東京オリンピック公認マーク
本当です。
1931年(昭和6年)10月、東京市議会は皇紀2600年に当たる1940年のオリンピックを東京に招致したいと満場一致で決議しました(皇紀とは、神武天皇が即位したとされる西暦紀元前660年を元年として数えたものです)。翌1932年(昭和7年)6月には、永田秀次郎東京市長名で斎藤実外務大臣に書簡を送って東京開催への協力を要請しています。この書簡には、東京での開催は皇紀2600年の絶好の記念となるのみならず、国民の体育教育にも有益であり、また外国人の日本への理解と関心を一層深めることにつながると記されています。
こうした東京市からの要請等もあり、外務省ではその後、関係方面への協力要請や情報収集に努めました。特にIOC(国際オリンピック委員会)委員も務めていた杉村陽太郎駐イタリア大使は、イタリア首相であったムッソリーニに働きかけて、有力な開催候補地であったローマを辞退させ、逆に東京への支持を取り付けるなど、オリンピック誘致に向けて積極的な活動を展開しました。こうした諸方面の努力が実を結び、1936年(昭和11年)7月31日、ベルリンで開催されたIOC会議において対立候補であったヘルシンキを破り、第12回オリンピックの東京開催が決定しました。
開催決定後、国内では大会組織委員会を設置するなど準備が進められました。しかし、1937年(昭和12年)7月の盧溝橋事件勃発以降、日本に対する国際的な批判の高まりを背景として、東京でのオリンピック開催に反対する動きが各国で強まっていきました。また、国内からも、現在は物心両面で国の総力を挙げて戦局に対処すべきであるとして、オリンピック開催に反対する声が高まっていました。こうした国内外からの反対を受けて、1938年(昭和13年)7月15日、日本政府は東京での開催を取り止めるのが適当であると大会組織委員会に通達し、翌16日に大会組織委員会は「国策ニ順応シ報国ノ誠ヲ致スベキヲ信ズ」との声明文を発表して、東京大会開催返上を決定しました。
この「幻の東京オリンピック」に関する記録は、外務省記録「国際「オリムピック」競技大会一件 本邦大会関係」等に収められています。また、アジア歴史資料センターホームページからも御覧いただけます。
蒙古の徳王が起草した「蒙古建国促進案」を所蔵していますか。
Answer
徳王(1902~66)は、蒙古民族の自治・独立を求めて活動した政治家で、1938年(昭和13年)10月と1941年2月に来日しています。41年に来日した際、徳王は近衛文麿総理に「蒙古建国促進案」を直接手交し、蒙古を自治国として承認してほしいと要望しました。外交史料館では「蒙古建国促進案」のオリジナルは所蔵していませんが、外務省記録「各国名士ノ本邦訪問関係雑件 蒙古人ノ部 徳王」の中にその写し(日本文)があります。
河相達夫初代駐オーストラリア公使の同国での活動を示す記録はありますか。
Answer
関係文書が外務省記録「英国内政関係雑纂 属領関係 豪州連邦関係」ほかにあります。
第二次世界大戦が始まっても日本とソ連は中立関係にありましたが、ドイツ軍の侵攻によりモスクワが危険な状態にあった時も日本の大使館はモスクワにあったのですか。
Answer
ドイツ軍の侵攻により、1941年(昭和16年)10月より43年(昭和18年)8月までソ連政府および各国外交団はモスクワの東南東の方角約1,000キロの所に位置するクィブィシエフに移動していました。日本の大使館もその間はクィブィシエフにありました。
1941年(昭和16年)、松岡洋右外相はドイツの外相にメッセージを送り、独ソ戦を回避するよう伝えたそうですが、このメッセージを所蔵していますか。
Answer
1941年5月28日、松岡外相はドイツ駐在の大島浩大使に対して電報を発し、ドイツ政府がソ連との武力衝突を回避することを希望する旨のメッセージをドイツ外相に伝達するよう命じました。この電報は外務省記録の中には残っていません。ただし、当時首相であった近衛文麿の旧蔵資料(ご遺族が管理している近衛家の旧蔵記録「陽明文庫」)の中に電報の写しが残っています。
1941年(昭和16年)に日本政府が派遣した、「仏印資源調査団」について教えてください。
Answer
日中戦争の長期化とアメリカ、イギリスの対日経済圧迫の強化による物資の先細りが懸案となっていた日本は、南方進出に不足資源補充の活路を見いだそうとしており、その前提として南方への調査団派遣が急務となっていました。
外務省記録「仏領印度支那資源調査団派遣関係一件」によれば、1940年(昭和15年)9月、仏印(フランス領インドシナ)に農・林・鉱業等の専門家からなる調査団を派遣することが閣議で承認されました。これをうけて、翌1941年5月に締結された「日仏印経済協定」に基づき、同年9月、関係各省の技術官、民間の技術者および企業家からなる「仏印資源調査団」が組織され、10月より漸次派遣されました。重要必需物資の獲得のみならず、「邦人企業の強化拡充」の礎を築くことを目指したこの調査団は、横山正幸(元駐エジプト公使)団長のもと、農林、水産、塩業、鉱業、水力発電から衛生事情に至るまで幅広い分野にわたる調査を行い、その成果は分野ごとに詳細な調査報告書としてまとめられました。
なお、この調査団は、調査期間中に太平洋戦争が勃発したにもかかわらず、「仏印に特殊かつ豊富な資源」につき更なる調査を要するとして、戦争開始後も引き続き現地に滞在しました。調査を終えた全団員が帰国したのは1942年(昭和17年)6月のことでした。
太平洋戦争勃発直前に行われた日米交渉の際、「マリ子」という合言葉が使われたのは本当ですか。
Answer
本当です。
外務省記録「日・米外交関係雑纂 太平洋ノ平和並東亜問題ニ関スル日米交渉関係」に、そのことを示す史料が残されています。その史料には、寺崎太郎アメリカ局長と若杉要駐米公使との国際電話で用いる合言葉が示されており、「マリ子」は「駐兵問題ニ関スル米側態度」を示す合言葉として用いられていました。その他にも、当時ワシントンの在米大使館と東京の外務本省との間では、「伊藤君」(=「総理」)、「伊達君」(=「外務大臣」)、徳川君(=「陸軍」)、「縁談」(=「日米交渉」)、「君子サン」(=「大統領」)、「子供カ生レル」(=「形勢急転スル」)、「七福神ノ懸物」(=「四原則」)、「ソノ後ノ公使ノ健康」(=「交渉ノ一般的見透」)といった合言葉が使用されていたと史料に示されています。
なお、「マリ子」とは、当時在米大使館の一等書記官で、寺崎アメリカ局長の弟である寺崎英成の長女の名前に由来したものです。
テレビ番組で「ハル・ノート」が紹介されているのを観たのですが、その内容を記した史料はありますか。
Answer
1941年(昭和16年)11月26日、アメリカのハル国務長官から野村吉三郎、来栖三郎両大使に手交された「ハル・ノート」に関する史料は、外務省記録「日、米外交関係雑纂 太平洋ノ平和並東亜問題ニ関スル日米交渉関係(近衛首相「メッセージ」ヲ含ム)」に収められています。なお、同史料は、外務省編『日本外交文書』「日米交渉 一九四一年」(下巻)にも掲載されており、また、アジア歴史資料センターのホームページ![]() でもご覧いただくことができます。
でもご覧いただくことができます。
太平洋戦争において日本と諸外国との間で行われた宣戦布告の年月日を教えてください。
Answer
1944年(昭和19年)11月30日現在における一覧表が外務省記録「大東亜戦争関係一件 各国ノ態度」の中にあります。
外交史料館の所蔵記録の中に、戦前期、日本が外国の暗号電報を解読していたことを示す記録があるとテレビ番組で見ました。それは何という記録ですか。
Answer
外務省記録「日米外交関係雑纂 太平洋ノ平和並東亜問題ニ関スル日米交渉関係 『特殊情報』綴」という記録です。太平洋戦争直前、日米間では武力衝突を回避するために外交交渉が行われていましたが、この時期にアメリカや中国が打電した暗号電報を日本側が密かに解読した文書が収録されています。
太平洋戦争期、外交官等の交換を目的として派遣された日米及び日英交換船に関する記録はありますか。
Answer
日米及び日英交換船に関する記録は、外務省記録「大東亜戦争関係一件 交戦国外交官其他ノ交換関係」に含まれています。
太平洋戦争の開戦直後から、外務省は敵国及び断交国にある官吏及び在留民の交換計画を研究し、中立国を通じてアメリカ及びイギリスと交渉した結果、1942年(昭和17年)5月、両国との間に外交官等の交換に関する協定が結ばれました。これに基づき、日米交換船は、第1次(1942年6月から8月)と第2次(1943年9月から11月)の二度実施され、第1次帰還者は1421名、第2次帰還者は1517名にのぼりました。また、日英交換船は、1942年7月から10月にかけて実施され、総計1742名が帰還しました。交換に際しては、日本側からは浅間丸、竜田丸、鎌倉丸等が、交換地のロレンソ・マルケス(当時ポルトガル領。現在はモザンビークのマプート)に派遣されました。
太平洋戦争中に上海にあったわが国の敵国人収容所に関する写真はありますか。
Answer
外務省記録「大東亜戦争関係一件 帝国権下敵国人収容所視察報告」の中にあります。
外務省調査局に嘱託職員として勤務した青木文教が執筆した史料について教えてください。
Answer
青木文教(あおき・ぶんきょう、1886-1956)は、イスラム教及び蒙古問題の調査を目的に、1941年(昭和16年)11月、外務省調査部の嘱託職員として採用されました。青木は1912年(明治45年)から1916年(大正5年)にかけてダライ・ラマ13世の弟子としてチベットに滞在し、チベット語学・歴史・文化などの研究に従事した人物です。
外交史料館では、青木が在職時に執筆した調書として、「西蔵問題ト其対策」(1941年12月27日)、「西蔵拉薩天気概況」(1942年3月9日)、「西蔵政府代表訪日ノ成果ト西蔵問題ノ調査ニ関スル所見(西蔵代表招致報告)」(1942年9月)、「西蔵問題」(1943年1月)を所蔵しています。
*西蔵=チベット
*拉薩=ラサ

「西蔵拉薩天気概況」
「西蔵拉薩天気概況」(左図)には、1913年(大正2年)2月7日から翌年9月30日までの毎日午前8時の観測として、月日、天気記号、温度(華氏)および摘要が記述されています。
この中で青木は、ラサの気候は「温和」であると述べていますが、一方で、最も不快なのは「砂塵風」であるとも述べています。
大正期にチベット滞在中の青木が記録したものをまとめた調書と思われます。
*華氏13度=摂氏 -10.6度
*華氏40度=摂氏 4.4度
太平洋戦争時に、オーストラリアの捕虜収容所で発生した日本兵捕虜の集団脱走未遂事件に関する記録はありますか。
Answer
1944年(昭和19年)8月、オーストラリアのシドニー近郊にあったカウラ捕虜収容所で、日本兵捕虜が集団脱走を図った事件が起こり、多くの死傷者を出すこととなりました。外務省記録「大東亜戦争関係一件 交戦国間敵国人及俘虜取扱振関係 一般及諸問題 対敵国抗議関係」には、この事件を扱った査問会報告書などの関連史料が含まれています。
太平洋戦争末期、バチカンで太平洋戦争を終戦に導こうとする工作があったというのは本当ですか?
Answer
本当です。
1945年(昭和20年)5月、バチカンのローマ法王庁ヴァニヨッチ(Vagnozzi)司教は、日本公使館嘱託の富沢孝彦師に対して、「一米人」より和平問題について日本側と接触するための橋渡しをしてほしいとの申し出があったと明かしました。この申し出の内容は、ソ連の極東進出への警戒感から、米国側が日本に複数の休戦条件を提示しているというものでした。原田健(はらだ けん)駐バチカン公使はこれに対し、素性・目的とも明確でない人物とこのような交渉を行うことはできないとの観点から、消極的な回答を先方に伝えました。この回答を受けた「一米人」は、再度ヴァニヨッチを通じて、今後日本側から米国側に伝達希望があれば取り次ぐ準備があることなどを伝えてきただけで、その後具体的な交渉にはつながりませんでした。
この終戦工作については、外務省記録「大東亜戦争関係一件 「スウェーデン」、「スイス」、「バチカン」等ニ於ケル終戦工作関係」に関連記録が収められています。また、アジア歴史資料センターのホームページ(http://www.jacar.go.jp/ ![]() )からもご覧いただけます。
)からもご覧いただけます。
軽井沢には戦前から多くの外国人が別荘などを造っていましたが、第二次世界大戦中には、日本の同盟国ないしは日本と中立関係にあった国々の多くが大使館ないしは公使館をおき、大勢の外交官達が住んでいたと聞いています。このような人々に関する記録は残っていますか。
Answer
外務省記録「大東亜戦争関係一件 在日外交団ニ対スル処遇並ニ物資ノ供給関係」(第1巻)に、「軽井沢在住外交官員現在数」という記録があります。ちなみに、1945年(昭和20年)6月段階で約300名が住んでいました。
インドの独立運動家として知られるチャンドラ・ボース(Subhas Chandra Bose)に関する記録はありますか。
Answer
外務省記録「大東亜戦争関係一件 印度問題」や「大東亜戦争関係一件 「スバス・チャンドラ・ボース」ノ印度仮政府樹立関係」などに、太平洋戦争中のチャンドラ・ボースの動向を示す記録が含まれています。
太平洋戦争開戦当時、ボースはドイツに亡命していましたが、開戦の報に接すると、ヒトラー総統や大島浩駐独大使とたびたび面会して、インド独立のため一日も早くアジアに赴いて日本と協力したいとの希望を繰り返し表明しました。1943年(昭和18年)春、ドイツの潜水艦でアジアへ戻ったボースは、同年10月に自由インド仮政府を樹立して自らその主席に就任すると、東京で開催された大東亜会議(1943年11月)にオブザーバーとして出席したり、1944年3月より展開されたインパール作戦にインド国民軍を率いて参戦するなど、対日協力を推進しました。しかし、インパール作戦が失敗に終わった頃から、ボースらと日本側現地特務機関(光機関)との摩擦がいっそう強くなり、ボース自身も光機関との関係について不満を漏らしていたことが記録に記されています。
なおボースは、終戦直後の1945年8月、台湾での飛行機事故により死亡しました。

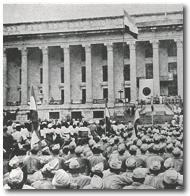
チャンドラ・ボース(左)と自由インド仮政府結成大会(右)
