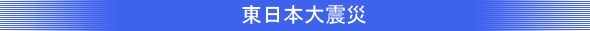
「がんばれ日本! 世界は日本と共にある」(世界各地でのエピソード集)
アジア(南西アジア)
スリランカ
- 3月17日,JAGAAS(日本帰国留学生の会)が,義援金を日本大使館に託しました。
- 3月18日,大統領と外務大臣が日本大使館を訪問し,記帳しました。
- 3月27日,全国各地で行われる追悼式の第一弾として,大統領官邸にて大統領,閣僚が出席し追悼仏教式典が行われました(在留邦人100名を含む約250名が参加)。全参加者が菩提樹の木に献花し,僧侶の読経,カップに水を注ぐ儀式が行われました。
- 3月27日以降,各地の仏教寺院で追悼式の実施を企画。
- スリランカ政府より,義援金と紅茶ティーバッグ300万個の提供がありました。紅茶ティーバッグの一部は,在京スリランカ大使が被災者に直接手渡しました。
- 3月31日,南部マータラで日本語授業を実施しているサクラ日本語学院が,義援金を日本大使館に託しました。
- カランナーゴダ駐日大使が,4月1日に宮城県気仙沼市で紅茶を,3日には福島県田村市で800食の温かいスリランカカレーを,それぞれ被災者に振る舞いました。
- 4月4日,スリランカ日本友好協会がコロンボ市ガンガラマヤ寺院で被災者に対する追悼式を行いました。
- 4月8日,Colombo Overseas Schoolの学生がランチ代などを切り詰めるなどして有志から募った義援金が,日本大使館に託されました。
- 4月20日,ケラニア大学日本語学科が,義援金を日本大使館に託しました。
- 4月29日,スリランカNGOのスランガニ基金が,義援金を日本大使館に託しました。同NGOは,低所得者層の子供たちの教育資金を支援する教育里親制度等を実施しています。里子や幼稚園関係者等が「2004年の津波のときに日本は支援してくれたが,今度は自分たちが支援する番」として,村々を回って募金を集めました。また,支援を受けている子供たちが「日本は大変なときだから今月はお金はいらない」と奨学金を受け取らず,募金に回しました。5月6日,生け花インターナショナル・スリランカ支部が,生け花展入場料及びバザーの売り上げを義援金にして日本大使館に託しました。
- 5月11日,観光庁が主催し,ケラニア寺院(コロンボ近郊で最大の仏教寺院)で被災者に対する追悼式を開催しました。
- JASTECA(日本スリランカ技術文化協会)が,義援金を日本大使館に託しました。
- スリランカの復旧支援チーム(災害管理省の要員15名)が, 5月12日来日し,石巻市を中心にがれき除去等の活動を実施。約3週間にわたり,石巻市内の工場,個人宅,公道の側溝などの汚泥やがれき除去を行い,6月4日に帰国しました。その迅速かつ懸命な仕事ぶりは地元住民などから高い評価を受けました。
- 7月9日,コロンボで開かれた盆踊り大会で,スリランカ復旧支援チームが紹介されるとともに,「Love from Lanka」と記したチャリティ・ステッカーが販売されました。
- 8月2日,NGOピースボートに乗船した福島県の中学生約50名がコロンボを来訪し,これらの中学生を招き,3日に大統領及び大統領夫人が歓迎会を主催しました。また,中学生達は,NGOセワランカにより,2004年インド洋大津波で被災したスリランカの子供達と交流会を行いました。
ネパール
- 物資支援や義援金の申し出が日本大使館に寄せられました。
- 「被災地の復興を信じている」等の書かれた千代紙(日本大使館が文化事業で使用したもの)を利用した手作りのメッセージが日本大使館に届きました。
- 3月14日,立法議会が,犠牲者及びその遺族に対する弔意,負傷者の一刻も早い回復,救済活動に対する日本との結束,並びにこの苦難を日本国民が乗り越えられることを希望すること等を趣旨とする特別決議を採択。
- 3月14日,カナル首相(当時)が弔問のためネパールの日本大使館を訪れました。
- 3月28日,カトマンズ市内で日本の被災者のための追悼式が行われました。
- 3月24日,トリブバン大学にて,日本語教師協会が,被災者のためのお祈りと募金収集のための会を開催(日本語科以外の学生も含め100名参加)。
- 4月~6月,タマン駐日ネパール大使が被災地を3回訪問し,ネパール料理の炊き出し,支援物資(生活必需品,ネパール産コーヒー等)の配布,義援金の寄付,被災地域の清掃等を行いました。
- 各種仏教団体や商工部会などが,日本の被災者のために祈るための会合を各所で開催。
- バクタプール市の日本語学校が主体となり,「1日分の給与を日本に」を掲げた「Pray for Japan」キャンペーンを実施。
パキスタン
- パキスタン俳句協会会長が,様々な機会に被災者へのお見舞いのメッセージと連帯の意の表明を行い,現地の新聞12紙で報道されました。
- オブザーバー紙及びナワー・エ・ワクト・グループ各紙が,日本の被災者に対するお見舞いメッセージを発出。日本から受けた寛大な援助を忘れてはならないこと,そして地震により甚大な被害が生じている日本に対し支援をする用意があることを表明しました。
- カラチの私立小中高等学校Foundation Public School及びCity School PAF Chapterから,「日出ずる国に,再び日が昇る(The Sun will rise again in the Land of the Rising Sun)」等のメッセージが記された被災者への見舞いの寄せ書きが日本総領事館に届きました(両校は2008年,2010年に訪日プログラムに参加)。
- 3月15日,イスラマバード市内のJapanese Parkにて,市民グループが被災者への献花を行いました。
- 3月20日,イスラマバード市内で,2005年のカシミール地震被災者を中心とした障害者支援NGOが献花式を行った。
- 3月20日,カラチのパキスタン日本文化協会シンド及びパキスタン日本ビジネス・フォーラム(PJBF)が,被災者に対する応援と連帯を求める行進「Walk for the Rising Sun」を開催し,約800名が参加。
- 3月22日,パキスタン上下両院の議会演説において,ザルダリ大統領が震災の犠牲者に対するお見舞いのメッセージを述べました。
- 3月23日,イスラマバード市内のJapanese Parkにてお見舞い・激励の集会が開かれました。「日本は常にパキスタンを助けてくれた,全てのパキスタン人がこの悲しみを共有している。」と主催したNGOの代表が挨拶しました。
- 3月24日,ザルダリ大統領が日本大使館を弔問し,記帳しました。
- 3月24日,オマール・サナ基金代表とサラセミア(地中海性貧血)を患う40人の子供(9歳~15歳)がカラチの日本総領事館を訪問し,被災者への見舞いと激励のメッセージに加え,被災した日本の子供達に対してサッカーボール10個を寄贈しました。同代表は,「過去度重なる自然災害に苦しめられてきたパキスタン人であるからこそ日本人が現在直面している苦難を理解できる。サラセミアに苦しんでいる子供達は真剣に日本の同年代の子供が苦しんでいる状況について心配しており,少しでも心理的な苦しみを解消したいと,遊び道具であるサッカーボールを寄贈させていただいた」と述べました。
- 日本在住のパキスタン人の方々が,被災地で支援物資配布やカレーの炊き出しなど,様々な形で支援を行いました。
- 3月27日,NGOの日パ・ウェルフェア・アソシエーションが,地震・津波被災者支援チャリティ・バザーを開催。
- 3月31日,Pakistan Poverty Alleviation Fundの代表が日本大使館を訪れ,2005年のパキスタン大地震や2010年のパキスタン大洪水に際する日本の支援への恩返しの意味もこめて,約150名の職員の1日分の給与を義援金として寄付しました。
- 4月6日,アボタバード市の学校生徒及び職員がJICA事務所を訪れ,被災者への義援金を寄付しました。
- 4月6日,パキスタン文部科学省帰国留学生同窓会のメンバー及び学生が,国会議事堂前で,被災者へのお見舞いと連帯の気持ちを表明する集会を開きました。参加者は弔問帳に署名し,「頑張れ!日本!」と叫びながら行進を行いました。後日同窓会のメンバーは義援金を寄付。
- 4月28日,国立現代語大学日本語学科の学生が,小遣いを寄付し合い,義援金として大使館に託しました。
- パキスタン外務省婦人会と在京パキスタン大使館婦人会が義援金を募り,在京大使館が,その資金をもって日本国内で物資を調達して被災地に届けました。
- 4月18日,シアルコート商工会議所で,社会奉仕団体THINKERS FORUMが,被災者に対する連帯を示すセミナーを開催し,連帯の気持ちを綴った横断幕を作成しました。後日,横断幕は日本大使館に寄贈されました。
- 5月6日,財団法人海外技術者研修協会(AOTS)のラホール同窓会が,被災者への義援金を寄付しました。
- 5月24日,自動車製造会社から,日本総領事館に義援金が寄付されました。
- 5月31日,イスラマバードで,パキスタン俳句協会と日本大使館の共催による,被災者に捧げる俳句の朗読会が開催されました。参加した俳人は,被災者への連帯を表す句を詠みました。
- 6月6日,ラーワルピンディーのRoots School System学校の生徒たちが,被災者への連帯を示すために日本大使館を訪れ,日本の景色や文化が描かれた自作のカードを寄贈しました。
- 2012年2月,ラーワルピンディーのRoots School System学校の生徒たちが,震災発生1年を前に再度日本大使館を訪れ,連帯やお見舞いのメッセージやイラストが描かれた自作のカードを寄贈しました。
バングラデシュ
- チッタゴンの小学校2校が,生徒による犠牲者追悼の署名簿を日本大使館に託しました。
- 3月12日,ダッカ大学の学生ボランティア団体が,犠牲者を追悼する行事を行い,キャンドルを手に祈りを捧げました。同団体は,同行事の際に作成した「Our heart and our tears are with you」とのメッセージを書いたパネルを日本大使館に渡しました。
- 3月12日,アメリカン・インターナショナル・スクール・ダッカ校生徒が,紙で作成した日本国旗にお見舞いと激励のメッセージを記載し,日本大使館に託しました。
- 3月20日,国会にて,犠牲者に哀悼の意を表する決議案を全会一致で採択。「国会は,日本のこの危難の時に日本政府及び国民と共にある。」との声明を発表。
- 3月22日,日本学術振興会フェロー同窓会の理事会が,義援金を日本に贈ることを決定。
- 日本在住のバングラデシュ人の方々が,ホテルの無償提供や炊き出しなど様々な形で被災者・避難者に対する支援を実施。
- 4月11日,日本で職業訓練研修を受けた有志が,日本大使館に義援金を届ける意向を表明。
- 義援金6月5日からバングラデシュのテレビ番組制作チームが,東日本大震災の特集番組を制作するために来日しました。
ブータン
- 国王陛下から「ブータンにできることはとても小さいが,困難な状況にある日本の人々との連帯を示したい。」との発言がありました。
- 3月12日,タシチョゾン(王宮,寺院,中央官庁が集まるティンプー市内の城塞)内の寺院で,国王陛下主催により,被災者の安全を祈祷するための式典が開かれました。
- 3月13日,タシチョゾン内の寺院にて,ブータン政府により,被災者の安全を祈祷するための式典が開かれ,首相以下政府関係者,上下両院議長他の国会議員,市長,在留邦人等が出席しました。
- 3月13-15日,5県で県知事主催による追悼式典が行われたほか,各種の政府関連行事に際して黙祷が行われました。
- 3月18-20日,全国の寺において犠牲者を追悼する法要が行われ,3月20日には,タシチョゾン内の寺院で3日間の法要を締めくくる式典が開かれました。
- 3月20日,ティンプー市内寺院にて,JICA帰国研修生同窓会による追悼式典が行われました。
- 3月20日,ティンプー市内の小学校がチャリティー・ウォークを開催し,生徒,保護者約100人が参加しました。
モルディブ
- 3月15日,閣議において1分間の黙祷。
- 3月16-18日,モルディブ国旗を半旗で掲揚
- 3月18日,副大統領及び首都マレ市役所の主導で,全国で震災被災者支援ウォークが行われ,マレ市(人口10万人)では2万人が参加しました。
- 3月18-19日,モルディブ国営テレビが義援金を募る24時間テレビを放送。
- 3月18日,大統領が全国民に向けたラジオ放送で,日本のモルディブ発展への貢献に触れ募金を呼びかけました。
- 4月5日,首都マレで,追悼式及びツナ缶引渡式が開催されました。ナシード大統領,ナシーム外務大臣,アフィーフ内務大臣,ジャミール保健・家族大臣等の閣僚ら計約150名が出席し,国営放送が生中継で放送しました。大統領は,「2004年のモルディブの津波に際して,日本が建設してくれた津波防護壁により首都マレは大きな被害をまぬがれた。また,その際に負った被害に対し,日本は様々な形で支援してくれた。今回の日本の被災に際しては,我々は出来ることは何でもやりたいと考えている」と発言しました。モルディブ政府から提供のあったツナ缶は被災地に随時配られています。
 ,
カラチ(パキスタン)
,
カラチ(パキスタン) )
)