平成23年度第2回「外務省セミナー『学生と語る』」
~結果報告~
平成24年1月
平成23年12月20日(火曜日),外務省において平成23年度第2回「外務省セミナー『学生と語る』」を開催いたしました。
全体講演および分科会の内容について,アンケートにご協力をいただいた参加者の感想を引用しつつ,紹介します。
1.全体講演
開会挨拶(大臣官房 国内広報課 佐久間研二課長)
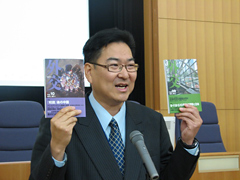
『学生と語る』開催主旨の説明に続き,大学生を主な対象とした外務省主催事業『外交講座』,『大学生国際問題討論会』の他,外務省ホームページ『わかる!国際情勢』,さらに外務省が発行するわが国唯一の外交論壇誌「外交」最新号(第10号)の中国特集について紹介した。
基調講演
「アフガニスタンにおける平和構築の課題」
(13時35分~14時40分)
(在アフガニスタン大使館 松田誠参事官)

はじめに,講師が勤務するアフガニスタン大使館(カブール)では,未だ実質的には戦時下にあり,館員約30名は全員大使館敷地内に居住し,自由な外出は一切できず,業務での外出時には防弾車に乗るとともに英国軍隊出身のボディガードと行動する等,厳しい勤務環境について紹介した。生活物資では,現地では入手できない食料品も多くあるが,アフガン人コックのおかげでそれなりの食事をことができるため,美食家でなければ大きな問題はないと語った。
続いてなぜ日本をはじめ国際社会の主要国がアフガンに関与するのかについて,まず,同国の歴史を通して解説した。
- (1)1979年,ソ連侵攻によってアフガンは冷戦の象徴となり,国際社会の注目を集めることになった。
- (2)1989年,ゴルバチョフ大統領のとき冷戦の終了に向かう中でソ連はアフガンから撤退したが,これにあわせ米国をはじめとする国際社会もアフガンからの関与を引いたため内戦が勃発した。
- (3)1990年代,イラクのクウェート侵攻に始まる湾岸危機など大きな国際問題などが起こり,アフガンの問題は国際社会から注目されることなく,アフガンは内戦により荒廃し,その結果としてタリバーンが台頭することとなった。
- (4)1996年以降,タリバーン政権の下,アルカイダがアフガンに入り,軍事要員をアフガン内の訓練キャンプで教育した。1990年代末,アルカイダはアフガンの拠点から全世界へテロを繰り広げ,ついに2001年,アルカイダは米国に対して同時多発テロを行った。
- (5)米国は,アルカイダを殲滅すると同時に,アルカイダをかくまっている国も敵と同等と見なすと宣言し軍事作戦を展開するためアフガンに侵攻し,瞬く間にタリバーン政権を崩壊させた―――
とアフガンの歴史を解説した。その後の国際社会の課題は,民主的なアフガン政府による統治を確立させ,治安を安定させて再びアフガンがテロの温床になることを阻止することであると強調した。

続いて2001年から2011年まで国際社会が行った10年間の政策の評価について解説した。その中で,10年前との比較においては明らかに目に見える進展はあるが,(1)大使館員が防弾車での移動を余儀なくされる生活であることからも明らかなように,治安状況は未だ完全には回復していないこと,(2)アフガン政府の統治能力も十分とは言えないこと,したがって,この10年間の国際社会の努力にもかかわらず、アフガンは完全には再建されていないのが現状であると言及した。
その理由については,多義的ではあるも,客観的に言えば一つの原因はイラク戦争だったとの指摘があると解説した。すなわち,2003年に始まったイラク戦争により,結果として国際社会はその関心と資源をイラクに向けることになったが,その裏で2006年頃からタリバーンが再び台頭することになってしまったと語った。
その後,国際社会は再びアフガンに対する関与を強め,タリバーンに対して優位に立ちつつあると評価されていること,いずれにせよ,10年前,アフガンには実効的な政府はなく,無法地帯が存在しただけだったことに比べれば,現状には一定の問題はあるも, 10年前よりはるかに改善されていることなどを語った。
次に当面の課題について,2014年末までの「権限移譲プロセス」を中心に詳説した。その中で,現在,アフガンの治安維持は約10万人のNATO軍が行っているが,2014年末までにアフガンから撤退することとなっているとし,2015年からはアフガンの軍と警察が治安を責任持って確保することが期待されている解説した。この関連で,アフガン治安部隊については,治安部隊としての能力拡充,住民からの信頼確保が課題であるとした上で,治安部隊の数を増大させることについては,その財政を誰が負担するのか,また,肥大した治安部隊を将来のアフガン政府がきちんと統制することが可能かという課題があると語った。
続いてアフガン政府による文民統治が可能とするために何が必要かについて言及し,その中でアフガン政府の行政能力は未だ十分ではないとし,きちんとした官僚機構のない国で,政府,官僚の能力開発をどうするのかが急務の課題だと語った。

さらに権限移譲がもたらす経済面の課題について言及。その中で,現在のアフガンの経済の相当部分は,外国駐留軍の活動によって支えられていること,したがって,駐留軍が撤退すると経済が危機に瀕するか可能性があると語った。これに関連し,アフガンの国家財政についてデータを基に,現在の税収は約20億ドルであるが,それに対して歳出は約40億ドルあり,その半分近くは国際社会が経済支援で負担していると解説。さらに国際社会の民生 支援は約160億ドルあり,これはアフガンのGDPに匹敵し,加えて米国の軍事支援費には1200億ドルに達していることに触れ,国際社会がアフガンへの関与を急激に低下させれば,アフガン経済には甚大な影響が及ぶという大きな懸念があると語った。
最後に日本政府はアフガンに対して多額のODA支援を行っていることにつき,その理由について解説した。これは基本的には,国際社会にとっての安全保障のためであり,アルカイダを含む国際的なジハージストが日本を含む西側の国を攻撃する可能性は未だ排除できないため,これを阻止するのが,我々がアフガンを支援する目的であると説明した。その中で,こと安全保障の問題については,行政官としては最悪の事態も念頭におきつつ,決して安易な判断を行ってはならないこと,同時に成果を目に見える形で示すことは難しく,国民に対して丁寧な説明が必要であると強調した。
結びに,アフガンでの業務について,アフガンは治安リスクが非常に高く,特別な赴任先であるが,館員は全員志願兵で高い意識を持っていると紹介した上で,まさに命を張っての国益のために日々業務につくのは圧倒的なやりがいを感じると語り,アフガンでの業務は国家の再建というスケールの大きい仕事であり,日本では経験できない仕事ができると語って講演を結んだ。
<参加者の感想>
- 大使館の日々の生活の話しから,国益に関する今後の課題や論点まで、幅広く伺い,包括的かつ適格にアフガン平和構築に内容を捉えることができた。
- 相当危険な地域での業務,生活は全く想像もつかない内容で面白かった。今国内で少し関心の薄れているアフガンについて知り,安全保障などについて考え直すきっかけとなった。
「省員による体験談」(14時40分~15時25分)
(広報文化交流部人物交流室 石田春菜事務官)

はじめに自身の略歴を紹介しつつ,入省以来7年間に印象に残った業務や外交の現場等について語った。その中で,入省後まもなくして日本外交団の一員として国連の現場で交渉を行った経験等に触れ,外務省は若いうちから責任とやりがいのある仕事ができる職場だと述べた。また,本省勤務後の在外研修では,語学のほか,フランス行政組織の仕組みや意志決定プロセスについても研修したと語った。さらに研修後の大使館勤務での業務(情報収集,二国間の調整,交渉,要人訪問等)について詳説し,帰国後は人物交流室(所属部署)で外交政策の決定プロセス等を日々改めて勉強していると語った。また,自身の出産・育児経験にも言及した。続いて現在の思いを語る中で,入省前に外務省を志望した動機や思いは裏切られることなく,特に,日々の業務を通じて少しずつでも「より良い日本」の実現に貢献していけることや,心持ち一つで個人ができることは大きいと同時に終わりなき自己研鑽が求められるといった点が外務省の魅力だと実感していると語った。また,カウンターパートのおかれた論理構造への深い理解や人としての魅力が重要だと考えていると述べたうえで,最後に内向きならず日本の外へ飛び出して欲しいなど,参加学生にメッセージを送り,講演を締めくくった。
<参加者の感想>
- 具体例を交えた話は面白かった。激務の印象がある外交官でも,女性が出産,育児と両立して仕事ができることにも魅力を感じた。
2.分科会(15時40分~17時40分)
全体講演終了後,6つの会場に分かれて分科会が開催され,各分科会では,外務省員によるプレゼンテーション,質疑応答,参加者によるディスカッション等活発な意見交換が行われました。
「広報文化交流」
(広報文化交流部 総合計画課 永岡和道課長補佐)

広報文化外交とは何か,それが近年益々重要になってきている理由,広報文化外交を取り巻く環境,担い手と訴求対象に合わせた具体的手段(ツール)について概観したあと,外務省が実施している海外への情報発信,文化交流,人物交流,文化面での国際協力について,写真や実例を交えながら詳しく説明しました。また,東日本大震災以降の対外発信の取組に関し,地震発生後から今日までの時期に応じた広報の重点分野の展開や,実際に制作した広報資料についても紹介しました。
参加者からは,外国政府による文化流入規制の問題や,インターネットの拡大と網羅的な情報収集・モニタリングの困難性,地方自治体の国際交流の取組に対する外務省の支援,日本のプレゼンスの相対的な低下に対する広報活動の限界,ソフトパワーを巡る他国との競争状況における予算面での限界を克服するための工夫といった様々な論点について鋭い質問や意見が寄せられました。
<参加者の感想>
- 日本の伝統文化やポップカルチャーの発信だけでなく,政策決定者や有識者への情報発信についても解説があり,視野が広がると同時に,広報戦略について興味を持った。日本の伝統文化やポップカルチャーの発信だけでなく,政策決定者や有識者への情報発信についても解説があり,視野が広がると同時に,広報戦略について興味を持った。
「我が国の安全保障政策」
(総合外交政策局 安全保障政策課 小長谷英揚課長補佐)

本分科会では,まず「安全保障とは何か」「安全保障を確保するための手段として何があるか」という問題について参加者との対話形式で概念の整理を行った上で,我が国を取り巻く安全保障環境につき言及しつつ,我が国の安全保障政策について説明し,自国の防衛力の整備,同盟国との関係の深化及び安全な国際環境の整備といった分野での具体的な取り組みを紹介しました。
質疑応答では,参加者から,米国の国防予算削減が東アジアの安全処方環境に与える影響,動的防衛力への転換についての周辺国の受け止め方,米国の拡大抑止の下で日本が核軍縮を進めることの意義,安全保障上の危機に備える上で政府としてどのような観点から準備を行っているのかといった様々な論点について,鋭い質問や意見が多数寄せられました。
<参加者の感想>
- 日本を取り巻く様々な国際環境が日本の安全保障に直結することを改めて感じた。自国の防衛力整備,同盟国との協力,安全な国際環境の整備が肝要であると分かった。
「国連外交」
(総合外交政策局 国連企画調整課 中西勇介事務官)

国連・国際機関を取り巻く環境がどのように変化しているのか,その変化の中における国連・国際機関の役割及び活動,日本の国連・国際機関外交の位置付けやアプローチについて,参加者と意見交換しながら説明しました。
また,討論形式で,日本が国連・国際機関においてどのような貢献をなしえるか,国連・国際機関をどのように活用することができるか,国連・国際機関の限界について問題提起しながら,国連・国際機関とどう向き合うべきかについて議論しました。参加者からは,日本が国連・国際機関の場で取り組むべき課題,ルール作りや発信の場としての国連・国際機関の活用方法,G20などのフォーラムとの関係,邦人職員増強に向けた施策や安保理改革の意義など鋭い質問や意見が多数寄せられ,活発な意見交換が行われました。
<参加者の感想>
- 国連の活用の仕方,日本の強み,アピール方法,国連の限界等々,日本が今後,何を軸に発信し,行動していくべきかの基本的要素を得られたように思う。様々な意見を伺い,専門以外の具体的素材をたくさん掴んで持って帰られることができ良かった。
「日・EU外交」
(欧州局 政策課 赤塚玲奈課長補佐)

分科会の前半では,対EU外交の現場の様子について,日EU間で行われている様々なレベルの協議や具体的な協力案件について説明しつつ,年間を通じた大まかな業務のサイクルや業務の内容について紹介しました。その後,EUの拡大・深化のプロセスと日EU関係の発展の経緯を概観した上で,日EU関係強化の意義・重要性や,今後の日EU関係を考えるにあたって考慮すべき様々な要因について,参加者から寄せられた様々な観点からの質問を交えつつ議論しました。こうした説明や議論を踏まえ,最後に「もしEU担当官であるとしたら,『日EU共同シンポジウム』をどのように開催するか」をテーマにグループ・ディスカッションを行ったところ,各グループからは既存のテーマに縛られない様々な発想・アイディアが寄せられました。
<参加者の感想>
- 大変興味深い内容で詳細な解説だった上,グループセッションでは様々な意見交換ができ,有意義な時間だった。
「アフリカ外交」
(中東アフリカ局 アフリカ第二課 森本真樹課長補佐)

アフリカ全般及び東部の「アフリカの角」地域について,現状と日本の取り組みを説明しました。また,東日本大震災直後のアフリカからの支援についても紹介しました。その後,日本のアフリカ外交や支援策のあり方について,参加者と共に考察を深めていきました。
参加者からは,アフリカにおける新市場の開拓や民間投資促進の重要性が指摘されると共に,中長期的な視野に立ち,アフリカ諸国との信頼関係を更に強化すべきとの意見が出されました。これについて,トップ外交の促進や大使館増設の必要性を強調する意見が出されました。アフリカの角への支援については,治安の確保と人道支援の両面に取り組むことが大事であるとの意見や,政府承認に関する質問がなされました。
<参加者の感想>
- 概要から今後のアフリカ外交まで詳しい解説で勉強になった。アフリカにアグレッシブに関与すべきと感じた。
「日本の領土をめぐる課題」
(国際法局 国際法課 馬場隆治課長補佐)

我が国が抱える領土をめぐる諸課題として,領土問題である北方領土問題及び竹島問題,領土に関する外交上の問題である尖閣諸島を取り上げ,それぞれ歴史的経緯や我が国の基本的立場を中心に説明するとともに,問題解決の方策について国際法の観点からの基本的な考え方について説明を行いました。その後,参加者との間で非常に活発な質疑応答が行われ,国際司法裁判所(ICJ)への提訴の是非,実効支配の強化の動きが我が国の法的立場に与える影響や領土問題と世論・教育との関係といった領土交渉の本質に迫る質問のみならず,北方四島返還後の現四島住民の扱いといった将来的な課題についての質問も寄せられました。国際法という基本ルールの下で領土をめぐる諸課題に対応する外交実務の現場を感じていただく機会になったのではないかと思います。
<参加者の感想>
- 関心あるテーマであり,直接担当官から解説を伺うのは面白かったが,国際法の知識が不十分であることを実感し,また現場を知らないと分からない,判断できないことの多さを感じた。
3.懇親会(18時10分~19時40分)
分科会終了後に行われた懇親会には,参加者に加え,齋木参事官をはじめ全体会・分科会講師,入省1年目の省員など30名を超える外務省員が参加し,参加学生と外務省員が熱心に語り合う姿が会場の随所に見られました。その模様の一部については下記の写真をご覧下さい。
最後に
今回の「外務省セミナー『学生と語る』」には200名を超える応募がありました。会場の都合により残念ながらご参加頂けなかった方々には深くお詫び申し上げます。
ご参加頂いた方々のアンケートでは,参加して良かったという感想をはじめ分科会テーマ,議論の進め方などについて様々なご意見,ご提案をいただきました。アンケートに寄せられたご意見,ご提案を参考に本事業をさらに充実・発展させて参りたいと思います。
今回,本事業の広報活動にご協力いただきました各大学,大学院,予備校等の教育機関の教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。




