平成22年度第1回「外務省セミナー『学生と語る』」
~結果報告~
平成22年10月
平成22年10月1日(金曜日),外務省において平成22年度第1回「外務省セミナー『学生と語る』」を開催いたしました。
全体講演のおよび分科会の内容について,アンケートにご協力をいただいた参加者の感想を引用しつつ,紹介します。
1.全体講演
開会挨拶(大臣官房 国内広報課 佐久間研二課長)
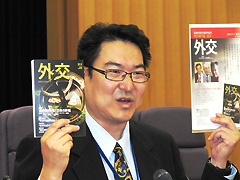
「学生と語る」開催の趣旨等を説明するとともに,昨年の事業仕分けの結果を踏まえ,今年度から新たに外務省自ら発行することとなった新外交専門誌『外交』の創刊について紹介しました。
基調講演「国際情勢について」(13時35分~14時40分)
(総合外交政策局 総務課 武藤顕課長)

最初に外交の目的について,1)わが国の安全のために 2)わが国の繁栄のために 3)地球規模課題への取組強化の3点を挙げ,これらはいずれも大きな課題に直面しており,いずれも従来の外交の地平線を切り開くような膨大な努力がなければ目的を達成できないところにわれわれは立っていると語り,とくに地球規模課題への取り組みについては,核軍縮・不拡散,PKO,テロ脅威のための対処,地球温暖化・生物多様性のためのルールメイキングなどに日本政府が積極的に参画することによって貢献を果たすことが重要だと語りました。続いて国際社会の共通課題および戦略バランスの変化について語り,北朝鮮による現実的な脅威,イランの核問題,アフ ガニスタン情勢の悪化などの国際社会の共通課題は,直接・間接にわが国周辺地域にも影響するとし,わが国は地域,国際社会の安定に主体的, 能動的に取り組むことが不可欠だと強調されました。戦略バランスの変化については,日本を取り巻く戦略バランスは急速に変化しているとし, 米国のおかれた戦略環境の変化,中国・インドの台頭,ASEANにおける中国の影響力増大(南シナ海問題等),ロシアの見方等について詳説した上で,いずれも中国の著しい台頭を抜きにこの地域の戦略環境について語ることはできないことが最近の変化の大きな特徴だと解説しました。そういう中でわが国は国際社会の課題,変化に対応するための手段として,1)日米安保体制の堅持,2)近隣国との安定した関係の構築,3)平和で安定した国際社会を実現するための努力,の3点について解説されました。

とくに日米安保体制の堅持についてジョージ・F・ケナン(回顧録)を引用し日米安保体制構築の米国側の事情を紹介しながら,日米安保体制は冷戦時に抑止力として機能してきたこと,冷戦後においては,北朝鮮の現実の脅威や9.11テロ等を受け,「アジア太平洋地域における安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎」として,「周辺事態」における協力への取組みなど新たな役割分担や貢献が期待されていると語りました。また,豪州,韓国,インドなど近隣国との協力を強化するとともに,中国,ロシアとは良好な二国間関係を構築していく必要があると解説し,さらにEPA,FTAなど経済連携の強化を図るともに日中韓,ASEAN+3,EAS,APECなど地域枠組みを多層的に広げていく努力が必要だと解説しました。さらに平和で安定した社会を実現するための努力について,日本は国際社会においてテロの予防,紛争の予防,平和構築のために能動的な外交が求められていると語り,とくに国際平和のための努力の貢献として国連PKOへの積極的な参加,そのためのPKO法の見直しの検討の必要性を強調されました。
最後に日本を取り巻く国際環境,とくに安全保障面が大きく変化してきている中で,日本の外交は安全保障面での貢献,近隣諸国との関係改善,国際社会での貢献が求められており課題が山積しているが,こうした問題を身近な問題として外交を考えていただきたいと学生に語りかけました。
<参加者の感想>
- 既存のアーキテクチャーではもはや国際問題を解決するのは難しいという言葉が印象的でした。世界的にパワーオブバランスが徐々に変動していく中,日本はいかに世界で「自己アピール」できるか考えさせられました。
- 日本の安全保障について外務省の考え方,政策の概要を聞き勉強になりました。。中国との関係はやはり難しい課題があることを再確認しました。
「省員による体験談」(14時40分~15時25分)
(大臣官房人事課 佐藤大輔課長補佐)

最初に外交官を目指した動機について,公的な仕事で,世界をフィールドとする仕事を探求したところ外交官に行き着いたと語り,外交官試験合格時の喜びの様子を紹介しました。続いて入省後,最初に担当官として携わった業務が学生時代に研究したテーマと関連していたことを通して,学生時代に学んだ知識が実務に役に立つ一方で知識と実務の間に差異があることを,具体例を挙げて語りました。本省での勤務の後,米国での語学研修,研修終了後のシンガポール大使館勤務で経験した業務を紹介し,なかでも天皇皇后両陛下のシンガポール訪問という歴史的な事実に立ち会えたことは感動的だったと振り返りました。続いて在外勤務を終え,本省での担当業務を説明する中で,G8洞爺湖サミットでのアフリカ・パートナーシップ・フォーラム(国際会議)での議長声明をまとめるにあたっての苦労話を紹介し,国際会議での貴重な経験だったと語りました。これら9年間の勤務の経験を通して,外務省での仕事は,1)世界を舞台に仕事ができる,2)世界は広く,面白いと実感できる,3)業務では様々な経験が積めるし自分自身の確かな成長を感じることもできる,4)歴史の一つのきっかけに関わることも可能である,と説明しました。最後に採用担当として今後のリクルートについての業務説明会への参加を呼びかけ,講演を締めくくりました。
<参加者の感想>
- 体験談はリアルな舞台裏が見え,またその時の苦労や感動も詳細に語っていただいたので,実際の省員の方の生活や仕事内容がイメージできました。
- 外交官のフィールドの広さと好奇心をそそる体験を聞き,さらに外交官への興味が沸きました。
2.分科会(15時40分~17時40分)
全体講演終了後,6つの会場に分かれて分科会が行われました。各分科会では,外務省員によるプレゼンテーション,質疑応答,参加者によるディスカッションが行われました。
「広報文化交流」
(広報文化交流部 総合計画課 永岡和道課長補佐)

広報文化外交が近年益々重要になってきている理由,わが国の広報文化外交を取り巻く環境,相手国の訴求対象に応じた取組について概観したあと,外務省の行っている海外への情報発信,文化交流,人物交流,国際機関を通じた協力について,写真等を交えながら詳しく説明しました。関係省庁等との連携にも触れ,オール・ジャパンで日本の魅力を発信している例を紹介しました。参加者からは,日本語教育への取組,留学生交流 の重要性,ポップ・カルチャーの効果的な利用,機動的な広報活動,ソフトパワーの限界といった様々な論点について質問・意見が寄せられました。
また,もし自分が大使館のPRコンサルタントとして広報・文化事業を立案することになったとしたらとのテーマで,広報戦略立案時に留意すべき点や取り組みたい事業についてグループ単位で考えて発表してもらったところ,有名人や時宜を得たイベントの活用,政治色が強まらない配慮等地域の特色を踏まえた提案が多く出されました。
<参加者の感想>
- 体系的な学問の話から,現地での具体的な体験まで様々な話が聞けて,非常に有意義でした。
「対中東外交」
(中東アフリカ局 中東第一課 杉浦雅俊課長補佐)

中東地域の概要と最近の地域国際情勢に触れつつ,同地域の重要な問題である中東和平を取り上げ,初めにイスラエル・パレスチナ紛争の歴史的経緯について概観した後,イスラエル・パレスチナ間の直接交渉の動き,日本の役割等につき,説明しました。 参加者からは,「中東外交を進めていく上で米国との関係はどのように調整しているのか」,「日本が中東地域で独自の役割を果たす上で何が重要か」といった点から,様々な意見が述べられ,距離的には遠い中東地域についても関心が高まっている点が垣間見えました。
<参加者の感想>
- 中東和平の概要についての説明はわかりやすかった。質疑応答でも一つ一つ丁寧に説明いただき,日頃抱いていた中東に関する疑問を解消できました。
「東アジア外交」
(アジア大洋州局 地域政策課 西野修一課長補佐)

本分科会においては,時代を通じて変わらない日本外交の柱の1つである東アジア外交について,東アジアの安全保障情勢やアジア経済の強みと課題について説明しながら,防衛計画の大綱の見直し,新興国の台頭の最近の動き等についても言及し,その後参加者の関心ある事項について,質問を受けながら一緒に議論しました。参加者からは,日本と韓国のEPAの違い,尖閣諸島周辺領域内におけるわが国巡視船と中国漁船との接触事案への対応等について鋭い質問が出され,今後のEPAのあり方や中国との関係について議論を行いました。また,これからの東アジア外交を考える前提として,少子高齢化が進む日本としてどのような国作りを進めたらよいかについても一緒に考えてみました。参加者からは,優れた技術・人材の輸出,得意分野での国際貢献,経済だけに頼らない国のあり方,さらに内向きになっていると言われる日本人がより積極的に海外と関わっていくにはどうしたらよいかといった点について意見が出されました。
<参加者の感想>
- 日本と新興している東アジア諸国との関係を実務的な視点からお話しいただき,大変に参考になりました。
「核軍縮・不拡散」
(軍縮不拡散・科学部 不拡散・科学原子力課 大西一義課長補佐)

原子力についての初歩的な科学的事実,そして原子力が核兵器としても使われたが,平和的利用による利益も享受できることについて簡単に触れた上で,NPTの三本柱の一つである核不拡散のための国際的な枠組みについて概観し,現在国際社会で議論されている課題や,日本の基本的な立場・取組を説明しました。
内容がやや難しいものであったことから,この分科会では,最近行われたNPT運用検討会議やIAEA総会について写真や講師の実体験を交えて紹介し,随時,参加者からの質問の時間を設けながら理解を深めてもらうよう工夫したところ,参加者からは,追加議定書の締結促進や地域の核問題,NPTからの脱退の問題といった様々な論点について,鋭い質問が寄せられました。
<参加者の感想>
- 日頃触れることのないテーマで,すべての話がとても興味深いものでした。1つの政策に関してここまで詳しく聞ける機会はあまりないと思うので,とても貴重な時間でした。
「日米外交」
(北米局 北米第一課 畠山健太郎課長補佐)

オバマ政権の日本に対する見方や日米間の課題等にも言及しつつ,最近の日米関係の現状について紹介しました。また,その上で,日米外交を考えるということは,様々な地域及びグローバルな課題について,日本が国際社会においてどのような役割を担っていくかを考えることにつながっていくとの認識のもと,中国や北朝鮮,東アジア共同体等のアジア太平洋地域情勢,更にイラン,アフガニスタン,軍縮・不拡散等のグローバルな課題について説明しました。
この分科会では,随時,参加者に自由な発言や意見を求めながら,討論形式で実施したところ,参加者からは,日米関係を深化させていくというプロセスは例えばPKO派遣等の分野で日本の対応可能な限度を超えることもあるのではないか,米国への依存を減らしバランスをとるためインドと関係を深化させていくべきではないか,ASEANがより成熟していくために必要なプロセス如何,高速鉄道等に関する閣僚によるトップセールスのあり方如何,マルチの会合と二国間の議論の場を外交的に如何に使い分けるか,といった様々な論点について,鋭い質問や意見が多数寄せられました。
<参加者の感想>
- 二国間における問題を様々な側面から考え,解決へ向けてのプロセスを他の学生と意見好感できたのは有益でした。
「日本APEC」
(経済局 アジア太平洋経済協力室 粂井真課長補佐)

本年我が国が15年ぶりに議長を務めるアジア太平洋経済協力(APEC)について,会議の発足の経緯,他の地域フォーラムと比べたAPECの特色,本年の議論の柱,11月の横浜での首脳・閣僚会議で目指すべき成果等について 説明を行いました。参加者からは,ボゴール目標(注:自由で開かれた貿易・投資を実現するとの目標)達成評価の見込み,交渉ではなく協力を中心とした枠組みの意義,APECと東アジア共同体構想との関連,APECの活動の合理化の必要性,尖閣諸島の事案がAPECに及ぼす影響を始めとした多くの論点について,活発な質問や意見が寄せられました。
最後に,日本が今後の経済成長を図る上で,アジア太平洋との協力の深化が必要であり,APECを活用して我が国が地域におけるイニシアティブを発揮することが大切とのまとめを行いました。
<参加者の感想>
- APECの存在意義や日本の取組が理解できました。11月の日本APECに注目していきたいと思います。
最後に
今回の「外務省セミナー『学生と語る』」には190名を超える応募がありました。会場の都合により残念ながらご参加頂けなかった方々には深くお詫び申し上げます。
ご参加頂いた方々のアンケートでは,参加して良かったという感想をはじめ分科会テーマ,議論の進め方などについて様々なご意見,ご提案をいただきました。アンケートに寄せられたご意見,ご提案を参考に本事業をさらに充実・発展させて参りたいと思います。
今回,本事業の広報活動にご協力いただきました各大学,大学院,予備校等の教育機関の教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。
