平成21年度第3回「外務省セミナー『学生と語る』」
~結果報告~
平成22年2月
平成21年12月22日(火曜日)、外務省において平成21年度第3回「外務省セミナー『学生と語る』」を開催いたしました。
当日のプログラムとその様子について、アンケートにご協力をいただいた参加者の感想を引用しつつ、紹介します。
1.全体講演
開会挨拶
(大臣官房 国内広報課 佐久間研二課長)
基調講演「日本外交の現状と展望」(13時35分~14時45分)
(総合外交政策局 総務課 加納雄大外交政策調整官)

加納調整官は本年を振り返り、自身が直接関わった業務では 1)4月のパキスタン支援国会合の開催、2)5~6月の北朝鮮の核実験を受けた新たな安保理制裁決議の採択、3)先般の気候変動枠組条約締約国会議(COP15)が特に印象深かったと語った後、日本における大きな節目であった今年の政権交代は、日本外交にも少なからぬインパクトを与えたと解説しました。具体的分野として日米同盟、アフガニスタン・パキスタン支援(インド洋での給油支援を含む)、気候変動、核軍縮・不拡散への取組などの現状について詳しく説明しました。さらに明年の日本外交の主要課題として、1)昨年来続く世界経済危機への対応(G20の取組など)、2)日米安保改定50周年を迎える日米関係、3)東アジア情勢(北朝鮮、中国、インド、オーストラリア、東南アジア等)、4)グローバルな課題(気候変動、核軍縮・不拡散、開発援助)、5)新たな課題の解決のための国際的枠組み構築を巡る議論(G8/G20、安保理改革、東アジア共同体など)と日本の取り組みについて解説しました。最後に講師自身の外交官としての体験から、問題と解答が予め決まっている学生時代の試験とは異なり、現実の社会では何が問題なのかを特定するところから始めなくてはならない、国際社会が取り組むべき問題を「発見」して世界に「提示」し、更にそうした問題を「解決」する方策を示す能力を磨くことが必要だと学生にアドバイスしました。
<参加者の感想>
- 現在の外交政策の全体図が聞けた。今後日本がどう外交政策をとって世界と向き合っていくのか自分なりに考えるいい機会となった。
「省員による体験談」(14時45分~15時25分)
(大臣官房人事課 吉廣朋子課長補佐)

初めに外務省の組織と業務について概説した後、講師自身の体験を通して、入省してからのキャリアアップについて説明しました。続いて外交官の仕事の魅力・面白さについて、講師が体験した具体的な業務の事例を紹介しながら 1)自分の可能性を最大限試すことができる職場 2)日本のために、日本を背負う気概で粉骨砕身できる場 3)多様な現場と様々なツールが存在するという3点についてわかりやすく説明。最後に外交官になるための試験について解説しました。
<参加者の感想>
- 外務省を志したきっかけから外交官のやりがいまで話していただき、「外務省に入ったらどのように働くのだろう」というイメージが具体化できた。
2.分科会
(15時40分~17時40分)
全体講演終了後、6つの会場に分かれて分科会が行われました。各分科会では、外務省員によるプレゼンテーション、質疑応答、参加者によるディスカッションが行われました。
「アジア太平洋経済協力」
(経済局 アジア太平洋経済協力室 網谷耕介課長補佐)

冒頭、APECの経済外交上の意義を説明するとともに、特に2010年日本がAPECの議長年であることを念頭に日本APEC開催の意義、課題について説明しました。そして、1989年に設立されたAPECが2010年には節目の年を迎えること、この年に日本が「チェンジ・アンド・アクション」のテーマを掲げて、積極的にAPECの議論を主導することについて紹介しました。この分科会では、「2010年APECを成功させるためにはどうしたらいいか」について参加者の学生一人一人に主体的に考えてもらい、自由に議論してもらうこととしました。実際、APEC首脳会議で扱うべき政策課題から、APEC広報のあり方、あるいは首脳会議の集合写真のイメージに到るまで、きわめて実践的かつ示唆に満ちた提言が出され、政策担当者にとっても有益な意見交換の機会となりました。
<参加者の感想>
- APECの体制がよく理解できた。2010日本APECの動向をニュースや報道で追いたい。
「核・軍縮」
(軍縮不拡散・科学部 軍備管理軍縮課 望月千洋課長補佐)

本年5月のNPT運用検討会議を控え、世界的な核軍縮の気運が盛り上がる中、我が国が戦後一貫して積極的に取り組み、日本外交の柱の一つをなしてきている核軍縮について、核をめぐる現状やNPTを基礎とした国際的核軍縮・不拡散体制とそこにおける対立構造、我が国の核軍縮外交の考え方や具体的取組を中心に、核不拡散や原子力の平和的利用にも言及しながら、説明しました。
この分科会では、随時、参加者に自由な発言や意見を求めながら、双方向で実施したところ、我が国を取り巻く安全保障環境と核軍縮のバランス、核兵器廃絶に向けた具体的方法、日本ができることとできないこと等様々な質問及び意見が多数寄せられました。
<参加者の感想>
- 核・軍縮の世界的な流れを知ることができ大変良かった。
「国連外交」
(総合外交政策局 国連政策課 佐藤美奈事務官)

日本外交の重要課題である安保理改革について、安保理の権能、安保理が国連の中でもなぜとりわけ重要な機関とされるのか、なぜ安保理改革が必要なのか等を概観した後、安保理改革の機運が高まった2005年当時の日本外交の攻勢及びなぜ最終的に改革案が採択に至らなかったのかという理 由、その後の国連での動き、安保理改革に関する各地域グループの主張などを説明しました。
この分科会では、質問タイムを設けた後参加者同士で討論してもらうことを想定していましたが、そうした時間が取れない程、参加者から講師に対する質問が積極的になされました。具体的には、日本は常任理事国としてどのような役割を果たすべきか、安保理改革実現のために日本はどの様な戦略で臨んでいるのか、本来の任務を果たし切れていない安保理の存在をそもそもどう考えるのか、各地域グループの主張の違い等について、非常に積極的かつ鋭い質問・意見が寄せられました。
<参加者の感想>
- 国連がそれぞれの国の利害や思惑がぶつかり合う外交の最前線だと理解できた。
「ODA」
(国際協力局 開発協力企画室 足立秀彰課長補佐)
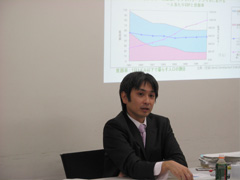
ODAの定義や日本のODAの概要・歴史などの基礎的な事項について簡単に説明した後、日本のODAの特徴(日本の知見・技術の伝達、無償・有償・技協の連携、民間企業との連携)、ODA政策の枠組みと実施体制(国際協力局の機構改革)、ODA予算の現状について説明しました。また、最近の主な取り組みとして、官民連携や気候変動について触れつつ、途上国の開発のためには、ODAと民間資金との連携が重要である旨説明しました。その後の質疑応答では、ODAのあり方や官民連携など、ODAに関する様々な質問や意見が活発に出されました。
<参加者の感想>
- ODAの意義、日本の立場、考えなど外務省としての意見が新鮮だった。
「在日外国人問題」
(領事局 外国人課 藤田小織課長補佐)

分科会では、「在日外国人問題の現状と課題」として、出入国管理及び難民認定法と在留資格、外務省設置法、南米日系人の雇用環境、子弟の不就学等の問題、研修・技能実習制度における不適正な事例と新しい研修・技能実習制度、人身取引問題、外国人問題に関する政策決定等政府の方針について説明し、最後に入管法改正による新しい在留管理制度の導入と研修・技能実習制度の見直しについて説明しました。質疑応答では、難民の第三国定住受入れでは人道的見地からハンディキャップがある者も受け入れるべきである、ミャンマー人以外の国籍者も難民として認定すべきである、との意見や、在留外国人の外国人登録証明書等の常時携帯義務の是非、外国人の日本語能力要件など様々な論点について、鋭い質問が多数寄せられました。
<参加者の感想>
- 在日外国人問題のバランスのとれた知識を得ることができた。
「資源外交」
(経済局 経済安全保障課 井上隼一課長補佐)

冒頭、エネルギー・鉱物・食料といった資源の確保が我が国の対外関係上いかに重要であるかについて、歴史的経緯や官民の役割分担の観点から説明しました。次に、政府が行っている取組について、世界全体の資源問題の解決に貢献することがひいては我が国の資源安全保障に繋がるということを強調しつつ説明しました。その上で、参加者とともに「資源外交」という言葉についても批判的に考えることによって、総合的・多面的な外交政策の必要性、資源国との互恵関係の構築の重要性を共有しました。更に、レアメタルを例にとり、資源国との二国間関係のあり方について外交政策シミュレーションを行いました。参加者はこれに積極的に取り組み、日本が有する様々な外交ツール、WTO等の多国間枠組み等を活用していかなる戦略的関係を構築すべきかについて、活発な意見交換が行われました。
<参加者の感想>
- シミュレーションが大変に面白かった。どういった決断をすればどこに影響が出るかという点を考えることが難しくもあり、楽しくもあった。
3.懇親会
(18時10分~19時40分)
分科会終了後に行われた懇親会には、参加者に加え兒玉外務報道官をはじめ基調講演及び分科会講師、入省1年目の若手省員など50名近くの外務省員が参加しました。参加学生と外務省員が熱心に語り合う姿が会場の随所に見られました。
その様子については下記の写真をご覧下さい。
最後に
今回の「外務省セミナー『学生と語る』」には200名以上の応募がありました。会場の都合により残念ながらご参加頂けなかった方々には深くお詫び申し上げます。
ご参加頂いた方々のアンケートでは、参加して良かったという感想をはじめ分科会テーマ、議論の進め方などについて様々なご意見、ご提案をいただきました。アンケートに寄せられたご意見、ご提案を参考に本事業をさらに充実・発展させて参りたいと思います。
今回、本事業の広報活動にご協力いただきました各大学、大学院、予備校等の教育機関の教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。



