ベトナム
面積:330,363平方km、人口:7,633万人(1999)
名目GNP:31.3百万ドル(2000)
一人当たりGNP:350ドル (1998) |
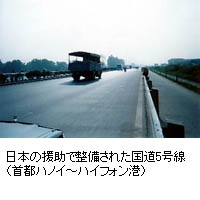
(クリックすると画像が変わります)
|
2.ベトナムへの援助実績:
1992年から1999年までの日本の対ベトナムODA援助累計額は、有償・無償・技術協力を合わせて6,910.28億円である。日本は、ベトナムの道路、港湾、鉄道、発電所、病院、小学校、大学、農業、その他人材育成などの援助を行なっており、ベトナムへの援助総額のうち48%が日本からの援助であった(1999年)。これは、同国の財政支出の10%あまりが日本からの援助によって賄われたことになる。 |
3.評価調査団:
佐々木 亮 (財)国際開発センター 研究員(総括)
小川 政道 (財)国際開発センター 主任研究員
神事 直人 (財)国際開発センター 研究員
栗木 レタンギェップ 城西国際大学教授(外務省委託有識者)
若井 晋 東京大学教授(外務省委託有識者) |
| 4.調査実施期間:2001年11月9日~2002年3月15日 |
5.評価の目的:
日本がこれまで実施した対ベトナムODAの効果を総合的に分析するとともに、今後の対ベトナムODAのさらなる改善のための提言を行う。 |
6.評価結果:
| (1) |
日本の援助は、それぞれの分野で高い効果を発揮しており、ベトナム政府からも高く評価されていることがわかった。特に、「市場経済化支援開発政策調査」(通称「石川プロジェクト」)や「経済改革支援借款」(いわゆる「新宮沢構想」の延長線上の支援)などの政策支援は、我が国初の試みであったが、前者はベトナムの5カ年国家開発計画(2001-2005年)に活かされているほか、後者は投資や貿易を促進するための制度構築や市場環境の改善に大いに貢献したとして評価されている。 |
| (2) |
日本は、円借款により道路、港湾、鉄道、発電所などの経済インフラの整備に重点を置いて援助を実施してきた。発電に関しては、過去10年間の発電能力の伸びの38%が日本の援助によって実現した。また、首都ハノイと主要港湾を結ぶ国道5号線の整備(首都ハノイと北部の最重要港ハイフォン港を結ぶ約100キロの道路で、以前の5時間の所要時間が1.5~2時間程度に短縮されたとのこと)、ハノイと南部の商業都市ホーチミンを結ぶ国道1号線の整備、ホーチミンにおける東西道路など、ベトナムの主要な幹線道路が日本の援助によって整備されている(一部整備中)。これらはベトナムの物流を大幅に改善し、同国の急激な経済発展に貢献し、また今後貢献度合が高まっていくものと評価されている。 |
| (3) |
ハノイ、ホーチミンという南北の中心都市におけるナショナル・レベルの病院整備、台風の被害を受けていた200件近くの小学校整備、情報処理センターでのIT研修、農業分野における大学レベルでの技術支援などを含む個別の援助案件も、それぞれ所期の効果をあげていることが確認された。 |
|
7.提言(今後のフォローアップ、改善すべき点等):
| (1) |
ベトナムでは、他の援助国による「援助協調」の動きが活発化している。ベトナム政府のオーナーシップにより、ドナー、国民との協議を通じて、セクターごとに開発戦略・政策を策定し、協調して実施する援助協調の動きとともに、欧州6カ国(英、蘭、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、スイス)主導による援助手続調和化に関する議論が活発化しているが、日本としてもこうした動きに、より積極的に対応することが必要である。他方、ベトナムには、インフラ整備をはじめとした莫大な援助需要があり、トップ・ドナーである日本は、個別の援助案件について従来通りベトナム政府と協議して、独自に継続的な援助を行なっていくべき。(「顔の見える援助」の継続・拡充)。 |
| (2) |
上記の「援助協調プラス個別案件支援」を効率的に実施するために、外務本省から大使館へ、JICA・JBICなど実施機関本部から現地事務所への、より一層の権限の委譲を行なうべきである。具体的には、2000年に策定・公表された「対ベトナム国別援助計画」の見直しも、現地のJICA・JBIC事務所の協力を得て大使館が主導して行なうことを提案する。さらに、現地で、援助国の代表者が一同に介して議論し、その場である程度の意思決定がなされることが増えており、日本もこうした現地会合の場で意思決定ができるような権限の委譲も必要である。また、他の援助機関との協議を緊密にこなすため、各現地事務所の人員の強化も必要である。(いわば「フロント・ラインの強化」) |
| (3) |
一方で、日本の援助全体に関わる政策の変更については、外務省本省で決定し、各大使館へ明確に通知されていないように見受けられる。政策や統一方針の決定と現場への通知を徹底することによって、日本が援助を供与している途上国全体での統一的な援助目的及び援助政策の実現を確保する必要がある。 |
| (4) |
円借款案件の実施面において、日本による援助実施の決定後、ベトナム側による事業の実施に遅れが見られた場合があることを指摘せねばならない。特に、道路や発電所案件などでこの傾向が見られた。すみやかな実施をベトナム政府側に求めていかねばならない。 |
|
8.外務省の一言:
| (1) |
国別援助計画の策定にあたり、大使館が主導してドラフトを作成することとしており、本提言の趣旨に合致したものとなっている。 |
| (2) |
政策や統一方針の決定と現場への通知を徹底すべきとの提言については、例えば、外務省本省で援助協調に関する統一的な考え方を決定し、それを各大使館へ通知するなどしており、本提言に沿った形で援助が実施されつつあると言える。 |
|
