ベトナム・ゲアン省
リプロダクティブヘルスプロジェクト
|
1.評価対象プロジェクト: リプロダクティブヘルスプロジェクト |
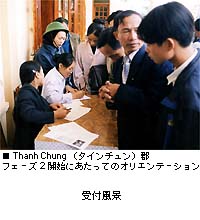
(クリックすると画像が変わります) |
||||
| 2.国名:ベトナム国 実施機関名:ゲアン省人民委員会 | |||||
|
3.援助形態 プロジェクト方式技術協力
|
|||||
| 4.評価実施機関名:在ベトナム大使館 | |||||
|
5.現地調査実施期間: 2001年03月08日~2001年03月10日 |
|||||
| 6.プロジェクト、プログラムの分野:保健・医療 | |||||
|
7.政策目的又は政策の方向性: 日本政府は人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティブを1994年に発表し、人口、リプロダクティブヘルスをODAの重点課題の一つとして位置づけている。また、2000年6月に発表されたベトナム国別援助計画においても、「プライマリーヘルスケア(PHC)を中心とした保健医療サービスの山岳部等を含めた全国的な拡充が当面の急務」としている。 | |||||
|
8.当該プロジェクトの目的: 貧困且つ助産婦が少ない中北部のゲアン省(1市1町17郡の内8郡)をモデル地域として村レベルで妊産婦ケアと保健サービスの向上を図ることを目的とする。 また、2000年9月に開始されたフェーズIIでは、対象地域がゲアン省全域に拡大された。 | |||||
|
9.評価結果: このプロジェクトのフェーズIは、「安全な出産のための環境づくり」として助産婦を対象とした技術協力を中心としている。具体的には、(1)258人の助産婦・準医師に対する1ヶ月研修の実施と、専門家による140以上の村に対する直接訪問によるモニタリングの実施、(2)延べ6,000人以上の女性連合メンバーと村の指導者等に対する研修の実施、(3)244のコミューン(村)の全ての保健センターに対し、機材の供与、施設の改善(うち148は草の根無償による改修)の実施等である。 フェーズIの評価としては、JICA専門家の献身的な活動が実を結び、PDM(プロジェクト・デザイン・マトリックス)(注)で設定されていた指標は多くの項目で達成された。例えば、妊婦1人あたりの検診受診回数は目標の3回を上回る3.3回に達し、全出産のうちコミューンヘルスセンターで出産する割合も、96年の59.5%から98年には81.1%へと向上した。(別表参照) 現在、プロジェクトのフェーズIIが継続中であり、「産前産後のケアも含めたヘルスプロモーション」を視野に入れ、助産婦教育をより一層推進するとともに、住民啓発をも含んだ内容で協力を展開している。(対象地域はゲアン省全域。) 今回の評価にあわせてタインチュン郡で開かれたワークショップ(フェースIIの内容を説明する一連のキックオフミーティング)に参加したところ、各コミューンの人民委員会・女性連合・コミューンヘルスセンター所長等の越側参加者から、本プロジェクトに対する意欲が伺われ、フェーズIで培われた相互の信頼関係が強固なことが確認できた。 | |||||
10.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点、政策的な観点からの提言):
| |||||
|
11.外務省からの一言: 本プロジェクトは、2000年9月よりフェーズ2を対象地域(ゲアン省全体)を拡大して継続中であるが、提言にもある通り、本省としても今後とも各援助スキームの連携を図る等、より効果的、効率的な援助の実施に努めていきたい。 | |||||
|
注:プロジェクト・デザイン・マトリックス:
1.PDMの起源であるロジカル・フレーム(通称ログフレーム)は、より効果的なプロジェクトの計画・実施のために、プロジェクトの運営・管理を容易にする手法として、60年代に米国開発庁(USAID)により開発されたものである。PDMはプロジェクトの目標や、成果、投入、外部条件等、プロジェクトの主要な要素とそれらの関係を簡潔に整理した一覧表であり、ログフレームとほぼ同様のものである。プロジェクトの概要が一目で分かり、計画から実施評価までの管理に便利なことから、国際機関に広まり、80年代には、ドイツ技術協力公社がログフレームをさらに発展させたZOPPと呼ばれる手法を開発した。 日本でも、90年代に入り、ZOPPをさらに発展させたプロジェクト・サイクル・マネージメイト(PCM)手法を開発した。PCMは、PDMを利用することにより、プロジェクト・サイクルの中で、計画立案から実施、評価に至までの一貫性の確保や関係者の共通認識の共有などを可能にするものである。JICAでは、94年より、効率のよい運営管理のため、同手法を取り入れている。 |
| 成 果 | 達成度(プロジェクト対象8郡) | |
| 1. | 妊婦1人あたりの妊婦検診受診回数が3回以上 | 達成されている。平均3.3回. |
| 2. | 妊産婦検診を受けた妊婦が95%に達する | 96年からの4年間で82.5%、86.9%、91.9%、88.2%と増加傾向にあるが、さらに時間を要する。 |
| 3. | コミューンヘスルスセンターでの出産が全出産の85%に達する | おおむね達成されている。96年の59.5%から、98年には81.1%に上昇した。 |
| 4. | 婦人科検診を受ける女性の数が96年から2000年までの間、年間2.5%ずつ増加する | 達成されている。96年からの年間増加率は19.1%、7.6%であり、目標を大きく上回っている。 |
| 5. | CBR(出生率)が減少する | 達成されている。96年の22.1人口千対から、99年6月時点で は9.4人口千対と、顕著な減少が見られる。 |
| 6. | 破傷風予防接種を2回受けた妊婦の数が96年から2000年まで年間2%増加する | 年間増加率の平均は0.87%であるが、今後、継続的な努力により目標の達成は可能。 |
| 7. | MRを含む中絶の件数が96年から2000年まで年間6%ずつ減少する | MRのデータが十分になく判定困難。 |
| 8. | 近代的避妊方法の普及率が96年から2000年まで年間3%ずつ増加する | 達成されている。96年の66.3%から99年6月には77.8%に増加し、年間増加率の平均は3.83%であった。 |
| 出典: |
リプロダクティブヘルスプロジェクト終了時評価報告書 (平成12年2月、国際協力事業団) |

