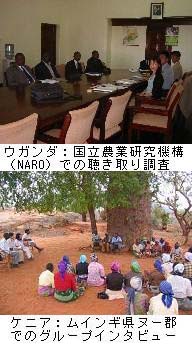「TICADプロセスを通じた対アフリカ支援の取り組み」の評価
(重点課題別評価)
| 1.テーマ:TICADプロセスを通じた対アフリカ支援の取り組み (重点課題別評価) |
|
|
2.調査対象国:アフリカ53か国 現地調査国:ウガンダ及びケニア |
|
|
3.評価チーム: (1)評価主任:望月 克哉 (アジア経済研究所新領域研究センター専任調査役) (2)アドバイザー: 斎藤 文彦(龍谷大学国際文化学部教授) 壽賀 一仁(日本国際ボランティアセンター事務局次長) (3)コンサルタント: みずほ情報総研株式会社 |
|
| 4.調査実施期間:2007年8月~2008年3月 | |
|
5.評価方針 (1)目的 2008年に開催される第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)以降のTICADプロセスの有意性を更に高め、今後の我が国の「対アフリカODA政策」像を導き出すための教訓や提言を得ること、また、評価結果を公表することで国民への説明責任を果たすことを主要な目的として、これまでにTICADプロセスを通じて行われてきた支援策の効果について総合的なレビューを行った。 (2)対象・時期 総論における評価対象は、日本がTICAD II及びIIIのフォローアップとして特に掲げた政策の枠組み(柱立て)及び例として挙げられた施策・事業とした。ケース・スタディにおいては、当該国に対する日本の支援一般とする。評価時期は基本的に2000~2006年とした。 (3)方法 政策の妥当性、結果の有効性、プロセスの適切性の3つの視点から評価を行った。評価にあたっては、文献調査、国内でのインタビュー調査に加え、ウガンダとケニアにおける現地調査でインタビュー調査及び資料収集を行った。 |
|
|
6.評価結果 (1)「政策の妥当性」に関する評価
TICADプロセスを通じた日本の対アフリカ支援と、その国際的上位枠組みと位置付けられるミレニアム開発目標(MDGs)、TICAD東京行動計画、TICAD 10周年宣言、TICAD III議長サマリーとの整合性はおおむね確保されており、この点において政策は妥当であると評価された。しかし、MDGsや東京行動計画が掲げているジェンダー及び環境の2分野に関しては、整合性が特に見出されなかった。また、TICAD III議長サマリーについては、「市民社会との対話」という開発課題に対する配慮が明確ではなかった。 (2)「結果の有効性」に関する評価
日本の対アフリカODAは、サブサハラ・アフリカ向けの贈与を中心に2004年から急速に拡大しており、世界の対アフリカ支援における地位も回復しつつある。2004年以降の贈与の6~8割は債務救済であるが、2003年のTICAD IIIで掲げた日本の対アフリカ支援の主要素に「債務救済」があることを踏まえれば、TICADプロセスを通じた日本の対アフリカ支援は、債務救済という結果には有効に結実していると評価できる。また、債務救済以外の贈与額も2006年には2割増となっており、一定の評価はできよう。ただ、TICADプロセスが1990年代から続いていることを考えれば、ODA投入増加という結果が出たのは遅かったといえる。 (3)「プロセスの適切性」に関する評価
日本の支援プロセスにおける相手国政府との協議・調整については、ケース・スタディ国から高い評価がなされており、おおむね適切であると考えられる。日本の特徴である準備・交渉期間が長い点は、後のスムーズな事業実施につながっているとして高く評価されることが多いが、支援の「速さ」に問題があると捉える向きもある。 |
|
|
7.提言 (1)フォローアップされていない開発課題に取り組む必要性 TICADプロセスを通じた日本の対アフリカ支援は、国際的上位枠組みとの間で、ジェンダー、環境、市民社会との対話といった横断的課題では整合性が確認できなかった。これらの課題は、TICAD IVに向けて国連諸機関がとっている「クラスター・アプローチ」においても、クラスターないし分野横断的問題として挙げられている重要なものであり、日本は今後、これらへの取組を明確に打ち出すべきである。 (2) 包括的・総体的な支援を一層推進する必要性
日本の支援は、特に保健・医療分野等において、無償資金協力によるインフラ支援、技術プロジェクトおよび青年海外協力隊やシニア・ボランティアによる現場への技術移転・人材育成のための支援というスキーム連携による「包括的な支援」の有効性を示唆している。欧米米ドナーがあまり注力しないインフラの供与は日本の対アフリカ支援における比較優位点であり、これを活かした包括的支援を一層推進していくことが望ましい。 (3) MDGsを一層念頭において支援を展開する必要性
アフリカにおけるMDG指標の変化は、全体としては一応改善の方向にあるものの、ほとんどすべての指標において改善度合いはまったく不十分であり、指標によっては悪化している国も相当程度に存在している。基礎的な社会ニーズに関わるアウトプット指標を短中期的に改善することは極めて困難であるし、それに対し日本の貢献の度合いを検証することは原理的に不可能であるが、MDG指標の改善という目に見える結果に繋がるような支援を積極的に設計し実施していくことは、MDGsの重要性に鑑みれば是非とも必要である。 (4) 貿易投資振興や経済成長を実効的に支援する必要性 TICADプロセスに対し、経済成長や、それをもたらす貿易投資振興といった、具体的・実際的な「果実」を求める声は多い。人材育成やインフラ建設といった経済基盤の整備も、実際の経済成長を伴うものとなれば、一層説得的なものとなる。この点を踏まえれば、経済成長や貿易投資振興について顕在的かつ相当程度の結果をもたらすような支援のあり方が模索されることが望まれる。経済成長をもたらすためには然るべき投入が必要であり、その観点から、プレッジング会合ではないというTICADの基本的性格を見直すことも一案である。 (5) 教育における「量」と「質」の両立に注力する必要性 アフリカの教育においては、就学率では一定の改善が見られるが、進級率の改善は芳しくなく、また女性のドロップアウト率は男性に比べ依然高い。単純な就学率で測られる教育の「量」だけでなく、進級率やその男女比で測られる教育の「質」について、有効な結果をもたらすような支援のあり方を模索することが望まれる。初等教育で「万人のための教育」が一定の成果をあげつつある現状において、「質」を伴った「量」の確保こそが求められている。 (6) 南南協力を一層推進する必要性 対アフリカ支援における南南協力は、農業、保健医療、教育・人材育成等の分野で援助プロセスとしての適切性を示しており、今後は一層、TICADプロセスを通じて、日本が個別の国に対して行っている同分野の支援を互いに連携させる南南協力を、明確かつ具体的に推進するべきである。南南協力は、担当者同士の知人関係といった偶発的・属人的な要素に依存して発展することがあるが、そうではなく意識的に協力を創り出していく仕組みを作るべきである。 (7) 他ドナーとの連携を一層推進する必要性 TICADプロセスを通じて日本が対アフリカ支援の枠組を強く打ち出したことが、「ドナーとしての日本」を世界に印象付け、日本と他ドナーとの連携を促進したという事象が、農業や保健医療等の分野で観察された。日本において、ODA予算の確保が厳しくなっている中では特に、こうした国際機関や他のドナー国との連携は、非常に有効なものとなる。国連や世界銀行等が共催者であり、多くの国際機関やドナー国も参加するTICADプロセスを通じて、日本と他ドナーとの連携を図ることは、TICADプロセスないしTICAD会合の重要な役割として、今後も一層推進していくべきである。 (8) スキーム連携を一層推進する必要性 TICADプロセスが契機となり、日本の援助においてスキーム連携が進んだ例も、保健医療分野で見られた。このようなスキーム連携も、援助プロセスの適切性という観点から一層推進すべきであり、その触媒としてTICADプロセスないしTICAD会合を大いに活用すべきである。 |
|
注)ここに記載されている内容は評価実施者の見解であり、政府の立場や見解を反映するものではありません。