1.評価対象プロジェクト名:
エイズ予防地域ケアネットワークプロジェクト
|
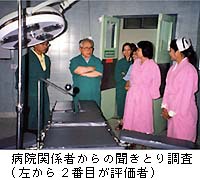
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:タイ |
3. 援助形態:
技術協力、98~2003年、専門家派遣25名 |
|
4.評価者:佐藤喜一 黒部温泉病院院長
|
|
5.現地調査実施期間:2000年10月27~31日
|
|
6. プロジェクトの分野:保健・医療(感染症) |
7.プロジェクトの目的:
国家レベルでのエイズ対策に適応するエイズ予防及び地域ケアに係る継続的・包括的な実施モデルの開発と普及。
|
8.評価結果:
| (1) |
99年末時点でのタイのHIV/エイズ感染者数・患者数は75.5万人、成人感染率は2.15%(UNAIDS報告)となっている。その中でもパヤオ県を中心とする北部はタイ国内においても特にHIV/エイズ感染者数・患者数の多い地域となっており、エイズ対策に対する支援を実施するにあたっての地域の選定は妥当であった。 |
| (2) |
エイズ問題への対応は多くの問題が関わるだけに困難であるにもかかわらず、派遣されたJICA専門家が積極的に活躍していることが大変印象的だった。また、JICA専門家の努力により、衛生局長の信頼を得た結果、プロジェクトの実施が容易になっており、現地職員やNGOスタッフとの協力も得て順調に進んでいる。 |
| (3) |
主な予防対策は、タイ側によるコンドームの配布と啓蒙活動、HIV検査、母子感染予防などである。
| (イ) |
母子感染予防措置として行われている出産前後の薬剤の投与と母乳からの感染を防ぐための粉ミルクの投与が成果をあげており、感染率は7%まで抑えられている。 |
| (ロ) |
エイズ患者の多くが周囲から差別されることをおそれて隠していることが、エイズ患者支援活動とエイズ感染予防の妨げになっている。 |
| (ハ) |
タイ側が、コンドーム100%キャンペーンなどでコンドームの配布と啓蒙活動を行った結果、売春婦からの感染が減少した一方で、夫婦間でのコンドームの使用が信頼問題であるとの認識から夫婦や恋人間での感染が相対的に増加していることへの対応が必要となっている。 |
|
| (4) |
主なエイズ患者のケアは、結核発症予防、日和見感染症の治療、カウンセリングなどである。
| (イ) |
タイ側によりデイ・ケア・センターを活動の中心としてエイズ患者に対する情報の提供やカウンセリングなどの支援が行われ、成果を上げてい る。 |
| (ロ) |
エイズ患者のほとんどが20代~30代の働き手であることから患者を含む家族が経済的困難を抱えている。デイ・ケア・センターを中心に手芸や小物造りなど患者の所得向上のための支援が行われているが、必ずしも十分とは言えない。また、孤児に対する支援も必要となっている。 |
|
|
9.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):
| (1) |
専門家などの関係者は、地域に密着しつつ順調に目的を果たしているが、エイズに関連する多くの問題への対応が必要であることから、引き続き支援を継続する必要がある。
|
| (2) |
今後は患者及び家族の生活向上や孤児に対する支援も重要であり、短期・長期的視点からの収入向上に向けた支援も必要である。その為には、NGOや他のJICAプロジェクトと連携が不可欠である。
|
| (3) |
技術協力は、「顔の見える経済協力」として友情と信頼関係の育成に効果があり、その観点からも、日本もNGO等との連携を進めるとともに、エイズに関する情報の提供やカウンセリングなど、草の根レベルでのエイズ患者支援を拡充することが望まれる。
|
| (4) |
エイズ患者が結核を併発する症例が多くなっている。結核の治療を担う専門家の派遣も検討すべき時期に来ている。
|
| (5) |
草の根レベルのフィールド活動には、移動手段が不可欠である。車両など移動手段を十分に確保することも大切である。 |
|
10.外務省からの一言:
| (1) |
「沖縄感染症対策イニシアティブ」としてHIV/エイズ対策を重視しており、特にタイの予防啓発を中心とする政策に注目している。その中で、このプロジェクトは日本のHIV/エイズ対策支援の範となるべきものであり、他国への普及をも念頭に、一層の改善に向け努力していきたい。 |
| (2) |
エイズの分野で専門家派遣事業が効果を生んでいることが評価されたことは、嬉しい。専門家が現地の担当者やNGOと協力して活躍しており、「顔の見える経済協力」と言えよう。今後もこの様な技術支援を継続・強化したい。
|
|
