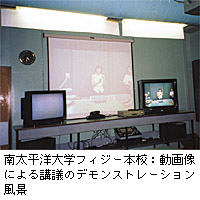1.評価対象:
| (1) |
南太平洋大学通信体系改善計画(フィジー) |
| 平成10年度 2.98億円 一般無償 |
| (2) |
南太平洋大学通信体系改善計画(サモア) |
| 平成10年度 0.67億円 一般無償 |
|
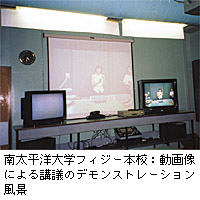
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:フィジー、サモア
|
3.評価者
小林 泉 大阪学院大学教授
|
|
4.現地調査実施期間:2001年3月16日~21日
|
5.プロジェクトの目的:
太平洋地域12カ国が加盟する国際機関大学である南太平洋大学(本校・在フィジー)では、加盟諸国に所在する分校あるいは大学センターへの遠隔教育を、短波回線や国際商業電話回線を通じた音声により行ってきたが、機材の老朽化や衛星回線使用料の問題から効率的で円滑な遠隔教育の実施に支障が出ていたため、衛星による専用回線への切り替え、映像画面の送受信機能の付加等、通信機能の質量両面に亘る改善・拡充を図る。
なお、南太平洋大学通信体系改善計画は、裨益国12カ国、援助側を日、豪州、ニュージーランドの3カ国とする共同協力案件であり、フィジー・サモアに加え、日本は、トンガ、ツバル、ソロモン、マーシャルに、豪州は、バヌアツ、キリバスに、ニュージーランドは、クック、ニウエ、トケラウ、ナウルに支援を行った。別表参照
|
6.評価結果:
| (1) |
これらプロジェクトは計画通りに実施され、従来の音声による遠隔教育のハード面について質的向上が見られると共に、これまでになかった映像画面を伴う本校と分校間の相互通信が可能になった。これにより、遠隔教育の効率化が一気に進むと共に、画面を通じての理系実験科目の実施や討論、会議等、これまでできなかった分野でのコミュニケーションのシステムが確立された。 |
| (2) |
2000年5月に起こったフィジーの国会占拠事件に端を発する社会不安により、フィジー本校への留学生が帰国するという事態が発生した。その際、本施設、機材の効力が発揮され、中断された講義や学習指導が帰国地の分校あるいは大学センターを通じて遠隔教育されたため、帰国学生のすべてが所定の期間内に予定カリキュラムを消化した。今回視察したフィジー本校・ハブ局およびサモア校・ミニハブ局の供与施設・機材は、視察時に休眠状態にあったものはなく、いずれもフル稼働しており、利用状況は良好であった。 |
| (3) |
以上により、これらプロジェクトは、援助要請目的が十分に達成された成功事例として、高く評価できる。また、二国間援助を基本とする我が国の無償援助スキームの中で、国際共有組織(南太平洋大学)に対して、しかも、豪州、ニュージーランドとの協調プロジェクトとして援助が実現したことは、極めて特筆に値する。極小諸国が散在する太平洋地域の特殊性に鑑み、こうした地域事情に対応した柔軟な援助方式が、今後の援助案件を検討する際にも十分取り入れられることを期待したい。 |
|
7.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):
| (1) |
これらのプロジェクトは、国際機関への援助を他の援助国と共同で実施したが、極小諸国が散在する太平洋島嶼国地域の特殊性に鑑み、今後の援助案件を検討する際にも、地域事情に対応した柔軟な援助方式が十分取り入れられることを期待する。 |
| (2) |
太平洋島嶼国地域への援助に当たっては、次の二点を十分考慮してほしい。 |
| (イ) |
本件プロジェクトにおいて、最新の施設と機器類を供与したにもかかわらず、テレビのように完全動画が常に送信されないので講義科目が限定される、語学教育を行うには音声が不明瞭である等、現時点で技術的には種々制約がある。そういう状況の中で、教授陣、受講者の双方が新たな施設・技術の利用に慣れるまでにある程度の時間を要する一方、技術的な問題は技術の進歩によって解決され、その結果、供与した施設や機器類は陳腐化する。
供与後の機材の老朽化への対応については従来指摘があるが、IT関連機材は、技術の先進性、進歩の急速性の故に、老朽化する以前に陳腐化するものであり、その時点で最新技術と機器類が求められる。しかし、途上国の自助努力では実際上対応は困難で、陳腐化した供与施設や機器類を放置すれば、我が国援助に対する不評や批判が強まる可能性は高い。大洋州・島サミットにおいて、日本側のイニシアティブの一つとして大洋州IT推進プロジェクトの実施が挙げられているが、IT関連援助については、我が国は、技術の進歩に伴った技術や機材の継続的な供与の可否を含めて、対応振りを用意しておく必要がある。 |
| (ロ) |
南太平洋大学は、島嶼諸国の協調や連帯という理想を推進させる実施機関として、またそのシンボルとして位置づけられているが、他方、島嶼諸国がナショナリズムを競い合う現実のなかで、独自の大学設置を望む国がある。国立サモア大学がその事例で、我が国は両大学への援助を実施している。そのため、地域連帯の方向性を支持しているのか、それに反するかのように見える独自行動を支援しているのか、援助意図は極めて不明確であると思われる。それゆえ、援助している我が国の援助意図は何処にあるのか、はっきりとした答えを用意しておくべきであろう。さもないと、被援助国に評価されても、他の諸国からは反地域連帯行為としてマイナス評価になるか、あるいは各国から大学創設への援助要請を受け、その全てに対応しなければならないといった可能性がある。 |
|
8.外務省からの一言:
| (1) |
本件プロジェクトは、地域事情に鑑みて他の援助国との共同で実施したが、今後も、御指摘の通り、太平洋島嶼国地域の特殊性に対応した柔軟な援助方式を検討していきたい。 |
| (2) |
南太平洋大学に対する協力は、この地域の遠隔・広域教育の拠点として今後とも重要であり、一方、国立サモア大学等個々の国における大学への協力も、当該国に対する高等教育、人材養成のために重要と考えている。 |
|