農業・農村開発に関わる我が国ODAの評価
(重点課題別評価)
| 1.テーマ: 農業・農村開発 |

(クリックすると画像が変わります) |
| 2.調査対象国:タイ、バングラデシュ、ガーナ、ペルー 現地調査国:タイ |
|
| 3.評価チーム: (1)評価主任:野田 真里 (名古屋NGOセンター理事・中部大学助教授) (2)アドバイザー:松本 哲男 (名古屋大学農学国際教育協力研究センター教授) (3)コンサルタント: 加藤 正勝 アイ・シー・ネット株式会社 シニア・コンサルタント 畔上 尚也 同 シニア・コンサルタント 山崎 三佳代 同 コンサルタント |
|
| 4.調査実施期間:2006年7月~2007年3月 | |
|
5.評価方針 (1)目的 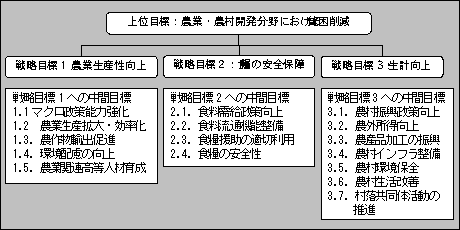 (2)対象・時期 また、本評価調査はODA大綱・中期政策などに規定される重点課題別の援助政策を主な対象とする重点課題別評価と位置づけられ、日本の農業・農村開発援助の貧困削減への貢献を政策レベルで大局的に検証・評価することを目的とするため、その調査対象は1)当分野における日本の政策レベルの取り組みの分析と2)本調査目的に最も適切と思われる途上国から選定された4カ国(タイ、バングラデシュ、ガーナ、ペルー)の国別ケーススタディからなる。ケーススタディ対象国の選定に際しては、まず農業・農村を取り巻く特徴により大きく4つの地域グループとして1)東南アジア、2)サブ・サハラアフリカ、3)南西アジア、4)中南米を設定した。次に各地域グループから、日本からの援助供与額、国別援助計画策定の有無、国家経済における農業・農村セクターが占める重要性などの観点から、農業・農村開発分野での日本のODAの貢献を評価する国を選定した。 (3)方法 政策レベルの分析では、農業・農村開発援助に関する全体的な政策の評価を、おもに援助政策の目的と結果の観点から行うが、関係プロセスも考慮する。「開発援助政策の目的」については、その内容の妥当性に焦点をあて、当分野援助の国際的な開発目標、我が国の施策指針やアプローチとODA大綱や中期計画、あるいは他の外交政策など上位政策との整合性、開発途上国の政策や自立発展への努力、受益者のニーズやミレニアム開発目標(MDGs)など国際的な優先課題との整合性を総合的に検証した。「農業・農村開発援助の取り組み・アプローチ」は、国別援助計画における農業・農村開発援助への取り組み、ODAタスクフォースの役割、機能などの観点から評価した。「援助政策の結果」については、援助事業の実施形態・分野、対象地域など多方面にわたっていることから、すべての事業のアウトプット、インパクトを把握することは困難であるため、インプットの実績を把握・分析し、ケーススタディ国での主要結果を参照することで、当該分野における日本の援助政策の貢献度を検証した。 ケーススタディ国の分析では、農業・農村開発に関わる案件を目的の妥当性、結果の有効性、プロセスの適切性と効率性の視点を基本にしつつ、インパクト、自立発展性も視野にいれた評価とする。また、上記の3つの評価視点に加えて、1)NGO/市民社会など多様なアクターとの連携、2)効果的なスキームの組み合わせ、3)南南協力・広域協力、4)他ドナーの動向と援助協調、5) 持続可能な農業・農村開発の推進を今後さらに重要となる援助アプローチの課題として取り上げて、各国の事例を検証、評価した。 1 本評価調査においては「食糧」は「生きていくための糧」を示す用語法および固有名詞(世界食糧農業機構など)の場合に用い、「食料」は上記を含む食べ物一般を示す用語法、固有名詞をさす。なお、引用・参照については、これにかかわらずそのまま元の文章の用法を踏襲している。(例:ODA大綱における「食料」など)。 |
|
|
6.評価結果 (1)農業・農村開発援助の政策レベルの評価結果 (イ)開発援助政策の目的の妥当性 (ロ)農業・農村開発援助の取り組み・アプローチの適切性 (ハ) 結果の有効性 (2)ケーススタディ国農業・農村開発援助プログラムの評価 (イ) 目的の妥当性 (ロ) 結果の有効性
・プロセスの適切性・効率
・妥当性、有効性、適切性・効率性に影響を与えた貢献・阻害要因
・今後さらに重要となる援助アプローチと課題 |
|
|
7.提言 (1)農業・農村開発援助政策に関する提言 (2)農業・農村開発援助プログラムに関する提言 |
|
注)ここに記載されている内容は評価実施者の見解であり、政府の立場や見解を反映するものではありません。

