1.評価対象プロジェクト名:
モンゴル母と子の健康プロジェクト
|
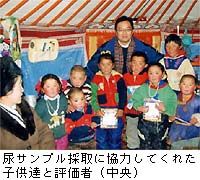 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:モンゴル |
3. 援助形態:
プロジェクト方式技術協力(1997年10月~2002年9月)
専門家派遣(長期:年間3~4人)、
研修員受け入れ(年間2~3人)、
機材供与(年間2,000~3,000万円) |
|
4.評価者:河原雄三 経済ジャーナリスト
|
|
5.現地調査実施期間:2000年11月6日~10日
|
|
6. プロジェクトの分野:保健・医療 |
7.プロジェクトの目的:
モンゴルでは、1960年代から予防接種拡大計画(EPI)(対象疾病は、BCG、ポリオ、麻疹等)を推進、現在まで国際機関等の援助によるワクチンの調達で高い接種率を確保している。また、内陸国である同国では、ヨード欠乏症(IDD)が深刻な問題となっており、その対策としてヨード(千葉県が無償で供与)を混入した塩の普及などが喫緊の課題。このプロジェクトは、IDDの制圧とEPIの自立運営に向けた同国の努力を支援する。
|
8.評価結果:
| (1) |
予防接種拡大計画(EPI)
視察対象となったウランバートル市のスフバートル地区保健センターでは、管内の予防接種率が国家目標の95%をほぼ達成。地方(ウブルハンガイ県)におけるEPIも、目標に近づいている。現場レベルのモラールも高く、プロジェクトが順調に進展しているとの印象を受けた。 |
| (2) |
ヨード欠乏症(IDD)
安価なヨード化塩を家庭に供給するため、ウブルハンガイ県の3つのソム(村)で98年から実施している住民参加型のスプレー式ヨード化塩生産のパイロット・プロジェクトを視察。タラグト・ソムに於けるヨード化塩の普及率(推計値)は、99年の5.8%から2000年には60.2%へと大幅な伸びを示しており、過剰・過少摂取をチェックする調査が実施されている。また、日本からの援助についての広報・宣伝活動等にも熱心に取り組んでいる。 |
|
9.提言 (今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):
| (1) |
EPIの自立運営に向けた課題は、ワクチンの調達と臨床医・看護婦のレベル向上。ワクチン調達についてモンゴル側は、その原資となる「ワクチン基金(250万ドル)」への拠出をドナー国に要請しているが、同国の財政事情と自助努力の双方を踏まえた対応が今後求められよう。また、臨床医等のレベル向上に向け、研修員受け入れを拡充してはどうか。 |
| (2) |
遊牧民が多い上に日本の4倍もの広大な領土を有するモンゴルでは、小児への予防接種の実施のための小児の所在を確認する作業を進めていくのは至難の業である。こうした特殊事情を考慮すると、モンゴルにおいてEPI対策を支援するためには、車両供与の増強を図る必要があると思われる(1997年度21台のジープを供与済)。 |
| (3) |
モンゴル側は、医療分野で感染症対策の強化を課題に掲げており、感染症関連は医療施設の整備が要請案件として浮上している。日本側がこれに応ずる場合、単に資金協力にととまらず、ソフト面の協力(技術協力)を組み合わせることも一案ではないか。
|
| (4) |
IDDへの対策は着実に進展しているが、対策を強化するために塩の調達資金やヨード化塩生産機材、広報・宣伝機材の整備等が課題となっている。いずれへの協力も検討に値するが、会計システムの整備やランニング・コストの負担能力など、受け入れ側に態勢が整っていることが前提となろう。 |
| (5) |
モンゴル国民の健康問題は、先の選挙でも大きな焦点となった。人民革命党に政権が移行したモンゴル政府は、この分野への取り組みを最重要課題に掲げており、その意味でもこの分野での日本の支援を真剣に検討する必要があるのではないか。 |
|
10.外務省からの一言:
| (1) |
感染症対策における、資金協力と技術協力(ソフト面の協力)との連携の提言(9.の(3))については、極めて重要であると認識しており、今後も「母と子の健康プロジェクト」同様、資金協力と技術協力の有機的な結合を図っていきたい。
|
| (2) |
現在、モンゴルでは、都市と地方の地域格差が問題となっており、今年7月に誕生した新政権も政策として地域格差の是正を掲げている。このプロジェクトは、都市部だけでなく地方での保健・医療サービス向上に寄与しているとして、モンゴル人より評価されている。 |
|
