ラオス教育分野の評価(第三者評価:NGOとの合同評価)
| 1. テーマ: アジアの基礎生活分野(BHN)の評価 |
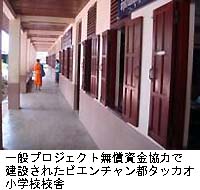 |
| 2. 調査対象国:ラオス人民民主共和国 現地調査国:ラオス人民民主共和国 |
|
| 3. 評価チーム: (1)評価主任:池上 清子 (国連人口基金東京事務所 所長) (2)アドバイザー:乾 美紀 (大阪大学大学院 助教) (3)NGO代表:黒田 かをり (CSOネットワーク 共同事業責任者) 米山 敏裕 (特定非営利活動法人 地球の友と歩む会 事務局長) (4)協力:西田 良子 (財団法人 家族計画国際協力財団 調査研究担当部長) (5)コンサルタント:アイ・シー・ネット株式会社 |
|
| 4. 調査実施期間:2008年8月~2009年3月 | |
5. 評価方針 (1)目的 本評価調査は、ラオス基礎教育分野に対する日本の協力を総合的に検証し、より効果的・効率的な援助の実施に向けた提言を得るとともに、NGOとの効果的な協力・連携を含めた今後のODA実施の方向性を導くことを目的とする。併せて、評価結果を公表することで納税者への説明責任を果たし、日本のODAに対する理解を促進することを目的とする。 (2)対象・時期 2000年度から2007年度までの8年間(2000年4月1日~2008年3月31日の間)に、対ラオス国別援助計画の重点分野「基礎教育の充実」のもと実施された一連の援助事業(合計152事業)を対象とした。評価にあたっては、現地調査時点(2008年10月)までの情報を参考として取り扱った。 (3)方法 本評価調査は、1)評価デザインの策定、2) 国内調査、3) 現地調査、4) 収集情報の分析と報告書作成という4つの手順に沿って実施し、「政策の妥当性」、「結果の有効性」、「プロセスの適切性」の視点から総合的に分析した。 |
|
6. 評価結果 (1)「政策の妥当性」に関する評価 イ 日本の上位政策である「ODA大綱」、「ODA中期政策」、教育セクターの基本政策である「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN)」と整合している。 ロ ラオス政府が掲げる「万人のための教育(EFA)」達成への教育分野の3課題、「公平さとアクセス」、「質と適切性」、「行政とマネジメント」に貢献する形で実施されており、ラオスの開発政策と整合している。 ハ ラオス政府の「ミレニアム開発目標(MDGs)」を達成するための取組を支援しており、国際的な優先課題や潮流と整合している。 ニ ラオス政府・ドナーとの援助協調、セクター・ワイド・アプローチ(SWAps)の協議の過程に参加しつつ、現在では今後の枠組みを見極める段階であり、現行の協力プログラムである「基礎教育改善プログラム」は、明確な枠組みの確定までは至っていない。 (2)「結果の有効性」に関する評価 イ 日本の基礎教育分野への支援の投入では、「教育環境・アクセスの改善」が半数以上と大きく、学校建設、教育施設や備品の整備を通した教育環境・アクセスの改善への日本の支援については、定量的に上位目標の指標(就学率等)への影響という点を明確にすることは難しいが、一定の貢献を果たしてきていると考えられる。 ロ 教育の質の向上の面では、理数科教育分野の技術協力プロジェクト(SMATT)における教員の養成による教授法や教材作成などに成果をもたらしているとの評価も確認され、長期的には質の向上につながっていくものと推測できる。 ハ ODAとNGOとの連携事業についてみると、貧困層、女性、障害者など社会的弱者といわれる人たちを対象とした教育環境・アクセスの改善や、就学阻害要因の軽減に重点を置き、独自のネットワークを活かし、コミュニティや地域住民と共に実施する形態が多い。こうしたNGOの強みを活かして、地域ぐるみの学校教育支援、図書・読書普及支援、文化活動の推進、女性や障害者を対象とした職業訓練などが、グッドプラクティス(成功事例・好事例)として、基礎教育改善へ向け地道な貢献を果たしている。 (3)「プロセスの適切性」に関する評価 イ 急速に進む援助協調・SWApsの動きの中、日本は、政策アドバイザーの配置を通して援助協調へのプロセスへ参加し、ラオス政府との政策協議を進めてきている。一方で、援助協調の中で基礎教育分野に対する日本の支援の経験や強みが他ドナーに十分に理解されているとはいえず、日本の支援の経験や知見、成果の文書化やその発表や共有が今後の課題である。 ロ 日本のODAの様々なスキームを現地の現状やニーズ等によって、効果的に選択・連携する試みが始まっている。たとえば、ハード面では学校建設や教育環境整備をODA(無償)で実施し、ソフト面ではコミュニティが学校運営や教育事業をマネジメントできるよう技術プロジェクトあるいはNGOとの連携により支援するという試みが始められている。さらに、南部3県における技術協力プロジェクトでは、国際NGOとの連携により、地方行政や地域住民の参加による初等教育改善への包括的なアプローチの試みが進められている。 ハ 今回の評価対象となったODAとNGOの連携事業の中には、コミュニティや住民とともに実施している教育環境・アクセスの改善や就学阻害要因の軽減への取組の好事例もみられ、こうしたNGOの経験や知見をODAの枠組みの中で共有・活用することで困難な課題解決に一歩近づくことも可能であると考えられる。 |
|
7. 提言 (1) 初等教育の継続と修了を目指した基礎教育支援の強化 初等教育就学率は改善しつつあるが、依然として国内に格差が存在し、2015年までのEFAとMDGsの達成は危ぶまれている。初等教育完全普及の達成までに残された「ラスト10%余り」の児童への対応が求められている。こうした背景の中で、2008年10月現在、ラオスでは、援助協調により「教育セクター開発枠組み(ESDF: Education Sector Development Framework)」の策定が進んでいる。その中で、日本政府は、これまでの日本の支援の経験を活かしつつ、国際社会の共通の目標に沿って基礎教育分野への支援を強化する。 (2) 援助協調・他ドナーとの戦略的な連携強化―SWApsへの積極的な参加 SWApsへの流れに積極的に参加し、日本の「基礎教育改善プログラム」をより戦略的に形成し、他ドナーとの協調・連携をもとに日本の支援対象や得意とする分野・課題を明確に提示する。これまでの日本の支援実績を分析すると、日本の得意分野としては、教育環境・アクセスの改善(小学校の建設・改修)、教育の質の向上(理数科教育にかかる教員養成)とともに、NGOとの連携によるコミュニティへの働きかけを通した就学阻害要因の軽減(読書推進、コミュニティ啓発等)が挙げられる。 (3) 初等教育の完全普及への支援―連携強化による援助効果の拡大 イ 包括的アプローチを目指した連携強化 ロ 現地のニーズにあわせた日本の各種援助スキーム間の連携推進 ハ 地方行政の能力強化 ニ 住民やコミュニティと関係の深いNGO等との連携 (4)国内および現場レベルでの情報と知見、グッドプラクティスの共有 SWApsの潮流に合わせ、「教育セクター開発枠組み(ESDF)」という新しい枠組みの中で、日本が積極的に意思決定にかかわり、日本のプレゼンスを高めながら効率的・効果的に援助を実施していくことがますます求められている。現地ODAタスクフォースのリーダーシップや調整機能強化により、対ラオス支援の経験や知見・グッドプラクティス(成功事例・好事例)の文書化を促進し、NGOや民間も含めた援助関係者による情報、アイデア、知見の共有の場や機会の確保を図る。これには、以下の点で効果が期待できる。1)具体的な協力・連携事業の検討、2)日本が得意とする分野や課題への選択・集中の可能性、3)グッドプラクティスの適用の可能性を計画段階から見出すこと。 |
|
注)ここに記載されている内容は評価実施者の見解であり、政府の立場や見解を反映するものではありません。

