| 1. テーマ:ラオス国別評価 |
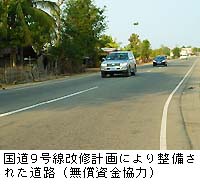 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
| 2. 国名:ラオス |
3. 評価者他:
(評価主任)
橋本ヒロ子 外務省ODA評価有識者会議メンバー、十文字学園女子大学社会情報部学部長
(監修)
西澤信善 近畿大学経済学部教授
福井清一 神戸大学大学院国際協力科教授
(コンサルタント)
中村桐美 オーバーシーズ・プロジェクト・マネージメント・コンサルタンツ(株)
井上果子 オーバーシーズ・プロジェクト・マネージメント・コンサルタンツ(株)
|
| 4.調査実施期間:2004年8月―2005年3月
|
5.評価方針
(1) 目的
- ラオス国別援助計画の策定と今後のより効果的・効率的な援助の実施に参考となる教訓を抽出し、提言を行うこと。
- 本評価結果を公表することにより、援助の透明性および説明責任を確保すること。
(2) 評価の実施要領
- a. 評価の対象:評価の対象は、1997~2003年度におけるわが国の対ラオス援助政策および実績である。当該期間に実施された対ラオス援助政策としては、1998年に策定された「対ラオス国別援助方針」があり、本評価においては、同方針がどのような目的をもち、いかなるプロセスを経て策定・実施され、どのような結果をもたらしたのかを総合的かつ包括的に評価する。
- b. 評価の枠組み:本調査にあたっては、1)対ラオス援助政策の目的、2)対ラオス援助政策 のプロセス、3)対ラオス援助政策の結果について、調査・分析し、それぞれの項目について評価を行なった上で、総合評価としてとりまとめる。
|
6.評価結果
(1) ラオスの開発とわが国の協力
- ラオスの開発の現状と課題
ラオスでは、1980年代後半に開始された新経済メカニズム(NEM)導入による経済改革により、市場経済化および経済開放政策が進められ、1990年代後半には、ASEAN正式加盟など、近隣諸国との経済関係の強化が図られた。その結果、年率平均5%以上の経済成長を維持している。一方、AFTA(ASEAN自由貿易地域)に組み込まれ、段階的な関税引き下げなどのプロセスを進めることとなり、税収に占める関税など間接税の割合が高いラオスにとって税収の減少が懸念されている。また、地方分権化が、特に財政に混乱を招いている問題もある。予算策定過程では、経常予算と開発予算の間での調整が十分に行われていない。このような、財源の問題も含めて、ラオス側の援助受入能力が不十分であることから、整備されたインフラの維持管理が適切に行われない、インフラが有効に活用されない、ドナーによる支援が終わると成果が持続されないということが生じており、援助の持続性にも影響を及ぼしている。
- わが国の対ラオス援助
対ラオス国別援助方針では、ラオスが、1)インドシナ全体の経済圏としての発展を図る上で重要であること、2)後発開発途上国(LDC)であることに加え、内陸山岳国という経済発展上の制約があること、3)市場経済化および民主化に取組んでいること、4)AFTAへの加盟により財政構造改革など諸制度・組織の整備が不可欠となっていることなどを踏まえ、わが国が同国への支援を実施するとし、対ラオス援助の重点分野として、1)人造り、2)BHN支援、3)農林業への支援、4)インフラ整備支援が設定され、加えて、分野横断的な問題として、開発計画の策定、政策の立案と実施能力の向上、法的・制度的基盤強化のための支援が必要であるとの指摘もなされている。わが国からのラオスに対する援助は、1997年から2003年までの支出純額ベースでの累計金額は6.6億ドル(およそ700億円)であり、そのうち無償資金協力が4.2億ドル、技術協力が2.2億ドルであった。
(2) 対ラオス援助政策の目的に関する評価
対ラオス国別援助方針で設定されている援助の重点分野およびサブセクターが、わが国ODA 上位政策やラオスの開発ニーズにほぼ整合していることが確認できた。一方、それは、広範囲において援助ができるように設定されたともいえる。開発途上にあるラオスのあらゆるニーズに対応できるように重点分野が設定されたという意味では、そのような総花的な援助のあり方も評価できる。しかし、「援助の目的」は対ラオス国別援助方針に明示されておらず、援助目的達成のため援助戦略を確認できなかった。また、わが国は、NGPES 策定の過程において、ラウンドテーブル会合などでラオス政府および他ドナーとの協議を行い、様々な機会に「貧困削減」の観点からも意見を発表している。プロジェクトの実施にあたっても、貧困削減を意識した取組みが行われるようになっているが、今後さらに貧困地域に焦点を充てた援助のあり方を検討することも必要となろう。
(3) 対ラオス援助政策のプロセスに関する評価
対ラオス国別援助方針の策定プロセスは、わが国関係省庁・機関の参加を得、かつラオスの開発ニーズを把握するプロセスが得られていたという点でプロセスの適切性の確認ができた。しかし、援助政策の目的と達成するための戦略としての各重点分野のアプローチの妥当性については検証できておらず、援助政策のプロセスについても、わが国の援助政策の妥当性を検証するプロセスが適切になされていたか、否かについての分析を行なうことができなかったという限界があった。また、対ラオス援助を取り巻く環境は、NGPES の策定・貧困削減に向けた取り組み、ドナー協調の活発化、中国からの援助額の増加など急激に変わりつつある。わが国の対ラオス援助政策については、1998 年3 月の経済協力総合調査団の派遣で重点4 分野が合意されて以降、1999 年7 月の政策協議ミッション、2003 年度以降のODAタスクフォースでその有効性が確認されているものの、制度として定期的に見直す機会は設けられていない。
(4) 対ラオス援助政策の結果に関する評価
ロジックモデルによる対ラオス援助政策の目的と実施されたODA案件との論理性、因果関係の検証の結果、重点4分野は広くカバーされ、ラオスの多様な開発ニーズに対応しようとしているが、その中でも保健・医療を中心とするBHN支援および運輸セクターを中心とするインフラ整備に関するプロジェクトが多く実施されている。また、1)ラオスのマクロ経済成長への有効性、2)NSEDPの開発目標達成への有効性、3)MDGs達成への有効性、の3つの観点からの分析では、わが国の対ラオス援助政策の結果は掲げられたさまざまな開発目標に対して関連性が高く、ラオスの開発に有効であった。また、わが国からの資金協力は、ラオス開発予算の重要な財源となり、インフラ整備を中心とするラオスの開発事業の推進に貢献したことからも有効性は高かった。重点4分野に対する我が国支援の貢献は大きいものの、開発事業の運営・維持管理、開発効果の持続性・自立発展性については課題を残している。なお、対ラオスの援助政策の実施は、対東アジア地域への我が国の援助政策とも整合しており、妥当であったといえる。
その他、政府の財政基盤の脆弱性(経常予算不足:ODA案件の効果や持続性への悪影響)、他主要ドナーからの援助額削減の傾向(わが国ODAの相対的重要性向上)についても留意が必要である。さらに、わが国とラオス二国間関係への影響については、アンケート調査の結果、わが国ODAがラオスの人々にとって好意的な印象を与える好機となり、友好関係の維持に重要な役割を果たしてきたことがわかった。また、わが国支援があった東西回廊計画により、今後のベトナム中部、ラオス中南部、タイ東北部の物流活性化を通じた経済発展が期待されている。ニーズの高いインフラ整備等を中心に支援したわが国の対ラオス支援に対する国際的評価は、非常に高いが、今後は運営・維持管理を含めたソフト面の支援とハード支援の連携が求められている。
|
7. 提言
今後、わが国の援助全体の方針として、ODA予算が減少する中で、わが国の援助をますます戦略的、効率的、重点的に行い、効果を最大限とすることが求められる。本評価においては、わが国の各重点分野への援助とラオスの経済発展の因果関係を客観的に検証するにはいたっていないが、わが国援助政策の有効性の観点から、少なくとも現在策定中の国別援助計画においては1)ラオスの経済発展のための地域経済統合への支援:インフラ整備と人材育成、2)貧困削減への支援:BHN支援と貧困地域への支援、3)分野横断的課題:ジェンダーへの取組みの視点での重点分野の検討が求められる。有効性の高い、かつ効率的な援助政策の実施に当たっては、戦略的援助政策と案件形成プロセスの一貫性の確保も重要である。国別援助計画の策定過程においては、わが国の援助政策の目的・目標を示し、また、できるだけ具体的に各重点分野への支援の目的・目標を示したうえで、ラオス政府との協議において、今後何に対して援助を行うかということを議論し、共通の理解を持つことが重要となる。このようなプロセスが取られることで、重点分野の目標達成に向けたより戦略的に体系立てられた案件形成がおこなわれるようになり、援助の効率性の向上に結びつくことが期待される。同時に、案件形成においては、要請主義を踏襲しつつも、ラオス側のキャパシティを鑑み、参加型開発への支援の取組みの強化も含め、わが国からもラオス側の案件形成能力の向上を支援する形で行なうことも必要である。
なお、ラオスの財政基盤の強化の問題は重要であり、ODA実施にあたっては少なくとも運営維持管理費の確保をプロジェクトの中に組み入れ、それを具体化させることを条件付けさせるなどの方策も対ラオス援助において検討されるべきである。また、ラオスの自立性を促し、オーナーシップの意識を高める手段として、国別援助計画を策定する段階で、ラオス側とどのくらいの期間でどこまで支援を行うかということを取り決め、同時に、重点分野における一定の目標達成のための時限的支援であることをラオス側にも認識させることが必要であり、進捗状況をモニタリングする体制を整えるといったことが必要となる。
さらに、わが国からの援助の効率性を高める上では、わが国の援助メニューから、ラオスで実施可能な形態の支援を行うだけでなく、スキームの対象範囲を拡大するといった対応や、新たなスキームの整備、他ドナーとの連携のあり方など、ラオスの開発ニーズの実情に即したメニュー作り、援助の枠組みの構築を行うことも視野に入れた、援助計画を策定すべきである。
|
