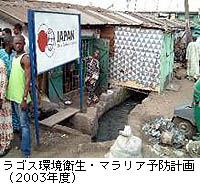|
6.提言
6-1 選定プロセス簡素化による効率性の確保
(1)現行の人員体制をベースに実施可能な案件数を設定する。
本スキームの対象案件数を決定する際には、1案件を承認するまでに要する時間を考慮し、現行の実施体制のもとで質を確保しながら実施が可能な数を設定することは一案である。現行体制に見合った年間の承認案件数を目安として定めた上で計画的に案件選定を行うことは人員不足への1つの対応策となる。
(2)申請前スクリーニングを行う。
限られた人員で効率的に案件選定を行うための工夫として申請前スクリーニングの設定が挙げられる。仮審査の段階で、申請団体に対して文書や口答説明によって本スキームの趣旨を説明し、申請内容が本スキームの趣旨に合致している場合のみ申請書等を送付することで、本スキームの援助趣旨に合わない申請を予め除外することが出来る。
6-2 申請団体の実施能力を効率的に確認する方法
(1)他NGOおよび他ドナーから情報収集を行う。
申請NGOの実施能力を確認するために、サイト訪問の際に申請NGOのオフィスを訪問してオフィスの人員体制や運営状況を確認したり、申請NGOの活動状況について他のNGOから聞き取り調査を行うことの他、他ドナーの小規模無償プログラム担当者から申請NGOの実績を確認することも有効な方法である。
(2)被供与団体に関するデータベースを作成・活用する。
上記(1)の方法で収集した情報に関してはデータベースを作成し、必要に応じて活用することを提言する。情報としては、過去の本スキーム支援を受けた経験の有無、他ドナーの支援を受けた経験の有無、過去の実施案件とその成果に関するリスト、他NGOや他ドナーによる評価などが考えられる。
(3)被供与団体の実施能力を担保する方法
被供与団体の実施能力を担保する方法として、草の根ニーズおよび公平性を確保しつつ、実績のあるNGOを優先的に選定したり、被援助国のガバナンス状況によっては郡の行政機関による推薦を重視することが考えられる。NGOの信頼性を確認する方法として、申請書の添付資料に、過去の活動報告書および財務報告書を含むことが考えられる。その他、申請団体が過去に実施したプロジェクトとコミュニティに与えた便益に関するリストや申請NGOが属する大手のNGO(Intermediary
NGO)があるかどうかに関する情報を添付してもらうことも一案である。
6-3 現地ODAタスクフォースの有効活用による実施プロセスの効率化
(1)案件形成プロセスにおける現地ODAタスクフォースの活用
現地ODAタスクフォースが活動を行っている国においては、タスクフォースの会合を利用して、知識と経験の豊富な日本のODA人材の意見を案件形成・発掘に反映させることを提案する。さらに進んで、タスクフォースによって草の根無償案件の選定を行うことも一案である。本スキームのもとでは、現在は在外公館における案件選定委員会の設置および同委で選定された案件の在外決裁はないため、効率的に案件選定を行うために現地ODAタスクフォースの活用が最良であると言える。現地ODAタスクフォースの活動が限定的である国においては、JICA関係者(専門家、企画調査員、無償資金協力調査員等)を、必要に応じて草の根無償の案件形成・審査に活用することを提案したい。
(2)草の根ニーズの把握とモニタリング・フォローアップへの既存の人的リソースの活用
現地ODAタスクフォース以外にも草の根ニーズの把握や実施案件のモニタリング・フォローアップ活動のために、現地に根ざした活動を行っている既存の人的リソースを活用することにより効率的なスキーム運用が可能になる。
6-4 本スキーム実施によって高い援助効果を得るための方策
(1) 間接費支援の強化
「人間の安全保障報告書(2003年5月)」においては、「人間の安全保障」実現のために、人間一人ひとりの保護と能力強化(エンパワーメント)の必要性が強調されている。間接費支援は特にコミュニティや個人の能力強化に貢献するものであることから、本スキームへの「人間の安全保障」強化を推進するためにも間接費支援の強化が望まれる。
(2)「分野を超えて複数の支援活動を1つの地域で行っているプロジェクト(Added Value Project)への積極的な支援
外務省無償資金協力課が2003年4月に発表した「草の根・人間の安全保障無償‐人間の安全保障分野における支援の強化」においては、分野を超えて複数の支援活動を1つの地域で行っていくプロジェクト(Added
Value Project)を積極的に支援していくとの方針が示されている。こうしたプロジェクトへの支援は、「人間の安全保障」理念の強化を推進するものであり、今後のさらなる取り組みが期待される。分野を超えて複数の支援活動を1つの地域で行っていくプロジェクト(Added
Value Project)に関する調査については、今後とも本スキーム評価調査の調査項目とされたい。
(3)国毎の援助環境を考慮した柔軟な連携案件の発掘・形成
援助ニーズや本スキームを取り巻く援助環境(日本の援助人材および他ドナーの活動状況等)は国毎に異なる。当該国の援助環境を考慮しつつ、ニーズに柔軟に対応することが求められる。ケーススタディ2ヶ国の例は、国毎に援助環境の違いをふまえて、本スキームと日本の他の援助スキームとの関係づけ方、連携協力の程度や方法を考えていくことが重要であることを示唆している。ナイジェリアにおいては、開発調査や技プロが現在実施中であるが、JOCVは派遣されておらず、支援分野も限られている。他方、ガーナにおいては、これまでに日本の各種援助スキームによって多岐にわたる分野に支援が実施されてきた結果、当該国では教育分野においてスキーム間の連携が積極的に行われるようになったばかりでなく、最近では国別援助アプローチの枠組みの中に効果的に本スキームを位置づけることについての検討が行われるまでになった。
(4)JOCV/技プロとの連携によるサービスの「質」の向上
当該スキームの援助品目は施設建設・資機材供与が主である。こうしたハード面での支援は教育や保健等の社会サービスへの「アクセス改善」に貢献するものであるが、援助効果を高めるためには、併せてサービスの「質」の向上が必要である。本スキームがサービスへの「アクセス改善」のみならず、「質」の向上にも貢献するためにJOCVや技プロとの連携を行うことは効果的・効率的な連携の一例である。
6-5 実施案件中のモニタリング及びフォローアップを強化するための提言
| 1. |
実施団体(被供与団体)による自己評価のための評価シートを在外公館が作成し、その評価シートに沿って実施団体(被供与団体)が事業完了時又は完了後一定期間内に対象プロジェクトに関する自己評価を行うことを義務付ける。また、実施団体(被供与団体)による実務報告書提出を徹底させる。より効率的・効果的にモニタリング・フォローアップを行うため、中間・最終報告書のフォーマットを修正する。 |
| 2. |
JOCV/JICA専門家および外部委嘱員等の既存の援助人材・リソースを積極的に活用する。 |
| 3. |
案件審査のためのサイト視察の際に実施中案件のモニタリングを行う。 |
| 4. |
本スキームの優先分野における案件であることを前提とし、プロジェクト・サイトが近い郡の案件を優先的に選定する。あるいは、年毎に地域を特定して支援を実施する。 |
6-6 効率的なスキーム運営のための提言
(1)通信環境の改善による日常業務の効率化
応募書類をダウンロードできるWEBサイトやインターネットを駆使した照会への対応を可能にする通信環境を整備することによって、効率的な業務の実施が可能になるであろう。
(2)在外公館(または、現地ODAタスクフォース)相互の情報共有システムの構築
インターネットへのアクセス、回線の充実によって、在外公館相互で、館内運用実施マニュアル(仮申請、事前調査、モニタリング、フォローアップのチェックリスト)、データベース活用策、応募者向け案内書・申請書類、外部委嘱員への委嘱業務(TOR)と契約書、現地NGO
事情と活用策、申請団体の実施能力の確認法、問題案件への対応のノウハウ、成功例の紹介などを含む各種情報を共有し、経験交流できるシステムづくりを行う。
(3)対象国の行政能力に応じた実施戦略の採用
本調査のケーススタディ国であるガーナとナイジェリアでは国の状況(地域ニーズや被供与団体であるNGOや地方行政組織の実施能力等)が異なるが、当該国のコンテクストの中で本スキームの特性である「迅速性」と「柔軟性」を考慮に入れて、本スキームの効率的運営のための工夫をしている。ガーナでは地方政府(郡)は必ずしも強くはないが一定の行政能力をもつため、地方自治体による申請案件が優先的に選定されており、NGOによる申請の場合には郡議会あるいは郡の行政機関による推薦状の提出を原則としている。本スキームを国別アプローチの枠組みの中に位置づけていくという現地ODAタスクフォースの方針も、こういった点と密接に関係している。他方、ナイジェリアにおいては地方政府の機能が弱いため、過去3年間に実施された案件のすべての資金供与先はNGOであり、実施能力のあるNGOの選定が課題となっている。
6-7 中・長期的な視野に立った実施体制の整備
現地職員及び外部委嘱員を本業務に有効活用するためには、中長期的な展望に立った在外公館における本スキーム業務の実施体制の整備(人材育成)が必要となる。特に、外部委嘱員は、草の根実施体制の強化と安定化に向け有効に活用すべきツールであるが、国によっては現地で優秀な人材を確保することが難しいことに加え、優れた人材でも予算執行制度上契約更新を前もって確約できないことや、同一人物による契約が原則として最長2年間までとされていることから、在外公館における安定した業務補助員と位置づけることが困難である。こうした点を踏まえ、在外公館の事情に応じて現地職員・外部委嘱員による担当業務のTORに柔軟性をもたせることも必要である。
|