1.テーマ:
人づくり・教育
|
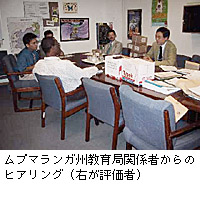 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:南アフリカ、ザンビア、ケニア
|
3.評価者:
今里 義和 東京新聞論説委員
|
|
4.現地調査実施期間:2001年2月12日~22日
|
5.視察対象プロジェクト:
(1)ムプマランガ州理数科教員再訓練(南アフリカ・ムプマランガ)
(2)ルサカ市小中学校建設(ザンビア・ルサカ)
(3)ケニア理数科教員養成大学(ケニア・ナイロビ)
(4)理数科教員の青年海外協力隊員による授業(ケニア・マクエニ地区)
|
6.評価結果:
| (1) |
資源小国の日本が明治の開国以来、欧米各国に肩を並べるまでに経済成長した大きな理由の一つは、教育による人的資源の充実だったといわれる。
IT、グローバル化が経済成長のキーワードになっている今日、発展途上段階にあるアフリカ各国が確実に成長の歩みを速めていくためには、特に理数科教育の充実が不可欠である。 |
| (2) |
しかし、大部分が長く植民地の地位におかれていたアフリカでは、黒人が理数科教育の機会を与えられず、自立を阻害されてきた国も多い。子供たちに学問を教えるべき世代にも理数科の知識は不足しているわけで、教員養成によってその空白を埋める努力(例えば「ムプマランガ州理数科教員再訓練」及び「ケニア理数科教員養成大学」)に対する支援は、国の土台を形成する上できわめて重要な支援である。
しかも、教員が日本に好印象を抱いた場合、生徒に日本のことを好意的に話す可能性が大きいことに着目すれば、二国間関係の視点からも戦略性の高い支援であるともいえる。 |
| (3) |
小中学校の建設や、教員の派遣事業なども、「国の土台となる人的資源を育成する」「次の世代に、日本に好印象を持ってもらう」の両目的に合致する。特に、井戸もないような宿舎に住み込んで学校教育にあたっている青年海外協力隊員は、二国間の貴重な架け橋になっている。 |
|
7.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):
| (1) |
優秀な人材は、理数科教員としての要請訓練を受け終わると、もっと待遇の良い国に出稼ぎに行ってしまう例がある。もちろん、援助受け入れ国自身が理数科教員の定着に努力すべきだが、日本側も、交流・研修のための日本招待などをインセンティブとして、優秀な人材の定着を促すべきだ。 |
| (2) |
学校建設に対する協力は、施設の水準の設定を柔軟に考慮すべきかもしれない。「タカマド・スクール」(ザンビア・ルサカ市)は、もちろん先進国の水準とは比べられないが、同国内や近隣国の標準的な学校と比べれば、日本の援助で相当恵まれた施設が整備されている。援助は「広く薄く」になりすぎてもいけないが、模範的な例として整備するにせよ、一件だけがあまりに先進的な事業になっても不均衡が生じかねない。
教室など施設の建設の協力だけでなく、当該校での日本に関する知識の教育などソフト面でも、押しつけにならない範囲で、協力を積極的に申し出るべきだ。「タカマド・スクール」の教室の外壁に日本地図が描かれていたのは、一つの参考例になる。 |
| (3) |
青年海外協力隊員たちは、厳しい生活環境の中で、よく頑張っている。ただ、強盗や病気、けがなどの危険も非常に高い。まず募集、赴任にあたっては、こうした危険について十分に告知すべきである。赴任した現地では、宿舎の安全対策として施錠や格子戸などの構造、無線や発電器具の装備など、危険を避けるための対策に万全を期すのは当然として、万一不幸な出来事に遭った場合に備え、医療や心理カウンセルなどまで含めた支援態勢の整備が望まれる。 |
|
8.外務省からの一言:
| (1) |
2000年4月の世界教育フォーラムで採択された「ダカール行動枠組み」(注:基礎教育分野に関し、2015年までの無償初等教育の普及等、国際社会が取り組むべき目標及び戦略等が示されている)の目標達成に向け、特に基礎教育分野での取り組みを積極的に行っていきたい。 |
| (2) |
海外への経済協力関係者の派遣に際しては、事前に注意喚起するとともに、現地到着後もJICA事務所、大使館から具体的な対処方法・注意を与えている。また、現地においては、緊急移送を含む緊急時への対応の見直しを定期的に行っているが、今後ともハード面、ソフト面での体制強化を図っていきたい。 |
|
