1.評価対象プロジェクト名:
女性職業訓練センターへの機材供与計画
|
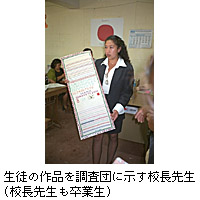 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:グアテマラ
|
3.援助形態:
草の根無償96年度、3.7百万円
|
4.被供与団体:
グアテマラ市地域社会局
|
5.評価者:
荒木 光彌 (株)国際開発ジャーナル社編集長
中畝 義明 (社)世界経営協議会研究調査部長
幡谷 則子 アジア経済研究所地域研究2部副主任研究員
橋本 吉之 アイ・シー・ネット(株)企画部プログラム研究員
|
|
6.現地調査実施期間:2001年1月20日~2月5日
|
7.プロジェクトの目的:
本件は、グアテマラ市役所地域社会局が建設・運営する、貧困地域に住む17歳以上の女性を対象とした職業訓練センターへの機材供与である。具体的には市内第12区及び第18区の二つのセンターで使用される足踏みミシンの供与によって、貧困女性の職業訓練、生活水準および社会的地位の向上を支援するものである。
|
8.評価結果:
| (1) |
今回の評価調査で視察したのは、第12区の職業訓練センターである。同訓練センターでは、主としてグアテマラ市の貧困層女性を対象に、裁断、縫製の職業訓練を行っている。草の根無償によって計80台のミシンが供与された。第12区センターでは、技術レベル別に3つのクラスに分かれている。それぞれの訓練室を視察したが、数台は修理を必要とする状態にあった。 |
| (2) |
本案件の効果は次の3点である。 |
| (イ) |
貧困地区出身で、職業訓練機会のなかった女性達に、年齢の上限を与えずに「手に技術をつけ、職を得る」機会を与えた点であり、これを支援した草の根無償の意義は大きい。これは、調査団の視察中に意見交換した実習生の声からも明らかであった。 |
| (ロ) |
第二は、職業訓練センターにおいて訓練を修了したものから指導者が輩出し、同センターの指導者として養成されていることである。これは、本案件の持続可能性を裏付けるものであり、草の根無償が自立発展性をもち、かつ地域のニーズに根ざしたプロジェクトを支援した意義は大きい。 |
| (ハ) |
第三は、参加女性に現金収入の道が開けたことと、社会的地位の向上・経済的自立心の形成があり、総合的に女性の地位向上に役立っていることである。訓練(計9ヶ月)修了後、訓練生には、(1)自宅で縫製を請け負う仕事場を設ける、(2)既存の縫製所に就職する、(3)縫製指導者として教室を開催する、などの選択肢が開かれた。さらに上級の技術習得を目指すものには、市内の別地区のセンターに進むことも可能である。世帯主として十分な収入を得るまでにはいたらないが、同センターの上級コースで訓練を受けながら、すでに質の高い作品を販売にまわすなど、生計の一助になっている。
|
| (3) |
現在12区のセンターのみでおよそ400名の生徒を擁しており、グアテマラ市貧困地域におけるインパクトは大である。特に、大衆層にとっては、たとえ実収入の上昇に即時につながらなくとも、技術習得によって家庭内の女性の地位向上、社会参加への意識改革には役立つ。同プロジェクトが日本政府からの援助を受けていることは、受講生全員が周知しており、また、2000年9月には、国内大手情報誌のひとつである、「クロニカ(Cronica)」にも紹介されている。 |
|
9.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):
| (1) |
供与内容のミシンについては、若干修理が必要なまま放置されたものがみられた。これらが裨益団体の自助努力でまかなわれる程度のものであれば、その助言をすべきだし、そうでなければ、機材メンテナンスのフォローアップが必要であろう。 |
| (2) |
本案件は貧困女性の技術養成と所得向上をめざすものであり、受講者の意欲は非常に高かった。しかしながら、安定的就職機会の確保には、さらに高水準の技術取得が必要であり、そのための養成能力はグアテマラ市社会開発局ではまだ限られている。同センターの9ヶ月の訓練修了証書は、正式な技能資格証明とはならない。職業訓練が専門的な就職に結びつくように、インフラ面でも制度面でもフォローアップできる体制づくりがのぞまれる。そのために草の根無償がどのように活用され得るか、検討の余地はあるだろう。 |
| (3) |
本職業訓練センターは、グアテマラ市社会開発局の中でも、特に女性の地位と生活水準向上をめざすプロジェクトして位置づけられるている。今後、ますます同様の性格のプロジェクトは増えてくると考えられる。裨益者の所得水準向上をめざすのみならず、草の根の開発リーダーとしての育成まで含めた効果が期待できるような案件を形成・支持すべきであろう。 |
|
10.外務省からの一言:
このような女性の地位向上(WID)に役立つ案件は、草の根無償でも今後積極的に支援していきたい分野である。供与機材には当然耐用年数があり、その維持・管理の問題は援助の直面する課題の一つである。今後実施団体と協議をして修理・維持管理のための技術協力を検討したい。また、案件の事前の調査も今後より一層徹底していきたい。 |
