1.評価対象プロジェクト名:
(1)灌漑小規模農業振興
(2)灌漑施設改修計画
|
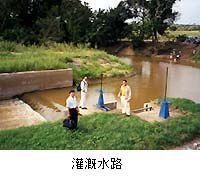
(クリックすると画像が変わります)
|
|
2.国名:ガーナ |
3. 援助形態:
(1)97~2002年度/プロジェクト方式技術協力/専門家派遣19名
(2)98年度/無償資金協力/7.64億円 |
4.評価者:
小浜裕久 静岡県立大学国際関係学部教授
高橋基樹 神戸大学大学院国際協力研究科助教授
|
|
5.現地調査実施期間:2000年9月11~15日
|
|
6. プロジェクトの分野:農業(灌漑及び営農・農民組織)
|
7.プロジェクトの分野:
ガーナ食糧農業省の傘下にある灌漑開発公社が管轄する灌漑農業地域において、無償資金協力による灌漑施設改修とプロジェクト方式技術協力によるモデル営農システムを確立する。 |
8.評価結果:
| (1) |
現在、首都アクラから東へ約30kmのアシャマン灌漑事業区(56ha)とアクラから西へ約70kmのオチェレコ灌漑事業区(81ha)の2つのモデルサイト及びアクラの研修センターで協力を実施中である。アシャマン灌漑事業区の方が進んでおり、オチェレコ灌漑事業区では、9月上旬に灌漑用ポンプが動き始めた段階であった。 |
| (2) |
農民自身の手による協同組合を再活性化し、彼らにその管理(資金管理、投入財の調達、水路など)を任せるといった方式は大変評価できる。農民のイニシアティブを重視した協力思想も高く評価できる。 |
| (3) |
アシャマン灌漑事業区では、小規模クレディット(種子、肥料などの経常投入)がうまく機能している。運営は、農民組合が担当し、生産性が向上した。このようなアシャマン灌漑事業区で実施されているソフト中心の援助は望ましい援助形態である。
|
| (4) |
ただし、小規模クレディットの原資は、プロジェクト方式技術協力の現地業務費などから捻出されているのが現状である。
|
|
9.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):
| (1) |
小規模クレディットの原資として見返り資金を活用する、或いは適切に予算化するなどの対応が望ましい。 |
| (2) |
自立発展性について、
| (イ) |
アシャマンで農民組合に小規模クレジットの運営を任せていることは、財務的な自立発展性に向けた一歩と評価できるが、将来的にはオチェレコも併せて、日本の援助が終了した後も農民組合を中心とするガーナ側が自主的に資金調達できるよう誘導する必要がある。 |
| (ロ) |
商品作物の市場、出荷方法、生産のための資金調達手法などを開発し、農民が自立的に担っていくようにするのが望ましい。 |
| (ハ) |
ディーゼルで水を汲み上げる揚水式を採用しているオチェレコについては、運転費用と農業収入の釣り合いのみを見ると、黒字となるのか、疑問である。今後は、小規模な灌漑に高いコストを必要とする揚水式を採用することには慎重であるべき。さらに、現在のガーナの名目金利は約40%であるので、支援方法・時期を決定するに当ってはその点をも勘案すべき。
|
|
| (3) |
日本の対ガーナ援助方針を示した国別援助計画はあるが、「総花的」で「優先順位」がついていない。分野別・地域別に優先順位をつけるのが望ましい。 |
|
10.外務省からの一言:
9.(2)(ハ)に関して、この計画は、小規模灌漑農業振興の観点から、既存のオチェレコ湖からの自然流下水で不足している水量を補うためには揚水を行わざるを得ない、との前提に立ったもの。外務省としては、ガーナ側が維持管理費用についても拠出可能と判断しているが、引き続き注意していきたい。
|
