評価対象:
我が国政府がエジプトにて実施しているカイロ首都圏の水供給セクターの無償資金協力とプロジェクト方式技術協力から代表的な4件を選び評価の対象とした。
|
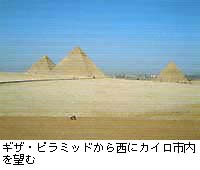 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
1. 現地調査対象国名及び主な調査対象:
(1) 調査対象国:エジプト
(2)調査対象:
- ギザ市ピラミッド南部地区上水道整備計画(無償)
- 第二次アメリア浄水場施設改善計画(無償)
- 第二次ギザ市モニブ地区上下水道網整備計画(無償)
- エジプト水道技術訓練向上計画(プロ技) |
| 2. |
評価者: |
| 村上雅博 |
|
高知工科大学・社会システム工学科・教授
(総括) |
| 西村浩二 |
|
外務省・調査計画課・事務官
(現、国土交通省北海道開発局勤務) |
|
| 4.調査実施期間:2002年2月26日~3月31日 |
5.評価の目的および視点:
エジプトの水供給分野に対する我が国の援助がどのように実施され、何を達成し、どのような効果を上げたかを中心に評価を行い、今後の同分野におけるより効果的、効率的な援助実施および新しい方向性について検討することを目的とする。
なお、本件評価調査では、上水道整備プロジェクトが結果として下水道整備と対応出来ていないために環境汚染につながる状況を懸念して、取水(水源)、上水道、下水道を一連の水循環システムとして把握して評価できる視点を組み入れている。 |
6.評価結果:
無償資金協力による水道施設の拡大や改修・リハビリによってカイロ首都圏の局地的水不足地域において安定した飲料水の供給が可能になっている。半スラム化している地域において、劣悪で非衛生的な日常生活からの開放(ベーシックな生活環境の改善)、婦女子や子供の水汲みの重労働からの開放、健康の確保と増進、都市計画の促進などが可能となり、市民生活の安定と向上に大いに寄与している。給水率は数字の上では85%を超えて24時間給水が実施されている。裨益する住民に対する生活環境改善へのインパクトも絶大である。
カイロ水道庁には有能な人材が潜在しており、また欧米との長い関係のなかで様々な水道技術を保有しているので、自立して水道技術訓練向上センターを運営していくに必要な技術移転の施設基盤(インフラ)整備ができ、人材育成の貴重な第一歩を踏み出している。ただし、運営組織・資金・会計・人材管理に代表されるマネジメント・ソフトコンポーネントに関しては抜本的な検討が必要である。
地元コントラクターの技術レベルに問題はなく長年に亘って工事をくり返し継続して経験も積み重なっているので、無償であれ有償であれ資金さえつけば効率的に建設工事を実施し、ほぼスケジュールどおりに完工できる。たがって、これらの計画が日本の無償資金協力によって実施された意義は物理的に大きく、当初の数値的な目的を果たしている各プロジェクトの妥当性があると判断される。
しかし、プロジェクトレベルで検討された対象地域の裨益人口代表される数値評価の裏には、水道システム全体の非効率、マネージメントの欠如、無駄(漏水、不明水)、料金体系の妥当性などの諸問題が数多く隠れ潜んでいる。プロジェクト単位での有効性が評価されたとしても水供給セクターのプログラムレベルで有効かどうかは別問題である。平均的な造水コスト(維持管理費用)が0.40/m3 LE(エジプトポンド)に対して平均的な水道料金収入が0.16 LEであるため、構造的な大幅赤字収支で独立採算の事業体にはなっていない。水道料金への補助金政策をとりつづける政府のもとに慢性的・構造的な赤字財政を余儀なくされ経営の自立ができない水道事業体のなかで、自立的発展性に関しては大きな疑問と課題が残っている。 |
7.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点):
| ● |
外国援助まちの施設整備計画をから脱却して、自立した水道整備計画をたてて実行できるよう水道財政を健全化させるためのシステム的な取り組みが必要である。水道事業が政府補助金から脱却するためにも、貧困層に対するミニマムな配慮を条件に、需要水量と漏洩を抑制する料金体系に改めるためのソフト(マネジメント)コンポートメント分野の協力に援助の視野を拡大すること。 |
| ● |
料金(改訂)設定や収支バランスのとれた経営や運営などのソフトや水道システム全体の効率的な管理システムをマネジメントできる組織(Institutional Capacity Building)および人材(Personal Capacity Building)の育成に取り組むこと。 |
| ● |
局所的な水不足解消を事業のターゲットにした量的拡張主義の開発妄想から、節水や有効利用を含む需要コントロールへのパラダイム変換が必要である。開発から管理へ協力の方向性を変換していくことが肝要であり、特にデマンド(水需要)マネージメンとリスクマネージメント(危機管理)は重要であり、組織制度・料金制度を含む国レベルの総合的なマネージメント・マスター・プラン(Water Supply Management Master Plan of Republic of Egypt)の策定に協力していくこと。
|
| ● |
健康、教育、水供給がエジプト政府の新しい援助政策プログラム(Verbal Note (March 5, 2002)、Programmed Top Priority Sectorの最優先分野であるが、水供給プログラムは健康・保健・衛生プログラムとも密接にリンクしている課題でもあるため、水源⇒浄水⇒給水網⇒排水網⇒下水処理⇒再利用(資源循環)と人間の生活と接点をもつ生命体型水循環システムを総合的にとらえるアプローチを踏まえた包括的な水分野の援助プログラム形成に向けて第一歩を踏み出すこと。水供給セクターと環境セクターの両者にかかわる下水処理と処理水の循環再利用計画を優先的に進め、地域の水環境と水資源を保全すると同時に有効かつ効率的に水供給のポテンシャルを高めるための持続的な開発・管理プログラムを戦略的に策定すべきである。エジプトの持続的・循環型社会を形成するために、環境開発・管理型プログラムの策定にあたってはキャパシティービルディングの視点が欠かせない。
|
| ● |
自立して社会公共財を形成するための負担についての市民意識の啓発、惰報公開、住民意志決定過程の定着などが、社会墓盤整備を支えるるための課題であることを認識し、技術移転型にとどまらずに市民参加型・生涯教育型のキャパシティービルディングのプログラム策定に協力すること。 |
| ● |
貧困撲滅にむけて、大規模インフラ整備依存型の経済開発優先政策から脱却し、首都圏カイロから地方の開発に目を向けて構造的な貧困問題を解決するための自立した管理ができる住民参加型水供給援助政策プログラムの策定に協力すること。
|
|
