1.国名:カンボジア
対象案件
一般無償:
チュルイ・チョンバー橋復旧計画(1992-93年度 29.89億円)
国道6A号線復旧計画(1993-94年度 30.12億円)
道路建設センター改善計画(1993-94年度 20.76億円)
国道6号・7号線修復計画(1996-99年度 45.78億円)
メコン架橋建設計画(1996-2000年度 65.07億円)
国道6号線シアムリアップ区間改善計画(2000-01年度 13.53億円)
国道6A号線橋梁整備計画(2000-01年度 13.59億円)
国道7号線コンポンチャム区間改修計画(2000-03年度 20.53億円) |
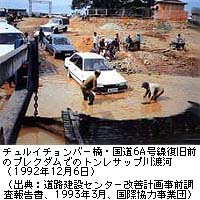 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
対象案件(つづき)
技術協力事業:
研修員受入(1992-2002年度 本邦研修42名・第三国研修9名)
専門家派遣(1992-2002年度 長期9名・短期14名)
開発調査(メコン河本流架橋計画調査 1994-96年度、および プノンペン市都市交通計画調査 1999-2001年度)
草の根無償プロジェクト:
スバイコーム溜め池・アクセスロード改修計画(2000年度) |
2.評価者:
原 尚生 八千代エンジニヤリング(株)国際事業部社会開発部
中川 義也(株)パデコ
アドバイザー
天川 直子 アジア経済研究所地域研究第1部 研究員 |
| 3.調査実施期間: 2003年2月3日~3月31日 |
4.評価の目的・視点:
本調査は、1970年頃から約20年間続いた内紛のため中断していたカンボジアに対する二国間援助が再開されてほぼ10年間が経過したのを節目とし、再開後の援助の中でも実施件数の多かった道路・橋梁分野に対して行われた一連の協力事業をプログラムと見なして評価するものである。
本評価調査の目的は、わが国のカンボジアに対する道路・橋梁(道路網整備)分野における一連の協力を1つのプログラムとして客観的に把握・評価し、(1)今後のカンボジアに対する道路・橋梁分野での協力のあり方について有意義な教訓・提言を得ること、(2)評価結果を公表することにより説明責任を果たすことである。
評価は、目的・プロセス・結果の3つの視点から総合的に行った。すなわち、(1)プログラムの目的はわが国援助方針、カンボジアの上位計画(国家開発計画・運輸分野の開発計画)・ニーズと整合・合致したものであったか(目的の妥当性)、(2)目的(方向性)が設定されていくプロセスは適切であったか(プログラム策定過程の適切性)、プログラムのもとで各事業は適切なプロセスで(連携・調整されながら)要請・採択・審査・実施されたか(プログラムにもとづく各案件の要請・採択・審査およびプログラム実施の適切性)、(3)プログラムの目的がどの程度達成され、目的達成の結果としてどのような直接効果・波及効果をどの程度生んだのか、生み続ける見通しはあるか(プログラム実施の結果:プログラム実施の効果・インパクト・自立発展性)、について客観的に評価し、また可能な限り数量的に分析するよう試みた。 |
5.評価結果:
5.1. 目的の評価
| (1) |
プログラムの目的の想定
評価の対象となっている事業は当初からプログラムとして実施されたわけではないが、無償プロジェクトは、チュルイチョンバー橋復旧、開発調査によるメコン架橋のルート選定(コンポンチャム・ルートに決定)を経て、プノンペンから国道6A号線、6号線、7号線と北東に向かって伸びていった。また、技術協力事業においては、無償プロジェクトの進捗と呼応して、無償資金協力の優良案件要請のための道路・橋梁管理全般についての研修員受入・専門家派遣から始まり、案件の円滑な遂行のための施工・施工管理、案件の完了後に必要となる維持管理へと力点がシフトしていった。
トンレサップ湖・川、メコン河により分断される主要道路の特性、プログラム策定の流れ、プログラムを構成する各事業の内容等から、プログラムの目的を『プノンペンとトンレサップ水系・メコン河の北東の開発拠点・隣国との間、開発拠点と後背地との間を結ぶ主要国道、首都近辺の主要国道の修復・改修・維持管理』と想定した。
|
| (2) |
プログラム目的の妥当性
わが国は一貫して、運輸インフラの整備、政府機関における人材の育成、メコン河流域等の広域開発への協力を重点分野としてきており、カンボジアの国家開発計画、道路・橋梁分野の開発計画においても、プログラムに含まれるプノンペン-シアムリアップを結ぶ主要国道の整備、メコン架橋は国家の優先プロジェクトとして掲げられ、地域経済との再統合にも重点が置かれてきたことから、プログラムの目的は上位方針・計画との整合性が極めて高いと評価される。また、プログラムは他ドナーの把握するカンボジアのニーズとも合致していた。
|
5.2. プロセスの評価
| (1) |
プロセスの分析
わが国の政府開発援助は相手国からの要請に始まり、要請内容の検討、採択(選定)、実施というプロセスで行われる。また、一般プロジェクト無償では案件選定後、実施計画策定のための調査が行われ、審査、実施となっている。わが国のカンボジアの道路・橋梁分野への協力における案件の要請-採択までのプロセスは、わが国・カンボジア双方の努力により改善が重ねられ、上位計画との整合性の高さが担保されるような仕組みが出来上がっている。
|
| (2) |
プログラム策定過程の適切性
プログラム策定の軸となったチュルイチョンバー橋復旧の採択・無償プロジェクトと並行した技術協力事業重視の政策の採用、および、メコン架橋建設ルート選定においてカンボジアの政府機関と協議が重ねられ、プログラム策定は十分な協議を経て適切に行われたと評価される。 |
| (3) |
プログラムにもとづく各案件の要請・採択・審査過程の適切性(わが国の協力事業間、他ドナー事業との連携)
わが国の支援による無償プロジェクトはプノンペン側から徐々に北東へ延び、道路交通の観点から見ても、交通量すなわち受益者の多い区間から始められ、整備区間が延長するにつれてこれまでに整備した区間の交通量(受益者)が増えていくように計画された。また、無償プロジェクトの要請-採択のプロセスには技術協力との連携が計られるような仕組みが織り込まれている。
また、カンボジア側・他ドナーとの密接な協議が続けられたことから、評価期間中に無償プロジェクト・技術協力事業で他ドナーと重複した例は一切なく、カンボジア側・他ドナーの上位計画・方針の変更に対応を迫られるようなこともなかった。さらに、同種の事業が並行して行われる際に生じうるリスクにも十分な配慮がなされた。
各事業における代替案の検討については、メコン架橋建設では開発調査でルート選定も含めて地方開発、経済・技術面からの検討が行われた。各事業においても施工性・コスト面・維持管理の面からさまざまな代替案が検討されたが、都市間部分(地方部)における整備水準(拡幅するか否か)に関して、費用便益分析を含む経済性も比較した上で、整備水準と整備延長についての検討が含まれれば、さらに効率的な支援となったものと思料される。 |
| (4) |
プログラム実施の適切性
1992年にわが国は2度に亘るニーズ確認の調査団を派遣し、さらに、チュルイ・チョンバー橋・国道6A線復旧が素早く実施され、緊急のニーズに対応した。その後すぐにメコン架橋建設についての開発調査が実施され、同調査によるルート選定にもとづいて、復旧・改修工事が順次北東へと延び、各事業も予定工期通りに終了し、プログラムとしてタイミング良くスムーズに進捗した。
無償資金協力事業の着手と並行して1992年・93年に12名の研修員に対して道路・橋梁の管理全般に亘るコース(カンボジアの道路・橋梁分野のために特に設置されたコース)が開催され、研修員の多くはその後の無償事業に参画した。また、無償プロジェクトの現場を活用してのOJT(現場研修)が実施され、技術協力事業との連携が図られた。
わが国の整備区間が他ドナーの整備区間と接した例である国道6号線シアムリアップ区間改修においては、世界銀行との緊密な連携がとられ、景観上統一した古代橋の修復が計られ、世界銀行の施工計画との調整も十分に行われた。さらに、同種の事業が並行して行われることによる問題も発生しなかった。
|
5.3. 結果の評価
| (1) |
プログラム目的の達成度
本調査においてプログラムの目的についての目標値は設定しなかった。目標達成度の評価としては各プロジェクトの目標達成度を整理するとともに、プログラムに含まれた事業間の連携効果を定性的・定量的に評価するよう試みた。
各事業は全て目標を達成した。また、無償プロジェクトと技術協力事業との間、技術協力事業間で連携の効果が見られたと評価される。 |
| (2) |
プログラム実施の効果(移動時間・費用の減少および交通量の増加)
プノンペン-コンポンチャム間の移動時間は約6時間から約2時間に短縮され、シアムリアップ-ロリュオス間に移動時間は30分から15分へと半減した。時間コストは2001年で一人・一時間当たりUS$0.35と推計され、移動時間の短縮に伴い移動費用が節減された。車輌運行費用も30%~40%軽減したと推計される。また、プログラム実施によりプノンペン-コンポンチャム間のバス運賃がUS$7.4-9.3からUS$1.8に下がった。
各区間の復旧・改修によりそれぞれの区間の交通量が大幅に増加したのみならず、後続の復旧・改修プロジェクトが実施されるにつれて、以前に復旧・改修された区間においても交通量の増加が見られた。また、大型車がプログラムの実施につれて増加し、プログラムが全体として長距離交通の促進・効率化に寄与したことが判明した。
|
| (3) |
プログラム実施により期待されたインパクト(地方経済・社会への寄与)
沿道住民の雇用・所得、沿道住民の生活、沿道の商店・レストランの数、沿道の農業生産、沿道の工場数・資本金、観光開発(ホテル・客室数)、沿道の土地資産価値(価格)等に関して、プログラムの実施は絶大な好ましいインパクトを沿道地方の経済・社会に与えたと評価される。また、プログラムの実施はカンボジア国民に広く認知されていると判断される。 |
| (4) |
マクロ経済への寄与度
全国の人・貨物の移動・輸送、国内総生産、輸出・輸入、物価、カンボジアへの訪問客数等の指標について分析した。プログラムの進捗時期と、これらの指標が好ましい変化を見せた時期とが一致することから、プログラムの実施がマクロ経済の発展に寄与したことをうかがわせるが、数値的な分析が十分できず、プログラム実施の寄与度は分析できなかった。 |
| (5) |
プログラム実施による負のインパクト
交通事故の増加、過積載車による道路・橋梁への損傷が負のインパクトとして指摘されているが、プログラム実施によりどの程度これらの負のインパクト引き起こされたかの分析はできなかった。 |
| (6) |
自立発展性(カンボジア側による整備された道路・橋梁の維持管理および類似プロジェクトの実施可能性)
本調査の現地調査の時点では、プログラムにより整備された全区間で目立った損傷は見られなかったが、過去の調査によればプログラムにより整備された道路・橋梁が完成後ずっと十分に維持管理されてきたとは言い難い。
今後の維持管理について、人材、施設・機材面ではほぼ問題ないと判断されるが、予算面がボトルネックであると考えられる。
今後の類似プロジェクトとしては主要国道以外の国道・州道・地方道の整備があるが、その膨大な距離から、資金協力等について、引き続きわが国をはじめとするドナーの支援が求められよう。 |
|
6.教訓と提言:
| (1) |
案件要請・採択までのプロセスの他国援助への適用
カンボジアの道路・橋梁分野への支援においては、わが国・カンボジア側双方がお互いの計画・方針を理解し合い、協調しながら上位目的と整合性のとれた案件が要請・採択され、適切な実施が確保できるようなプロセスがうまくでき上がっている。また、協力の重点分野として道路・橋梁分野が掲げられるとすぐに、多数の研修員受入が行われたことは、その後の無償資金協力プロジェクトのスムーズな実施に大きく寄与した。他国での援助のモデルとしても適用可能な点が多い考えられる。 |
| (2) |
ベースライン調査 ・モニタリングの実施と援助効果に関するデータの蓄積
基本設計調査の段階から、期待される効果、効果発現の程度を計測するための指標、指標データの入手手段について、わが国・カンボジア側双方で検討・協議することが提言される。また、カンボジア側においてもカウンターパートとしてベースライン調査・モニタリングを行い、少ない費用でも可能なデータの収集・分析を行えば、各事業やプログラムの効果を客観的に示すことができ、より効果的・効率的な援助資源の活用と将来の優良案件要請につながると考えられる。 |
| (3) |
維持管理財源確保のための制度整備・運営支援
今後の道路維持管理の実施はそのための予算措置次第といえる。カンボジア政府・公共事業運輸省は車輌登録税、通行料金、国境通行税、燃料税等の徴収して道路・橋梁の維持管理に充てることを計画し、独自財源確保への取り組みを始めたばかりである。定期的な保有登録・車検制度、自動車保有にかかる税金(重量税等)の徴収制度等について、わが国の経験を生かした制度整備・運営のための支援が提言できる。 |
| (4) |
日常点検・清掃・早めの修繕の実施
限られた予算で維持管理を効果的に行うためには、日常的な点検・清掃・早めの修繕が重要であることは論を俟たない。まず、カンボジア側に着実な実施を提言したい。わが国に対しても、日常的な点検・清掃・早めの修繕を実際に担当する各州公共事業運輸局・その傘下の地方事務所職員の人材育成を目的とした、カリキュラム・教材の開発および講師育成のための支援が提言される。 |
| (5) |
国土のグランドデザインにもとづくマスタープラン策定への協力
今後も、一般国道・州道・地方道レベルの道路修復に対しての支援が求められるが、優先度・整備レベルは地方々々の社会経済開発の方向性によって異なってくる。援助資源の最適配分のためには全国的な視野に立った道路網整備に関するマスタープランが必要である。マスタープランのさらに上位に位置する、日本でいう全国総合開発計画のようないわば国土のグランドデザインにもとづくマスタープラン策定に向けて、わが国の経験を生かした技術協力が提案できよう。 |
| (6) |
一般国道、州道の修復に対する協力
一般国道・州道を合わせると距離でいえば主要国道の2倍以上となる。上記のマスタープランにもとづく協力の対象となる候補区間もしくは地区の絞り込み・整備水準の検討、および、地元業者のより一層の活用等が課題となると考えられる。また、道路・橋梁の復旧・改修の整備水準と整備延長に関して、社会性・経済性等の分析結果を示した上で、カンボジア側との協議・検討を重ねることにより、さらに効率的な援助資源の活用が可能となろう。 |
| (7) |
地方道の修復に対する協力
農村における道路整備は灌漑施設・社会インフラ施設とも密接に関わり、農村でのインフラ整備はセクター毎のアプローチよりも、農民組織を単位とするアプローチの方がうまく機能する可能性が高いと考えられる。コミューン(Commune)等を単位とするコミュニティーが主体となる計画・実施、および、地方開発省(中央・州・地区(District)レベル)による計画立案支援と計画審査のための技術協力と事業実施のための資金協力とを組み合わせた仕組みの構築が必要となろう。草の根無償プロジェクトのような事業を本格的・全国的(もしくは重点地区)に展開するための新たな協力スキームの構築が提言される。
|
|
7.外務省からの一言:
| (1) |
チュルイ・チョンバー橋に続き、わが国の無償資金協力援助で完成したメコン架橋「きずな橋」についても2003年4月に発行された500リエル新紙幣の図案に採用された。カンボジアのわが国の支援に対する感謝の気持ちが伺われ、わが国の援助がカンボジアの発展に寄与している表れと思料する。 |
| (2) |
報告書にある溜め池アクセスロード改修プロジェクトを支援した草の根無償協力は、2003年度より草の根・人間の安全保障無償資金協力に発展改正され、1つの地域において、インフラのみならず教育、医療等複数の分野の活動を総合的に支援することとしている。 |
|
