1.評価対象プロジェクト・プログラム名:
サンパウロ州森林・環境保全研究計画 |
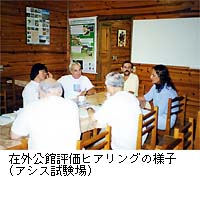 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
| 2. |
国 名:ブラジル
実施機関名:サンパウロ州環境局森林院 |
|
| 3. |
援助形態:
プロジェクト方式技術協力/1992~97年度/
専門家派遣29名/研修員受入11名 |
|
4.評価実施機関名:
在サンパウロ日本国総領事館(現地コンサルタントによる評価) |
|
5.現地調査実施期間:2001年2月12日~2001年2月15日 |
|
6.プロジェクト・プログラムの分野:環境 |
7.政策目的又は政策の方向性:
サンパウロ州森林院による土壌浸食防止及び森林回復に関する研究成果が実用技術開発に活用される。
|
8.当該プロジェクト・プログラムの目的:
浸食地の実態及び機構の解明、土地利用形態による浸食への影響調査、浸食防止法の開発と実証、森林造成法の開発、環境保全効果の検討を行い、サンパウロ州森林院が、荒廃地における土壌浸食防止及び森林回復に関する研究を自立発展的に行う能力を高めること。 |
9.外務省からの一言:
| (1) |
本評価では、98年1月の技術協力終了以降の森林院による同プロジェクト関連活動を中心に評価を実施した。
この結果、協力期間中に開始された研究活動は引き続き維持され、その研究成果は、学会、学術論文及び出版物等による発表(約40件)、ホームページ(http://www.bdt.org.br/mata.atlantica/flora/caetetus/)及び(http://www.bdt.fat.org.br/cerrado/flora/sp/)
内のデータベース(随時更新中で協力期間中に収集した天然植物に関する情報を掲載)、市民に対する環境教育(年間約1万人)、第三国研修、農業技師による農家啓発の実施等により各層に普及され、有益な結果をもたらしているものと評価できる。 |
| (2) |
プロジェクト対象地域は、しばしば地域の大学生の研究・実習テーマとして取り上げられるとともに、技術者や農家に対する環境回復技術の説明にも活用されている。 |
| (3) |
我が国からの供与機材施設に関しては、フィールドで使用する観測用パソコンの故障や量水堰堤に軽微な改修を必要とする箇所があった他は、概ね良好な状態で維持管理されていることが確認された。 |
|
10.提言(今後のフォローアップ、改善すべき点、政策的な観点からの提言):
| (1) |
同プロジェクトによる土壌浸食や植林が環境に与えるメカニズムの解明には長期の継続観測が必要であり、今後とも研究が継続されその成果の普及が推進されることが望まれる。
同プロジェクトにおいて移転された技術は、国内をはじめ南米諸国及びポルトガル語圏アフリカ諸国の技術者を対象とした第三国研修等を通じ海外にも普及されている。このJICAとの第三国研修は1990年から99年にわたり実施され、約110名の外国技術者に研究成果が移転されている。
現在森林院では、同研修の実施によって得たノウハウを活かした新たな第三国研修を計画中とのことであり、今後は、当該分野における南米地域の拠点として、森林の乱開発による環境破壊が社会問題化している国や地域に対して同プロジェクトの成果が広くに普及されることが期待される。 |
| (2) |
同プロジェクトで導入された各種観測機器は、研究の特殊性から日本製のものが多いが、メンテナンスの際ブラジル国内では交換部品が見つかりにくい場合もある。一方、プロジェクト開始後10年以上が経過し、分野によっては国内製観測機器を用いた研究が可能となったものもあることから、今後は、コスト・パフォーマンスを十分検討した上で国内で維持管理が可能な機材と交換していくことが望ましい。 |
| (3) |
土壌浸食防止研究に関しては、プロジェクト期間中に開始された地元パラガス農業大学との提携による研究生の参加は現在も継続されているが、更に効率的な研究推進のために、試験地の人員の増強が望まれる。このため、森林院自身の研究体制整備とともに、関連する分野の他の研究機関、普及機関との連携の拡大も考慮されるべき事項である。 |
|
11.外務省からの一言:
ブラジルは、「地球の肺」とも呼ばれるアマゾン熱帯雨林に代表される、鬱蒼とした自然林を持つことで知られていますが、一部の地域では、森林減少が進み、そのために水の汚濁や枯渇といった問題まで出始めている。地球の財宝とも言えるブラジルの自然林の保護と破壊された森林の回復のため、日本は今も協力を続けている。
|
