| 1.評価対象プロジェクト名:植物ウィルス研究計画 |
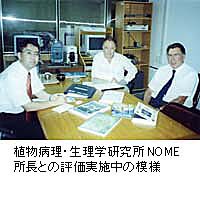 (クリックすると画像が変わります)
(クリックすると画像が変わります)
|
2.国名:アルゼンチン
実施機関名:国立農牧技術院(INTA)、植物病理・生理学研究所(IFFIVE) |
| 3.援助形態: |
プロジェクト方式技術協力/1995年~2000年/ |
| | 機材供与額 282,410千円/ |
| | 専門家派遣(長期5名、短期13名) |
| | 研修員受入18名 |
|
|
|
| 5.現地調査実施期間:2001年3月15日 |
| 6.プロジェクトの分野:農業 |
7.政策目的又は政策の方向性:
植物ウィルス病に対する防除法を確立してアルゼンチンの農作物の生産性及び品質を改善する。 |
8.当該プロジェクトの目的:
アルゼンチンで栽培されているトウモロコシ、ダイズ、トマト、ヒマワリ4作物のウィルス病の問題解決を通して、植物病理・生理学研究所 (IFFIVE)の研究活動を強化する。具体的にはトウモロコシ(リオ・クワルト病、トウモロコシ・ドワーフ・ウィルス病)、ダイズ(ダイズ・モザイク病、ジェミニ・ウィルス病)、トマト(ベステネグラ病)、ヒマワリ(退緑斑紋ウィルス病、軽微モザイク病)の作物に感染する7つの主要ウィルス病を対象にして研究を行う過程で、植物病理・生理学研究所の研究員(カウンターパート)の資質の向上を目的に必要な研究施設の充実、研究資機材の供与などを行うとともに長期・短期専門家がそれらの施設・機材を駆使してカウンターパートに技術移転を行い、また、技術移転で不足する部分については、日本における研修で更に高度な技術移転を行う。 |
9.評価結果:
本プロジェクトを通じて、目的とされた4作物のウィルス病のウィルスの分離、同定に関する技術が確立された。また実験マニュアル及び病害解説書が作成され、各地に所在する農業改良普及所に対して配布が行われたことにより地域レベルでのウィルス病の診断及び防除法が可能となった。
2000年より04年まで植物病理・生理学研究所 (IFFIVE)において「植物ウィルス病の同定と診断」ついて中南米諸国の研究機関の研究者に対してアルゼンチンと我が国が協力して第三国研修を実施しており、中南米における植物ウィルス病に関するリーダー的な位置付けとなっている。プロジェクト終了後も年次報告書の発行、学会等への論文発表を積極的に行っており、目的とされた4作物以外のウィルス病の解明にも取り組むなど成果を上げている。
電子顕微鏡を初めとする各種分析・検査機材等の供与機材については、各責任者が決められて適正に整備・管理が行われており、故障して放置されている機材、修理不能になったり、廃棄された機材は確認されず、現在においても調査・研究のために有効に利用されていた。しかし、植物病理・生理学研究所は人件費を除く運営費については自主的に賄うシステムになっており、今後、供与機材を有効に維持管理するための経費の確保が課題である。特にウィルス診断技術として血清を応用した診断キットを作成し、販売を試みているが単価が高いためか予想されていた収入には結びついていない。
本プロジェクトは2000年に終了した事業であるため、現時点において対象作物についての生産量に関する統計的なデータについて確認・比較することは難しく、さらに行政サイドでの農業作物に関する収穫量等の統計に関する整備がなされていない。 |
10.提言:
本プロジェクトの導入により、植物病理・生理学研究所の研究機材の環境整備は大きく改善され、植物ウィルスに関する技術移転も行われたが、今後も定期的なアフターケアを実施することにより、移転された技術の継続・発展を図ることが重要である。
特に、本分野における技術的な進歩は早くなってきており、「過去の技術」とならないようにするためには、アルゼンチン自身の研究に対する取り組みが必要である。
「顔の見える援助」を行うためには、プロジェクトの成功とともに、技術移転の終了後も継続してアルゼンチンにおける我が国の援助の成果を積極的に広報することが重要である。 |
11.外務省(本省)からの一言:
提言にある通り、技術的な進歩が早い本分野については、アルゼンチン自身の研究に対する取り組みが必要となります。そのため、プロジェクトが終了した2000年から5年間、第三国研修「植物ウィルス病の同定と診断」を実施しており、その枠組みの中で本邦から研修講師を派遣し、同分野の最新の情報を提供するなど、引き続き側面支援を行っています。 |
