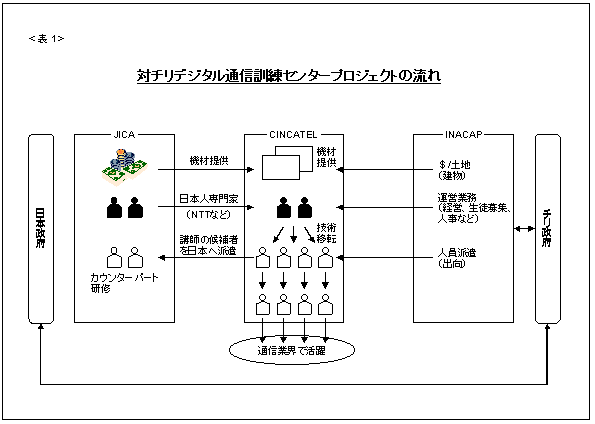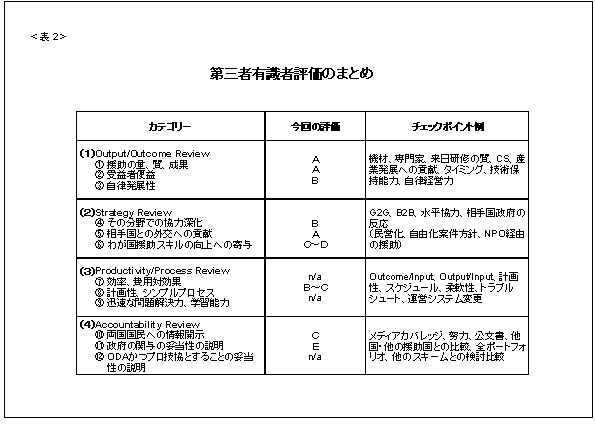有識者による評価
チリ・デジタル通信訓練センタープロジェクト評価報告書
上 山 信 一
ジョージタウン大学政策大学院教授
2001年7月7日
本報告書の構成
要旨
1.評価対象プロジェクトの概要
| (1) |
我が国は何を提供したのか(Output)
わが国は、チリの通信電話サービスのスムーズなデジタル化を支援するために、1992~97年の5年間にわたって、非営利法人(元政府機関)であるINACAP(Instituto National de Capacitacion Profesional、全国職業訓練所)が新規に設立するCINCATEL(Centro Internacional de Capacitacion en Telecomunicaciones、デジタル通信訓練センター)に対して、JICAを通じたプロジェクト技術協力を行った(表1)。
わが国が技術移転した分野は、次の4分野である。
(イ)デジタル交換技術
(ロ)デジタル伝送技術
(ハ)デジタル無線技術
(ニ)通信網計画技術
また、93~97年間の受講生の数は、それぞれ次の通り。
| 93年 |
368人 |
| 94年 |
702人 |
| 95年 |
926人 |
| 96年 |
461人 |
| 97年 |
742人 |
|
| 総計 |
3,198人 |
|
| (2) |
援助のために投入された資源(Input)
本件プロジェクトのために、INACAPは土地と校舎、および事務管理機能を用意し、わが国が研修の内容そのものの設計、技術移転を行った。総額およそ12.9億円のプロジェクトで、そのうち約3割をチリ側が、残りの7割をわが国が負担した。(内訳 日本10億円、チリ2.9億円)
わが国の負担は、次のとおり。
(イ)教官を教育するための長期専門家延べ6人、(ロ)同じく短期専門家述べ23人(うち長期調査員3名)、(ハ)機材15セット(総額5億5百万円相当)を無償で供与。
|
| (3) |
成果(Outcome)
直接的な成果は、(1)専門家派遣と来日研修によって、講師を20人育成したこと、(2)さらに彼らが供与した教材を使用し、5年間に延べ3,198人の受講生を通信業界に送り出したことにある。
さらに、2次的な成果としては、そのことを通じて、(3)自由化直後、かつデジタル化の課題に直面していた通信業界およびサービスの発展に貢献したこと、(4)プロジェクト終了後も、INACAPは、この分野での研修事業を拡大し、技術者の育成に貢献し続けていること、(5)さらに、INACAPがJICAとの協働事業として、中米などの第三国からも研修生を受け入れるまでに育ったこと、(6)以上のことを通じて、日本とチリ、チリとラテンアメリカ諸国、さらには日本とラテンアメリカ諸国の友好に寄与していること、などが挙げられる。
|
2. 評価のアプローチ
ODAのいわゆるプロジェクト評価は、これまで、ともすれば「相手国の満足度」および「対象案件が所期の目論見どおりに機能しているかどうか」という視点からの評価に終始しがちだった。しかし、上記の2つは、援助活動を企業活動に例えれば、いわば「商品」の品質が良く,かつ顧客に愛されているか、という最低限のことを検証するものでしかない。
例えば,援助プロジェクトの真の成否は、むしろ案件供与の後に相手国がどのような自助努力を始めたか,あるいはその後,民間レベルの交流も含めた交流がどれだけ盛んになったか,といった「戦略持続可能性」の観点からチェックされるべきである。でなければ、単にわが国から相手国に外交的な贈与をしたに過ぎず,いくら資金を投入しても際限がない。
また、プロジェクトには多額な税金が投入されている。しかも、プロジェクトのコストは、単に相手国に供与した金額にとどまらない。「プロジェクトの運営効率」は、当然、評価の対象とするべきである。即ち,案件の発掘段階からの一連の作業や援助活動自体の効率性やスピードもチェックすべきである。ちなみに、これは単に担当者の技量や意識の問題だけではない。東京と在外の両方でのJICAや外務省の組織のあり方,そして仕事のやり方などにも大きく左右される。
要するに,ODAの成否は、個々の援助対象案件(施設建設や人材育成活動など)の成否だけからは、判断できない。援助関係者も国民も,援助活動のいわば「商品」にしかすぎない案件評価,すなわちプロジェクト評価の結果でもってODAの成否を論ずるという発想を卒業するべきである。
確かに援助した機材が有効に使われていないといった例がありうるかもしれない。しかし、わが国のODAは、もはやそういった初歩レベルの課題は克服しつつある。そして、国民の関心も「そもそも,なぜあれだけ多大な人材と予算をODAに投入し、援助をする必要があるのか?案件はいったい誰がどういう判断のもとで決めるのか?」といった根源的なところにシフトしつつある。さらには、「援助活動自体が,いわゆるお役所仕事の非効率なものになっていないか」といった疑念が一部にあることを直視すべきである。
そこで、本件評価では、評価の対象はあくまでもチリのデジタル訓練センタープロジェクトとしつつも、極力、上記のような視点で評価をすることにした。これまでの「有識者による評価」の前例は全て参照した。その上で、今回は、従来の報告書のスタイルは一切踏襲せず,時代の要請にあった新しい切り口からの評価を試みた。
また、作業にあたっては,ODAを特別視せず,公共事業や一般市民サービスにおける行政評価のノウハウを全面的に採用することにした。援助の「顧客」は他国民であり,あるいは他国の経済社会そのものである。そのこと自体はユニークである。また、外交的配慮も必要である。
しかし、わが国国民の税金を投入して行われている以上,一般国民に納得の行く形での説明,そして評価が不可欠である。以上の考え方に従い、今回は、次の(1)~(4)の4つの視点からの評価をすることにした。
| (1) |
援助対象案件の価値(Output/Outcome Review)
(従来、「プロジェクト評価」とされていたものの大半はここに相当)
| - |
提供した援助の量・質の妥当性と成果(No.1)) |
| - |
最終受益者(相手国の産業界、相手国国民など)にとっての便益(No.2)) |
| - |
自律発展性(移転した技術の維持、施設のメンテナンスなど)(No.3)) |
|
| (2) |
戦略的持続可能性の評価(Strategic Review)
| - |
相手国とのODA and/or ODA以外の形態での次の次元の協力関係への発展(民間レベルの協力、官民レベルの協力など)(No.4)) |
| - |
相手国との新たな外交関係への発展(No.5))) |
| - |
このプロジェクトの経験をわが国自体が新たな援助・政府間協力スキームの開発(水平協力、三角協力、新スキームなど)につないでいるか(No.6)) |
|
| (3) |
プロジェクトの運営効率の評価(Productivity/Process Review)
| - |
効率性:OutputおよびOutcomeに対して、必要十分かつタイムリーなInputだったかどうか(No.7)) |
| - |
計画性とシンプルプロセス:事前に十分な計画を立てたか。また、不必要な不安や無意味な手続き、手待ち時間を生じなかったかどうか(No.⑧) |
| - |
フォローアップを十分にやっているか。また、プロジェクトの途中で生じた問題点を迅速に解決し、かつ今後の他のプロジェクトのやり方にも生かせているか(No.⑨) |
|
| (4) |
説明責任評価(Accountability Review)
| - |
本件プロジェクトの概要、成果などを正しく、オープンに日本国民(納税者、議員など)と相手国民に伝えているか(No.⑩) |
| - |
そもそも、なぜ政府が関与すべきテーマであったかということについて、説明可能か(No.⑪) |
| - |
そもそも、なぜODAでやるべきであったのか、ということについて説明可能か(No.⑫) |
なお、以上の視点は,従来「プロジェクト評価」といわれていたものの域を,大きく超える。また、わずか1週間の間に、しかも、私一人でやりきれるような作業ではない。従って,どこまで正式な評価結果と言い切れるかは、疑問なしとしない。しかし、従来型の(ありきたりの)プロジェクト評価を単にやったのでは,それこそ私自身が評価者としてのアカウンタビリティーを国民に対して果たしえないと考えた。
以下の報告は,上のような事情を念頭に置いてお読みいただきたい。 |
3.現地調査の概要
今回の評価活動のために行った活動は、以下の通り。
| (1) |
事前打ち合わせ(@日本)
過去の関連資料の読み込み、ブリーフィング、面談インタビュー先の選定、データ収集
|
| (2) |
現地調査
以下の機関を訪問し、面談インタビューをした。なお、調査には外務省経済協力局の職員と大使館員が同行した。英語による面談は通訳を使用しなかったが,スペイン語については通訳を使用した |
| (イ) |
プロジェクトの直接的な関係者
| - |
INACAP、研修生派遣企業(ENTEL、Telefonica CTC) |
| - |
国際協力庁、通信省次官官房 |
|
| (ロ) |
チリの電気通信市場、民営化、自由化についての有識者
| - |
ラテンアメリカカリブ経済委員会、経済省、CORFO、国際電気通信連合(ITU)、三菱商事、NEC、SONDA |
|
| (ハ) |
日本側関係者
| - |
在チリ日本大使館(ODA担当者)、在チリJICA事務所 |
なお、今回の評価活動では、予算、人員の制約があり、以下のような本格的な評価分析作業は行っていない。 |
| (a) |
受益者に対するアンケート調査 |
| (b) |
マクロ経済データ、セクターデータ(デジタル化など)と本件プロジェクトの相関関係の両国関係機関のトップマネジメントレベルへのヒアリングについての計量分析 |
| (c) |
現地資料による文献調査 |
4. 評価結果
まとめは、表2の通り。その根拠を、以下に示す。 なお、定量分析をする時間も資源もないので今回は、私が期待する達成水準を現状と比べ、主観的な格付けをしてみた。 具体的には、5種類で、A:期待を上回る達成状況、B:期待水準をクリアーしている、C:今後の工夫で努力の余地あり、D:できていない。E:そもそも、これまで重要課題としてあまり認識されていない、とした。
ちなみに、以下は、政策評価の専門家としての知見に基づくものではあるが,あくまで、主観的な格付けにしか過ぎない。解釈に当たっては,くれぐれも誤解のないようにされたい。
|
(1) |
援助対象案件の価値(Output/Outcome Review)
| 1) |
提供した援助の量・質の妥当性と成果(A)
| ・ |
供与機材については、当時のチリでは唯一ここにしかないものであり、極めて効果が高かった。(A) |
| ・ |
派遣した専門家の技量、日本での研修内容については、当時のチリの通信産業が抱えていたニーズにマッチしていた。(B~C) |
| ・ |
チリ大学が主に理論面やエンジニアを、INACAPがより実践的な分野を中心とするテクニシャンを育成するという分担がうまくいった。(B) |
| ・ |
受講生の満足度も高い。特に、設備を使った実習が十分にできる場としての評価が高い。(A) |
|
| 2) |
最終受益者(産業界、相手国国民など)にとっての便益(A)
| ・ |
INACAPを通じて、既存大手企業だけでなく新規参入者や保守メンテナンス企業にも同時に学習機会を提供でき、産業全体への貢献ができた。(A) |
| ・ |
チリの通信産業は、民営化、自由化に続いて、本件を含む技術導入をスムーズにこなし、その後の外資をテコとする海外市場への展開(Entel)や、インターネット対応をスピーディにこなした。(A) |
|
| 3) |
自律発展性(移転した技術の維持、施設のメンテナンスなど)(B)
| ・ |
INACAPは、本件プロジェクト以降、通信分野の事業を安定収益事業として維 持している。現在まで、年間1,000人弱の研修実績を保っている(ただし、教授コースの内容は、当時のものではない)。(A) |
| ・ |
INACAPは、デジタル化以降、情報通信業界が直面したインターネット対応においても、CISCO社とうまく提携し、技術提供している。(A) |
| ・ |
ただし、無線分野では、専任講師がいないなどの問題点があり、また、日本の援助で提供した機材や知識、きめ細かなアップグレードができていない。(D)
|
|
|
| (2) |
戦略的持続可能性の評価(Strategy Review)
| 4) |
相手国とのODA and/or ODA以外の形態での次の次元の協力関係への発展
(民間レベルの協力や官民協力など)。(B)
| ・ |
本件でINACAP移転した技術を、さらにラテンアメリカの第三国に移転する研修プロジェクトを日智共同で実施している。参加者の満足度は高く、このことはINACAPに技術がうまく保全継承されていることの証左でもある。また、わが国のボリビアに対する技術協力の専門家派遣をINACAPが行うという実績もある。(A)
|
| ・ |
本件終了後、我が国の関係企業(NTT、NEC、DoCoMoなど)とINACAPとの交流は特になく、先方は物足りないという印象を持っている。しかし、JICAとしては、2000年10月にDoCoMo技術者を政府電気通信総局(SUBTEL)に派遣し、携帯端末サービスを実施する等のフォローアップを行っている。援助を受ける側は評価者に対し、通例、「もっとフォローアップを欲しい」と述べる傾向にある。従って、先方から得た印象をどこまで重要視すべきかについては慎重であるべきである。しかし、チリ側の当時の担当者とは、もっと積極的なコミュニケーションを意識的に続けるべきである。(C)
|
|
| 5) |
相手国との新たな外交関係への発展(A)
| ・ |
本件以降、チリとの協力案件として第三国向け光ファイバー伝送システム研修が成立。(A) |
| ・ |
大統領がIT分野でのわが国への協力依頼を表明。(A)
|
| ・ |
第三国向け研修をきっかけに、チリの国際協力庁が水平協力、三者協力のパートナーとして日本を頼りにしており、チリの対ラテンアメリカ外交政策への貢献としても寄与。(A)
|
|
| 6) |
わが国の新たな援助・政府間協力スキーム開発への貢献(新スキームなど)。(C~D)
| ・ |
本件は、対政府機関ではなく、政府からの要請に基づくものの、INACAPという非営利機関への援助。独立採算を強いられる機関であり、援助の受け入れに対する姿勢や技術の保持にも、極めて熱心。INACAPの運営スキル自体が他国向けや他の案件の援助にも生かせたかもしれない。例えば、相手国に同様の機関を設立するよう勧める、あるいはINACAP自体の経営スキルを三角協力として第三国に移転するなど。(E) |
| ・ |
わが国関係者の中には、「民営化してしまった電話会社への協力」が援助足り得るか、という逡巡が見られるが、NPOを介するという手法の斬新さや、急激な自由化に伴い競争についていけないベンチャー中小企業に対する技術供与という「市場環境作り」へのメリットを正しく理解すべきである。(C~D)
|
| ・ |
本件をきっかけに、チリおよびラテンアメリカの情報通信産業に関わっていこうという「国家としての意思」あるいは「ビジネスセンス」の弱さを感じる。これは、外務省やJICAだけの問題ではないし、現行の援助・予算制度などの制約要因に負うところも大きいが、技術援助だけやり、あとはノーコメント・ノーウォッチというのはおかしい。例えば,JBICの海外投資に対する融資などのスキームに切り替えて、何らかの形で引き続き関与する工夫など幅広い選択肢を考慮すべきである。(C~D)
|
|
|
| (3) |
プロジェクトの運営・効率評価(Productivity/Process Review)
| 7) |
効率性:OutputおよびOutcomeに対して、必要十分なInputだったかどうか。
(n/a)今回のわずか1人での1週間の調査では、この点の分析は不可能)。
|
| 8) |
計画性とシンプルプロセス:事前に十分な計画を立てたか。また、不必要な不安
や無意味な手続き、手待ち時間を生じなかったかどうか。(B~C)
| ・ |
チリ側関係者の間に不満は見られなかった。JICAの仕事は、おしなべてきっちりしており、予定通りあらかじめ定めた目標に沿って物事をやり抜くという評価を得ている。(A) |
| ・ |
しかし、オペレーション上の細かなことや日本における研修の日程、時間割などがあまりにも厳格かつ詳細に過ぎ、柔軟性に欠けるという指摘があった。
(C~D) |
| ・ |
また、当初のプロジェクト計画書を見ると、デジタル化という従来にはない変動に際しての研修需要であるにもかかわらず、技術者の従来の労働時間に占める研修時間の割合を基に需要を算出しており、合理的根拠に欠ける。現に、実績値との乖離が大きい(表3参照)。但し、この問題の根っこには硬直的な政府全体の予算制度の問題があり、おそらく計画策定能力の問題ではないと思われる。(C~D) |
|
| 9) |
フォローアップを十分にやっているか。また、プロジェクトの途中で生じた問題点を迅速に解決し、かつ今後の他のプロジェクトのやり方にも生かせているか。(n/a)
| ・ |
今回の調査の範囲では、そもそもプロジェクトの途中で特に大きな問題が発生したという事実が発見できなかった(n/a)。 |
| ・ |
しかし、関係者の一部には、プロジェクトの終了後のフォローアップがないことや、以後の援助要請に対して十分な回答(だめな場合の理由の説明がないなど)がないことへの不満が聞かれた。前者については政府全体の予算制度の問題にも起因するが運用上の工夫が欲しい。後者については、いわゆる「お役所仕事」への不満であり、抜本的な対策が必要。(D)
|
|
|
| (4) |
説明責任評価(Accountability Review)
| 10) |
本件プロジェクトの概要、成果などを正しく、オープンに日本国民(納税者、議員 など)と相手国に伝えているか。(C)
| ・ |
CINCATEL/INACAPが日本の協力によるものであることは、必ずしもチリの通信関係者の間で知られていない。新聞報道も記録があって確認できたものだけだが、わずか4回と限られている。(C) |
| ・ |
当時のチリ側の関係者の中には、「日本側(JICA)は、日本が援助したことをあまりいたづらにアピールしたくないともらしていた」と述べる人がいた。このような態度については、「相手国の事情にもよるし、今では違うが、かつてはそれが援助の美風とされていた」というコメントを帰国後複数の日本人の援助関係者から得た。(D) |
| ・ |
JICAのプロジェクト終了時の評価報告書は、良い点のみならず、将来の懸念事項(専門家がCINCATELの評議会に入っていないなど)も含めた率直な内容コメントを書いている。ODAの基礎知識のある議員や関係者に対する説明責任が、一応は果たせている。(A)
|
|
| 11) |
そもそも、なぜ政府が関与すべきテーマであったかということについて、説明可能か?(E)
| ・ |
今回、訪問調査の結果,筆者は本件援助が有効であり,必要なものであったという確信を抱くに至った。しかし、そもそも、当時,政府として対チリ援助、特に本件援助の必要性について十分に国民に対して説明しようという姿勢があったかどうかは疑問である。 |
| ・ |
例えば,プロジェクト関連の一連の公文書を見る限りは、すべてが「外交上の重要性」「相手国の要請」のみを論拠にしており、なぜ本件援助が必要なのか、という根幹に触れる説明がない。
|
| ・ |
わが国には、銅、水産などの資源外交やアルゼンチン、ブラジル、メキシコなどとの外交バランス上の配慮から、またAPEC外交のうえからも、チリとの関係を深める固有の理由がある。しかし、中進国であるチリに対しては、例えば米国は一切援助をしていない。また、世銀やUSAIDは情報通信分野は、そもそも援助対象としていない。従って,特にチリに対する、通信案件の採否の経緯については、本来は,国民に対して積極的な説明をする必要があったのではないか。
|
| ・ |
上のようなことは,当時の政治行政風土に照らしてみれば、特に落ち度があったと責めるほどのことではない。しかし、こうしたことの積み重ねが、今日の八方美人外交orばらまき援助という批判の要因となっていることは想像できる。現場職員の献身的な働きぶりにもかかわらず,ODAが批判にさらされやすい要因の一つには,このような消極的なコミュニケーションの姿勢があると思料される。
|
|
| 12) |
そもそも、なぜODA、しかもプロ技協でやるべきであったのか、ということについて説明可能か?(n/a)
| ― |
プロジェクト関連の公文書を見る限りは,本件がなぜ,プロジェクト方式技術協力に値するのかを説明した記述はない。当時の援助の制度や予算の枠組みから考え,関係者の間では,おそらく当然の判断だったと思料される。筆者もまた,結果的にそれが問題であったという印象はまったく持たない。(n/a) |
| ― |
しかしながら、説明責任という観点からは、とうてい受け入れられるものではない。今後の案件については,即刻、改善すべきである。(D) |
|
|
5.今後に向けた課題提起
本件調査案件自体は、すでに成功裏に終了しており,特段の提言はない。ただし、今回の現地での評価作業を終え,今後に向けてのいくつかのアイディアを得たので、紹介しておきたい。ちなみに、わたしは,「行政評価」および「行政経営」の専門家であり,農業や通信といった「援助対象技術」やODA自体の専門家ではない。また,普段は主に米国で活動しており,国内の慣行・制度の常識にとらわれない視点を大事にしたい。そこで、以下では,行政機関が行う「事業経営」としてのODAの制度、運営方針、さらには「評価制度」自体についても若干の課題提起をしたい。なお、「本件調査は、あくまで個別案件を対象にしており,それに直結しない内容は課題提起といえども、作業の成果とするかどうか疑問」という批判がありうる。あるいは「チリの案件調査からだけで導き出せる意見ではない。また、有識者評価の域を越えた一個人の意見に過ぎない」という疑問もありうる。確かに,分析を経た意見でもなく,所詮は,課題提起にしか過ぎない。しかし、私の専門知識は、ともあれ「経営と評価」に関するものである。喩えていえば,「あるプロジェクトや商品(案件)を評価することによって当該企業の経営について、さらにその企業の経営評価のレベルまで、おおよそ察しをつける」という類の洞察を専門とする。しかも、「専門家としての良識に則って,気づいたことは全て記述する」というのがこれまた、海外の行政評価の常識である。このような文脈のなかで、以下は解釈されたい。
| (1) |
援助の政策と執行に関する課題提起
| ― |
米国の大手IT企業のCISCO社がチリ大学とINACAPに対して技術協力をしている(おそらく他国でもやっている)。今後のIT協力の分野では、政府間の意見交換だけでなく、これら企業との情報交換も大切。 |
| ― |
独立採算のNPO(今回のINACAPなど)を経由した援助の成功率は高いのではないか。今回の評価対象プロジェクトはNPO経由の援助のユニークな成功例といえる。政府間援助の形態にのみこだわっていると、スピードが遅い。また、特に先進技術の分野では内容も陳腐化する。今後は、政府機関に対する援助だけではなく、このようなNPO経由の援助の可能性を追求すべきではないか? |
| ― |
チリのような中進国に対する援助では、「民営化」、「健全な自由競争市場の形成」への貢献を援助の対象分野として明確に位置付けるべきである。それに先立ち,これらの政策が産業全般の生産性向上に与えるインパクトの大きさやそこへの有効な援助戦略の分析などが必要ではないか? |
| ― |
南南協力は、外交上のメリットだけでなく、援助の業務の効率化という意義も大きい。この点は,国民に対し、もっとアピールすべき。成果を計量化して明示するべき。 |
|
| (2) |
作業に付随して得たODAの制度・経営体制についての仮説的な課題提起
本プロジェクトは、個別プロジェクトとしては、かなりうまくいった案件である。また、現地で、さらに東京でお会いした関係者の士気も高かった。とかく、批判されがちなODAではあるが,想像以上にしっかりと管理、運営されているという印象を得た。
しかし、今回のチリの案件の現地調査、およびその準備の学習過程では、すでに識者が指摘するとおり、「ODAには制度疲労が目立つ」という印象も得た。制度疲労の問題は、政府関係者の権限と責任の域を越えており,また彼らの努力だけで解決できる問題でもない。また、政府部内から出てくる知恵にはおそらく限界がある。広く,国民各層がこの問題を理解し、政府の外から関与していく必要がある。そこで、今回の調査の副産物として得たわたしの問題意識を記しておきたい。
なぜならば、冒頭にも述べたとおり、本件調査の直接の対象となったチリの案件のような「個別案件(プロジェクト)」の成否やその実施の改善方法を見直すだけでは、評価者として国民に対する説明責任を果たしたことにはならない。さらにまた、いかなる評価作業も、究極の目的は、「国民がより納得する,よりよいODAの運営」にあるからである。以下は,今後,外務省と国民各層が、今後のODA、そしてODAの評価のあり方を考えるきっかけとして紹介しておく。
| 1) |
まず,チリに行く前の事前準備の過程で戸惑ったのが、わが国ODAの全体戦略が分かりにくいということである。案件段階になると、目的も計画も非常に明快でありわかりやすい。だが,そこより上位の戦略レベルになると,抽象的な用語が並び、たいへんわかりにくい(ただし,これは,何もODAに限ったことではなく,公共事業などわが国政府の事業全体についていえることである)。ともあれ、参考までに公開されている米国のUSAIDの年次戦略計画書を紐解くと,言語のハンディーを超えても、ずっと明快でわかりやすかった。例えば、USAIDの戦略計画書の場合,地域や事業分野といった枠組みを超えて、「国策」という視点から数項目の(例えば,「民主化支援」など)重点戦略領域を示し、それに沿ったデータと、それに基づいたODA戦略を示している。また,それに沿った実績評価報告書を毎年出しており、極めてわかりやすい。
|
| 2) |
また、行政評価の専門家として、今回、チリの現地に赴き,とりわけ痛感したのが,「プロジェクト(個別案件)」レベルでの評価から,戦略,政策レベルの評価への力点のシフトの必要性である。そして、それに基づく上記1)で述べたような戦略計画の充実の必要性である。わが国では歴史の浅い行政評価だが、米国行政学会等の専門家会合の場では、「評価の手法は、政策課題,国民の関心事にあわせ、ダイナミックに進化させるもの」という考え方は常識に近い。すでに、外務省も作業に着手しつつあるが、今後は早急に戦略、プログラム面での評価へとバージョンアップする必要がある。理由は,3つある。第1には,国民の関心の変化である。かつては,国民やマスコミの関心も援助物資が有効に生かされているか、といった,「プロジェクト(個別案件)」の成否に集中していた。しかし、今や、国民の関心事は、戦略、政策、あるいは案件選択の考え方,といった領域に移りつつある。第2には,わが国のODAの実施能力の向上である。案件の選択に始まり,その実施、フォローに至るまでノウハウの蓄積がなされてきており,外部からの評価を充実させるよりも、自助努力をさらに求め,むしろその過程と結果の妥当性は、実施機関の情報公開に求めていくべきである。第3には,中央省庁と実施機関、あるいは独立行政法人が政策評価をそれぞれ、どのように分担するかという観点からの見直しの必要性である。例えば,他省庁では、個別の事務事業やプロジェクトの評価は、実施機関(あるいは独法)に任せ,中央省庁はむしろ戦略、プログラム面の評価に注力するという考え方が一般化しつつある(ただし、公共事業などの大きな、あるいは重要な事業については例外(総務省の政策評価ガイドライン))。例えば、JICAやJBICの案件については、外務省は「プロジェクト(個別案件)」レベルの評価よりも、戦略、プログラムレベルの評価、あるいは「委託先」としての彼らの仕事ぶりの評価へとシフトさせる案が考えられる。ODAの評価については、外務省もJICAも従来、他省庁に先駆け、早くから熱心に取り組んできた。しかし、それが故にかえって、先例、慣行にとらわれ,結果として戦略,プログラム面の評価についての取り組みが遅れるといった事態に陥ってはならない。ちなみに、セクター別,あるいは国別援助政策をもって「戦略」あるいは「政策」とすればよい、という考え方が一部にある。過渡的には、そういう作業も有効である。しかし、それは所詮、個別案件についての評価を積み上げただけのものであり、「戦略」や「政策」とはいえない。概して,既成事実を整理,裏書きする以上の効果は期待しにくいのではないか。すでに着手しつつあるバージョンアップの作業であるが,さらに加速させ,かつ目標を高く設定していくべきである。
|
| 3) |
さらに、今回の調査で感じたのが、今後は、現行制度で決められたODAの「商品メニュー」の限界である。例えば今回のチリの案件は、対政府機関援助ではなく、NPOに対する援助という点で、当時としては斬新であり、またプロジェクト技術協力という方式も妥当であった。しかし、以後の訓練施設(援助対象施設)の発展過程を現地で実際に詳しく見ていくと,やがてインターネットの時代に入り,米国のCISCO社がチリでの同社の商品普及を狙って無償で技術協力をする形で進化を遂げていた。これは、形態上は民間企業が見返りも考え,NPOに援助をしているに過ぎない。しかし、関係者は,結果として米国に親しみを持ち,あたかもODAに対するのにも似た感謝の念を抱いているという印象を受けた。本件の場合,CISCO社に匹敵する技術が、残念ながら本邦企業にはなかった。しかも、案件自体ODAになじむかどうかもわからない。しかし、もしも既存のODAの「商品メニュー」の制約を取り払って考えれば、ユニークな協力形態が考えられた可能性は否定できない。おそらく金融商品が複合化、多様化するのと同じように「援助商品」も進化すべき時代に入っているのではないか。少なくとも関係者は、旧来からのプロジェクト方式技術協力、無償資金協力、円借款という「商品リスト」だけにとらわれていては,いけない。こうした新規の「商品開発」の発想は個々の案件を考える中から見えてくる。もちろん、見直しの対象は,単に「商品リスト」だけではない。先進国でも特段に硬直的といわれる予算会計制度等の見直しも必要である。今回のわたしの経験は、ささやかなものだったが,現地の具体プロジェクトに則してこそ,このような自由な発想が生まれる。現場の問題意識を広く吸い上げ、商品メニューを見直すべきである。
|
| 4) |
さらにいえば、商品の見直しとセットで、ODAの経営体制の見直しも必要だろう。これは,組織形態や規模の是非の問題以前に,むしろ業務執行体制のバージョンアップという課題である。例えば、卑近な例をあげれば,民間企業では、海外オペレーションは極力、現地の企業や現地採用スタッフに任せている。国を代表しての援助なので、外国人や現地企業に安易に業務委託は出来ない,という意見はよくわかる。しかし、効率を考えれば、必ずしも,日本人がやる必然性のない仕事もありうる。これも、3)とおなじく、現行の予算・会計・定員等の制度の問題があり,援助の実施機関の判断の域を越えた問題である。しかし、こういった経営体制の見直しなくしては、せっかく評価をしてみても、効率と質の抜本的な改善は,見込めないだろう。
|
|
| (3) |
今後の「第三者有識者調査」のあり方に関する意見
最後に、今回、私がお手伝いした「第三者有識者調査」のやり方および、その発展可能性についての意見を述べておきたい。
| (ア) |
個別案件レベルの「第三者有識者調査」によって評価者および関連職員が得る情報,知見、さらに問題意識は極めて豊かなものがある。必ずしもODAについての専門家ではない有識者を「教育」するという効果も大きい。しかし、海外での調査であり,諸経費はもちろん同行する職員のマンパワーも投入するわけである。それだけの投資をするわけであり、事後にもさらに、有効活用する手立てが考えられないだろうか。例えば、過去1-2年の「第三者有識者調査」の経験者を集め、セクター別・地域別、あるいは課題別のブレーンストーミング(政策提言)の場を設けるなど、重層的活用の仕組みを考えるべきである。
|
| (イ) |
そもそも、「有識者」が行う評価のマニュアルを外務省が作るべきかどうか疑問である。少なくとも、マニュアルが欲しいとおっしゃる有識者から要請があった場合にのみ提供するべきである。わが国には、例えば議員が議会で質問する質問すら、行政当局が準備するという慣行が一部にある。更には、質問を取りに行かないと議員の側から抗議の声があがるという場合すらある。こうした風土を前提とすれば外務省が有識者による評価のマニュアルを用意するという事情はわかるし、実際に有効な場合も多いと考える。
しかし、今回の調査では、私はマニュアルは一読はしたものの使用は、しなかった。なぜなら、有識者は、委託調査の専門作業員ではない。専門分野で培った知見と経験を総動員し,行政当局や関係者が自ら気が付かなかった視点まで提供して初めて,価値が出せると考えたからである。また有識者がマニュアルに沿って評価をしていては,外部の第3者という意味も薄まりかねない。
ちなみに、今回の調査については、マニュアルについての私のこうした方針を外務省は即座に理解した。そして、私自身、調査の準備に当たっても,事後のまとめの段階においても、何ら不都合を感じる場面はなかった。しかし他の有識者の中には、律儀にマニュアルを参考にされる方もおられるかもしれない。そしてマニュアルが評価の質や内容に意図せずして“サブリミナル的”な影響を与えないとは言い切れない。
評価手法は,情報公開によって最も磨かれ,高められる。なぜなら,公開されることによって、「評価される側」だけでなく,「評価する側」も、きびしく評価を受けるからである。そのことをわかった上で,評価者も過去の事例を凌駕する高品質の仕事をしようとする。より良い手法は、報告書を公開し続けることによって、自然に淘汰され,生き残っていく。そしてマニュアルを凌駕する洞察を提示してくれる。評価制度は、情報公開とあいまって、すばらしい力を発揮する。このような力を最大限引き出すような制度運用を期待したい。
以上
|
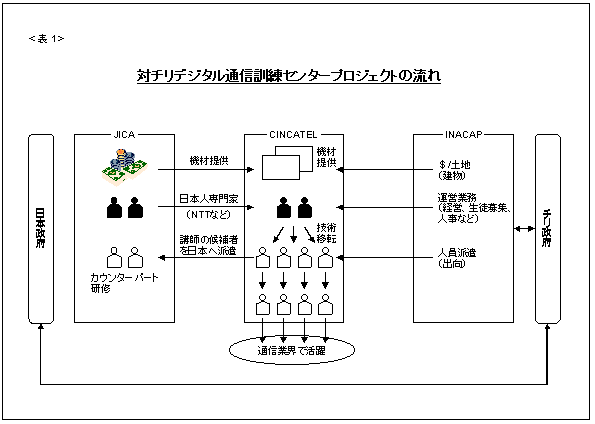
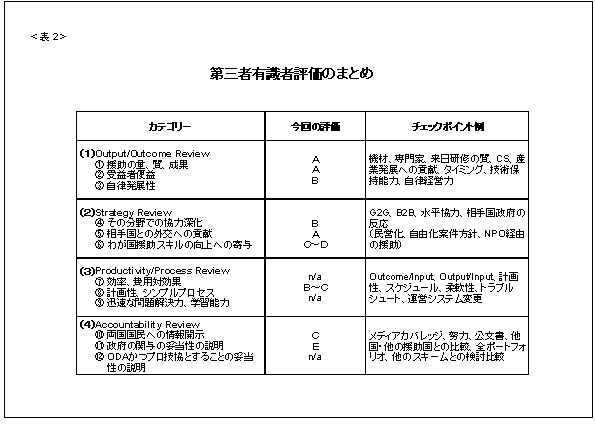
|